「最近、物忘れが増えた気がする…」
「年齢のせいか集中力が落ちたような…」
そんなふうに感じたことはありませんか?
記憶力は年齢とともに変化しますが、実は「いつピークを迎えるか」は記憶の“タイプ”によって異なります。
たとえば、語彙や知識のような記憶は中年期以降も伸び続ける一方で、作業記憶や反応の速さは比較的若いうちにピークを迎えると言われています。
つまり、「もう年だから」とあきらめる必要はありません。
「年齢を重ねるて記憶力が落ちてきたかも」という人は、ぜひ最後までよんでみてくださいね。
なお、記憶力の上げ方については記憶力を上げる方法とは?|誰でもできる記憶向上テクニックを紹介の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
もくじ
年齢のピークを超えると記憶力が低下するって本当?
記憶力の低下は年齢が関係していると思いますか?
年齢を重ねると記憶力の低下を感じる人も多いようです。
最近、記憶力が低下している。自分のやったこと、体験したこと、いろいろなことを忘れてしまっている。これって、年齢的なものなのかな?
— 走る舞夢 (@runmime) July 25, 2021
最近疲れからかぼーっとすること多いし、記憶力無くなってきた(年齢?)
— 限界社畜あおぼうず(きくっち) (@shiren_kk) July 25, 2021
記憶力には確かに年齢によるピークがありますが、一概に「年を取れば必ず低下する」とは言えません。
記憶の種類(語彙や作業記憶など)によってピーク時期が異なるためです。
たとえば、MITの研究では、名前の記憶や顔の認識、情報処理能力それぞれが異なる年齢でピークを迎えます。さらに、日本の調査では、20~30歳代で多くの記憶力のピークを迎えるケースが多く見られます。
本当に年を取ると記憶力は落ちるのか?
年齢とともに記憶力(特に作業記憶やエピソード記憶など)は一般的に低下します。
作業記憶は注意力や処理速度と密接に関連しており、集中力のピークが43歳前後であることも示されています。
集中力が落ちれば、情報のインプット能力も衰え、結果として記憶力の低下につながるのです。
一方で、「経験や知識による意味記憶」や「手続き記憶」は加齢による影響が小さいとされ、多くの知識型記憶はむしろ高年齢期に成熟する場合もあります。
記憶力がピークになる年齢は18歳!
脳には年齢によるピークがあります。
マサチューセッツ工科大学 認知科学研究者のジョシュア・ハーツホーンらの研究によると、
記憶力のピークは一律ではありませんが、情報処理や短期記憶といった能力はおおよそ18歳前後にピークを迎えるとされています。とはいえ、年齢を重ねること=記憶力が必ず落ちる、というわけではありません。
実際には、加齢によって脳の一部機能は緩やかに低下していく一方で、語彙力や知識といった「意味記憶」は中高年以降も伸び続けるという研究もあります。
つまり、記憶力は年齢によって一部は衰えても、正しい対策をすれば十分に維持・強化が可能なのです。
年齢を重ねて記憶力の低下を感じる40代の方は、以下の記事で記憶力アップ法がわかります。ぜひ、合わせてよんでみてください。
あなたの記憶力は今どの年代?【簡易診断】
「記憶力は年齢とともに落ちる」と言われますが、実際に自分の記憶力がどのレベルにあるのかを客観的に把握している人は多くありません。
そこでここでは、簡単なセルフチェックで、現在の記憶力の傾向を知ることができる診断をご用意しました。
5つの質問で簡単にチェック
まずは、以下の5つの質問に「はい」または「いいえ」で答えてみてください。
これは、記憶力・集中力・日常の認知傾向を測る簡易的なセルフチェックです。
| 質問 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 最近、人の名前や予定をすぐに忘れることが増えた | ☐ | ☐ |
| 会話中に「あれ、今何の話だっけ?」となることがある | ☐ | ☐ |
| 短時間で複数の作業をこなすのが苦手になってきた | ☐ | ☐ |
| 電話番号や買い物リストなどをすぐに忘れてしまう | ☐ | ☐ |
| 昔より集中力が続かないと感じる | ☐ | ☐ |
「はい」が3つ以上あれば、記憶力に軽度の低下が見られる可能性があります。
ただし、これはあくまで簡易チェックです。
本格的に記憶力の状態を知りたい方は、エーザイの「のうKNOW」やCogSmartのチェックツールなどを利用することをおすすめします。
診断結果別に見る記憶力維持のヒント
診断結果が平均以上・平均・平均以下のどれであっても、それに応じた記憶力維持のヒントが必ずあります。
たとえば
- 処理速度に不安がある人→「すきま時間の脳トレ習慣」、
- 記憶の定着が弱い人→「反復・アウトプット重視の暗記法」
- 集中が続かないと感じる人→「生活リズム見直しと運動習慣」
が効果的です。
これらは科学的に認知機能を支える習慣と一致します。
なぜ年齢とともに記憶力は低下するのか?主な原因7選

この章では、「記憶力低下の主な要因」を7つ紹介します。
加齢だけに原因を求めるのではなく、生活習慣や環境の影響に目を向けることで、記憶力を保つヒントが見えてきます。
さっそくみていきましょう。
原因①:過度なストレス
年齢以外で記憶力を低下させる原因の1つ目は「過度なストレス」です。
過度なストレスを感じると、年齢に関係なくコルチゾールが大量に発生します。
コルチゾールが大量発生すると以下のような症状が起きてしまいます。
過度なストレスは、記憶力の低下だけでなく、さまざまな影響を及ぼします。
年齢を重ねるにつれて、責任感やストレスが増えてきます。
定期的にリフレッシュしてストレスを溜め込まないようにしましょう。
ストレスが記憶力に与える影響や発散方法については、以下の記事で解説しています。
気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
関連記事 : ストレスは記憶力の大敵!脳との関係・記憶を回復させる対処法を解説
原因②:睡眠不足
年齢以外で記憶力を低下させる原因の2つ目は「睡眠不足」です。
睡眠不足は年齢に関係なく、以下のような影響を及ぼします。
毎日少しずつ睡眠不足を感じてはいませんか?年齢を重ねるにつれて、睡眠不足が積み重なってしまいます。
睡眠不足は年齢に関係なく、記憶力の低下以外にも、体にさまざまな悪影響を及ぼしかねません。
睡眠時間を削って仕事をしたり、勉強したりすることは、あまり得策とは言えませんね。
年齢を重ねると感じる記憶力の低下を防ぐには、6時間以上の睡眠を確保するようにしましょう。
関連記事 : 記憶力と睡眠の関係
原因③:食生活の乱れによる栄養不足
年齢以外で記憶力を低下させる原因の3つ目は「食生活の乱れによる栄養不足」です。食生活が乱れると、記憶力を維持するために必要な栄養素が不足しがちです。
また、年齢を重ねると、ストレスの増加など、疲労回復に必要となる栄養素が増えてきます。栄養バランスの整った食事を取ることで、年齢による記憶力低下を感じにくくなるのです。
以下のような栄養素が不足すると、記憶力の低下の原因となってしまいます。
年齢を重ねると、特に必要な栄養が増えてきます。必要な栄養素が不足しないように、普段の食生活を気をつける必要があります。
以下の記事では、記憶力に良い食べ物を紹介していますので、ぜひ読んでみてください。
関連記事 : 記憶力がアップする食べ物とは?勉強のお供やテスト本番にもおすすめ!
原因④:スマホの使い過ぎ
年齢以外で記憶力を低下させる原因の4つ目は「スマホの使い過ぎ」です。
スマホを使いすぎると、 膨大の量の情報を目にしてしまい、必要な情報と不要な情報の区別がつかなくなります。
そして、脳が混乱してしまい、記憶力が低下してしまうのです。
スマホの使いすぎは、年齢に関係なく、記憶力低下の原因となってしまいます。
さらに、スマホを使いすぎると、記憶力の低下以外にもさまざまな悪影響を及ぼすのです。
スマホの使いすぎは、年齢に関係なく記憶力を低下させてしまいます。
スマホを使いすぎていると感じる方は、以下のことに気をつけると良いでしょう。
<スマホの使い過ぎを避ける方法>
・起きてすぐスマホをチェックしない
・食事や会話中にスマホを使用しない
・お風呂、トイレ、寝室にスマホを持ち込まない
関連記事 : スマホの弊害は?記憶力を低下させるメカニズムも紹介
原因⑤:思い込み
年齢以外で記憶力を低下させる原因の5つ目は「思い込み」です。
「2019年度 記憶力日本選手権大会」優勝者の池田 義博さんによると、
偽の薬でも効くと信じて服用すると、本当に効果が出ることがあります。
これと同様に「覚えられない」「無理だ」という ネガティブな思い込みは、記憶スイッチをオフにしてしまうのです。
年齢を重ねても記憶力が衰えない人は「歳だから覚えられない」とは考えません。
年齢とともに低下するのは、記憶力ではなく、覚えようとする意欲なのです。
記憶力のピークを過ぎた年齢だから、記憶力が低下しても仕方ないと思っていませんか?
「記憶力に年齢は関係ない」と思い込むことで、記憶力の低下を抑えることができるでしょう。
原因⑥:飲酒・喫煙
飲みすぎ、吸いすぎは、脳の老化に繋がります。アルコール依存症や大量飲酒者の場合、脳が委縮して認知症やうつ病のリスクが高くなります。
記憶力や学習力が低下し、日常生活や仕事への影響も大きいです。
喫煙は、脳細胞へ悪いダメージを与え、精神疾患や睡眠障害のリスクが高まります。
多くの病気の原因となり、認知症、がん、脳や心臓病、肺や気管支の病気、糖尿病、腎臓病、アレルギー性疾患、目や鼻の病気などにかかりやすくなります。
ヘビースモーカーであった人は、禁煙を25年続けても、吸わなかった頃のように大脳皮質の厚みは回復しないという報告もあります。
関連記事 : お酒と記憶力の関係を解説|脳に与える危険性や勉強にも活かせる上手な付き合い方まで
原因⑦:運動不足
運動不足は、脳の働きを低下させます。
25歳を過ぎると脳細胞は1秒あたり10万個のペースで死滅しているため、脳細胞の働きを促すには、運動が必要になります。
体を動かすことで、脳内で「BDNF」という物質が分泌されて脳内細胞を活性化できます。
また、パソコン作業やオンライン学習などで一日家にいる場合は、合間に身体を動かすことは、運動不足の解消や気分転換にもなって、脳の働きが良くなります。
記憶力をアップするためにも、適度な運動とリフレッシュできる時間を作りましょう。
記憶力に関するよくある悩み
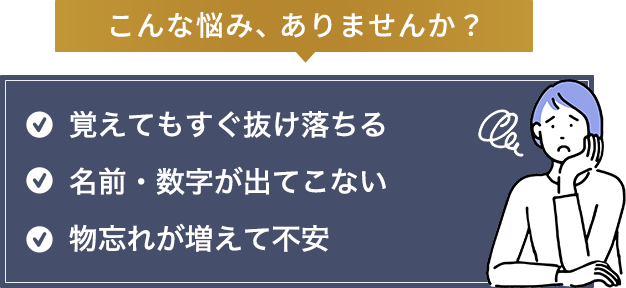
覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。
それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。
無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
実年齢に関係なく記憶力を維持・強化する7つの習慣

今から、年齢を気にせず記憶力が良い人の習慣をご紹介します。
年齢を気にせず記憶力が良い人の習慣は、以下の7つです。
上記を読むと、年齢を気にせず記憶力が良い人の習慣がわかります。
さっそくみていきましょう。
習慣①:ノートやメモを使いこなす
年齢を気にせず記憶力が良い人の習慣1つ目は「ノートやメモを使いこなす」です。
人の脳は年齢に関係なく、覚えたことをすぐに忘れるようにできています。そのため、ノートやメモに記録しておき、後から見返す必要があります。
見返すことで、記録した内容を思い出し、記憶に定着させるのです。
年齢を気にせず記憶力が良い人は、記録したその日のうちに見返す傾向にあります。
工夫して記録することで、記憶に残りやすくなり、年齢とともに記憶力の低下を感じること少なくなるでしょう。
記録することは、年齢に関係なくできることです。
記憶力のピーク年齢を過ぎていても、記録する習慣を身につけることで、記憶力の低下を防ぐことができるでしょう。
習慣②:6時間以上の睡眠をとる
年齢を気にせず記憶力が良い人の習慣2つ目は「6時間以上の睡眠をとる」です。
ハーバード大学のスティックゴールド博士によると、
学生に図形を次々に表示し、その向きを答えるテストを行いました。
その後、学生たちを以下のグループに分け、3日後に同じテストを実施しました。
・グループA:テスト後は徹夜
・グループB:6時間睡眠
結果は、グループAに比べて、グループBの方がはるかに成績が伸びていたのです。
このことから、「記憶力を高めるには、覚えたその日に6時間以上眠ることが欠かせない」と結論づけています。
年齢を気にせずに記憶力を維持するためには、6時間以上の睡眠を習慣にすることが大切ですね。
習慣③:日記をつける
年齢を気にせず記憶力が良い人の習慣3つ目は「日記をつける」です。
日記を書くため1日を振り返ることで、脳が活性化します。
出来事を振り返ると、年齢に関係なく記憶に定着しやすくなるのです。
年齢を気にせず記憶力が良い人は、日記を習慣にしている傾向にあります。
手軽に始められる日記で、年齢を気にせず記憶力が良い人を目指していきましょう。
日記を始めたいけど、何を書いたらいいかわからないという方には、以下の内容がおすすめです。
習慣④運動する
日常生活に有酸素運動を取り入れることで、脳の働きを活性化させる効果があります。
体を動かすことで、脳内ドーパミンが分泌されやすくなり、記憶力や学力、集中力などが向上します。
持久的な有酸素運動を行うことで、脳の海馬の縮小を抑えて記憶が定着しやすい状態を維持できるようになります。
有酸素運動は、過度な運動ではなく持続して毎日できる軽い運動が適切です。
運動をしていない状態よりも少し辛くて呼吸が早くなる程度が目安です。
ウォーキング、ジョギング、自転車、水泳、などや、室内でできるスクワット、踏み台昇降、などがおすすめです。
習慣⑤アウトプットする
記憶を定着させるには、人に教えたり話したりして、アウトプットすることが大事です。
情報をインプットするだけでは、海馬で情報処理しきれずに記憶として残らなくなってしまいます。
情報は、インプットとアウトプットを程よくすることで、脳の大脳皮質に長期記憶として保管し、必要に応じて取り出して思い出すことができるようになります。
習慣⑥:新しいことに挑戦する
新しいことを覚えたり挑戦することで脳が活性化され、シナプスの数が増えて記憶力が向上します。
シナプスとは、複数の神経細胞を繋げる接合部分です。シナプスの活動によって脳の働きが変化し、情報をたくさん受け取って記憶に残すことができます。
50代になっても、常に新しいことに好奇心を持って挑戦することは、脳の老化防止にも繋がります
習慣⑦:認知機能改善に良い栄養・成分を摂っている
DHAや EPAを含む食品を積極的に摂ると、脳機能の改善に効果的です。脳を活性化して記憶力をはじめ、認知機能を高めます。
DHAは、脳細胞を柔らかくし情報の伝達性を促します。
EAPは、血栓を防ぎ、抗炎症作用、免疫調節作用、脂質代謝改善作用を高めることができます。
-
- 魚類:まぐろ、さんま、さば、いわし、あじ、かつお、ぶり
- 油類:エゴマ、アマ二、なたね、大豆、マーガリン、バター
- 野菜類:キャベツ、チンゲン菜、にら、バジル、ブロッコリー、ほうれん草
- 肉類:豚肉、鶏肉、牛肉、卵、牛乳、ナチュラルチーズクリーム
まとめ|診断→対策→習慣の3ステップで記憶力を保とう
記憶力は年齢によってある程度変化するものですが、それ以上に重要なのは、「自分の記憶力の現状を把握し、それに合った対策を続けられるかどうか」です。
この記事で紹介したように、
- 簡易診断で自分の記憶傾向を知る
- 原因を理解して、生活習慣のリスクを減らす
- 記憶力を高める習慣を毎日コツコツ実践する
という3ステップを意識すれば、年齢に関係なく記憶力は維持・向上できます。
そして、さらに効果的に記憶力を伸ばしたい方には、「記憶術」を学ぶのもおすすめです。
Wonder Educationでは、誰でも記憶力を高められる記憶術講座を提供しています。再現性の高い指導で、記憶力向上とそれによる目的の達成をサポートしていますので、ご興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせください。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。














