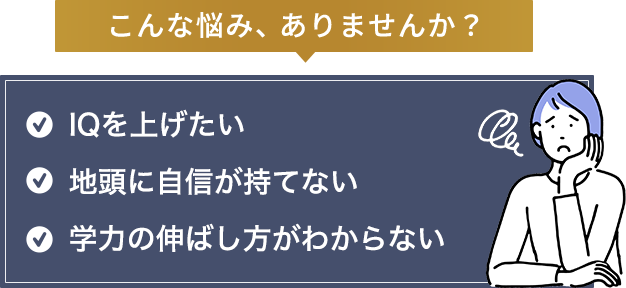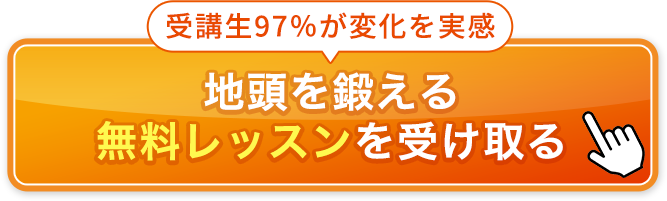キツネさん
キツネさん
「賢そうに見えるだけの人と、真の知性を持つ人の違いって何?」
同じように疑問を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、IQ・EQ・AQという3つの観点や、頭がいい人の特徴や思考・習慣・学び方まで徹底解説します。
「本当の意味で賢い人とは何か」を知りたい方や、自分の知性を磨きたい方に役立つ内容です。
頭がいい人の考え方を知れば、人生の選択や人間関係もきっと変わります。
どうぞ最後まで読み進めて、やれることから実践してみてください。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
頭がいい人とは?3つの分類と特徴

「頭がいい人」とは、単に学力が高い人を指すわけではありません。
知能、感情、逆境への対応力といった複数の要素が関係しており、それぞれに異なるタイプの賢さが存在します。
- IQ|知能指数:知能を測る基準
- EQ|心の知能指数:感情を理解・管理する能力
- AQ|逆境指数:ストレスへの耐性を表す
それぞれ順番に解説します。
IQ|知能指数:知能を測る基準
IQは、言語理解力や論理的思考力、計算力などを数値で表す指標です。
IQが高い人は、情報処理や問題解決を得意とし、論理的に物事を整理する力に長けています。
知識の吸収が速く、複雑な内容でも短時間で理解できるのが特徴です。
学業や研究、専門職などではIQの高さが大きな強みとなり、成果を出しやすい環境に適応しやすい傾向にあります。
EQ|心の知能指数:感情を理解・管理する能力
EQは、自分と他人の感情を適切に認識し、共感や対話を通じて良好な関係を築く力を指します。
EQが高い人は、感情のコントロールが上手く、人間関係での衝突を避ける柔軟さを持っています。
職場や家庭など、他者との協調が求められる場面で特に力を発揮することが多いです。
チームビルディングやリーダーシップにも優れており、現代社会では高く評価される能力といえるでしょう。
AQ|逆境指数:ストレスへの耐性を表す
AQは、困難やプレッシャーに直面したときに、それを乗り越える力の強さを測る指標です。
AQが高い人は、困難な状況でも冷静に状況を分析し、柔軟に解決策を模索できます。たとえば失敗から学びを得て次に活かす姿勢が、長期的な成功につながるのです。
苦しい状況でも前向きに捉える姿勢があり、結果として成功を収める確率が高まります。
長期的な目標に向けて努力を続けられる人にとって、AQの高さは確実に武器となるでしょう。
頭がいい人と勘違いしてる人|見分け方

一見、頭がよさそうに見える人でも、実は中身が伴っていないことがあります。
本当に賢い人は、言動や態度に一貫性があり、相手を尊重しながら知性を発揮するのが特徴です。
- 見かけ倒しな言動の特徴
- 本当に賢い人の見抜き方(会話・態度)
それぞれ順番に解説します。
見かけ倒しな言動の特徴
表面的には知的に見えても、実際は知識の浅さや配慮のなさによって誤解を招くことがあります。
- 難しい言葉を並べるが、内容が伴っていない
- 相手を見下すような話し方をする
- 議論よりもマウントを取ることを優先する
- 相手の理解よりも自分のアピールを重視する
一見知的に見えても、浅い知識や配慮のない発言はすぐに見抜かれます。その結果、信頼を失い、人間関係に悪影響を及ぼすことも少なくありません。
結果として、周囲の信頼を得にくくなる原因になりがちです。
本当に賢い人の見抜き方(会話・態度)
本当に頭がいい人は、相手に合わせた話し方や、配慮ある振る舞いを自然に行う力があります。
知識や経験を一方的に押しつけるのではなく、相手の理解を深める工夫ができるのが特徴です。
- 難しい内容もかみ砕いて丁寧に説明する
- 相手の理解度に応じて話し方を調整する
- 自分の意見を押し付けず、相手に耳を傾ける
- 表現や態度に思いやりがあり、マウントを取らない
- 知識を誇示せず、必要なときだけ的確に使う
こうした態度を見れば、知識だけでなく人間性のバランスが取れていることがわかります。
知性は、内容よりも伝え方に表れるものといえるでしょう。
本当の意味で頭がいい人の9つの特徴

「頭がいい」と聞くと学歴やIQの高さを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、本質的な賢さはもっと多面的なものです。
ここでは、人間関係や仕事、日常のあらゆる場面で信頼される「本当の意味で頭がいい人」の特徴を人物のエピソードを交えて紹介します。
- 論理的に話し考える習慣がある
- 客観的な視点で柔軟に対応できる
- 好奇心があり無知を認めて学び続ける
- 相手の話を丁寧に聞いて理解できる
- 感情を適切にコントロールできる
- 問題の本質を見抜く力がある
- 相手に合わせてわかりやすく説明できる
- ユーモアで場の空気を和ませる
- 常に改善や工夫を続けている
それぞれ順番に解説します。
① 論理的に話し考える習慣がある
頭がいい人は、感情や思い込みに流されず、常に筋道を立てて考える習慣を持っています。
話すときには結論と理由が明確で、相手に伝わりやすい構成になっていることが多いのも特徴です。
たとえば、Appleの創業者であるスティーブ・ジョブズは、iPhone発表時に「電話」「音楽」「インターネット」という3要素を一つにまとめる革新性を、論理的かつ印象的に語りました。
このように感情に流されず、理路整然と伝える力が、周囲からの信頼を集める要因となるのです。
② 客観的な視点で柔軟に対応できる
視野が広く、物事を多面的に捉えるのも、頭がいい人の重要な資質です。
自分の意見に固執せず、他者の視点やデータを受け入れながら、状況に応じて判断を更新できます。
ノーベル平和賞受賞者である教育活動家のマララ・ユスフザイは、タリバンに襲撃されるという悲劇に遭っても報復ではなく教育の重要性を訴え、国際社会と対話を続けました。
こうした柔軟性が、時代や環境の変化にも強く、信頼されるリーダーとしての力を発揮するのです。
③ 好奇心があり無知を認めて学び続ける
頭がいい人ほど、自分の無知を認め、そこから学び続けようとする姿勢を持っています。
これは古代ギリシャの哲学者であるソクラテスが提唱した「無知の知」に通じ、自らの無知を自覚することが知恵の始まりであるという考え方です。
マイクロソフト創業者のビル・ゲイツは、毎年数十冊の本を読み、医療・教育・気候問題などの新しい知見を吸収し続けています。
「わからないことを素直に認め、学ぶ姿勢を持ち続ける」ことが、信頼と成長の原動力となるのです。
④ 相手の話を丁寧に聞いて理解できる
頭がいい人は「聞く力」にも優れ、相手の言葉の背景や意図を丁寧にくみ取ることができます。
ただ耳を傾けるだけでなく、内容を要約し返すことで、相手との信頼関係を深めていくのが特徴です。
元アメリカ大統領のバラク・オバマは、タウンホールミーティングなどで一人ひとりの発言を真剣に聞き取り、その内容に応じた返答を丁寧に行いました。
このように、双方向のコミュニケーションができる姿勢は、信頼と共感を得るための基盤といえるでしょう。
⑤ 感情を適切にコントロールできる
怒りや不安といった感情に左右されず、状況にふさわしい判断ができるのも賢さのひとつです。
頭がいい人は、自分の感情を客観的に捉えた上で、冷静に最善の選択肢を選び取る力を持っています。
宇宙開発企業SpaceXのCEOであるイーロン・マスク(マスク氏)は、ロケットの打ち上げに3度連続で失敗した際も感情的にならず、分析と改善に集中しました。
4回目で成功を収めたその冷静さと粘り強さこそ、信頼と成果を引き寄せる大きな力といえるでしょう。
⑥ 問題の本質を見抜く力がある
頭がいい人は、目の前の結果にとらわれず、「なぜその問題が起きたのか」を探る傾向があります。
「なぜそれが起きたのか」「本当に解決すべき問題は何か」と問い続ける姿勢は、精度の高い判断につながるでしょう。
理論物理学者のアルベルト・アインシュタインは、光の速度が一定であることに着目し、既存の物理学を問い直した結果として相対性理論を打ち立てました。
表面の数字や状況、そして常識にとらわれずに本質に迫る視点が、大きな発見や革新を生む鍵となるのです。
⑦ 相手に合わせてわかりやすく説明できる
知識があるだけではなく、それを相手に応じて「伝わる言葉」に変換できるのが、本当に賢い人です。
専門用語に頼らず、たとえ話や簡潔な表現を活用し、相手の理解度に合わせて工夫する姿勢が見られます。
iPS細胞の研究でノーベル賞を受賞した医学者の山中伸弥は、iPS細胞を「細胞のタイムマシン」と説明し、一般の人にも意義をわかりやすく伝えました。
相手の立場を考えて伝える力は、知識の深さだけでなく人間力の高さも反映しているといえます。
⑧ ユーモアで場の空気を和ませる
頭がいい人は場の空気を読み、適切なタイミングでユーモアを交えることで緊張をほぐすことができます。
そのユーモアは単なる笑いではなく、場の空気をコントロールし、人間関係を円滑に進めるための戦略でもあります。
第二次世界大戦中のイギリス首相であったウィンストン・チャーチルは、議会で激しい批判を受けた際にウィットに富んだ一言で場を和ませ、対立よりも結束を生み出しました。
このように、場を読む力と柔らかな言葉遣いが、知性と余裕を感じさせるのです。
⑨ 常に改善や工夫を続けている
頭がいい人は「これで十分」と満足せず、常により良い方法を模索し続けます。
たとえうまくいっている状態であっても、改善の余地を見出して工夫を重ねる姿勢が見られます。
自動車メーカーであるトヨタ自動車の生産現場では、一般社員が提案した部品の配置変更によって、年間数百時間もの作業効率が向上したという実例が知られています。
この「カイゼン(改善)」の精神は、立場に関係なく学びと工夫を継続することの大切さを教えてくれます。
継続的な成長意欲が、知性を支える土台となっているのです。
IQに関するよくある悩み
▼IQを高めたい、地頭に自信を持ちたい、
学力の伸ばし方が分からない——。
その悩みは、「記憶術」で解決できます。
記憶術は、脳の仕組みに基づいた再現性の高い学習法。
まずは無料動画で、その効果を体感してみてください。
LINE登録だけで、5大特典もプレゼント中です。
頭が良い人が実践している習慣や考え方

頭が良い人は、知識や思考力だけでなく、日常の過ごし方にも独自の工夫をしています。
日々の習慣が思考の質や判断力に直結するため、その行動はとても参考になるでしょう。
- 毎日学ぶ時間を確保している
- 自分の考えを言語化している
- 失敗から必ず学びを得ている
- 多様な意見に耳を傾けている
- 物事をシンプルに整理している
- 時間管理の方法を学んでいる
- 意識的に考えない時間を作っている
- 運動を習慣にしている
- 十分な睡眠を取っている
それぞれ順番に解説します。
① 毎日学ぶ時間を確保している
頭が良い人は、日々の生活の中で自然と学びを取り入れています。
自分に合った学習スタイルを見つけ、無理なく継続する仕組みを作っています。
継続的な学びが、知識だけでなく思考の深さにもつながっているのです。
- 朝の15分間で読書をする
- ニュースを1日1本だけ丁寧に読む
- スキマ時間に学習アプリを使う
- 週に1回、自分に質問して答えを書く
毎日の積み重ねが大きな差を生み出します。
学ぶ習慣は、将来の自分への最高の投資です。
② 自分の考えを言語化している
自分の思いや考えを言葉にすることで、思考の整理と理解の深化を図っています。
また、言語化の習慣が、論理的思考やコミュニケーション力の向上にもつながっています。
頭がいい人は、内省する力が高く、行動の精度も上がるのが特徴です。
- 毎日1つ、自分の意見をメモする
- その日の気づきを3行日記にまとめる
- 会話中に「つまり〜」と要約して話す
- ブログやSNSで自分の考えを公開する
言葉にすることで、自分の考えや感情を客観視できるようになります。
まずは日々の気づきや疑問を、短くても良いので書き出してみましょう。それが、思考力を高める第一歩になります。
思考の質を上げたいなら、まずは書き出してみましょう。
③ 失敗から必ず学びを得ている
頭が良い人は、失敗をネガティブに捉えず、成長の糧としています。
同じ過ちを繰り返さないために、原因の分析や改善策を記録する習慣を持っています。
その積み重ねが、将来の成功確率を大きく押し上げる原動力となっているのです。
- 失敗した理由を「5W1H」で書き出す
- 次にどう行動すべきかを記録する
- 毎週「今週の学びメモ」をつける
- 友人とお互いの失敗を共有し合う
成長する人は、必ず反省を行動に結びつけています。
失敗を「終わり」ではなく「始まり」に変えることができるのは、賢さの証でしょう。
④ 多様な意見に耳を傾けている
頭がいい人は、自分と異なる意見を受け入れることで、視野を広げようとする意識があります。
意見をぶつけ合うのではなく、まず「聞くこと」を大切にしているのです。
その姿勢が、思考の柔軟性と人間関係の安定を生み出しています。
- 対立する記事を2つ読み比べる
- 議論では「それはなぜ?」と質問する
- 読書会やディスカッションに参加する
- 他人の意見を3行で要約する練習をする
他者の視点を知ることで、自分の視点も磨かれます。違いを受け入れる力が、本当の知性の土台になります。
⑤ 物事をシンプルにみる
頭の良い人は、複雑な状況でも本質を見抜く力 = 「物事をシンプルにみる」ことができます。
重要なポイントに集中し、情報を構造化して理解しています。
そのため、判断が早く、伝える力も強くなっていきます。
- 「結論→理由→例」の順で書く癖をつける
- ノートを3分割して要点だけを書く
- メモは1項目3行以内にする
- 5つ以上の情報はグループに分ける
整理された情報は、迷いのない行動につながります。シンプルに考える力が、複雑な問題も解決へ導きます。
⑥ 時間管理の方法を学んでいる
頭が良い人は、時間を「消費」ではなく「投資」として捉えています。
やるべきことと、やらなくていいことを分け、集中とリフレッシュのバランスも意識しています。
1日24時間を最大限に活用するための工夫を常にアップデートしているのです。
- タスクやTODOリストは前夜に決めておく
- ポモドーロ・テクニックで時間を区切る
- スケジュールには休憩も必ず入れる
- 1週間の振り返りを日曜日に10分だけ行う
時間は誰にとっても平等な資源です。その使い方こそが、成果の差を生む最大のポイントです。
⑦ 意識的に考えない時間を作っている
頭の良い人は、集中とリラックスの切り替えをとても大切にしています。
あえて何も考えない時間を確保することで、脳の処理能力や創造性を回復させているのです。
静けさや無意識の中に、新しい発想が生まれることもあります。
- 毎日10分間、散歩する時間をつくる
- 就寝前に深呼吸だけの時間をとる
- 考え事をしないでボーッとする時間を意識する
- 週に1回、自然の中で何もせず過ごす
脳も体と同じように「休ませる時間」が必要です。余白があるからこそ、思考はより自由に広がっていきます。
⑧ 運動を習慣にしている
頭がいい人は、身体の健康を維持することが、脳のパフォーマンスにも直結すると理解しています。
また、運動による集中力や思考力の向上を実感しており、日常に取り入れています。
継続可能なスタイルで運動を楽しむことも工夫のひとつです。
- 朝のラジオ体操を毎日5分だけ行う
- エレベーターより階段を使うようにする
- 寝る前にストレッチをする
- 土日のどちらかは30分以上歩くと決める
無理のない運動でも、継続すれば大きな効果が得られます。心身のバランスを整えることが、賢さの土台になります。
関連記事:【朝がいい?】集中力をアップさせる運動おすすめ7選
⑨ 十分な睡眠を取っている
頭が良い人は、睡眠の量だけでなく質にも強くこだわっています。
記憶の定着や判断力の維持には、良質な睡眠が不可欠だと理解しているからです。
規則正しい生活習慣も、集中力のベースを支えています。
- 寝る時間と起きる時間を毎日固定する
- 寝る前1時間はスマホを見ないようにする
- 睡眠アプリで睡眠の質をチェックする
- アロマや間接照明など睡眠環境を整える
ぐっすり眠ることは、明日の自分への準備です。疲れを残さず、最高のパフォーマンスを出すための基本となります。
関連記事:集中力が落ちるのは睡眠不足の可能性大!それでも頑張る人のための4つの対処法
頭がいい人が身につけている勉強・学習方法

頭がいい人は、生まれつきの才能だけでなく、学習への取り組み方に工夫があります。
限られた時間の中で成果を出すために、方法や習慣を自分に合う形で最適化しているのが特徴です。
- 目標や優先順位を付ける
- 要点を絞って効率的に学ぶ
- インプットとアウトプットのバランスが良い
- 過去の失敗を振り返り活用
- 分からないことをすぐ調べる
- 自分に合った方法を見つける
それぞれ順番に解説します。
目標や優先順位を付ける
頭の良い人は、ただ勉強するのではなく「何のために」「どこまでやるか」を明確にしています。
目的を意識することで集中力が高まり、無駄のない行動が取れるようになるのです。
優先順位を見極める判断力も、日々の積み重ねで磨かれていきます。
有名な方法:SMARTの法則
SMARTの法則とは、Specific(具体的)・Measurable(測定可能)・Achievable(達成可能)・Relevant(関連性)・Time-bound(期限)の略で、目標を明確に設定する手法です。
- 具体的な学習目標を設定する(例:英単語100個を1週間で覚える)
- 成果を数値で測れるようにする(例:1日20単語)
- 自分の能力や時間に合った内容に調整する
- 長期目標とのつながりを意識する
- 期限をカレンダーに記入して逆算する
目標があると迷いが減り、行動に軸が生まれます。計画的に進める力が、効率的な学習の土台になるでしょう。
参考:「SMARTの法則」を使った目標設定のコツとは|三菱電機
要点を絞って効率的に学ぶ
頭のいい人は、すべてを覚えようとはせず、本質的に必要な情報だけに集中しています。
どこを重点的に学ぶべきかを見極め、最短距離で成果につなげているのです。
このように、ムダを減らして本質を押さえる工夫が学習効率を大きく左右します。
有名な方法:パレートの法則(80対20の法則)
成果の80%は20%の重要事項から生まれるという考えで、学ぶべき「核」を見極めるのに最適です。
- 試験や仕事で重要視される部分に優先的に取り組む
- 全体から「特に重要な2割」をノートやマーカーで強調する
- 覚える量より、繰り返す頻度を重視する
- 重要でない部分は読み飛ばすか概要だけ押さえる
必要なところやまだ覚えていない箇所に集中できる人は、成績の伸びも早くなります。
学ぶべき範囲を絞る力は、まさに知性のあらわれといえるでしょう。
インプトットとアウトプットのバランスが良い
知識を得るだけではなく、それを使う機会を積極的に作っているのが特徴です。
説明したり書き出したりすることで、記憶が定着しやすくなります。
学んだ内容を活用することで、理解の深さや応用力も高まっていくのです。
有名な方法:ファインマン・テクニック
ノーベル賞学者リチャード・ファインマンによる、「人に教えることで理解を深める」手法です。
- 学んだ内容を子どもに説明するつもりでアウトプットする
- 難しい用語は使わず、やさしい言葉に言い換える
- 詰まった箇所を再度インプットし直す
- 最後に全体を簡潔に要約して整理する
アウトプットを意識するだけで、学習効果は大きく変わってきます。頭が良い人ほど、この循環をうまく使いこなしているのです。
過去の失敗を振り返り活用
頭の良い人は、ミスをそのまま放置せず、必ず原因と対策を明確にしています。
同じ失敗を繰り返さないよう、記録しながら改善の行動につなげる習慣があります。
失敗を前向きに捉え、次に活かす姿勢が大きな成長を生み出しているのです。
有名な方法:エラーログ(ミスノート)
ミスした内容を記録して「原因」と「再発防止策」を明確にする、受験生定番のノート術です。
- 間違えた問題をノートに貼るか転記する
- なぜ間違えたのかを言語化する(例:読み間違い・公式忘れ)
- 正しい考え方と再発防止策を書き加える
- 解き直したらチェックを入れて達成感を得る
反省と改善を繰り返すことで、学びの精度が高まります。頭の良さとは、こうした積み重ねから生まれるものかもしれません。
分からないことをすぐ調べる
疑問が浮かんだときにすぐ調べる習慣が、知識の広がりを支えています。
分からない状態を放置せず、その場で解決しようとする意識があるのです。
調べる行動そのものが、学習の自立性を高める要因にもなっています。
有名な方法:アクティブラーニング
アクティブラーニングは、「分からない」をそのままにせず、能動的に調査・検索する学習スタイルです。
- 疑問が出たら、即ネット・辞書・参考書で確認する
- 理解できたことは自分の言葉でメモにまとめる
- 調べた内容を誰かに伝えることで記憶を強化する
- 分からないままの箇所はリスト化して後日まとめて解決
疑問を放置せず、自ら解決できる力は大きな強みです。
調べる癖がある人は、自学自習の力がつきやすくなります。
自分に合った方法を見つける
頭の良い人は、人に言われた通りにやるのではなく、自分にとって最適な方法を選びます。
集中力や記憶力、得意不得意を把握し、自分に合う学習スタイルを構築しているのです。
その柔軟さが、継続する力や成果にもつながっています。
有名な方法:VARK学習スタイル診断
自分が「視覚」「聴覚」「読写」「体感」のどの学習スタイルに強いかを判別できる方法です。
- VARKの簡易診断をオンラインで実施する
- 視覚型:図やチャート、イラストを多用する
- 聴覚型:音読・講義・音声教材を中心にする
- 読写型:ノートまとめ、テキスト反復を重視する
- 体感型:実践・体験・反復演習を多く取り入れる
自分に合った方法を知ることが、学習をラクに変えていきます。型にとらわれず、自分流を確立することが成功の鍵です。
参考:VARKアンケート
頭がいい人に関するよくある質問
頭がいい人に関するよくある質問について解説します。
頭がいい人は頭がいい人を好む?
知的な人同士は、話のテンポや興味の対象が一致しやすいため、自然と惹かれ合う傾向があります。
価値観や思考の深さが共鳴しやすく、無理のないコミュニケーションが成立することが多いため、結果的に親しくなりやすいのです。
相手の意見に敬意を払う姿勢も共通しているため、信頼関係も築きやすいでしょう。
頭がいいと勘違いしてる人の違いは?
本当に頭がいい人は、他者の意見に耳を傾け、学び続ける姿勢を持っています。
一方で、勘違いしている人は、自分の知識を誇示しがちで、他人を見下す傾向が見られるのが特徴です。
論理的な説明ではなく、感情や主観で物事を語る場面が多い点にも違いがあります。
頭がいい人にはどんなオーラがある?
頭がいい人は、落ち着いた雰囲気や話し方から知性がにじみ出ていることがよくあります。
急かさず冷静に状況を判断し、相手の言葉をよく聞く姿勢がオーラとして伝わるのです。
また、場面に応じて的確に言葉を選ぶため、安心感や信頼感も自然と生まれやすいといえます。
頭がいい人あるあるは?
共通する行動には「話が要点を押さえていてわかりやすい」「質問の意図をすぐ理解する」といった特徴があります。
また、読書や学習を習慣にしていたり、物事を多角的にとらえる力が備わっているケースも多いです。
他人に教えるのも得意で、複雑な内容でも噛み砕いて説明する姿が見られることもあります。
頭がいい人の顔の特徴は?
明確な法則があるわけではありませんが、表情や目の動きに知性が感じられる人が多い傾向があります。
たとえば、話を聞くときに相手の目をしっかり見て頷く、考えるときに視線を上に向けるなどの所作が挙げられます。
感情表現が穏やかで、相手を威圧しない柔らかな雰囲気も特徴のひとつでしょう。
まとめ|頭がいい人の特徴を取り入れてより良く生きよう!

本記事では、頭がいい人の特徴、習慣、学習方法について解説しました。
単なるIQの高さだけでなく、EQやAQといった感情や逆境への対応力、日々の工夫や行動習慣が知性を形作っていることがわかります。
自分に合った学び方や考え方を取り入れることで、よりよく生きるヒントが得られるはずです。
ぜひ、今日から一つでも実践してみてください。
さらに記憶力を高めたい方には、「吉永式記憶術」を活用したトレーニングもおすすめです。科学的な手法に基づいており、誰でも習得できる実践的な内容が特徴です。
記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い学習サポートにより、記憶力の向上と目標達成をしっかりと後押ししています。
興味のある方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。