 キツネさん
キツネさん
誰もが一度は経験するこの状態は、努力不足ではなく原因が潜んでいることが多いものです。
本記事では、勉強が頭に入らない理由とその対処法、さらに集中力を取り戻す具体的な工夫について解説します。
最後まで読み進めることで、効率的に学習成果を高めるためのヒントを得られるでしょう。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
なぜ勉強が頭に入らない?よくある5つの原因
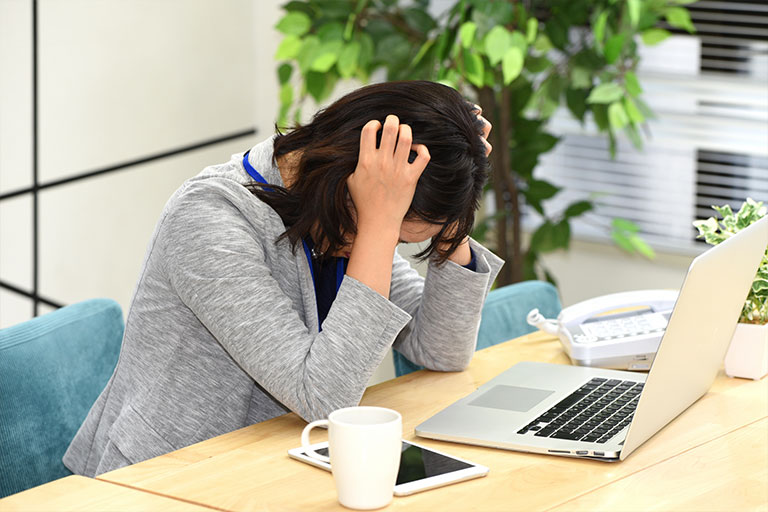
なぜ勉強が頭に入らないのかを理解することは、学習効率を上げる第一歩です。
学習がうまくいかないと感じるときには、生活習慣や環境に隠れた原因が存在しているケースが多いものです。
勉強が頭に入らない主な原因は以下の通りです。
- 睡眠不足や脳疲労の蓄積
- ストレス・不安による集中力の低下
- 勉強環境が悪い(スマホ・雑音など)
- インプット偏重でアウトプット不足
- モチベーションの低下・学習習慣の欠如
それぞれ順番に解説します。
① 睡眠不足や脳疲労の蓄積
勉強が頭に入らない最大の要因は、睡眠不足や脳疲労によって記憶の定着機能が低下することです。
十分な睡眠を取らないと、学んだ内容が整理されずに短期間で忘れてしまう可能性が高まります。
夜更かしや休憩不足を避け、睡眠時間が足りない場合は短い昼寝などで脳をリフレッシュさせることが重要になります。
勉強効率を上げるためには、1日7〜8時間の睡眠を確保することが欠かせません。
つまり休養を優先することで、自然に学習効果を引き上げることができるのです。
関連記事:集中力が落ちるのは睡眠不足の可能性大!それでも頑張る人のための4つの対処法
② ストレス・不安による集中力の低下
ストレスや不安は脳内の神経伝達物質を乱し、集中力や記憶力の働きを大きく損ないます。
安心できない精神状態では、注意が分散して学習内容が頭に入らない状態になりやすいのです。
深呼吸や軽い運動、趣味などを取り入れて心を整えることが改善の第一歩になります。
信頼できる人に悩みを打ち明けることも、心理的な負担を軽減する有効な方法の一つです。
精神的な安定を維持することが、学習の質を大きく左右する大切な要素といえます。
関連記事:ストレスは記憶力の大敵!脳との関係・記憶を回復させる対処法を解説
③ 勉強環境が悪い(スマホ・雑音など)
勉強が頭に入らない理由の一つは、スマホや雑音などの環境要因が集中を奪うからです。
通知音や人の声は思考を中断させ、再び集中するのに余計なエネルギーを必要とします。
このような負担を避けるには、学習中はスマホを遠ざけて静かな場所を確保することが効果的です。
耳栓やノイズキャンセリングイヤホン、集中音楽などを使うことも、余計な刺激を遮断して集中状態を維持する助けになります。
つまり環境を整える工夫が、学習効率を大きく高める条件となるのです。
④ インプット偏重でアウトプット不足
勉強が定着しない背景には、インプットに偏りすぎていることが挙げられます。
読む・聞くといったインプットだけでは、記憶は脳に十分に定着せず忘れやすいのです。
問題を解く・書く・説明するなどのアウトプットを繰り返すことで記憶は強化されます。
この方法はアクティブリコールとして知られ、学習効果を飛躍的に高めることが可能です。
つまり学習の計画にはアウトプットを必ず組み込むことが不可欠なのです。
関連記事:「思い出せない」を解決!アクティブリコールの効果と勉強法を解説
⑤ モチベーションの低下・学習習慣の欠如
モチベーションが下がると勉強の継続が難しくなり、学習内容が頭に入らなくなります。
習慣化されていない場合、机に向かう前から心理的に疲れてしまうことも多いのです。
小さな目標を設定して達成感を積み重ねると、学習意欲を維持しやすくなります。
また短時間の学習を繰り返すことで、抵抗感を和らげながら習慣化を進められるでしょう。
このようにモチベーションと習慣を両立させることが成果を高める基盤となるのです。
勉強が頭に入らないときの対処法

勉強が頭に入らないと感じるときには、正しい方法で環境や行動を工夫することが必要です。
集中力や記憶力を取り戻すために、日常生活の習慣から学習法まで改善できる点は多く存在します。
- 睡眠時間と休憩時間を確保し脳を休ませる
- ポモドーロ・テクニックで学習と休憩を繰り返す
- スマホを遠ざけ環境を整える
- 学んだ内容を声に出して説明する
- 毎日の復習で記憶を強化する
それぞれ順番に解説します。
① 睡眠時間と休憩時間を確保し脳を休ませる
勉強の効率を高めるためには、まず十分な睡眠と適度な休憩を取ることが欠かせません。
なぜなら脳は休息中に情報を整理し、学んだ内容を長期記憶として定着させる働きをするからです。
睡眠不足や休憩不足が続けば、集中力の低下や理解力の鈍化を招き、学習成果が大きく損なわれます。
そのため計画的に就寝時間を確保し、学習の合間には短時間の休憩を入れることが有効です。
つまり脳に十分な回復の機会を与えることが、勉強を効率よく進めるための最も基本的な対策といえます。
関連記事:記憶力と睡眠の関係
② ポモドーロ・テクニックで学習と休憩を繰り返す
勉強に集中できないときには、ポモドーロ・テクニックを取り入れる方法が効果的です。
これは25分の学習と5分の休憩を繰り返すシンプルな方法で、集中力の持続に優れています。
時間を区切ることで脳がリズムをつかみやすくなり、メリハリのある学習習慣を築けるのです。
また短い休憩を挟むことで疲労を防ぎ、集中の質を高めながら学習時間を延ばすことができます。
つまり計画的に時間を管理することで、集中力を維持しやすい学習環境を整えられるのです。
③ スマホを遠ざけ環境を整える
スマホは、勉強中の集中力を最も阻害するツールのひとつです。
SNS通知や動画アプリの誘惑は、一時的な快感を生みますが、その反動で「集中できない」「自己否定感が強まる」など、ストレスやうつ傾向につながる場合もあります。
そのため、スマホは物理的に机から遠ざけることが基本です。とはいえ、依存度が高い人ほど「触らない」こと自体が大きなストレスになることも。
そんなときは、以下のような遮断アプリを目的別に使い分けることで、負担を抑えながら集中環境を整えることができます。
- Forest:ゲーム感覚で木を育てながら集中を習慣化。楽しみながらスマホ使用を抑えられる。
- Detox:強制ロック機能で一度開始すると解除できない。衝動的な利用を確実に防げる。
- iOSスクリーンタイム:標準搭載で手軽に利用可能。アプリ制限や利用時間の可視化ができ、子ども管理にも有効。
このように、自分のメンタル状態や依存度に応じてアプリを使い分けることで、ストレスを減らしつつ集中力を回復させることができます。
④ 学んだ内容を声に出して説明する
記憶を強化するためには、学んだ内容を声に出して説明する方法が非常に有効です。
声に出して話すことで脳は「理解した知識を人に伝える」というアウトプット作業を行います。
声に出す過程で情報の整理が進み、理解度が深まるだけでなく記憶としても長く残るのです。
一人で勉強している場合でも、自分に向かって説明する練習を習慣化することが効果的です。
つまり知識を積極的に使う工夫を取り入れることで、学習成果を大きく高められるでしょう。
⑤ 毎日の復習で記憶を強化する
学習内容を長期記憶に転送するためには、短期記憶の段階で繰り返し刺激を与える「再認・再生」のプロセスが欠かせません。
エビングハウスの忘却曲線が示す通り、人間の記憶は急速に減衰するため、間隔反復(Spaced Repetition)を取り入れた復習が有効です。
具体的には、学習当日・翌日・3日後・1週間後といった間隔で復習を行うと、海馬から大脳皮質への記憶の定着が促されます。
また、短時間でも毎日復習を継続することで、シナプスの可塑性が強化され、理解度と想起のスピードが向上するのです。
このように計画的な復習サイクルを組み込むことで、効率的に知識を長期的に保持できるでしょう。
関連記事:忘れない勉強法|エビングハウスの忘却曲線と復習スケジュール完全ガイド
勉強内容が覚えられないときは記憶術を活用しよう
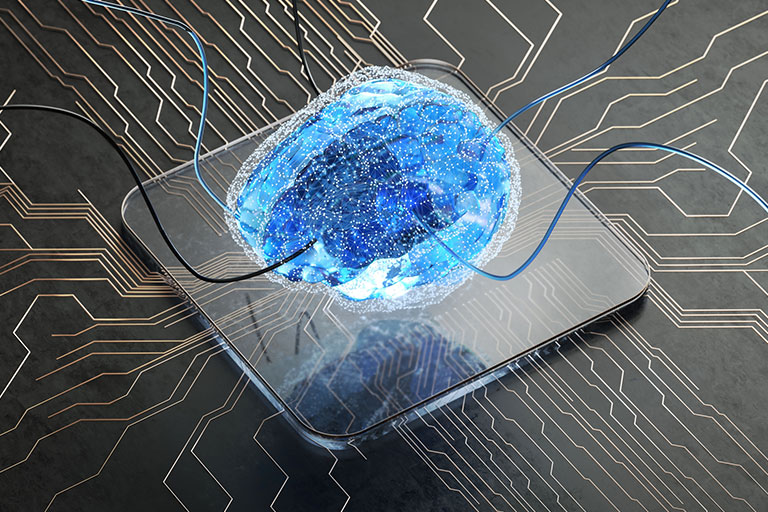
勉強内容が覚えられないときは、従来の反復学習に加えて記憶術を取り入れることが有効です。
記憶術は情報を関連付けて覚えやすくし、必要なときに思い出しやすくしてくれます。
- 場所法|自宅や通学路など身近な場所に知識を配置して整理する
- ストーリーメソッド|無関係な単語や数字を物語に変えて忘れにくくする
- 頭字語法(アクロニム)|単語の頭文字をつなげて新しい言葉にする
- イメージ連結法|複数の情報を印象的な映像でつなげて記憶する
- ペグ法|数字や順序をフック(ペグ)にして情報を結び付ける
- リズム・語呂合わせ法|音やリズムを利用して覚えやすくする
これらの工夫を取り入れることで、学習効率が飛躍的に高まり、前向きな気持ちで勉強に臨めるようになります。
そして、さらに記憶力を高めたいなら、科学的根拠に基づいた実践的トレーニングである吉永式記憶術を試すのもおすすめです。
東大理三卒のギネス記録保持者のノウハウを組み合わせれば、記憶力を高めて成果を最大化できるでしょう。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
社会人・大人が勉強に集中できない理由と改善策
特に仕事や家庭の責任に追われる社会人は、精神的・身体的な疲労が蓄積しやすく、脳の集中回路がうまく働かなくなることがあります。
この状態が続くと「覚えられない自分」に焦りやストレスを感じ、結果的にモチベーションの低下や軽度のうつ症状に繋がることもあるのです。
- 仕事の疲労や長時間労働 → 睡眠を優先し、短時間の集中学習に切り替える
- 家事や育児による時間不足 → スキマ時間を活用し学習を細切れにする
- ストレスや不安による気持ちの乱れ → 運動や瞑想で心を整える
- 学習環境の不備(スマホや雑音) → 集中できる環境を整える
- 明確な目的や目標の欠如 → 具体的なゴールを設定しモチベーションを維持する
このように大人が直面する集中力の問題は、環境改善や習慣化によって大きく改善可能です。
日常生活に合わせた勉強法を工夫すれば、限られた時間でも効果的に学習を続けられるのです。
定着率アップ|勉強のやり方を見直すヒント
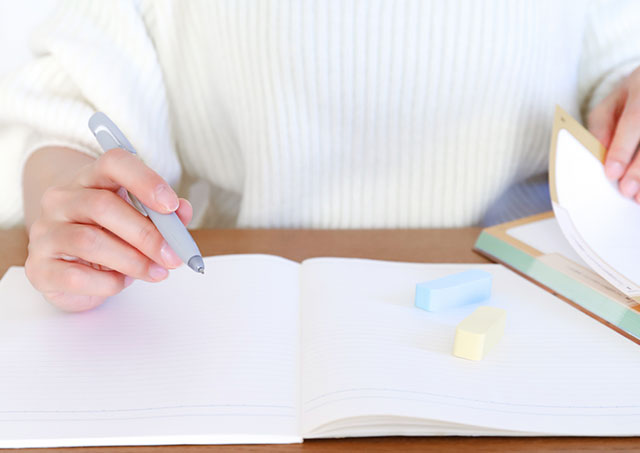
勉強していても「頭に入らない」と感じるときは、勉強法そのものが自分に合っていない可能性があります。
これは、記憶の定着に必要な脳の働き・集中のタイミング・行動の工夫が噛み合っていないことが原因です。
ここでは、「集中できない」「頭に入らない」状態から抜け出すために、今日から見直せる勉強のやり方を紹介します。
- 少しだけ難しいレベルから始める
- 朝など脳が冴えている時間帯に重要な学習を行う
- まずはできることから始めて行動のきっかけをつくる
それぞれ順番に解説します。
少しだけ難しいレベルから始める
勉強の内容は「簡単すぎず、難しすぎない」ちょうどよいレベルで取り組むことが効果的です。
脳は適度な負荷を与えられたときに最も活発に働き、理解や記憶が深まりやすくなる性質を持ちます。
簡単すぎると退屈になり、逆に難しすぎると挫折して学習意欲を失うリスクが高まります。
そのため現在のレベルより少し上の課題に挑戦し続けることが、成長を促す近道になるのです。
このように負荷の調整を意識することで、自然と学習の定着率を高めることができます。
朝など脳が冴えている時間帯に重要な学習を行う
学習の効率を高めるには、脳が最も活発に働く時間帯を活用して重要な勉強を行うことが重要です。
特に朝は睡眠で脳がリフレッシュされており、新しい情報を整理・吸収しやすい状態になっています。
夜遅くに勉強すると集中力が途切れやすく効率も低下するため、覚えたい内容は朝に取り組むのが効果的です。
朝には頭を使う学習が適しており、具体的には以下の内容がおすすめです。
- 数学や物理といった難解な問題演習
- 資格試験に向けた重要ポイントの確認
このように朝の時間を賢く使えば、理解度や記憶の定着が飛躍的に高まります。時間帯を意識するだけで、勉強の成果は大きく変わるのです。
まずはできることから始めて行動のきっかけをつくる
まずはできることから始めて行動のきっかけをつくることが大切です。
勉強を始められない原因の多くは「取りかかるまでの心理的なハードル」にあります。
難しい内容からいきなり取り組もうとすると脳が抵抗を示し、集中する前に挫折してしまうことも少なくありません。
そこで有効なのが「作業興奮」という脳の仕組みです。
簡単な作業や取り組みやすい内容を始めることで脳が活性化し、自然と集中状態に入りやすくなります。
例えば「とりあえず1問だけ解く」「5分だけ教科書を読む」といった小さな行動がスイッチとなり、その後の学習効率を高めます。
このように行動のハードルを下げて作業興奮を引き出せば、勉強を継続する力が格段に高まるのです。
勉強が頭に入らないことに関するよくある質問
勉強が頭に入らないことに関するよくある質問は以下の通りです。
勉強の記憶が定着しないときどうすればいい?
記憶が定着しないときは、インプットだけでなくアウトプットを重視することが重要です。
声に出して説明したり問題を解くことで、知識を呼び出す練習となり記憶が強化されます。
そのため復習を繰り返すことで、学んだ内容を長期記憶へ移し定着させることができるのです。
疲れていて勉強に集中できないときはどうする?
疲労が強いときに無理をすると効率が落ち、学習成果を得られず逆効果になることがあります。
まずは休養を取り、軽いストレッチや深呼吸で心身を整えてから再開するのが効果的です。
勉強中に眠気でまったく進まないときは、思い切って休み、翌朝に取り組む方が効果的な場合もあります。
短時間の学習から始めれば集中しやすく、継続にもつながり学習習慣を維持できるのです。
勉強が頭に入らない病気は?
勉強してもまったく頭に入らない状態が続く場合、うつ病やADHDなど、集中力や記憶力に影響を及ぼす病気が関係していることがあります。
特に以下のような症状がある場合は、単なる疲労ではなく精神的な不調が疑われます。
- 睡眠を取っても疲れが取れない
- 好きだったことにも興味が持てない
- 注意力が極端に続かない
- 何度も同じことを忘れてしまう
これらに心当たりがある場合は、生活習慣だけでの改善が難しい可能性が高く、専門機関への相談を検討しましょう。
精神科や心療内科では、症状の評価に加えて必要に応じた治療やアドバイスが受けられます。
早期対応が回復の鍵となるため、「少し違和感がある」段階での行動が非常に重要です。
30代・40代で勉強が頭に入らないときはどうする?
30代・40代は仕事や家庭での負担が大きく、集中できる時間が限られるのが現実です。
この年代では朝の学習やスキマ時間の活用など、効率を高める工夫が効果的になります。
小さな目標を積み重ねることで学習習慣を維持し、大人でも成果を出せるようになるのです。
まとめ|記憶に残らないのは“やり方”に原因あり

本記事では、勉強が頭に入らない原因と効果的な対処法について解説しました。
睡眠不足やストレス、環境の乱れは集中力を奪い、学習成果を大きく下げる要因となります。
記憶を定着させるにはアウトプットや復習が欠かせず、社会人や大人の場合は生活リズムに合わせた工夫も必要です。
日常に取り入れやすい習慣を意識すれば、学習効率を改善し成果につなげることができるでしょう。
実は、記憶力はトレーニングによって、何歳からでも高められることがわかっています。
「もっと記憶力を高めて勉強に活かしたい」という方には、「吉永式記憶術」もおすすめ。科学的根拠に基づいた実践的なトレーニング法で、初心者でも無理なく取り組めます。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い指導を通じて記憶力向上と目標達成をサポートしています。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。










