 キツネさん
キツネさん
「大豆って本当に記憶力に効果があるの?」
と感じていませんか?年齢に関係なく記憶力の低下は多くの人に共通する悩みです。
本記事では、大豆に含まれる成分が記憶力や脳機能に与える科学的効果と正しい摂り方を解説します。
食事で記憶力を維持したい学生、ビジネスパーソン、物忘れが多くなった高齢者の方に役立つ内容です。
脳の健康を守りたい方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
記憶力と大豆の関係とは?【基本メカニズム】

大豆は、記憶力や認知機能の維持に有益な成分を多く含んでいます。
その働きには科学的な根拠があり、継続的な摂取が脳の健康維持につながります。
- イソフラボン|抗酸化と神経保護
- レシチン|神経伝達を促進
- タンパク質|神経伝達物質の合成を支える
それぞれ順番に解説します。
イソフラボン|抗酸化と神経保護
大豆に含まれるイソフラボンは、記憶力や脳機能の維持に役立つ成分として知られています。
ただし、日本の大規模研究では、イソフラボンの摂取量が多い人ほど認知機能障害のリスクが1.51倍高かったと報告されました。
これは加齢や体質の影響も考えられ、摂取量が多ければ良いとは限らないといえます。
豆腐や納豆などの大豆食品は問題ないとされており、日常の食事では適量を心がけることが大切です。
参考:イソフラボン、大豆製品の摂取量と認知機能障害の関連について|がん対策研究所 予防関連プロジェクト
レシチン|神経伝達を促進
レシチンは脳の神経伝達に欠かせない栄養素で、記憶や学習能力の維持に深く関わっています。
体内で「コリン」に変わり、神経伝達物質アセチルコリンの材料として働くのです。
これにより脳内の情報伝達がスムーズになり、思考力や集中力の低下を防ぐ効果が期待されます。
レシチンは卵や大豆、レバーなどに含まれていますが、加熱で壊れやすいため、サプリメントで補う人もいます。
子どもから高齢者まで、年齢を問わず必要な成分といえるでしょう。
参考:脳を栄養したいなら、レシチンを試してみる必要があります。|バンコク病院
タンパク質|神経伝達物質の合成促進
大豆に含まれる植物性タンパク質は、神経伝達物質の合成に必要なアミノ酸の供給源となります。
特にセロトニンやドーパミンなど、感情や集中力に関わる物質の材料として働きます。
タンパク質は、脳の働きを支える基礎的な栄養素であり、精神の安定や学習能力の維持にも寄与します。
また、動物性より脂質が少ない点から、健康志向の人にも取り入れやすい特徴があります。
参考:低糖質・高タンパク質食生活で作業記憶能が低下-海馬の健康と食生活の関係を示唆-|群馬大学
大豆成分と記憶力の関係【科学的検証】

大豆に含まれる成分は、記憶力や認知機能にどのような影響を与えるのか。
科学的な研究によって、その可能性と注意点が少しずつ明らかになってきました。
- JPHC研究でわかった認知機能リスク低下
- イソフラボンの摂取量と脳機能の関係
- 納豆で認知症リスクが増える?
それぞれ順番に解説します。
JPHC研究でわかった女性の認知機能リスク低下
多目的コホート研究(JPHC Study)は、国立がん研究センターが行っている大規模な疫学調査です。
日本各地の住民約14万人を対象に、生活習慣(食事・運動・喫煙・飲酒など)と病気(がん、心臓病、認知症など)の関係を長期間追跡しています。
日本の大規模調査によると、大豆製品やイソフラボンの摂取量と認知症リスクには、全体として明確な関係は見られませんでした。
しかし、60歳未満の女性では、納豆をよく食べている人に認知症リスクの低下が見られました。
納豆に含まれるナットウキナーゼやポリアミンが脳の老化を防ぐ可能性があります。
記憶力を保ちたい女性の方は、納豆を適量取り入れることがひとつの手段となるでしょう。
参考:大豆製品摂取と認知症リスクとの関連|国立がん研究センター
イソフラボンの摂取量と脳機能の関係
イソフラボンは、大豆に多く含まれる栄養素で、脳の酸化を防ぎ記憶力をサポートする働きがあるとされています。
海外の研究では、1日100mg程度のイソフラボンを6週間〜6か月摂取すると、視覚記憶や判断力が改善したという結果も。
ただし、摂りすぎると効果が見られにくくなることもあるため、納豆や豆腐などを意識して食事に加えることで、脳機能の維持が期待できます。
日常生活の中で無理なく継続することが、記憶力強化につながるポイントです。
納豆で認知症リスクが増える?
一部では納豆は逆に認知症リスクを増やすのでは?と疑う人もいますが、そんなことはありません。
日本の大規模調査では、納豆をよく食べる60歳未満の女性において、認知症のリスクが約22%〜34%低いという結果が出ています。
これは、納豆に含まれるナットウキナーゼやポリアミンといった成分が、脳の老化を防ぐ働きをしている可能性があると考えられています。
研究では、摂取量が一定量まで増えることでリスク低下が見られますが、それ以上では効果が頭打ちになる可能性があります。
男性や大豆製品全般については、今のところ明確な関連性は確認されていないため、さらなる研究が必要です。
納豆は毎日の食事に無理なく取り入れられるため、記憶力を維持したい方におすすめです。
参考:大豆製品摂取と認知症リスクとの関連|国立がん研究センター
大豆ペプチドで記憶力を強化【注目成分】

大豆を加水分解して得られる大豆ペプチドには、脳の働きを助ける成分が豊富に含まれています。
最近では記憶力の維持や集中力の向上に役立つ可能性があるとして、幅広い年代に注目されているのです。
- 大豆ペプチドが記憶力に与える影響
- 認知症予防として注目される理由
- 若年層の学習・集中力改善にも有効?
それぞれ順番に解説します。
大豆ペプチドが記憶力に与える影響
大豆ペプチドは脳の神経伝達と記憶力向上に期待できる成分です。
日本の高齢者対象ランダム化比較試験では、週1回4gのペプチド摂取(約20〜30gの乾燥大豆に相当)を3か月続けると、記憶スコアが平均0.3ポイント上昇しました(認知機能テストACE‑R使用)。
また、若い健常者(20~22歳)による二重盲検試験では、1日8g・2週間の摂取後に注意力と語彙記憶が改善したとの報告があります。
さらに、マウスでは血液脳関門を通る大豆由来ジペプチド(Tyr‑Pro)が、16日間・100mg/kg投与後に作業記憶を有意に改善したという結果も。
このように、複数のエビデンスによって、大豆ペプチドの記憶力や集中力への効果が支持されています。
認知症予防として注目される理由
マウスを使った実験では、大豆ペプチドの摂取によって空間記憶テストの成績が向上し、神経育成因子(NGF・BDNF・NT‑3)の増加が確認されました。
さらに、アルツハイマー型認知症モデルのマウスでは、ジペプチド(Tyr‑Pro)を口から摂取することで、短期記憶と長期記憶の障害が改善されたと報告されています。
以上の研究結果を踏まえると、大豆ペプチドは脳神経細胞の保護と記憶機能の維持に積極的な効果をもたらす可能性があります。
将来の認知症予防を意識する方にとって、有望な栄養成分といえるでしょう。
若年層の学習・集中力改善にも有効?
大豆ペプチドは若年層の集中力や記憶力にも良い影響があると期待されています。
日本の研究では、大学生に大豆ペプチド(2.5~4.0g)を含む朝食を提供したところ、脳波のα波が増え、精神的なリラックスや集中の維持に役立つと報告されました。
また、高齢マウスを使った実験では、大豆ペプチドの摂取により空間記憶の成績が向上し、学習能力の低下を抑える効果が確認されています。
これらの結果から、勉強や仕事で集中力を求める若い世代にも、大豆ペプチドは取り入れやすく、日常生活の支えとなる栄養素といえるでしょう。
参考:朝食時大豆ペプチド摂取がその後のエネルギー代謝および血糖値に及ぼす影響|千葉大学
記憶力アップのための大豆の取り入れ方【摂取方法】

記憶力アップのために大豆を取り入れる方法は、日常の食生活に無理なく組み込める点が魅力です。
大豆製品は種類によって栄養や吸収のされ方が異なるため、目的に応じた摂取が大切になります。
- 納豆・豆腐・豆乳などの違いとおすすめの食べ方
- サプリメント利用の注意点
- 過剰摂取による男性ホルモンへの影響
それぞれ順番に解説します。
納豆・豆腐・豆乳などの違いとおすすめの食べ方
大豆製品は発酵や加工の有無によって、体への吸収性や機能が変わってきます。
主な大豆製品の特徴と、記憶力への影響は以下の通り。
| 製品名 | 主な特徴 | 記憶力への影響 |
| 納豆 | 発酵食品でナットウキナーゼやビタミンKが豊富 | ナットウキナーゼが血流改善に寄与する可能性 |
| 豆腐 | 水分が多く消化しやすい。加熱料理にも使いやすい | タンパク質源として脳の栄養補給に役立つ |
| 豆乳 | 液体で吸収が早く、食欲がない朝でも取りやすい | イソフラボンやタンパク質を手軽に摂取可能 |
| 大豆ペプチドサプリ | 大豆から抽出したペプチド。吸収効率が高い | 神経伝達物質アセチルコリンの分泌促進作用 |
| きな粉 | 大豆を粉砕した粉末。食物繊維やミネラルも含む | 大豆成分全体が含まれ、抗酸化作用にも期待 |
次に、各製品のおすすめの食べ方・摂取方法を紹介します。
- 朝食にご飯と一緒に
- 刻みネギや卵を加えて風味アップ
- 納豆チャーハンや納豆巻きにアレンジ
- 冷奴にして手軽に食べる
- 味噌汁や鍋料理に入れて温かく
- 豆腐ハンバーグなどで主菜に活用
- そのまま飲む(無調整がおすすめ)
- スムージーに混ぜて栄養バランス強化
- 豆乳スープやグラタンにアレンジ
- パッケージの摂取目安に従って毎日続ける
- 食事と合わせてタイミングを決めて習慣化
- 運動後や就寝前など吸収が高まるタイミングに
- ヨーグルトや牛乳に混ぜる
- お餅やトーストにまぶす
- スムージーに加えて香ばしさをプラス
どの食品も日常生活に取り入れやすく、継続的な摂取が記憶力維持をサポートする鍵となります。
いずれも継続して摂ることで、記憶力向上への良い影響をにつながるでしょう。
サプリメント利用の注意点
大豆由来成分を手軽に補えるサプリメントは、食事だけでは不足しがちな栄養を補う手段として役立ちます。
しかし、成分の特性や摂取量に注意しないと、かえって健康リスクを招くことも。
- イソフラボンの摂りすぎに注意
- ホルモン作用がある成分が含まれる
- 長期間の連用はリスクも考慮する
- 成分表示と用法をよく確認する
- アレルギー体質の人は慎重に選ぶ
- 医薬品との併用は医師に相談
サプリメントはあくまで食事の補完として活用すべきものであり、栄養摂取の中心には据えないことが重要です。
過剰摂取による男性ホルモンへの影響
大豆イソフラボンは、植物由来の成分でエストロゲンに似た作用を持ちます。
一部では、過剰摂取による男性ホルモンへの影響が懸念されていますが、2021年の臨床研究では、40件以上のデータを解析した結果、テストステロンやエストラジオールの値に有意な変化は見られませんでした。
このことから、通常の食事量での摂取では、男性ホルモンへの影響はないとされています。
ただし、極端に多量の摂取を長期間続けることは避け、パッケージ表示などを確認しながら適量を守ることが大切です。
参考:大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A|農林水産省「大豆イソフラボンの安全性評価について(第 25 回会合修正案) 」
記憶力に関するよくある悩み
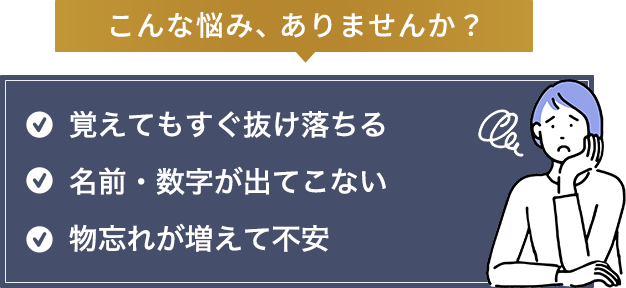
覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。
それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。
無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
大豆と合わせて効果的に記憶力を高める方法

大豆の記憶力向上効果を高めるには、生活習慣の工夫も欠かせません。
以下のような方法を意識すると、相乗効果が期待できます。
- 有酸素運動を週に2〜3回行う
- 睡眠時間を毎日7時間以上確保する
- 青魚やクルミなどの良質な脂質も摂取する
- 決まった時間に食事・起床・就寝を守る
大豆製品を継続的に取り入れると、神経伝達物質の生成が促進され、脳の情報処理効率が向上しやすくなります。
また、記憶術と組み合わせることで、大豆の栄養による脳機能の土台強化と、実践的な記憶戦略の相乗効果が期待できます。
よくある質問|記憶力向上に大豆は本当に役立つ?
毎日納豆を食べると記憶力アップにつながる?
納豆にはイソフラボンやレシチンなど、脳機能をサポートする栄養素が豊富に含まれています。
これらは神経伝達の改善や抗酸化作用によって記憶力の低下を防ぐとされています。
毎日1パック程度で十分な摂取が可能で、継続することで効果が期待できるでしょう。
ただし、過剰に摂るとホルモンバランスに影響を与える場合もあるため、適量を守ることが大切です。
大豆アレルギーでも代替できる食品は?
大豆アレルギーの人は、同様の栄養成分を持つ他の食品を選ぶことが重要です。
例えば、クルミやアーモンドにはオメガ3脂肪酸やビタミンEが含まれており、脳の健康に寄与します。
また、卵黄や魚の脂にもレシチンやDHAが豊富に含まれているため、無理なく置き換えが可能です。
アレルギーの程度に応じて、医師や管理栄養士と相談しながら食品を選ぶと安心でしょう。
まとめ|大豆を日常に取り入れて賢く記憶力アップ!

本記事では、大豆に含まれる成分が記憶力や認知機能に与える影響、摂取方法や注意点について解説しました。
イソフラボンやレシチン、大豆ペプチドなどは、脳の神経伝達や抗酸化作用に関与し、記憶力の維持に役立ちます。
納豆や豆腐など身近な食品から取り入れることで、無理なく継続が可能です。
生活習慣の見直しとあわせて、大豆を賢く取り入れ、日々の集中力や学習効率向上に活用してみましょう。
あわせて記憶術も取り入れたい方には、Wonder Educationの記憶術講座がおすすめです。
誰でも実践できる再現性の高い指導で、記憶力の向上と目標達成をしっかり支援しています。
「もっと効率よく覚えられるようになりたい」と感じた方には、記憶力を高めるトレーニングの活用もおすすめです。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールをお探しの方は、株式会社Wonder Educationにぜひご相談ください。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。












