 キツネさん
キツネさん
「やる気はあるのに気が散ってしまう!」
そんな悩みを抱えていませんか?自宅学習は誘惑が多く、思うように集中できないこともありますよね。
この記事では、すぐ実践できる集中力アップの方法や、年齢・時間帯に応じた学習術を解説します。
中学生や高校生はもちろん、サポートしたい親御さんや、勉強習慣を見直したい社会人にも役立つ内容です。
もくじ
勉強に集中する方法|今すぐできる集中力アップのコツ8選

集中できずにダラダラしたり、やる気が続かないと悩んでいませんか?
集中力を高めるには、ちょっとした工夫と環境づくりが効果的です。
- スマホは手の届かない場所に置く
- 勉強机を整理整頓する
- 簡単なウォーミングアップ問題から始める
- ポモドーロテクニックで時間管理する
- 短期目標を立てて進捗を見える化する
- 集中しやすい服装に着替える
- 朝のゴールデンタイムを活用する
それぞれ順番に解説しますので、試しやすいものから実践してみましょう。
① スマホは手の届かない場所に置く
スマホが視界にあるだけで集中力が下がるのは、「視覚的注意分散効果」によるものです。たとえ操作していなくても、脳は無意識に反応してしまい、学習効率が落ちる原因になります。
そのため、スマホを引き出しや別室に置いたうえで、通知を切っておくと安心でしょう。
手元から物理的に離すことで、気が散らず集中状態を保ちやすくなります。
② 勉強机を整理整頓する
視界に入る情報量が多いと、脳はその分処理にエネルギーを使い、集中力が削がれます。
机の上に必要のない書類や雑貨、飲み物などがある場合は、一度すべて取り除いてみてください。
文房具や教材を定位置に揃えておくだけで、学習の導入がスムーズになります。
環境の整理整頓は、集中できる状態を保つための土台になるため、日常的に片付けをルール化すると良いでしょう。
③ 簡単なウォーミングアップ問題から始める
勉強を始める際、いきなり難問に挑むと気持ちが重くなり、やる気を失いやすくなります。
そこで、最初の5〜10分を使って簡単な計算や漢字練習、単語の復習など、軽い課題に取り組むことが効果的です。
そうしているうちに、脳が徐々に学習モードに移行しやすくなり、その後の学習効率も向上します。
この習慣は集中力を高めるきっかけにもなり、習慣化すれば、学習に自然とメリハリが生まれます。
④ ポモドーロテクニックで時間管理する
ポモドーロテクニックは、25分間集中して作業し、5分間の休憩を取るという時間管理法です。
このサイクルを繰り返すことで、集中力の持続が難しい人でも無理なく勉強に取り組めます。
時間に区切りがあることで「あと少し頑張ろう」という気持ちが生まれ、途中で気が散ることも減るのです。
また、時間感覚を磨く習慣がつけば、勉強スタイルにも自然とリズムが生まれます。
⑤ 短期目標を立てて進捗を見える化する
大きな目標だけで勉強を進めると、達成までの距離に気持ちが折れてしまいがちです。
そこで、年単位、月単位と合わせて1日単位での小さな目標を立てると、達成感を得やすくなります。
さらにチェックリストやタイマーを使えば、進捗状況が一目でわかり、やる気の維持にも役立ちます。
自分に合った目標設定と見える化を習慣にすれば、学習の効率も高まるでしょう。
⑥ 集中しやすい服装に着替える
自宅での勉強でも、部屋着やパジャマのままだと気持ちの切り替えができません。
そこで、勉強する前に軽く外出できるような服に着替えると、意識が引き締まり集中モードに入りやすくなります。
体にフィットしすぎず動きやすい服を選ぶと、長時間座っていてもストレスを感じにくくなります。
服装は気分と行動を変えるきっかけになるため、集中したいときのルーティンとして取り入れるのがおすすめです。
⑦ 朝のゴールデンタイムを活用する
朝起きてからの2〜3時間は、脳が最もクリアな状態にあるため、ゴールデンタイムと呼ばれています。
この時間帯に勉強をすると、理解力や記憶力が高まりやすく、特に数学のような論理的思考を要する学習に向いているとされています。
朝型の生活に少しずつ移行することで、時間の使い方や学習効率が大きく変わります。
関連記事:【朝?夜?】暗記に最適な時間帯おすすめ3選 | 勉強に効果的な方法も
⑧ 水分補給をこまめに行う
水分不足は集中力や判断力を低下させる要因の一つです。
勉強中はのどが渇いていなくても、こまめに水やお茶を飲むことが良いでしょう。
飲み物を机の上に置いておけば、立ち上がる手間もなく気軽に水分補給ができます。
脳の働きを保つためにも、習慣として取り入れるとパフォーマンスの維持に効果的です。
関連記事:集中できる飲み物7選!おすすめの定番品から意外なものまでご紹介
なぜ勉強の集中力が続かないのか?原因と心理的背景
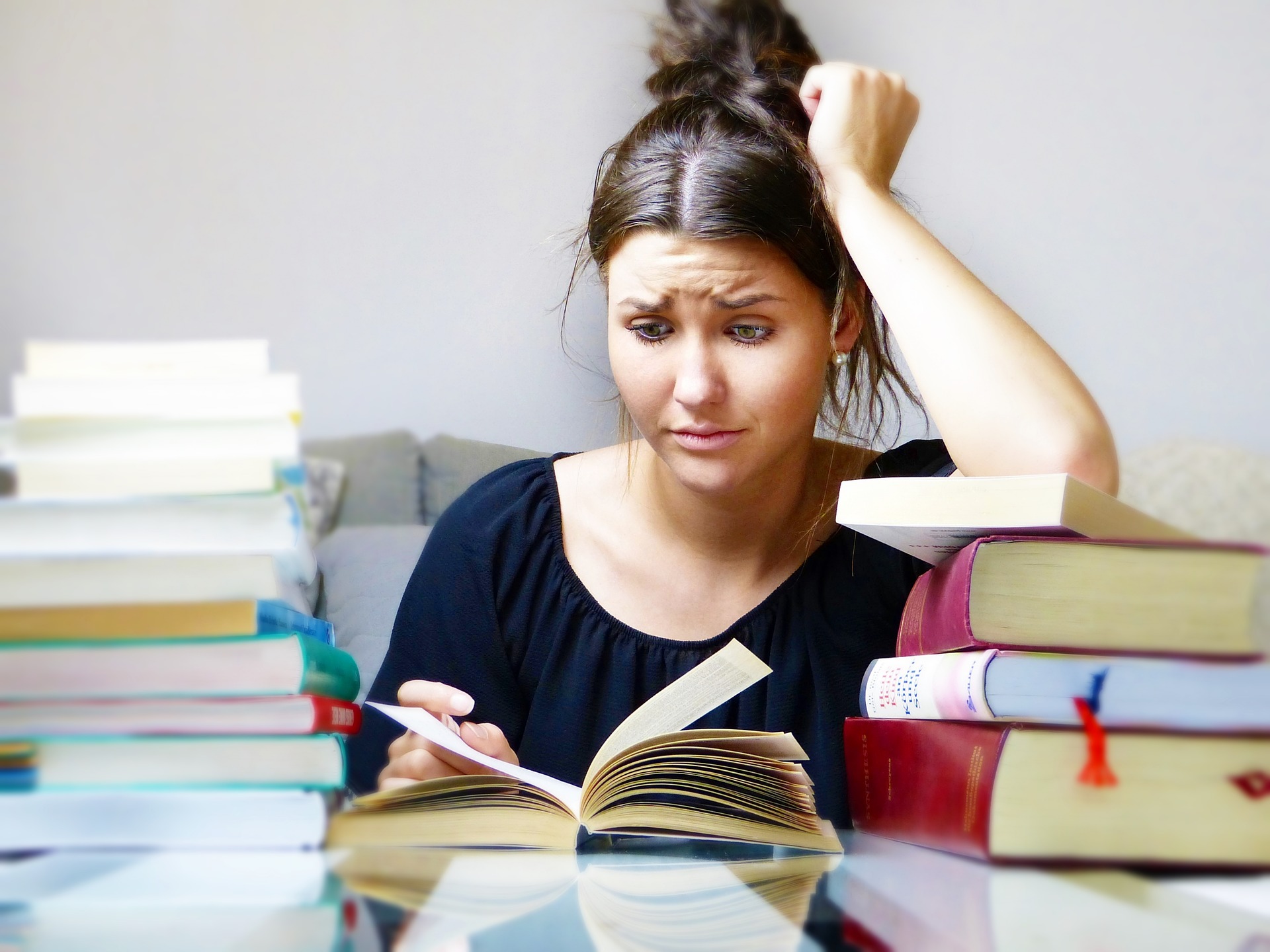
集中しようと思っても気が散ったり、机に向かっても全然はかどらないと感じた経験は誰しもありますね。
集中力が続かないのは、単なる意志の弱さではなく、心理的・環境的な原因が潜んでいる場合があります。
- スマホや通知に気を取られる
- 睡眠不足で脳が疲れている
- 勉強環境が雑音(音楽)で乱される
- 部屋が散らかって集中できない
- 姿勢が悪く疲れやすい
- 勉強内容に興味が持てない
- 長時間の勉強で集中が切れる
- 目標が曖昧でやる気が出ない
- 空腹や満腹で集中しづらい
- ストレスや不安がたまっている
- 休憩を取らず集中力が消耗する
それぞれ順番に改善方法も含めて解説しますので、当てはまる項目があれば、対策してみてください。
① スマホや通知に気を取られる
スマートフォンは、集中を奪う最も強力な誘惑の一つです。
SNSの通知やメッセージが来るたびに注意がそちらに向いてしまい、勉強に戻るのに時間がかかることもあります。
一度気がそれると、元の集中状態に戻すには20分以上かかるともいわれています。
勉強中は通知を切るか、スマホ自体を見えない場所に置くなどの対策が必要でしょう。
② 睡眠不足で脳が疲れている
寝不足の状態では、脳の働きが低下し、集中力や記憶力に悪影響を及ぼします。
どれだけ頑張ろうとしても、そもそも頭がぼんやりしていては効率的に学習することはできません。
慢性的な睡眠不足が続けば、感情のコントロールも難しくなり、やる気の低下にもつながります。
勉強の質を保つためにも、まずは十分な睡眠を確保することが大切です。
メリハリを付けたり、快眠グッズを活用することで、日中の集中力も維持しやすくなるでしょう。
③ 勉強環境が雑音(音楽)で乱される
一見集中しているようでも、歌詞付きの音楽や話し声などは脳の処理を妨げ、無意識のうちに注意力を奪います。
特に歌詞のある音楽やテレビの音などは、脳が無意識に処理しようとするため、集中を妨げる原因になります。
静かな場所やカフェなどのホワイトノイズなど、作業に適した音環境を選ぶことが必要でしょう。
音の影響を軽く見ることなく、環境整備にも意識を向けることが重要です。
勉強中は音楽は避けたほうが無難ですが、休憩時間に好きな音楽を聞くとリフレッシュになります。
④ 部屋が散らかって集中できない
余計な物が視界に入ると、それだけで脳の処理が増え、注意力が下がります。スッキリした机は集中力維持に不可欠です。
物が散乱した空間では落ち着いて勉強に取り組むことが難しく、集中が長続きしません。
「何から手をつけよう」と思った瞬間に、気持ちが途切れることもあります。
勉強前に机の上だけでも整理整頓しておくと、集中しやすくなるでしょう。
毎日少しずつ片づける習慣を持つことが、学習効率の向上にもつながります。
⑤ 姿勢が悪く疲れやすい
猫背や前かがみの姿勢で勉強を続けていると、首や腰に負担がかかり、体がすぐに疲れてしまいます。
身体の不快感が気になって、集中が保てなくなることも少なくありません。
また、姿勢が悪いと呼吸が浅くなり、脳への酸素供給も不十分になります。
集中力だけでなく、思考のキレも鈍くなる可能性もあるため、椅子や机の高さを見直し、正しい姿勢を意識することが大切です。
- 椅子の座面は、足裏が床につき、膝が90度に曲がる高さ
- 机の高さは、椅子に座った状態で肘が90度に曲がる位置
- 背もたれは腰をしっかり支える形状のものを選ぶ
- 長時間使用しても疲れにくいクッション性と通気性を備えた椅子が望ましい
長時間使うものなので、心地よい状態を維持できるよう工夫しましょう。
⑥ 勉強内容に興味が持てない
興味の持てない内容を学ぶことは、集中力の維持にとって非常に大きな壁になります。
「なぜこれを学ぶ必要があるのか」が見えないまま進めても、モチベーションは上がりません。
少しでも関心を持てるように、具体的な活用例や将来へのつながりを探してみることが効果的です。
関連する動画や実例に触れるだけでも、理解しやすくなることがあります。
自分なりに意味を見つける工夫が、集中力を支えるきっかけになるでしょう。
⑦ 長時間の勉強で集中が切れる
長時間ぶっ通しで勉強を続けると、集中力は確実に低下していきます。
脳が疲れると判断力や記憶力も鈍くなり、効率が悪化します。
そのため、適切に休憩をはさみながら、集中力を回復させることが大切です。
以下のようなポイントを意識すると、勉強の質を保ちやすくなります。
- 脳の疲労を感じたら、5〜10分の休憩をとる
- 25分集中+5分休憩の「ポモドーロ・テクニック」を取り入れる
- 休憩中はスマホを見ずに軽いストレッチや深呼吸を行う
- 長時間勉強する日でも、1〜2時間ごとに15分のリセットタイムを設ける
無理に続けるよりも、リズムある学習の方が集中力を長く保てます。
計画的な休憩が結果的に効率を上げる鍵になるでしょう。
⑧ 目標が曖昧でやる気が出ない
目標が具体的でないと、何のために勉強しているのかがぼやけてしまい、集中しにくくなります。
「とりあえずやる」という姿勢では、モチベーションを保つことが難しくなりがちです。
「何を(問題や課題)、いつまでに(期限)、どうしたいか(点数など)」を明確にすると、学習に対する姿勢が変わってきます。
短期目標と長期目標を両方設定することで、行動に方向性が生まれます。
目標を言語化し、定期的に見直す習慣をつけると、やる気の維持にもつながるでしょう。
⑨ 空腹や満腹で集中しづらい
空腹の状態では、血糖値が低下して脳の働きが鈍くなり、注意力や判断力が下がってしまいます。
一方で、満腹のときは消化にエネルギーが使われ、眠気を感じやすくなり集中が続きません。
勉強前には、腹八分目を意識した食事をとることがパフォーマンスの維持につながります。
糖質だけでなく、たんぱく質やビタミンを含むバランスの良い軽食が理想的です。
空腹と満腹、どちらも避けることで、安定した集中力が保ちやすくなります。
⑩ ストレスや不安がたまっている
心にストレスや不安を抱えたままでは、脳がそちらに意識を奪われてしまい、勉強に集中できません。
「ちゃんとやらなければ」と思うほどプレッシャーが増し、逆に手が止まってしまうこともあります。
感情を抱え込まず、紙に書き出す、誰かに話すなどの方法で外に出すことが効果的です。
深呼吸やストレッチなどで身体から緊張をほぐすのも有効な手段になります。
また、紙に書き出すことで頭が整理され、集中力が戻りやすくなります。心を整えることが、学習の第一歩です。
⑪ 休憩を取らず集中力が消耗する
長時間休憩を取らずに勉強を続けると、脳が疲弊し、集中力が急激に低下していきます。
短時間の休憩を挟むことで、脳の疲れをリセットし、再び集中モードに入りやすくなるのです。
休憩中はスマホを見るよりも、軽く体を動かしたり、目を閉じたり瞑想する方が効果的です。
集中力を長く保つには、メリハリのある勉強リズムをつくることが欠かせません。
年齢別|勉強に集中する方法
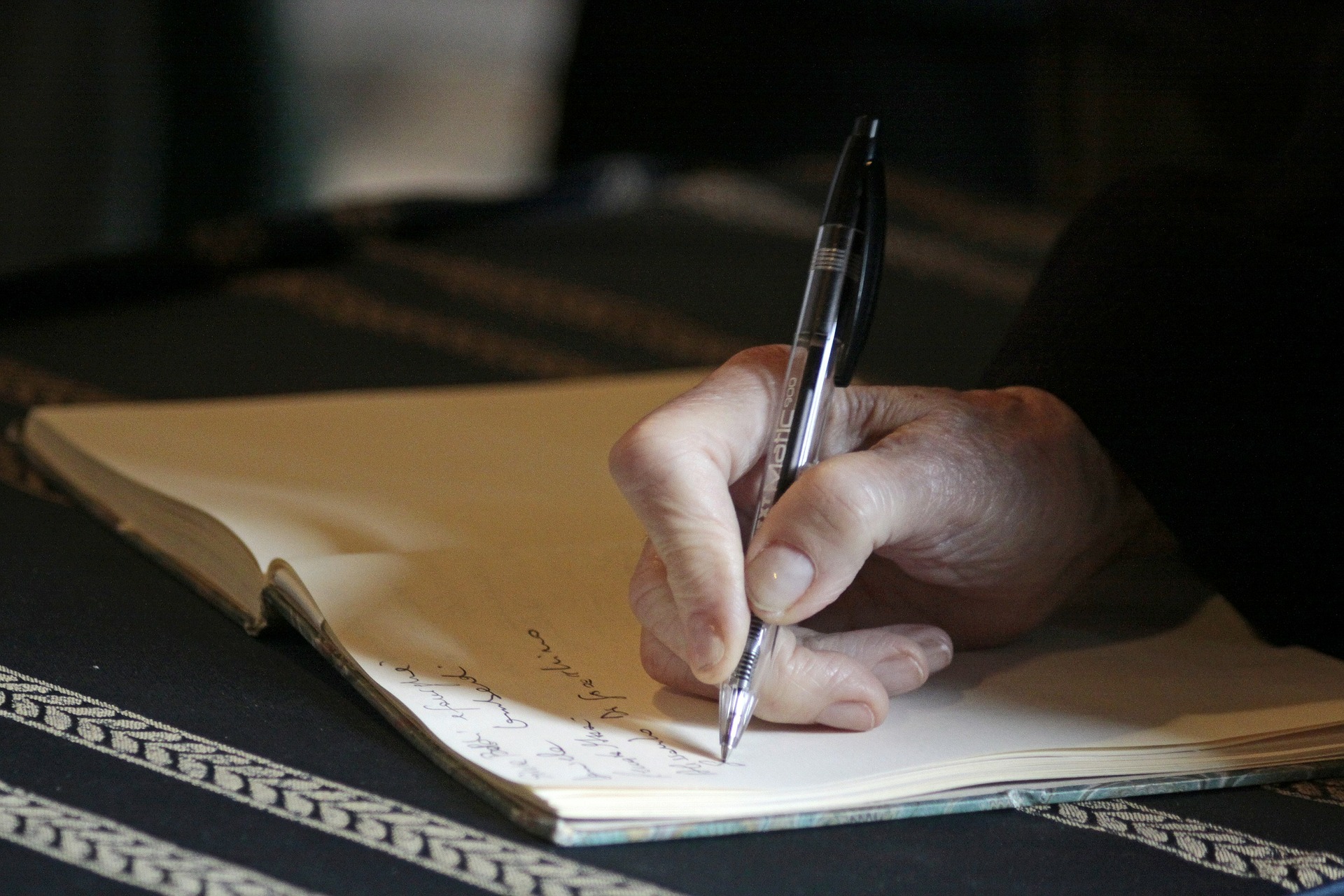
幼い子どもの場合、親が学びをサポートするケースも多く、集中力を維持するのに大変な思いをするケースもあるでしょう。
年齢によって最適な集中法は異なるため、子どもや学生が安心して学べる環境を整えるのが望ましいです。
年齢や学年別の集中力の維持方法について以下の通り解説します。
- 小学生が勉強に集中するコツ
- 中学生におすすめの集中力維持法
- 高校生向け受験勉強時の集中対策
なにか一つでも実践できるものがあれば、ぜひ試してみてください。
小学生が勉強に集中するコツ
小学生の集中力は持続しにくいため、「楽しく学ぶ仕掛け」と「親の関わり」がカギになります。
学年に応じた集中時間と、環境づくりの工夫を組み合わせることで、学習習慣が自然と身につきます。
- 集中時間は「学年+1分」が目安。
- タイマーで短時間に区切って学習する。
- 勉強後はすぐに褒めて達成感を与える。
- 視界から余計なものを外して環境を整える。
- 楽しめる教材で学ぶ意欲を引き出す。
短い時間で集中を積み重ね、親がそっと見守りながらポジティブな声かけをすることで、小学生でも学習習慣が自然と身につきやすくなります。
中学生におすすめの集中力維持法
中学生になると勉強内容が高度になり、集中を維持する工夫が必要になってきます。
特に「時間管理」と「環境整備」に注力すると効果的です。
自己管理力が高まると学習の効率も上がって、成績アップにもつながります。
- 45分勉強+5分休憩の繰り返しが理想。
- タイマーで集中のリズムを作る。
- 勉強の時間帯と場所を決めて習慣化する。
- スマホやゲームを視界から外す。
- 勉強前に深呼吸やストレッチを行う。
これらの方法を日常に取り入れると、集中力の波をコントロールしやすくなります。
継続することで自然と習慣化され、学ぶ姿勢が定着しやすくなっていくでしょう。
高校生向け受験勉強時の集中対策
高校生は受験に向けて学習量が大幅に増えるため、長時間の勉強でも集中力を維持できるかどうかが成果を左右します。
限られた時間を有効に使うには、目の前の課題をただこなすのではなく、目標を明確に設定し、それに基づいた計画的な学習を進めることが求められます。
「今日はここまでやる」と決めて達成感を積み重ねることで、集中力が持続しやすくなり、意欲の低下も防げるでしょう。
また、進捗を視覚的に整理し、見える形で管理する習慣をつければ、自分の成長を実感しながら勉強に取り組めるようになります。
- 長期・中期・短期の目標を立てる
- マインドマップなどで学習内容を整理する
- 模試や過去問を活用して実力を確認する
- スマホは別室に置くなど物理的に遠ざける
- 睡眠や食事のリズムを整えて体調を安定させる
受験期を乗り越えるには、単に根性で頑張るのではなく、自分を管理する力と効率的な集中の工夫を日常に取り入れていく姿勢が大切です。
時間帯別|勉強に集中するのに適したスケジュール

勉強の成果を高めるには、時間帯ごとの脳の働きに合わせて学習内容を変えることが有効です。
集中しやすい時間帯に思考力が必要な科目を、疲れてきた時間には軽めの復習を行うと、学習効率が上がります。
生活リズムに合わせて、無理なく続けられるスケジュールを組むことが大切です。
- 朝|数学などの思考力を使う学習
- 昼|復習や問題演習で定着を図る・眠ければ昼寝を
- 夜|軽めの復習や記憶ものと翌日の計画・準備
それぞれ順番に解説しますので、日々の学習に取り入れてみてください。
朝|数学などの思考力を使う学習
朝は脳が最もクリアに働く時間帯とされており、集中力や判断力が高まります。
この時間に数学や理科など、論理的思考や計算を要する科目に取り組むと、理解のスピードが上がりやすくなります。
朝イチは脳が少し働きにくいため易しい問題を解くことで、徐々に脳が働いてきます。
朝から活動することで体内リズムが整い、その日1日の学習全体に好影響を与える可能性もあります。
夜型生活の人は、朝型のリズムに少しずつ切り替えていく工夫が必要ですが、朝型メリットは計り知れません。
時間の使い方を改善したい人にとって、朝の学習は大きな武器となるでしょう。
昼|復習や問題演習で定着を図る・眠ければ昼寝を
昼は食後の眠気で集中力が低下しやすい時間ですが、復習や演習を取り入れることで記憶の定着が期待できます。
特に、午前中に学んだ内容を問題演習や簡単なテスト形式で振り返ると、知識が定着しやすくなります。
昼食後に強い眠気を感じる場合は、15〜20分の短い仮眠で脳をリセットすると効果的です。
無理に我慢するより、一度休んでから取り組んだ方が集中力は長続きします。
自分の体調や生活リズムに応じて工夫を行うのがポイントです。
夜|軽めの復習や記憶ものと翌日の計画・準備
夜は脳が疲れてきているため、あまり負荷の高い勉強は避けた方が良いでしょう。
この時間には、英単語や歴史の用語暗記など、反復で覚えるタイプの学習が向いています。
また、1日の学習内容を振り返ったり、翌日の予定や目標をメモしておくと、翌朝のスタートがスムーズになります。
就寝前に画面を長く見続けると睡眠に悪影響を及ぼすため、紙のノートや手帳を使うのが理想です。
心を落ち着けて寝る前の時間を過ごすことが、次の日の集中力にもつながります。
どうしても勉強に集中できない場合の対処方法
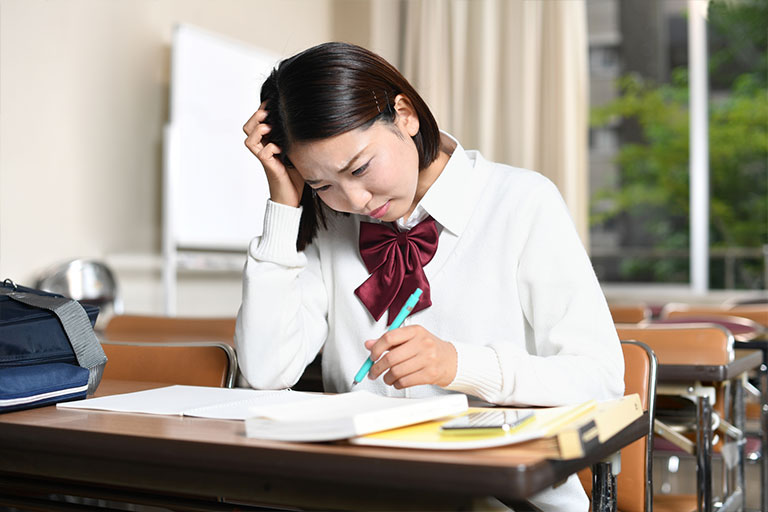
努力しても集中できない日は、環境や体調を整える工夫が大切です。無理をせず、視点を変えてみましょう。
集中できない場合の対処法は以下の通り。
- 軽い運動やストレッチでリフレッシュ
- エネルギー不足なら軽めに糖分を摂取する
- 短時間の仮眠で脳をリセット
- 深呼吸や瞑想で心を整える
- 友人・知人と一緒に勉強する
- カフェで勉強する
それぞれ順番に解説しますので、気になる方法があれば試してみてください。
軽い運動やストレッチでリフレッシュ
ずっと座っていると血行が悪くなり、脳への酸素供給も減ります。
集中力が落ちたと感じたら、立ち上がって軽く体を動かすだけでもリフレッシュできます。
ストレッチや軽いウォーキングは、思考を整理する時間にもなり、再び机に向かう意欲を取り戻せます。
数分でも十分な効果があるため、勉強に行き詰まったときの習慣として取り入れるとよいでしょう。
日常的に体を動かす習慣が集中力の持続にもつながります。
エネルギー不足なら軽めに糖分を摂取する
長時間の勉強では、脳のエネルギー源であるブドウ糖が消費されていきます。
空腹を感じたときや頭がぼんやりする場合は、少量の糖分を補給するのが効果的です。
チョコやドライフルーツなど、手軽に摂れるものを準備しておくと安心できます。
ただし、食べ過ぎると眠気を引き起こすこともあるため、あくまで軽くつまむ程度にとどめてください。
食べるタイミングも意識することで、集中力を効率的に回復させることができます。
短時間の仮眠で脳をリセット
疲労がたまっていると、どれだけ努力しても集中できません。
そんなときは15〜20分程度の短い仮眠を取ることで、脳がリセットされ再び集中しやすくなります。
長く眠ってしまうと逆に頭がぼんやりすることもあるため、タイマーを使って制限時間を設けるのがおすすめです。
横になるのが難しい場合は、机にうつ伏せになるだけでも効果はあります。
仮眠後には、軽く体を動かしてから再スタートすると、さらに効果が高まるでしょう。
深呼吸や瞑想で心を整える
不安や焦りなど、心の状態が乱れていると集中するのは難しくなります。
深呼吸や簡単な瞑想を取り入れると、自律神経が整い、気持ちが落ち着いてきます。
目を閉じて数分間、呼吸に意識を向けるだけでも、リラックス効果が得られるでしょう。
心を整える習慣は、集中力の土台をつくるうえで非常に重要です。
勉強前や休憩中などに取り入れ、日常のルーティンとして定着させるとよいです。
友人・知人と一緒に勉強する
一人で集中できないときは、他人の目がある環境に身を置くのも一つの方法です。
友人や知人と一緒に勉強することで、互いに刺激を受け、やる気が引き出されることがあります。
「見られている」意識が働くため、だらけにくくなるのもメリットです。
ただし、おしゃべりが中心にならないように、お互いのルールを事前に決めておくと良い雰囲気が保てます。
誰かと共に頑張ることが、集中へのきっかけとなることもあるでしょう。
日頃、家で勉強できないなと感じているなら、積極的に外で勉強してみましょう。
カフェで勉強する
家では集中できない場合、環境を変えてみることも効果的です。
特にカフェなどの適度な雑音がある場所は「適応的ノイズ」と呼ばれ、集中力を高めるとされています。
周囲の人も作業している空間では、自分も自然と集中モードに入りやすくなります。
ただし、混雑した時間帯や長居しすぎには注意が必要です。
客観的に家と比べて集中できているかを確認し、効率悪いと感じたらやめましょう。
場所を変えることで気分転換にもなり、新たな気持ちで勉強を再開しやすくなります。
よくある質問(Q&A)
集中力に関する疑問や不安を感じることは誰にでもあります。
ここでは、勉強中によく聞かれる質問とその対処法について紹介します。
勉強中に音楽を聴いてもいい?
歌詞のある音楽は言語処理と重なりやすく、基本的には勉強の妨げになりがちです。
一方で、環境音やクラシック音楽などは集中を助ける場合もあります。
自分にとって気が散るかどうかを判断基準にするのが賢明です。
集中力が切れたときのおすすめの休憩法は?
脳をリフレッシュさせるには、勉強と関係のない行動を取り入れるのが効果的です。
スマホを見るより、外の空気を吸う方が頭がすっきりします。
5~10分程度の休憩で、再び集中できる状態に戻しやすくなります。
お菓子やガムは集中力に影響する?
甘いものは一時的に脳を活性化させますが、食べすぎには注意が必要です。
ブドウ糖やチョコレートなどは、勉強前に少量摂ると集中しやすくなる場合があります。
また、ガムを噛む行為には覚醒効果があるとの研究もあります。
摂取のタイミングと量に気を配って取り入れてみてください。
まとめ|環境を整えて勉強に集中しよう

本記事では、集中力を高める具体的な方法や、集中できない原因とその対策について解説しました。
スマホの扱い方や時間管理の工夫、年齢や時間帯に応じた勉強法などを取り入れることで、学習の質を大きく改善できます。
自分に合った環境を整え、小さな工夫を積み重ねることで、集中力は自然と高まります。
集中を継続できる工夫を、ぜひ日常に取り入れてみましょう。
「勉強しても覚えられない」「集中力が続かない」と感じているなら、記憶の仕組みを理解することから始めてみるのも一つの方法です。
「もっと効率よく覚えられるようになりたい」と感じた方には、記憶力を高めるトレーニングの活用もおすすめです。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
Wonder Educationでは再現性の高い指導で、記憶力向上とそれによる目的の達成をサポートしていますので、ご興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせください。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。




