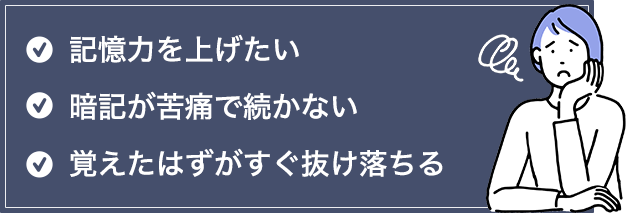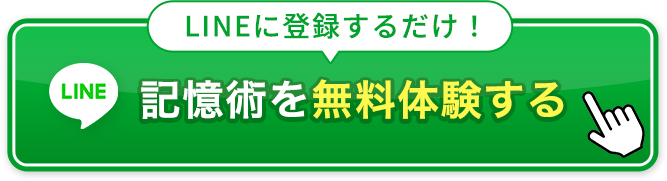キツネさん
キツネさん
覚えられないもどかしさに、やる気をなくしてしまうこともありますよね。
実は記憶術を正しく活用すれば、より労力少なく記憶することができるようになります。
この記事では、誰でも実践できる14種類の記憶術と、その具体的な活用法を詳しく紹介します。
資格試験や受験、語学学習に悩む方に向けて、記憶力を高めるためのテクニックと生活習慣をまとめました。
記憶に悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んで実践してみてください。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
記憶術とは?

記憶術とは、脳の仕組みに基づいて記憶を助けるための技法やアプローチのことを指します。
受験勉強や仕事、語学学習など、あらゆる場面で活用されています。
- 記憶のメカニズム
- 記憶術とは?歴史と分類
- 忘れるのを前提にする(エビングハウスの忘却曲線)
記憶術を学ぶことで、暗記のストレスを減らし、学びの効率を高めることができます。
記憶のメカニズム
記憶は私たちの学習や生活に欠かせない働きで、脳内で複数の段階を経て処理されています。
とくに重要なのが「記銘」「保持」「想起」の3つのプロセスです。
これらはそれぞれ異なる役割を担い、記憶の形成と活用を支えています。
- 記銘:はじめて会った人の顔や、レシピを読むことで脳に“刻み込む”
- 保持:試験勉強が数日たっても覚えている状態
- 想起:いざ発表会でセリフを思い出すように、必要な時に情報を引き出す
これらの機能は、ニューロンとシナプスの活動によって成り立っています。
また、強い感情や繰り返しの学習は、記憶をより定着させる要因となります。
そのため、効率的な学習には脳のメカニズムを理解することが欠かせません。
関連記事:生活に欠かせない短期記憶のメカニズムと鍛え方を徹底解説!
記憶術とは?歴史と分類
人類は長い歴史の中で、情報を効率よく覚えるための工夫を重ねてきました。
それが「記憶術(mnemonics)」と呼ばれる技術であり、古代から現代まで発展を続けています。
この記憶術の進化を知ることで、私たちは記憶の活用法をより深く理解できます。
- 古代ギリシャ(紀元前5世紀頃):キケロやシモニデスが「場所法(ロキ法)」を活用
- 中世ヨーロッパ(5〜15世紀):修道士たちが聖書暗記に記憶術を応用
- ルネサンス期(14〜17世紀):芸術家や学者がイメージ記憶法や記憶宮殿を探究
- 現代(20世紀以降):心理学や脳科学の知見と結びつき、科学的に分析される
記憶術は、単なる暗記の技術ではなく、創造性や論理性を高める手段でもあります。
今では学習・教育・ビジネスの場でも活用され、多くの人々に役立っています。
記憶術は、未来の学び方を変える可能性を秘めているのです。
忘れることを前提にしている(エビングハウスの忘却曲線)
忘却曲線は、時間の経過によって記憶がどれほど失われるかを示した理論です。
心理学者エビングハウスは、自らを被験者とし、意味を持たない音節を使って記憶の実験を行いました。
この実験から、記憶は最初の1日で急激に減少し、その後は徐々に忘れられていくという特徴があることがわかりました。
忘却の進行を数値化したものが「節約率」です。これは再学習に必要な労力が、最初に学んだときと比べてどれだけ減ったかを示します。
節約率の計算式は以下の通りです。
- 節約率(%)=(初回学習時間 − 再学習時間)÷ 初回学習時間 × 100
例えば、初回学習に10分かかり、再学習に4分かかった場合、節約率は(10 − 4)÷ 10 × 100 = 60% になります。
- 20分後:58%
- 1時間後:44%
- 約9時間後:35%
- 1日後:34%
- 2日後:27%
- 6日後:25%
- 1ヶ月後:21%
なお、これは「無意味な情報」を覚えた場合のデータであり、意味のある内容では記憶の保持率は高くなる傾向があります。
記憶術では、この忘却のパターンを活用して、復習のタイミングを適切に設定することが効果的とされています。
関連記事:エビングハウスの忘却曲線とは?最適な復習タイミングも紹介
位置・構造を使った記憶術
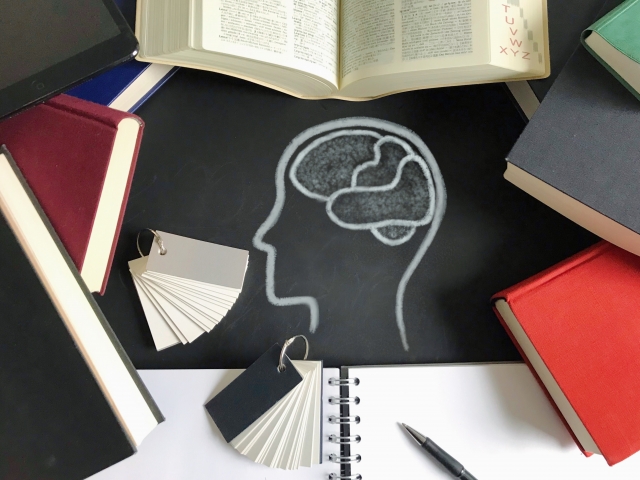
空間や構造を活用して記憶力を高める手法は、視覚的・体感的に情報を整理しやすい点が特長です。
思い出す際の手がかりが増えるため、記憶の再現性が高まることも期待できます。
- 場所法(ロキ法・Lociメソッド)
- 記憶宮殿法
- ペグ法
- マインドマップ法
それぞれ順番に解説しますので、気になった方法があれば一度試してみてください。
① 場所法(ロキ法・Lociメソッド)
| 記憶術名 | 場所法(ロキ法・Lociメソッド) |
| 活用シーン | スピーチ 買い物リスト 歴史年表やキーワード暗記などに有効 |
| メリット | 空間イメージで記憶を整理しやすく、長期記憶にも残りやすい |
| デメリット | 記憶する場所の選定と想像に慣れが必要で、最初は時間がかかることもある |
| 習得難易度 | 中級(慣れれば応用しやすいが、導入時にやや工夫が必要) |
場所法は、古代ギリシャやローマ時代から使われてきた代表的な記憶術です。
なじみのある空間、たとえば自宅の部屋や通学路などを思い浮かべ、その各所に覚えたい情報を配置します。
このようにして、視覚や空間のイメージと結びつけることで、記憶を呼び起こしやすくなります。
特に順序のある情報を記憶するのに適しており、スピーチや試験対策にも有効です。
関連記事:最強の記憶術「場所法」の使い方!勉強や仕事に役立つポイントを解説
② 記憶宮殿法
| 記憶術名 | 記憶宮殿法 |
| 活用シーン | 試験勉強 プレゼン 数字や単語の順序記憶 トランプ記憶など |
| メリット | 情報を大量に整理でき、順序や位置情報と結びつけることで再現性が高まる |
| デメリット | 宮殿(場所)の構築や視覚化に時間と集中力が必要で、維持にも手間がかかる |
| 習得難易度 | 上級(高い想像力と反復が求められるが、習得すれば非常に強力) |
記憶宮殿法は、場所法をさらに高度に応用した技術で、想像上の建物や部屋を脳内に構築し、その中に情報を配置していく方法です。
たとえば、巨大な館を想像し、その各部屋や棚に記憶したい項目を置いていくように使います。
この方法は、イメージ力を駆使するため、長期記憶にも強く、物語形式で整理すると効果が高まります。
一度作った宮殿は何度でも訪れることができるため、記憶の拡張にも向いています。
関連記事:記憶の宮殿とは?ギネス認定の記憶術を紹介
③ ペグ法
| 記憶術名 | ペグ法 |
| 活用シーン | 数字の暗記 順番付きリスト 単語学習 記憶コンテストなど |
| メリット | 数字や順序を正確に記憶でき、取り出しやすく、再現性が高い |
| デメリット | ペグ(固定イメージ)をあらかじめ覚える必要があり、初心者には煩雑に感じる |
| 習得難易度 | 中級(パターンを覚えれば効果的だが、慣れるまで繰り返しが必要) |
ペグ法は、覚える項目にあらかじめ用意された「つり下げるフック(ペグ)」を使って情報を固定していく手法です。
数字と語呂合わせで対応した言葉を決めておき、それに覚えたい情報を結びつけます。
たとえば、「1=いちご」「2=にんじん」のように視覚化しながら順に覚えることで、順序情報を正確に保持することが可能です。
暗記のスピードが上がり、番号の前後関係も明確になります。
④ マインドマップ法
| 記憶術名 | マインドマップ法 |
| 活用シーン | アイデア整理 試験対策 読書記録 スピーチ内容の構成など |
| メリット | 全体像を視覚的に把握しやすく、関連性を持って記憶が定着しやすい |
| デメリット | 手間がかかるうえ、整理が不十分だと逆に混乱を招くことがある |
| 習得難易度 | 初級(誰でも始めやすいが、効果的に使うには工夫が必要) |
マインドマップ法は、中心のキーワードから枝を広げて関連情報を放射状に展開する記憶術です。
情報の構造を可視化できるため、頭の中で整理しやすく、思考の流れが自然に記憶に残ります。
色や図形を使って視覚的に情報を補強することで、理解と定着の両面で効果が期待できます。
特に複雑な情報をまとめる際や、創造的な発想を伴う場面で活用されています。
意味や関連付けによる記憶術

情報同士の関係や意味をつなげて覚える方法は、理解を深めながら記憶できるため効率的です。
- ストーリーメソッド
- 語呂合わせ法
- 頭文字法(アクロニム・アクロスティック)
- チャンク化記憶法
- ナンバー変換法
それぞれ順番に解説します。
① ストーリーメソッド
| 記憶術名 | ストーリーメソッド |
| 活用シーン | 単語の順序記憶 スピーチ 買い物リスト 歴史事項の流れ理解など |
| メリット | 意味のない情報も物語にすれば覚えやすく、楽しく記憶できる |
| デメリット | 無理なストーリーだと逆に混乱しやすく、精度の高い記憶には不向きなことも |
| 習得難易度 | 初級(誰でもすぐ始められ、柔軟に応用できる) |
覚えたい情報を一つの物語に組み込むことで、記憶をスムーズに定着させる方法です。
たとえば「りんご・新聞・電車」といった無関係な単語も、「新聞を読みながら電車でりんごを食べる」と物語にすることで、記憶に残りやすくなります。
脳は物語を記憶するのが得意なので、順序や内容の再現性も高まります。
参考:物語を使って記憶力を劇的に向上!ストーリーメソッドの科学的アプローチ
② 語呂合わせ法
| 記憶術名 | 語呂合わせ法 |
| 活用シーン | 年号 数字 化学式 語句の暗記(例:語呂で年号を覚える) |
| メリット | 語感で覚えられるため記憶に残りやすく、暗記の負担を軽減できる |
| デメリット | 語呂が強引だと逆に覚えにくくなり、正確な理解が乏しくなることもある |
| 習得難易度 | 初級(覚えたい内容に合わせて自由に作れるが、質に工夫が必要) |
語呂合わせ法は、数字や文字を発音の似た言葉に置き換えて覚える記憶術です。
語呂合わせは「いい国つくろう(1192)鎌倉幕府」など、リズムと意味を融合させることで記憶に残りやすくなります。年号や数字を無理なく覚える工夫として有効です。
語感やリズムを意識することで記憶の定着が高まり、年号や電話番号の暗記にも効果的です。
暗記に楽しさを加えられるため、覚えることが苦手な人にも向いています。
③ 頭文字法(アクロニム・アクロスティック)
| 記憶術名 | 頭文字法(アクロニム・アクロスティック) |
| 活用シーン | 項目やステップの順序記憶 専門用語の暗記 教育・プレゼン資料など |
| メリット | 覚える項目を短い語やフレーズに圧縮でき、思い出しやすくなる |
| デメリット | 無理に頭文字を並べると意味不明になり、語順も限定されることがある |
| 習得難易度 | 中級(効果的に使うには工夫とセンスが必要) |
頭文字法(アクロニム・アクロスティック)は、覚えたい複数の語の頭文字を組み合わせて記憶する方法です。
たとえば英語の音階「E・G・B・D・F」を「Every Good Boy Does Fine」と文章にすれば、順序も意味も一緒に覚えられます。
アクロニムでは「NASA(National Aeronautics and Space Administration)」のように頭文字を単語にして記憶します。
単語化や文章化によって情報を整理できるため、複雑な内容もスムーズに覚えやすくなるのが特徴です。
④ チャンク化記憶法
| 記憶術名 | チャンク化記憶法 |
| 活用シーン | 電話番号 パスワード 文章構造 語句のグループ化など |
| メリット | 複数の情報をまとまりで処理でき、記憶容量を効率よく活用できる |
| デメリット | チャンクの切り方が不適切だと逆効果で、混乱や記憶ミスの原因になることも |
| 習得難易度 | 初級(ルールを理解すれば誰でも取り入れやすい) |
チャンク化記憶法は、情報を小さなかたまりに分けて覚える記憶術です。
人の短期記憶は一度に多くを処理できないため、情報を区切ることで記憶しやすくなります。
たとえば「20250718」は「2025」「07」「18」と3つに分ければ、負担が減りスムーズに記憶できます。
意味のある単位でグループ化することで、短期記憶の負担が減り、電話番号や日付などの記憶が格段にしやすくなります。
⑤ ナンバー変換法(数字変換法)
| 記憶術名 | ナンバー変換法 |
| 活用シーン | 数字の語呂化 暗証番号や年号の記憶 記憶競技など |
| メリット | 抽象的な数字をイメージや言葉に変換でき、印象に残りやすくなる |
| デメリット | 数字とイメージの対応表を先に覚える必要があり、慣れるまで手間がかかる |
| 習得難易度 | 中級(基礎のパターンを覚えれば幅広く応用できる) |
ナンバー変換法は、数字に特定の語やイメージを結びつけて覚える記憶法です。
「0=王様」「1=いちご」「2=にんじん」など、自分で連想しやすい対応関係を決めるのがポイントです。
抽象的な数字を具体的なイメージに変換することで、記憶に残りやすくなります。
特に数字の並びや順序を整理して覚えるときに効果を発揮します。
感覚を活用する記憶術

視覚や聴覚などの感覚を利用した記憶術は、直感的に情報を取り入れやすく、楽しく覚えられるのが特徴です。
- イメージ記憶法
- リズム・音楽記憶法
- 多感覚記憶法
それぞれ順番に解説しますので、ぜひ自分に合った方法を見つけて試してみてください。
① イメージ記憶法
| 記憶術名 | イメージ記憶法 |
| 活用シーン | 単語の意味記憶 語学学習 歴史や地理の視覚化 子ども向け教育など |
| メリット | 抽象的な情報も視覚的に覚えられ、印象に残りやすく感情とも結びつけやすい |
| デメリット | 抽象語や複雑な概念は視覚化が難しく、想像力に依存する傾向がある |
| 習得難易度 | 初級(誰でもすぐ始められるが、工夫によって効果に差が出やすい) |
覚えたい情報を視覚的なイメージに置き換えることで、記憶の定着を促す方法です。
たとえば「火山」という単語を記憶したい場合、噴火している火山の映像を頭に思い浮かべることで、より印象深く覚えることができます。
人は文字よりも映像のほうが記憶に残りやすい傾向があるため、イラストや写真を活用するのも効果的です。
記憶したい語に連想できる強いビジュアル(例:王様の絵や爆発中の火山)を組み合わせると、記憶の定着率が飛躍的に上がります。
関連記事:イメージ記憶とは?トレーニング方法と効率よく覚えるコツもご紹介!
② リズム・音楽記憶法
| 記憶術名 | リズム・音楽記憶法 |
| 活用シーン | 英単語や語呂 九九 公式 暗記用ソングなどの語学・学習全般 |
| メリット | 音やリズムに乗せることで覚えやすくなり、繰り返し口ずさむことで定着しやすい |
| デメリット | 音やリズムに頼りすぎると意味理解が浅くなり、応用力に欠ける可能性がある |
| 習得難易度 | 初級(身近なメロディを使えば誰でも簡単に実践できる) |
リズム・音楽記憶法は、覚える情報にリズムやメロディをつけて記憶する方法で、歌や韻を使うことで記憶が定着しやすくなります。
子どもの九九やアルファベットソングなどは、この原理を利用した代表例といえるでしょう。
リズムによって情報がまとまりとして認識されるため、脳が処理しやすくなります。
また、「語呂をラップ調で覚える」など、メロディに乗せた情報は無意識に再生されやすく、思い出すきっかけにもなります。
③ 多感覚記憶法
| 記憶術名 | 多感覚記憶法 |
| 活用シーン | 語学学習 実技訓練 プレゼン準備 子どもの学習支援など |
| メリット | 視覚・聴覚・触覚など複数の感覚を使うことで、記憶の定着率が高まる |
| デメリット | 実践には工夫や道具が必要な場合があり、環境に左右されやすい |
| 習得難易度 | 中級(感覚の組み合わせや活用法を試行錯誤する必要がある) |
多感覚記憶法は、視覚・聴覚・触覚など複数の感覚を同時に使う記憶術です。
たとえば「英単語を発音しながら書き、絵で意味を描く」ことで、脳の複数領域が連携し、記憶の接着力が格段に向上します。
感覚が増えるほど脳内で情報の接点が増え、記憶の呼び出しがしやすくなります。
とくに長期的な記憶の定着や学習障害の補助としても活用されている、実用的な記憶術です。
繰り返し・時間を活用する記憶術

記憶は一度では定着せず、時間をおいて繰り返すことで長く保持できるようになります。
- 間隔反復法
- 音読・暗唱法
それぞれ順番に解説します。
① 間隔反復法
| 記憶術名 | 間隔反復法 |
| 活用シーン | 語学学習 資格試験対策 長期記憶の定着 暗記科目全般など |
| メリット | 忘却のタイミングに合わせて復習することで、効率よく記憶を定着させられる |
| デメリット | スケジュール管理が必要で、継続には計画性と習慣化が求められる |
| 習得難易度 | 中級(仕組みは簡単だが、継続と管理に工夫が必要) |
間隔反復法は、時間をあけながら繰り返し復習し、記憶を強固にする学習法です。
人は時間の経過とともに忘れてしまいますが、ちょうど忘れかけた頃に復習すると記憶が再び強まります。
この方法は、エビングハウスの忘却曲線を活用した科学的なアプローチとして知られています。
「1日後→3日後→7日後→14日後」のように復習間隔を調整すると、記憶が自然に長期記憶に移行していきます。
② 音読・暗唱法
| 記憶術名 | 音読・暗唱法 |
| 活用シーン | 語学の発音習得 スピーチ準備 教科書や台詞の暗記 |
| メリット | 声に出して聴覚と運動記憶を同時に使うため定着が早い |
| デメリット | 場所や時間が限定されやすく、喉へ負担が掛かることも |
| 習得難易度 | 初級(方法がシンプルで誰でもすぐ始められる) |
音読・暗唱法は、声に出して読むことで視覚・聴覚・発話を同時に使い、記憶を深める方法です。
文字を見て音にする過程で脳が活性化し、黙読よりも記憶への定着が高まるとされています。
文章のリズムや構造を体で覚えられるため、語学やスピーチの習得にも向いています。
繰り返すうちに自然と口から出るようになり、学習への自信にもつながるでしょう。
記憶力に関するよくある悩み
▼記憶術は、「覚え方の手順」を身につけるための技術です。
吉永式記憶術は、基礎を丁寧に言語化しているため、誰でも再現しやすいのが特長。
まずは無料動画で、今日から使える記憶力アップのコツを短時間で確認してください。
今ならLINE登録だけで、
記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中
記憶力そのものを高めるコツ

記憶力の良さは、生まれつきの才能と感じる人もいるかもしれません。
しかし、実際には脳も筋肉と同様に鍛えることが可能ですし、記憶する行為も野球のバッティングのように練習で向上するスキルです。
つまり、誰でもトレーニングを積むことで、ある程度記憶力そのものを高めることができるのです。
例えば、以下のようなトレーニングが効果的です。
- 覚えた情報を自分の言葉でアウトプットする
- 思い出せそうな内容を自力で思い出す努力をする
- 毎日反復して記憶する
トレーニングといっても特別な訓練を行わなくても、日常生活のちょっとした工夫だけでも大きな効果が得られます。
記憶術のトレーニングについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:記憶力向上のために実践したいトレーニング11選とおすすめの記憶術
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶力そのものを高めるための生活習慣

記憶力を高めるには、記憶を司る脳のコンディションを整えることも大切です。
ここでは脳のコンディションを整えるため、脳によい生活習慣について詳しく解説します。
食生活
脳のコンディションを整えるため、よい食生活を送りましょう。
青魚などに多く含まれているDHAやEPAは脳の神経細胞を構成し、記憶力に好影響を及ぼすといわれています。
ツボクサ(ゴツコラ)は、記憶力向上の民間療法として知られ、一部の研究では認知機能改善の可能性が示されています(※効果には個人差があります)。
その他、脳のエネルギー源となる「糖質」や神経伝達に関係する栄養素「カルシウム」など、記憶力に関わる栄養素をバランスよく摂取することを心がけましょう。
食事の内容によっては、物忘れを悪化させる要因となる食品もあります。
詳細は、以下の記事をご参考ください。
関連記事:物忘れがひどくなる食べ物をチェック!認知症リスク要因を改善
運動習慣
運動習慣をつけることも脳に良い影響を及ぼします。
運動により脳への血流が増えると、注意力や集中力が向上し、認知機能面でさまざまなメリットがあります。
また、運動により体内のカルシウム代謝が促進され、脳にカルシウムが供給され、神経伝達物質のドーパミンが増えることがわかっているそうです。
ドーパミンは運動調節や学習、快楽に関わる神経伝達物質であるため、脳の活性化に非常に効果が高く、記憶力にも良い影響があるでしょう。
【関連記事】記憶力に効果的な運動3選 | 習慣づくりのコツも【たった10分】
良質な睡眠習慣
記憶力の向上には、良質な睡眠習慣も欠かせません。
脳は日中に学習した情報を、睡眠中に整理しているといわれています。特にノンレム睡眠時に出る脳波であるデルタ波は、記憶定着の役割を担っていると考えられています。
またレム睡眠中の脳活動が記憶の整理に関与していると考えられており、レム睡眠だけを削ると記憶の定着が難しくなるといわれています。
記憶を定着させるには、6時間半~7時間半の睡眠習慣が推奨されます。
記憶を妨げる生活習慣・行動

記憶力を高めようとしても、日常の習慣が逆効果になっていることがあります。
無意識のうちに記憶を妨げる行動をとっていると、どれだけ努力しても効果が出にくくなります。
- 睡眠不足
- ながら勉強
- 復習をしない
それぞれ順番に解説しますので、生活の改善も含めて意識してみてください。
① 睡眠不足
睡眠は、記憶を脳に定着させるうえで不可欠なプロセスです。特にレム睡眠の間に情報が整理され、長期記憶として保存されるといわれています。
睡眠が不足すると脳が十分に休息できず、記憶の定着が妨げられるだけでなく、集中力や判断力も低下します。
また、記憶力だけでなく感情のコントロールにも悪影響が及ぶため、日常生活全体のパフォーマンスが下がってしまうでしょう。
関連記事:集中力が落ちるのは睡眠不足の可能性大!それでも頑張る人のための4つの対処法
② ながら勉強
音楽やテレビをつけっぱなしにしたまま勉強する「ながら勉強」は、注意が分散しやすくなります。
脳は同時に複数の作業を処理するのが苦手なため、情報の理解や記憶の効率が大幅に下がってしまいます。
「音楽を聴きながらの勉強は集中しやすい」と感じても、実際には記憶効率が大幅に低下しているケースが多く、無音環境のほうが定着率は高まります。
集中したいときは、静かな環境を整え、一つのことに意識を向けるのが効果的です。
③ 復習をしない
一度学んだ内容をそのまま放置していると、脳は重要でない情報と判断して忘れてしまいます。
記憶を長期的に定着させるには、一定の間隔で繰り返し復習することが不可欠です。
特に、エビングハウスの忘却曲線によると、学習後すぐに復習することで記憶の保持率は大きく向上するとされています。
復習を取り入れるだけで、学習の効率と成果は大きく変わってくるはずです。
まとめ|脳をトレーニングして記憶術を身に着けよう

本記事では、記憶術の概要やおすすめの方法、記憶力を高めるコツを解説しました。
記憶術は特別な才能よりも「繰り返しの工夫」と「脳の使い方」が鍵です。身近な工夫から始めて、無理なく習慣化していきましょう。
「イメージ法」「ストーリー法」「場所法」など、ご自身にあったものを見つけて、ぜひチャレンジしてください。
合わせて、睡眠時間の確保や脳によい食生活や、規則正しい生活習慣も意識してみてくださいね。
また、記憶力をあげたい方は、吉永式記憶術もおすすめです。記憶術は科学根拠に基づくものであり、正しく学べば習得可能なスキルです。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
Wonder Educationでは、誰でも記憶力を高められる記憶術講座を提供しています。再現性の高い指導により、記憶力向上と目標達成をサポートしていますので、ご興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせください。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education
吉永式記憶術の口コミ・評判
吉永式記憶術は多くの方からお喜びの声を頂いております。
その声の一部をご紹介します。
50音に漢字のイメージをくっつけていく課題は、最初は覚えられなかったのですが、2週間ぐらい取り組むと10分ぐらいで覚えられるようになってきました。
真面目に取り組めば必ず結果が出る価値のあるものだと思います!孫にも伝えていきたいです!
引用:YGC吉永ジーニアスカレッジ 受講生実績
死ぬほど暗記が苦手だったのに、今ではスーッと覚えられて全く忘れないです!
ビジネスで成功して会社員から独立。人生が180度変わりました!
落ち続けた宅建試験に合格できました!
今まで苦労して勉強したTOEICのスコアがアップしました!外資系企業に転職できました!
学習障害の診断を受けて数学は絶対にできないと言われていたのに国公立医学部に合格できました。
引用:吉永式記憶術
先生のカウンセリングでトラウマに気づき語学習得も新たなチャレンジもできるようになりました!
引用:YGC吉永ジーニアスカレッジ 受講生実績

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。