 キツネさん
キツネさん
勉強中に音楽を聴くことで集中力が上がると一度は耳にしたことがあるでしょう。
実際に音楽と記憶や集中に関する研究は多く発表されています。
しかし、ただ勉強中に音楽を聞けば記憶力が上がるというわけではありません。聞くタイミングであったり、音楽の種類によって効果は変わってきます。
本記事では、研究や論文などをもとに、音楽と記憶力の関係について詳しく解説します。
どのような音楽を聞いた方が効果的であるかも記事の後半で解説していますので、最後までご覧ください。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
音楽を聴きながら学ぶと記憶力は上がる?
音楽を聴きながら勉強すると記憶力が上がる理由について、論文などを用いて解説します。
音楽と記憶力の関係については、以下のように言われています。
- 五感の刺激は記憶の定着をサポートする
- 音楽は記憶に影響を与える
- 音楽と知的能力は関係ないという説もある
音楽を聴きながら勉強したからといって、必ず記憶力が上がるわけではありません。IQがすぐに高くなるわけでもないです。
音楽は記憶力を上げるサポートをしてくれるのです。
音楽と記憶力の関係を理解することで、音楽を聴きながら勉強する意義がわかりますので参考にしてください。
五感の刺激は記憶の定着をサポートする
人間の記憶は視覚、触覚、味覚、聴覚、嗅覚の五感と密接に関わっています。
多くの人は「りんご」と言われたら、すぐに頭の中に形や色が思い浮かびます。
このように五感は物事を記憶するために必要なものです。
それでは、音楽はどうでしょう。小学生のときに聴いた音楽を覚えている人は多いのではないでしょうか。カエルの歌やチューリップなどを歌えと言われたら、すぐに口ずさむことができます。
これも五感の中の聴覚を通して記憶していることになります。
上記のことから、勉強中に五感を刺激することにより記憶に残りやすくなるといえます。
音楽は記憶に影響を与える
音楽が記憶に影響を与えるかどうかを示す研究や論文は数多くあります。
その中から山形大学の研究を参考に取り上げます。
山形大学の研究では、以下のような実験を行いました。
- 被験者に対して音楽を流しながら静止画像を見せた。このとき、音楽を聞いてくださいとは言わなかった
- 30分の休憩後、1で流れていた音楽を聴きながらイメージや想起できるものを記述してもらう
- その後、同じ音楽を聴きながら、音楽に合う画像をスクリーンに映し出される3枚の画像から選ぶように指示した
結果は、音楽を聞いただけで静止画像の内容を想起できていました。
山形大学の伊藤理絵氏によると、被験者は音楽に注意を向けていなかったにもかかわらず、無意識に聴覚刺激としての音楽を取り込み、視覚刺激としての静止画像の情報と結び付けていたと述べています。
上記の研究からもわかるように、音楽は記憶と大きく関係しています。意識しなくても音楽と情報を結びつけているからです。
音楽と知的能力は関係ないという説も
音楽と記憶は関係していると言われていますが、頭の良さと音楽教育は関係ないという研究論文もあります。
2020年7月にロンドンのフェルナンド・ゴベット氏は、音楽トレーニングと知的能力の過去の論文54件を調査し、音楽教育が知的能力を向上させるかを研究しました。
この研究論文での結果は、ピアノなどの音楽教育が必ずしも知的能力の向上に関係するわけではないとのことでした。
参照:Cognitive and academic benefits of music training with children: A multilevel meta-analysis
 キツネさん
キツネさん
音楽を聴きながら学ぶメリットと注意点
学びのパフォーマンスを引き上げるために、音楽には「リラックス効果」「集中力アップ」「雑音対策」などさまざまなメリットがあります。
一方で、歌詞入りの楽曲を聴くことで逆効果になることも。ここでは、効果と注意点をバランスよく解説します。
リラックスできる
音楽を聴くことで、リラックス効果が期待できます。
静岡大学の研究によると、音楽は交感神経を抑制して、副交感神経を活性化させることがわかったと発表しています。
副交感神経はリラックスしている時に活動します。
つまり音楽を聴くことによりリラックスできることがわかります。
音楽は高齢者や障害者に対して音楽療法としても用いられています。この音楽療法の効果でもリラクゼーションが挙げられています。
 キツネさん
キツネさん
集中力も上がる
音楽を聴きながら勉強するメリットは、リラックスするだけではありません。集中力を上げるサポートもしてくれるのです。
音楽を聴くことにより、集中力が上がるという研究結果も多数報告されています。
スタンフォード大学医学部の研究チームによると、クラシック音楽を聴きながら勉強することにより脳が活性化され、集中力、情報処理能力の向上がみられたという結果が報告されています。
参照:Music moves brain to pay attention, Stanford study finds
関連記事 : 集中力を上げる具体的な方法11選!集中できない理由と効率よく高めるアプローチ
 キツネさん
キツネさん
メリハリをつけられる(マスキング効果)
音楽を聴きながら勉強することによりメリハリをつけることができます。
それは、人間が音や声を聴くときにマスキング効果が働くからです。
マスキング効果は、2種類の音が同時に鳴っているのに、片方の音しか聞こえないことを言います。
例えば、飲食店やデパートのBGMがあります。BGMに意識を集中させ、騒音には注意を向けさせず、不快感を減らします。
ちなみにマスキングとは、「覆い被さる」という意味があります。
勉強をする時に音楽を聴くことで、このマスキング効果を利用しメリハリをつけることが可能です。外の音を掻き消し、すぐに勉強に集中できるようになります。
ずっと音楽を聴くのではなく、勉強の開始と同時に聴き始めましょう。
歌詞付きの音楽がNGな理由
歌詞入りの曲は、脳の言語処理を刺激し、ワーキングメモリ内の情報処理と競合することがあります。
結果として、読書や暗記など言語的タスクの効率が低下するという実験結果も。
学習中はインストゥルメンタルBGMを選ぶのが効果的です。
記憶力を高める効果的な音楽ジャンル
楽にもジャンルによって特性が異なり、記憶力や集中力を支援するもの、あるいは逆に邪魔になるものがあります。
ここでは、クラシックや環境音、ヒーリング音楽、そして東大生が実際に聴いている音楽や配信サービスまで、科学的根拠に基づいて効果的な音楽ジャンルを解説します。
クラシック(バロック・モーツァルトなど)
クラシックを聴くことで記憶力を上がることは研究でもわかっています。
サピエンツァ大学のウォルター氏によると、モーツァルトの音楽を聴くことで成人も高齢者も関係なく、記憶や認知、問題解決に関係する脳波の周波数が増加したと報告しています。
また群馬大学の研究では、クラシック音楽には不安を減らしたり、抑うつ気分に対する効果も確認されています。
 キツネさん
キツネさん
環境音(雨音・波・風・アンビエント)
環境音やアンビエントBGMは雑音をマスキングしつつ、α波を誘発して集中力と記憶の効率化に役立ちます。
例えば45dB程度のホワイトノイズやピンクノイズは、作業効率やワーキングメモリ向上に効果があると報告されています。
自然音のような柔らかい環境音は脳のリラックスにもつながり、学びのパフォーマンス向上に寄与します。
ヒーリングミュージック
その名のとおり、ヒーリングミュージックとは心を癒すために作られた音楽のことを指します。ゆっくりなテンポで同じメロディが繰り返されるような音楽です。
例えば波の音などの環境音にリズムを付けたような音楽です。
福岡工業大学の岡松恵太氏の研究によると、ヒーリングミュージックのテンポが60BPMの時、人間の心拍数に重なるため癒しの効果があると報告しています。
 キツネさん
キツネさん
東大生が聴いている音楽
日本でも最難関大学に入学した東大生は、音楽をどのように聴いて勉強しているのか気になります。
河合塾に通っていた東大生へのインタビューでは、勉強中に音楽を聴くのではなく勉強前に音楽を聴く方が良いと述べています。
理由は以下の3つです。
- 勉強中に音楽を聴くと注意がそれる
- 受験やテストの際には音楽を聴くことができない
- 勉強前に音楽を聴くことでやる気がアップする
勉強する前に気持ちを高める音楽を聴いて、勉強を開始すると同時に音楽を聴くのをやめるとのことです。
勉強中に音楽があると集中できないのであれば、試してみても良いかもしれませんね。
参照:東大受験を乗り切るために勉強がはかどる方法(文類)勉強前に音楽を聴く理由
おすすめ配信サービス・YouTubeチャンネル
効果的な音楽を手軽に聴ける配信サービスやYouTubeが多数あります。
- Spotify/Apple Music:集中BGMやα波プレイリストが豊富
- YouTubeチャンネル:「Mozart Effect 432 Hz」や「Ambient Rain Sounds」など科学的効果をうたい文句にした動画が人気
- 専門BGMアプリ(Brain.fmなど):脳波誘導型のBGM提供で集中促進に特化しています
記憶力に関するよくある悩み
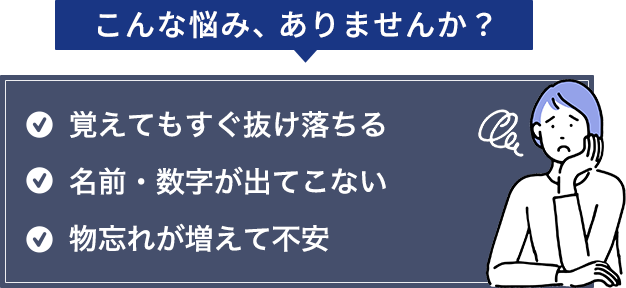 ▼
▼覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。
それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。
無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
記憶力を高める音楽の聴き方ガイド
音楽を聴きながら勉強することで記憶力が上がる理由やメリットについて解説しました。
ここからは、記憶力につなげるための音楽の聴き方について紹介します。
記憶力を上げるために音楽を聴いているのに、逆効果になってしまってはもったいないです。
記憶力を高めるには以下の3つに注意しましょう。
- ボリュームは最小限
- 勉強中と休憩中の音楽を変える
- おすすめ時間帯とプレイリストの組み方
ボリュームは最小限
記憶力に繋げるための音楽を聴くときは、ボリュームに気をつける必要があります。
オーストラリアのウロンゴン大学のバイロン氏によると、勉強する際に聴く音楽は以下の3つを意識する必要があると述べています。
- ボリュームが大きくない
- テンポが早くない
- 歌詞が少ない(ヒップホップは気が散りやすい)
テンポが早く、ボリュームが大きい音楽を聴きながら勉強をすると、逆にパフォーマンスが落ちるという結果が出ています。
クラシックのようなテンポが遅い音楽を、ボリュームを小さくして聴くことで記憶の定着に繋げられる可能性は高くなります。
最小限のボリュームとは、イヤホンを付けていても外の音が聞こえてくる程度を目安としましょう。
勉強するときと休憩時で音楽を変える
勉強をする時に、勉強中と休憩中の音楽を変えることでメリハリがつき、集中力を保つことができます。集中力を保つことができれば記憶にも繋がります。
勉強中と休憩中の音楽の選び方として、以下を参考にしてください。
- 勉強中はクラシックや歌詞の無い音楽
- 休憩中は好きな音楽の中でも気分が上がる曲を選ぶ
勉強中は集中するために、小さい音量でクラシックなどのテンポが遅い音楽を聴きます。
休憩中は少しアップテンポなテンションが上がる音楽を聴くことで気分が高揚し、やる気に繋げることができます。
このような小さな工夫で記憶力を上げられる可能性があるので試してみる価値はあります。
おすすめ時間帯とプレイリストの組み方
ベストな時間帯は集中力が比較的高い午前中と、夜のリラックス学習時です。
プレイリストは60~80 BPMの一定テンポで構成し、途切れの少ない1時間以上の連続再生にするのが望ましいです。
SpotifyやYouTubeの「Deep Focus」「Peaceful Piano」などが人気で、研究でも学習効率と集中維持に寄与すると示されています。
関連記事 : 集中力は時間帯で決まる!仕事や勉強で活かせる攻略法を紹介
まとめ|音楽を味方に、記憶力アップを習慣に

音楽は、記憶力を高めたい人にとって強力なサポーターとなります。
リラックスや集中を促すジャンルを上手に取り入れ、学習環境を整えることで、記憶の定着や作業効率が向上します。
ただし、歌詞付きの音楽や音量の設定には注意が必要です。
重要なのは「自分に合った音楽」と「適切な使い方」を見つけること。
まずは、クラシックやヒーリング音楽、環境音などから始めてみましょう。音楽を味方につけて、記憶力アップを日々の習慣にしていきましょう。
また、Wonder Educationでは、誰でも記憶力を高められる記憶術講座を提供しています。再現性の高い指導で、記憶力向上とそれによる目的の達成をサポートしていますので、ご興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせください。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。












