 キツネさん
キツネさん
自分には記憶する才能がないなぁ……。やっぱり頭がいい人を見ていると、記憶力ってはじめから才能で決まっているように感じるよね……。
頭がいい人、結果を出している人たちの多くは記憶力も良いものです。
そんな人たちを見て「やっぱり記憶力は才能で決まるんだよね……」と落ち込んでしまっている人も少ないないでしょう。
しかし果たして、本当に記憶力の良い・悪いは才能だけで決まっているのでしょうか?
先に結論を伝えると、記憶力の良さは能力によるところもありますが、「ふつうの人」でも真似をすれば身につけることができます。
才能があると思われている人が、普段からどのように記憶しているのか、その方法を覗き見してみましょう。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
記憶力は本当に“生まれつき”?それとも努力で伸びる?
結論から言うと、記憶力は後天的に伸ばすことが可能です。
現代の神経科学では、成人後でも脳の神経ネットワークは変化し続ける「可塑性」を持つことが明らかになっており、生まれつきではなく、学習や訓練によって記憶力は改善され得ます。
たとえば、シナプス(神経細胞間の接続部)の構造や機能が学習によって変化する構造的可塑性が記憶・学習に重要であることが示されています。
また、脳を動かす運動習慣が加齢による認知機能の低下を防ぎ、脳構造そのものにもポジティブな変化を促すという報告もあり、努力によって脳を鍛える科学的根拠が蓄積されています。
参照
: 慶應義塾大学病院 記憶・学習のメカニズムを分子レベルで明らかに―記憶・学習を操作できるか
: 京都大学大学 短期間の運動習慣が高齢期の認知機能や脳の可塑性を促す
- 脳は学習や経験によって形を変える「可塑性」がある
- シナプスの変化が記憶力の向上に関与する
- 運動や習慣で記憶力は大人でも伸ばせる
記憶力=才能と思われがちな理由
多くの人が「記憶力=生まれつきの才能」と認識しやすいのは、教育や社会的イメージの影響によるものです。
このセクションでは、まず教育制度がどのように記憶偏重を助長してきたかを整理し、次に「天才=才能だけ」という誤解について説明します。
日本の教育と記憶偏重の歴史
日本では戦後一貫して「覚えること」に重きを置いた教育が行われてきました。
良い高校や大学に入るには、テストを受けることが一般的です。それらのテストでは学んだことを覚えていれば点数が取れるものが多く、極端な話、記憶力があれば良い学校に入ることができました。
つまり、
- 記憶力がある人は良い学校に入れる
- 良い学校に入れる人は頭がいい(才能がある)
というように、無意識のうちに「記憶力がいい人は才能がある」とみなしてしまう人が多いのです。
しかし近年では「アクティブ・ラーニング」の導入により、思考力や応用力を育む教育が進められています。
 キツネさん
キツネさん
“天才=才能”というイメージの誤解
「天才」と聞くと、多くの人は「記憶力がずば抜けている人」と無意識に結びつけがちです。実際には、天才には様々なタイプが存在し、全てが記憶に秀でているわけではありません。
例えば、論理思考が強いタイプや発想力に優れたタイプもおり、「天才=才能」「記憶特化=万能」といった一括りのイメージは誤解を招きます。
関連記事 : 世界と日本のIQが高い人ランキング|天才たち21人のIQ・実績・人物像を解説
科学的に見た「記憶力は伸ばせる」根拠

ここでは、記憶力が後天的に伸ばせるとする科学的な根拠を整理します。
まずは脳が持つ「可塑性」の仕組みについて、次に加齢と記憶力の関係を説明します。
脳の可塑性とその鍛え方
脳は生涯を通じて「可塑性」と呼ばれる柔軟性を保ち続けており、学習や経験によって神経ネットワークが再構築されます。
例えば、東洋大学・児島教授によれば、「シナプスの可塑性(神経つなぎ目の変化)」が活性化されることで記憶・学習力が向上することが分かっています。さらに、ロンドン大学のタクシードライバー研究では、複雑な地理情報の記憶が反映して、海馬の構造変化が確認されました。
したがって、鍛えることで構造自体に変化を促すことが可能です。
参照
: 東洋大学 医学博士に聞く、記憶力・学習力アップに影響する脳機能「シナプス可塑性」とは?
: マインドフルネスプロジェクト マインドフルネスと脳科学 〜神経可塑性〜
- 脳は生涯にわたり柔軟に変化できる性質を持つ
- シナプス可塑性が記憶・学習力を左右する
- 実例として、長期間記憶訓練で海馬構造に変化
年齢と記憶力の関係
年齢を重ねると、新しい情報を覚えるスピードが低下する傾向がありますが、すでに身につけた記憶の“保持力そのもの”は比較的安定しています。
例えば、加齢マウスの研究では「記憶の保持は若年とほぼ差がない」ことが示された一方で、新たな学習速度には違いが出ました。
また、加齢による記憶力の低下メカニズムとして、海馬でのAMK(メラトニン由来物質)の低下が関与している可能性も報告されています。つまり、記憶力の“質”自体は維持されやすく、訓練や習慣によってさらに引き出せるということです。
参照
: 都健康長寿医療センター研究所 加齢により学習スピードは低下するが記憶保持力は維持
: 立教大学 老齢マウスを使って加齢にともなう記憶力低下の原因を解明
- 年を取っても既存記憶の保持力は比較的良好
- 新しい学習は遅くなる傾向あり
- 海馬内のAMK減少が記憶低下に関与する可能性
天才から学ぶ記憶力を上げる5つの習慣
このセクションでは、記憶力に優れる”天才”的学びのポイントを抽出して、誰でも実践できる5つの習慣に整理しています。
各習慣を取り入れれば、記憶力の後天的な向上が期待できます。
- 勉強前に“学び方”をまず学ぶ
- 情報を関連付けて覚える
- アウトプットで定着させる
- 復習で記憶を強化する“時間戦略”
- 早期成功体験の重要性
1. 勉強前に“学び方”をまず学ぶ
ただ漫然と暗記を試みるよりも、どのように学ぶのが”効率的”なのか知ることが重要です。
研究では、「メタ認知」(自分の学びを客観的に制御する力)が学習成果と強く相関することが示されています。要は、自分が何を理解できていないかを把握し、それに応じて戦略を立てる力が、”天才的”な学びの根幹です。
- 自分の理解度を見極める「メタ認知」が鍵
- 効率的な記憶は“学び方”の設計から始まる
2. 情報を関連付けて覚える
記憶は単独の情報よりも、関連がつながった情報のほうが定着しやすいです。
例えば「記憶術(メモリーテクニック)」として利用されている場所法(記憶の宮殿)は、空間と関連づけて覚える手法で、世界の記憶チャンピオンも多用します。こうした技術を応用することで、暗記を苦手と感じている人でも情報を長期的に保持しやすくなります。
- 情報を結びつけると記憶は定着しやすくなる
- 記憶術は“記憶が苦手”な人の強い味方
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
3. アウトプットで定着させる(思い出す訓練)
学習した内容を自分の言葉で書いたり、声に出して言い換えたりする「アウトプット」は、記憶を強化します。
Science誌掲載の研究では、学んだ直後にエッセイ形式に記述すること(retrieval practice)は、マッピング型よりも学習内容の定着に優れていました。
思い出すこと自体が記憶の強化につながるという点は、非常に実践価値の高い方法です。
- 「思い出す練習」が記憶定着のカギ
- 書く・話すアウトプットが記憶を強化する
4. 復習で記憶を強化する“時間戦略”
複数回に分けて学習内容を復習する「分散学習(Spaced Repetition)」は、詰め込み型よりも長期記憶の保持に優れています。
時間をかけた復習は忘却曲線を最小化し、記憶の定着率を飛躍的に高めます。特に24時間以内・1週間以内・1か月後といった戦略的なタイミングでの復習が効果的とされています。
- 復習は“タイミング”が成否を分ける
- 24時間・1週間・1か月の再学習が理想
5. 最初の成功体験を早めにつかむ
学びを習慣化するためには、最初にうまくいった成功体験が動機づけとなり、継続に繋がります。
これは心理的モチベーション理論にも合致し、小さな成功がさらなる挑戦を促す好循環を作ります。
結果として「できた」という実感が脳内報酬系を活性化し、より意欲的な学習行動が生まれるのです。
- 小さな成功が“やる気”の源になる
- 初期の達成感が継続学習の鍵を握る
関連記事 : 記憶力がいい人の特徴14選|性格・習慣からわかる天才肌の秘密とは?
記憶力に関するよくある悩み
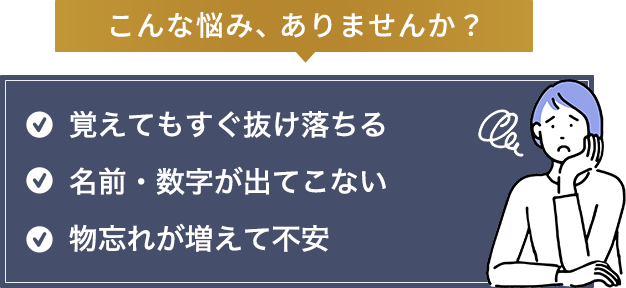
覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。
それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。
無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
記憶力がいい人に関するよくある質問
「記憶力がいい」と聞くと、好印象を持たれる一方で、「障害?」「精神的に不安定?」「スピリチュアル的に特別?」など、さまざまな疑問も湧くようです。
ここでは、代表的な4つの質問に科学的視点をもとに答えます。
記憶力がいい人=障害あり?
記憶力が異常に高い人の中には、サヴァン症候群のような発達特性を持つケースもあります。
たとえば、自閉スペクトラム症(ASD)に関連して、特定領域だけ極端に優れた記憶力を持つ人が報告されています。ただし、これはごく一部で、記憶力が高いこと自体は異常ではありません。
多くの人は、学習習慣や集中力などによって、後天的に記憶力を高めています。
参照 : LITALICO サヴァン症候群
記憶力とスピリチュアルとの関連は?
「記憶力がいいのは過去世の記憶を持っているから」などのスピリチュアル的な見解はありますが、科学的根拠は確認されていません。
実際には、遺伝的な認知傾向や環境、訓練による影響が主な要因です。
スピリチュアルな話は興味深いですが、記憶力のしくみや能力の違いを理解する際には、科学的な視点をベースにすることが大切です。
記憶力良すぎると病みやすいの?
記憶力が高いからといって、精神的に不安定になるわけではありません。
ただし、一部の人には、過去の嫌な体験を過度に鮮明に覚えてしまい、フラッシュバックやストレスにつながるケースもあります。特に感受性が強く、繊細な性格傾向を持つ人では、記憶の鮮明さがストレスの要因になりやすいことも。
重要なのは、記憶の強さと心のケアのバランスです。
記憶力が悪い天才って?
記憶力と天才性は必ずしも一致しません。
たとえば、ある分野で革新的な発想や高度な思考力を発揮する人でも、記憶力は平均的ということがあります。
逆に、記憶に特化した能力が高くても、他の認知機能は平凡というケースも。つまり、天才には多様なタイプがあり、「記憶力が悪い=非才」という図式は成り立ちません。
まとめ|誰でも記憶力は伸ばせる!
記憶力は生まれつきだけで決まるものではありません。脳の仕組みを活かし、正しい方法と習慣を身につければ、誰でも伸ばすことができます。
集中力が切れても問題ありません。休憩の取り方や記憶術を活用すれば、短時間でも学習効率を高めることができます。
特に「記憶の宮殿」などの記憶術を取り入れることで、情報をより深く・長く覚えられるようになります。
Wonder Educationでは、初心者でも安心して取り組める記憶術講座を提供しています。記憶力を伸ばして、学びや仕事の成果を高めたい方はぜひご参加ください。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。












