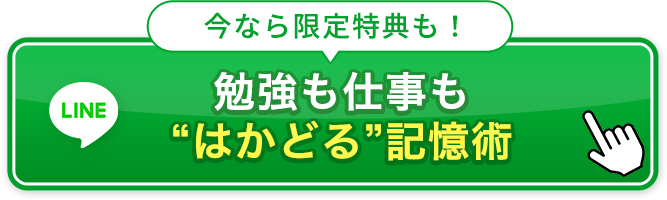緊張やイライラした時に深呼吸すると、気分が落ち着いたり、頭がすっきりした経験はありませんか。
脳や体に十分な酸素が行きわたると、本来の能力を発揮しやすくなります。
「なんだか集中できないな…」と感じるときに、呼吸を知ってれば誰でも集中力は高められるのです!
この記事では、集中力が高まる呼吸法や香り、体を整える呼吸方法についても解説しています。
ぜひ最後まで読んでみてください。
もくじ
集中力を高める呼吸法とは?仕組みとメリット

私たちが普段意識せずに行っている呼吸には、自律神経を整えたり脳へ酸素を十分に届けたりする重要な役割があります。
そのため、呼吸法を工夫することで集中力を引き出す効果が期待でき、日常のパフォーマンスを大きく向上させられます。
- 呼吸が自律神経に与える影響
- 酸素供給と脳の働きの関係
- 呼吸によるストレス低減効果
- スポーツや勉強に呼吸法が効果的な理由
それぞれ詳しく説明していきます。
呼吸が自律神経に与える影響
呼吸は自律神経の働きと深く関わっており、吸気の際には交感神経が、呼気の際には副交感神経が優位に作用します。
この切り替えは心拍数や血圧の変化を通じて心身に影響を与え、緊張とリラックスのバランスを調整する役割を果たします。
特に腹式呼吸では、副交感神経の活動が高まり、ストレス緩和や心拍変動の安定化につながることが研究で確認されています。
坂木佳壽美(2001)の研究では、呼気を吸気の2倍に設定した腹式呼吸により、副交感神経が優位に働き、その効果が持続することが示されました。
したがって意識的な呼吸の工夫は、自律神経のバランスを整え、集中力や精神的安定を保つための有効な方法といえます。
酸素供給と脳の働きの関係
脳は体全体の約2%の重さしかないにもかかわらず、酸素消費量は全身の約20%を占めるほど高いエネルギーを必要としています。
そのため呼吸が浅くなると酸素の供給が不十分になり、頭がぼんやりして集中力が持続しにくくなります。
反対に深い呼吸を意識して行えば血流が改善し、脳に十分な酸素が行き渡って思考力や記憶力が高まります。
集中したい場面で姿勢を正して深呼吸するだけでも、脳の働きは大きく変化すると言えるでしょう。
呼吸によるストレス低減効果
現代人の多くはストレスによって交感神経が優位に働きやすく、呼吸が浅く速くなる傾向があります。
そこで意識的にゆっくりとした腹式呼吸を行うことで副交感神経が働き、心拍数や血圧が落ち着いてリラックスした状態に切り替わるのです。
このリラックス感が心の余裕を生み出し、結果的に集中力を高める助けとなります。
短時間でも深呼吸を取り入れることで、ストレス対策と集中力向上を同時に実現できるのが呼吸法の大きな利点です。
参考:リラクゼーション法[各種施術・療法 – 一般]|厚生労働省
スポーツや勉強に呼吸法が効果的な理由
スポーツや勉強に呼吸法が効果的な理由は明確です。
運動では呼吸を整えることで酸素供給とガス交換が安定し、持久力の維持や瞬発的な出力向上につながります。
学習場面でも深くゆっくりした呼吸を意識すると脳への酸素が巡りやすくなり、集中が切れにくくなります。
さらに自律神経が整い、副交感神経が優位へ切り替わるため、本番前の過度な緊張がやわらぎ、パフォーマンスを発揮しやすくなるのです。
とくに試験直前や発表の前に数回の深呼吸を挟むと、不安の高まりを抑え、理解や記憶の定着が進みやすくなるといえます。
このように呼吸法はアスリートだけでなく受験生や社会人にとっても、成果を底上げする実践的なサポート手段です。
参考:呼吸法を学び、スポーツのパフォーマンスに役立てる|Nike
集中力を高める呼吸法おすすめ7選

集中力を高めたいときに役立つ呼吸法にはさまざまな種類があります。
それぞれの方法は心身を整え、学習やスポーツなど幅広い場面で活用できます。
- 片鼻呼吸
- 腹式呼吸
- 深呼吸
- 完全呼吸
- マインドフルネス呼吸
- ブラーマリー呼吸
- ウジャイ呼吸
ここから一つずつ特徴とやり方を解説していきます。
① 片鼻呼吸|左右の鼻を交互に使い自律神経を整える
片鼻呼吸は、ヨガの基本的な呼吸法のひとつで、自律神経のバランスを整える効果があります。
- 骨盤を立てて背筋を伸ばし、楽な姿勢で座る
- 右手の人差し指と中指を眉間にあてる
- 親指で右鼻を押さえ、左鼻から息をすべて吐き出す
- 左鼻から4秒かけて吸い、薬指で左鼻を押さえ右鼻から4秒かけて吐く
- この流れを数回繰り返す
呼吸のリズムが整うと心身がリフレッシュし、眠気や頭のぼんやり感が和らぎます。
短時間でも効果を感じやすいため、仕事や勉強の前に行うと集中力が高まりやすくなります。
参考:片鼻呼吸法とは?得られる5つの効果と正しいやり方を徹底解説|ヨガネス
② 腹式呼吸|横隔膜を使い深く息を吸ってリラックス効果を高める
腹式呼吸は横隔膜を大きく動かすことで肺に酸素をしっかり取り込み、心身を落ち着かせる呼吸法です。
お腹を膨らませながら鼻から息を吸い、吐くときにはお腹をへこませて体内の空気を出し切ります。
- 椅子に座るか仰向けでリラックスした姿勢をとる
- 鼻からゆっくりと3秒かけて息を吸い、お腹を大きく膨らませる
- 6秒程度かけて口から息を吐きながらお腹をへこませる
- このリズムを数分間繰り返す
繰り返すと、脳内でセロトニンが分泌され、同時にα波の発生が促されるます。
セロトニンが分泌されることでα波が増加し、精神が安定して集中力が高まります。
意識的に呼吸を変えることで、本来の自然な呼吸が戻り、呼吸のリズムが整う効果があるのです。
1日2~3分を1ヶ月くり返すと、集中力を高めるだけでなく、過度な緊張を和らげる効果も期待できます。
参考:1日2分を30日続けると自分が見違える|プレジデントオンライン
③ 深呼吸|ゆっくり息を吸って吐き心拍を安定させ集中を促す
深呼吸は最も身近で取り組みやすい呼吸法であり、ストレス軽減や集中力向上に即効性があります。
お腹に手を添えて鼻からゆっくり息を吸い込み、口から長く細く吐き出すことを意識すると効果的です。
- 椅子に座るか横になり、目を閉じて肩の力を抜く
- 鼻から4秒かけて息を吸い込み、お腹を膨らませる
- 口から8秒かけて息を細く長く吐き出し、お腹をへこませる
- これを繰り返し行う
深呼吸は酸素の取り込みを助け、血流や自律神経の働きを整えることで、集中力だけでなく体調改善にもつながります
参考:『深呼吸』で体調管理! ~体中に酸素を運ぼう‼~|神戸東洋医療学院付属治療院
④ 完全呼吸|胸式と腹式を組み合わせ効率的に酸素を取り入れる
完全呼吸は、胸式呼吸と腹式呼吸を組み合わせ、さらに鎖骨周辺まで意識を広げる深い呼吸法です。
お腹から胸、肩へと順に膨らませながら息を吸い込み、吐くときは逆の流れで空気を押し出すのがポイントです。
- 鼻から息を吐き切り、お腹をへこませる
- 鼻から吸い、お腹、胸、鎖骨へと順に膨らませていく
- 吸い込んだら、鼻からゆっくり息を吐き、お腹をへこませる
- 胸と肋骨を閉じ、肩を下げながら吐き切る
深い呼吸は自律神経を整え、ストレスや疲労をやわらげ、集中力の向上にも役立ちます
参考:ヨガの基本的呼吸「完全呼吸法」の効果とやり方、コツは?|LINE NEWS
⑤ マインドフルネス呼吸|呼吸に意識を集中し雑念を手放す
マインドフルネス呼吸は、呼吸そのものに注意を向け、雑念を取り払うための方法です。
自然な呼吸の流れを観察し、吸うときには「膨らむ」、吐くときには「縮む」と心の中で唱えることで意識が今この瞬間に集中します。
- 背筋を伸ばし、楽に座る
- 自然な呼吸のリズムを観察する
- 吸うときに「膨らむ」、吐くときに「縮む」と心の中で唱える
- 呼吸に集中し、浮かんできた雑念は手放す
呼吸に意識を向けることで思考が落ち着き、頭がクリアになり、集中力や記憶力の向上にもつながります
参考:命を守る!ストレス徹底対策「心を“今”に向ける」|NHK
⑥ ブラーマリー呼吸|ハミング音を伴い副交感神経を優位にする
ブラーマリー呼吸は「ハチの羽音の呼吸法」とも呼ばれ、鼻から息を吸い、吐くときにハミング音を出す独特の方法です。
耳を軽く塞ぎながら行うことで、音の振動が頭部に響き、リラックスを促します。
- 背筋を伸ばして座り、目を閉じる
- おへその下の丹田(たんでん)に意識を集中する
- 両手の人差し指で耳を軽く塞ぐ
- 鼻から息を吸い、少し止める
- 吐くときに「ンーー」とハミング音を響かせる
寝不足や日中の眠気を感じる人におすすめの、集中力を高める呼吸法です
参考:呼吸だけで集中力を高める?集中力を高めるブラーマリー呼吸法のやり方|ヨガネス
⑦ ウジャイ呼吸|喉を軽く締め摩擦音を出し心を落ち着かせる
ウジャイ呼吸は喉を軽く締めて呼吸の摩擦音を響かせながら行う胸式呼吸で、ヨガでも多用される方法です。
吸うときには「シューッ」と音を意識し、吐くときには「ハーッ」と手を温めるように息を吐き出します。
※ウジャイ呼吸法は力強い呼吸法のため、高血圧や妊娠中の方は、行う前に必ず医師へ相談してください。
また、香水や香りがあると喉を刺激する可能性があるため、無香の環境で行うほうが効果を実感しやすいです。
- 背筋を伸ばし、リラックスした姿勢で座る
- 鼻から息を吸い、喉の奥を軽く締め「シューッ」と音を出す
- 口から「ハーッ」と音を出しながら息を吐く
- 数回繰り返し呼吸音に意識を集中する
喉でなっている呼吸音に耳をすますと、内側に意識が向き、集中力が高まりますよ。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
集中力に関するよくある悩み
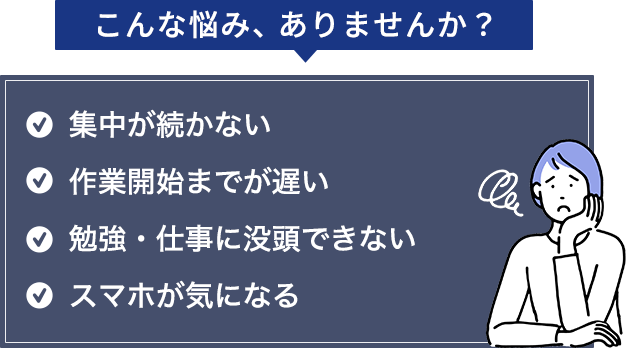 ▼
▼集中できず、勉強や仕事がなかなかはかどらない——。
それは意思や根性ではなく、脳の使い方が原因かもしれません。
まずは無料動画で、要点を捉えて整理し、思い出しやすくする基本の流れを確認。
理解のムダが減り、集中しやすい状態を無理なく実感できます。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
呼吸の質を下げる習慣と隠れ酸欠への対策
私たちが普段気づかないうちに行っている習慣の中には、呼吸を浅くし集中力を下げる原因になるものがあります。
姿勢の乱れや息を止めるクセなどは、自律神経や脳への酸素供給に影響を与えるため、集中力を阻害します。
- 浅い呼吸が集中力を奪う理由
- 猫背や姿勢不良が呼吸を妨げる仕組み
- 日常でできる呼吸改善の簡単な工夫
- 息を止めるクセと集中力の関係(セロトニンとの関連)
ここからは、それぞれ丁寧に解説していきます。
浅い呼吸が集中力を奪う理由
浅い呼吸は体内に十分な酸素を取り込めず、脳への供給が不足することで集中力の低下を招きます。
特に前頭前野は思考や判断を担う重要な領域であり、酸素不足になると作業効率が急激に落ちやすくなります。
また、浅い呼吸は自律神経の乱れを引き起こし、交感神経が優位になりやすいため、緊張や不安が増幅しやすくなるのも問題点です。
逆に深い呼吸を意識的に行うと、副交感神経が整い、精神的な落ち着きが得られ、自然と集中力が高まっていきます。
このため、浅い呼吸が続いていることに気づいたら、深呼吸を取り入れて酸素を取り戻すことが重要です。
参考:「呼吸が浅い」と何が問題?呼吸の質とカラダの関係 – メガロス
猫背や姿勢不良が呼吸を妨げる仕組み
猫背や姿勢不良は胸郭や横隔膜の動きを制限し、呼吸を浅くする直接的な要因になります。
背中が丸まると肺を広げるスペースが狭まり、酸素を十分に取り込めない状態が続くことになります。
さらに、肩や首に余計な緊張が加わるため、呼吸筋の働きが妨げられ、ますます浅い呼吸に拍車がかかります。
こうした姿勢の癖が続くと慢性的な「隠れ酸欠」状態となり、気づかないうちに集中力が下がるのです。
日常的に背筋を伸ばし、胸を開く姿勢を心がけることで呼吸の質が改善され、自然とパフォーマンスも上がります。
参考:猫背が呼吸を妨げる!?姿勢と呼吸の関係を整えよう!|小林整骨院 池田
日常でできる呼吸改善の簡単な工夫
日常でできる呼吸改善の簡単な工夫は、意識次第で誰でも取り入れられます。
特別な準備がなくても、姿勢や習慣を少し工夫するだけで呼吸が深まりやすくなります。
毎日の積み重ねが隠れ酸欠を防ぎ、集中力や心身の安定につながります。
以下は、日常で実践できる呼吸改善の工夫です。
- デスクワーク中に肩回しや胸を広げるストレッチをする
- 1日に数回、意識的に深呼吸を取り入れる
- 寝る前に腹式呼吸を数分行ってリラックスする
- 階段を上がる際に呼吸を意識して整える
- 呼吸筋ストレッチ体操をする
- 外出中に背筋を伸ばし、胸を開く姿勢を意識する
これらを日常に取り入れることで、呼吸の質が向上します。
続けるうちに心身のリフレッシュや集中力アップにも役立つはずです。
参考:呼吸筋ストレッチ体操で息苦しさを改善しよう|独立行政法人環境再生保全機構
息を止めるクセと集中力の関係(セロトニンとの関連)
作業中に無意識で息を止めてしまうクセは、酸素不足を招き集中力を大きく損なう要因となります。
呼吸が止まると脳への酸素供給が一時的に途絶え、判断力や思考力が鈍りやすくなるのです。
この点は、低酸素が注意力や判断の指標を下げうることを示した研究や、反復的な息こらえ後の認知機能を検証した研究からも示唆されます。
悪い姿勢から呼吸の浅さを招く「隠れ酸欠」とよばれる症状があります。
「なんだか息苦しい」と感じることがある
階段を上ると息切れする
仕事などでちょっと無理をすると息苦しい
スマートフォンを操作するときに肩が前に入り組んだ姿勢になっている
また、呼吸が浅くなると脳内のセロトニン分泌が減少し、気分の安定や集中維持が難しくなります。
逆に一定のリズムで深い呼吸を続けると、セロトニンが分泌され、心が落ち着き集中しやすい環境が整います。
したがって、息を止めるクセに気づいたら意識的に深い呼吸を取り入れ、集中力を支える習慣を作ることが大切です。
参考:低酸素環境におけるヒトの高次認知機能の検討|生理学研究所、悪い姿勢が招く「隠れ酸欠」 呼吸筋ほぐして深い息に|日本経済新聞
集中力を高める呼吸法を効果的に続けるコツ

呼吸法は一度試すだけでは十分な効果を得にくく、日常に取り入れて継続することが大切です。
特に朝昼夜のタイミングや短時間での実践法、そして習慣化しやすい環境を整えることが継続の鍵になります。
- 朝昼夜のおすすめタイミング
- 短時間で取り入れる実践例
- 習慣化のための環境づくり
ここからは、それぞれのポイントを掘り下げて説明していきます。
朝昼夜のおすすめタイミング
朝昼夜のおすすめタイミングを意識して呼吸法を取り入れると、効果を実感しやすくなります。
一日の始まりや切り替えの時間に行うことで、自律神経が整い心身の調子が安定します。
生活リズムに合わせて習慣化すれば、集中力やリラックス効果が長続きします。
以下は、朝昼夜におすすめの呼吸法の実施タイミングです。
- 朝:起床後に深い呼吸を行い、交感神経を整えてスッキリと一日を始める
- 昼:仕事や学習の合間に取り入れ、疲労を回復し気分をリセットする
- 夜:寝る前に腹式呼吸で副交感神経を優位にし、心身を落ち着かせて眠りに入りやすくする
既存の習慣や日常のタイミングに呼吸法を取り入れると、無理なく継続でき、自然に習慣として身についていきます。
自分のライフスタイルに合わせて最適なタイミングを見つけることが大切です。
短時間で取り入れる実践例
呼吸法は長時間行わなくても効果が得られるため、短い時間を活用する工夫が効果的です。
例えば通勤中やデスクワークの合間に1分間の深呼吸を挟むだけで、気分の切り替えになります。
また、昼休憩に3分程度の腹式呼吸を取り入れると、午後の集中力が持続しやすくなるのです。
最初から長時間に挑戦すると挫折しやすいため、手が空いたときに数十秒だけ取り入れるところから始めるのがおすすめです。
こうした小さな実践例を積み重ねることで、呼吸法を無理なく日常に溶け込ませることができます。
習慣化のための環境づくり
呼吸法を長く続けるためには、環境を工夫して習慣化しやすくすることが欠かせません。
まずは作業机のそばに「深呼吸」と書いたメモを貼るなど、目に入りやすいサインを用意すると自然に実践しやすくなります。
さらにアロマや落ち着いた音楽を組み合わせると、呼吸法の時間がリラックス習慣として楽しめるものに変わります。
スマホやスマートウォッチのリマインダー機能を使えば、決まった時間に通知が届くため、うっかり忘れることなく続けられる点も便利です。
毎日同じ時間や同じ場所で行うと脳が「ここで呼吸を整える」と認識し、モチベーション維持にもつながり、自然と無理なく継続できるようになります。
集中力を高める呼吸法を効果的に続けるコツ
呼吸法の効果を最大限に発揮するためには、呼吸以外の要素も組み合わせて取り入れることが重要です。
香りや姿勢、環境の工夫を加えることで、心身のリラックスや集中の持続がさらに高まり、学習や仕事の効率が向上します。
- 呼吸と一緒に取り入れると効果的な要素
- 香り(アロマ)を活用する方法
- 姿勢・環境を整える工夫
それぞれの特徴を詳しく説明していきます。
呼吸と一緒に取り入れると効果的な要素
呼吸法を続けるだけでも集中力やリラックス効果は期待できますが、他の工夫を同時に取り入れるとさらに効率が上がります。
例えば、呼吸に合わせて軽くストレッチを行えば筋肉の緊張がやわらぎ、血流が改善し酸素の巡りが良くなることで集中力が一段と高まります。
また、適度な休憩や水分補給を組み合わせることで脳への酸素供給や代謝が整い、呼吸法による効果を妨げない状態を保つことができます。
このように呼吸法は単独でも役立ちますが、補助的な工夫を同時に行うことで実践の質が高まるといえます。
香り(アロマ)を活用する方法
呼吸と相性が良いのがアロマの香りを取り入れる工夫です。
柑橘系の香りは脳を刺激して覚醒効果をもたらし、ローズマリーやペパーミントは集中を持続させる働きがあることが研究でも報告されています。
呼吸法を行う際にアロマディフューザーを使うと、吸い込む息とともに香りが脳に届き、気分の切り替えが自然にできるようになります。
さらに、自宅だけでなく持ち運びできるロールオンタイプやアロマスプレーを使えば外出先でも呼吸法に合わせて取り入れることができ、習慣化が容易になります。
参考:自律神経を整える深呼吸タイムを。思わず息を吸いたくなる7つのアロマと横隔膜をはたらかせる方法
姿勢・環境を整える工夫
呼吸法を効果的に続けるためには、正しい姿勢と環境づくりも欠かせません。
背筋をまっすぐに伸ばし、肩や首の余計な力を抜くことで横隔膜が大きく動き、深い呼吸がしやすくなります。
また、静かな場所や明るさを調整できる環境は集中を妨げにくく、呼吸法に意識を向けやすくしてくれます。
加えて、デスクや部屋の整理整頓や空調の調整なども、呼吸と同じく自律神経の安定に役立ちます。
呼吸法の効果を強化するためには、身体だけでなく周囲の環境にも気を配ることが大切です。
参考:デスクワーク中の姿勢を保つコツとは?長時間の座り仕事に使いたい、正しく座れるアイテムもご紹介!|ハンズ
集中力を高める呼吸法に関するよくある質問
集中力を高める呼吸法に関するよくある質問を解説します。
どの呼吸法から始めれば良い?
初心者が始めやすいのは深呼吸や腹式呼吸であり、シンプルな動作で無理なく実践できる点が大きな魅力です。
片鼻呼吸やウジャイ呼吸のような少し複雑な方法もありますが、まずは基本的な呼吸を整えることが安定した集中力につながります。
継続できる方法を選ぶことが成功の第一歩といえます。
1回の呼吸法はどのくらい続けるのが理想?
理想的な時間は3分から5分程度であり、長すぎると集中力が逆に途切れたり負担になったりする場合もあります。
短い時間でも毎日継続して行うことで脳の酸素供給が安定し、集中しやすい状態が作られます。
日常に無理なく組み込める長さを意識することが重要です。
ゾーン(フロー状態)に入りやすくなる呼吸法とは?
フロー状態を目指すなら、呼吸に意識を集中させるマインドフルネス呼吸がおすすめです。
息の感覚に全神経を傾けることで雑念が薄れ、深い没頭感が得られる環境を整えやすくなります。
呼吸を通じて心身を落ち着かせることが集中の鍵となります。
呼吸法と香りは一緒に使うべき?
香りと呼吸法を組み合わせると、相乗効果で集中力が高まりやすくなると考えられます。
たとえば柑橘系は気持ちをリフレッシュさせ、ローズマリーやペパーミントは集中をサポートする働きがあります。
香りを選ぶときは自分が心地よく感じるものを基準にすると良いです。
体調が悪いときでも行って大丈夫?
体調が優れないときには、無理をせず様子を見ながら行うことが大切です。
高血圧や妊娠中など特定の状態では医師に相談したうえで実践するのが安心です。
体の反応を見ながら無理なく続けることが安全な方法となります。
まとめ|集中力を高める呼吸法を実践し今日から仕事や勉強に活かそう
本記事では、集中力を高める呼吸法の仕組みとメリット、実践法について解説しました。
片鼻呼吸や腹式呼吸など七つの方法を整理し、スポーツや勉強で効果を発揮するポイントをまとめています。
浅い呼吸を招く習慣の見直しや隠れ酸欠対策、香りや姿勢の工夫から、今日から短時間で始められる継続コツまで網羅しました。
まずは数分からでも集中力向上に呼吸法を役立ててみると良いでしょう。
「もっと集中力や記憶力を高めて、勉強や仕事に活かしたい」という方には、「吉永式記憶術」もおすすめ。科学的根拠に基づいた実践的なトレーニング法で、初心者でも無理なく取り組めます。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い指導を通じて記憶力向上と目標達成をサポートしています。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。