 キツネさん
キツネさん
誰でも物忘れに悩む瞬間があり、その改善策を探している方は少なくありません。
実は短期記憶は意識的に鍛えられ、集中力や学習効率を高めることが可能です。
本記事では、短期記憶の仕組みと効果的なトレーニング方法について解説します。
今日から実践できる工夫を取り入れ、記憶力アップにつなげていきましょう。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
短期記憶とは?|長期記憶との違いを理解する

短期記憶とは、数秒から数十秒の短い間だけ情報を保持する仕組みを指します。
電話番号を一時的に覚えるといった場面で使われるため、生活のあらゆる場面で重要な役割を担っています。
短期記憶の特徴について深堀りしていきましょう。
- 短期記憶の特徴と容量(7±2の法則)
- 短期記憶が使われる具体的な場面
- 短期記憶が弱い=記憶力が弱いではない
それぞれ順番に解説します。
短期記憶の特徴と容量(7±2の法則)
短期記憶は一度に保持できる情報量が限られており、その容量は一般的に「7±2の法則」に従うといわれています。
これはハーバード大学の心理学者ミラーが提唱した理論で、人は一度に5〜9個程度の情報しか処理できないことを意味します。
そのため、電話番号や暗証番号のように桁数が多い情報は、まとまりごとに区切ることで覚えやすくなるのです。
また、短期記憶は保持できる時間も非常に短いため、意識的な反復がなければすぐに忘れてしまいます。
この特性があるからこそ、効率的に情報を整理する工夫が記憶力の向上につながります。
参考:日本語文における係り受けとマジカルナンバー7±2 – 英語文の場合も含めて -|郵政省 通信総合研究所 関西先端研究センター 知的機能研究室
短期記憶が使われる具体的な場面
短期記憶は私たちの生活に欠かせない働きを持っており、行動や思考を支える重要な役割を果たしています。
短期記憶は会話や作業の最中に使われることが多く、さまざまなシーンで無意識のうちに活用されています。
- 会話の流れを理解するために直前の言葉を保持する
- 料理の手順を覚えながら実際に作業を進める
- 道順を確認しながら目的地に向かう
- 読書で前後の文脈をつなげて内容を理解する
- 勉強中に解答手順や説明を一時的に保持する
このように短期記憶は、瞬間的な情報処理だけでなく、理解や行動を支える基盤として大きな役割を果たしています。
そのため、日常生活の多くの場面で必要とされる欠かせない機能だといえるのです。
短期記憶が弱い=記憶力が弱いではない
短期記憶の容量が小さいと感じても、それが必ずしも全体的な記憶力の弱さを意味するわけではありません。
なぜなら、長期記憶は短期記憶とは異なる仕組みで働き、繰り返しや関連付けによって強化されるからです。
むしろ短期記憶は入口のような役割であり、その後の学習方法や情報整理の工夫次第で成果は大きく変わります。
例えば、重要な情報をまとめてノートに書き出したり、関連づけてストーリー化することで長期記憶に定着しやすくなります。
したがって、短期記憶の弱さを悲観するのではなく、長期記憶へと橋渡しする工夫を意識することが重要です。
短期記憶を鍛えるメリット

短期記憶を鍛えることは、学習や仕事の効率を高めるだけでなく、脳の健康維持にもつながります。
心理学や神経科学の研究により、短期記憶の強化は長期記憶の定着や認知機能全般に良い影響を与えることが示されています。
- 学習効率が高まる
- 仕事や日常生活でのパフォーマンス向上
- 認知症予防や脳の健康維持
それぞれ順番に解説します。
学習効率が高まる
短期記憶は、学んだ情報を一時的に保持し、整理して長期記憶に移す役割を担っています。
カナダの心理学者アトキンソンとシフリンによる記憶モデルでは、短期記憶の強化が新しい知識の定着を促進すると示されているのです。
例えば語学学習において、単語や文法を短期的に保持できれば、繰り返しの復習によって長期記憶に移しやすくなり、結果として理解力と習得スピードが上がります。
さらに、実験心理学の研究では、短期記憶を訓練した学生は、試験での正答率が有意に向上することが確認されています。
したがって短期記憶を強化することは、効率的な学習習慣の基盤を築く要素となるのです。
仕事や日常生活でのパフォーマンス向上
短期記憶は、会議での発言内容を保持したり、作業手順を一時的に管理したりする際に欠かせません。
ワーキングメモリー研究で知られるバッドリーのモデルによれば、短期記憶の機能が高い人は、情報処理やマルチタスキング能力で優位に立てることが分かっています。
例えば営業職では、顧客との会話内容を正確に覚えながら即座に提案を組み立てる能力が求められます。
また家庭生活においても、料理の手順を記憶しながら他の家事を同時進行するなど、短期記憶がパフォーマンスを左右する場面は多く存在するのです。
このように、短期記憶を鍛えることは、仕事の成果や日常の生産性を高める有効な手段といえます。
認知症予防や脳の健康維持
短期記憶を活性化する習慣は、加齢に伴う認知機能の低下を防ぐ効果が期待されています。
米国アルツハイマー協会の研究によると、記憶課題や脳トレーニングを続ける人は、認知症リスクが有意に低下する可能性があるとのことです。
さらに、短期記憶の訓練は海馬や前頭前野の神経可塑性を刺激し、新しい神経結合を形成すると神経科学で明らかになっています。
クロスワードや数独などの軽い課題でも効果が見られ、脳の健康維持に寄与すると考えられています。
したがって短期記憶を意識的に鍛えることは、長期的な脳の健康を守るための投資といえるのです。
参考:吉村貴子ほか(2022)『アルツハイマー型認知症とワーキングメモリ』
短期記憶を鍛えるには「ワーキングメモリ」を意識しよう

短期記憶と似た言葉として、ワーキングメモリーを聞いたことがあるかもしれません。
短期記憶を高めるには、ワーキングメモリの役割を理解し、その仕組みを意識することが大切です。
ワーキングメモリの定義と鍛え方について見ていきましょう。
- ワーキングメモリの仕組みと短期記憶の関係
- 具体的なトレーニング法(Nバック課題・暗算・記憶ゲーム)
- アプリや脳トレを活用する方法
それぞれ順番に解説します。
ワーキングメモリの仕組みと短期記憶の関係
ワーキングメモリとは、一時的に情報を保持しながら同時に処理する機能を担う脳の働きで、短期記憶をベースにしているため両者は深く結びついています。
たとえば会話中に相手の言葉を保持しながら返答を考える場面や、計算を行うときに数字を頭の中で並べ替える作業はワーキングメモリが関与しています。
ワーキングメモリと短期記憶の違いは以下の通りです。
| 項目 | ワーキングメモリ | 短期記憶 |
| 定義 | 一時的に情報を保持しながら、同時に処理・操作を行うシステム | 限られた情報を一時的に保持する仕組み |
| 主な役割 | 情報の保持と同時処理、思考や問題解決、学習の基盤 | 情報の短期間保存(保持のみ) |
| 容量 | 約4~7項目を操作可能 | 約7±2項目を保存可能(ミラーの法則) |
| 持続時間 | 数秒〜数十秒(処理を伴う) | 数秒〜数十秒(保持のみ) |
| 活用例 | 暗算、会話の文脈理解、読解中の前文保持 | 電話番号を一時的に覚える、短いフレーズを記憶する |
| 関与する脳部位 | 前頭前野(特に背外側前頭前野)、頭頂葉 | 海馬や大脳皮質の一部 |
| 特徴 | 「保持」と「操作」を同時に行う | 「保持」に特化している |
短期記憶は一時的な保存が中心ですが、ワーキングメモリは情報を操作しながら使う点が主な違いです。
この違いを理解すると、効率的なトレーニングや学習方法を設計する助けとなり、実生活でも役立ちます。
関連記事:今話題の「ワーキングメモリ」って何?日々の生活に深くかかわる脳のはたらきを解説
具体的なトレーニング法(Nバック課題・暗算・記憶ゲーム)
ワーキングメモリを鍛えるためには、Nバック課題や暗算、記憶ゲームなどを継続的に取り入れることが効果的とされています。
Nバック課題は、数列や記号を一定間隔で覚えて答えるタスクであり、記憶の保持と更新を同時に求められるため脳に強い刺激を与えます。
暗算は頭の中で数値を処理する作業を繰り返すことで、情報操作の柔軟性を高める効果を持ちます。
また、トランプやカードゲームのように記憶を必要とする遊びも楽しみながら鍛えられる方法です。
日常にこれらを組み込むことで、無理なく継続しやすく、結果的に記憶力向上へと結びついていきます。
参考:Nバック課題(N-back task) | NeUro+(ニューロプラス)
アプリや脳トレを活用する方法
アプリや脳トレを活用する方法では、日常生活の中で自然にトレーニングを取り入れられる点が強みとなります。
スマートフォンやタブレットを通じて利用できるアプリは、短時間でも効果的な練習を可能にします。
また、自動で記録される進捗データにより、自分の成長を客観的に把握できるのも大きな利点です。
- Lumosity(記憶力・注意力を鍛える脳トレアプリ)
- Peak(短時間でできるパズルや記憶課題が中心)
- CogniFit(脳科学に基づく多様な認知トレーニングを提供)
- Brain Wars(世界中のユーザーと対戦しながら楽しく脳を刺激できる)
これらのアプリを活用することで、紙や書籍では続きにくい人でも習慣化がしやすくなります。
結果として、楽しみながら持続可能な形でワーキングメモリや認知機能を強化できるのです。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
短期記憶を鍛えるトレーニング5選

具体的に、覚えたい情報を「長期記憶」に変えていく方法について紹介していきます。
仕事や勉強において記憶力を発揮できるよう「脱短期記憶」を目指してみましょう。
- 映像を頭にイメージしながら覚える
- 丸暗記を避けて理解を伴う学習を行う
- 軽い運動を取り入れながら覚える
- 音読や復唱で情報を強化する
- 記憶ゲームや暗算で脳を刺激する
関連記事:記憶力がないのは能力のせいじゃない!その理由と今日からできる記憶力を高める方法を紹介
① 映像を頭にイメージしながら覚える
海馬は、視覚的な要素を含む情報を記憶しやすく、長期記憶に残りやすい傾向があります。
これを利用して、脳に定着させたいものがあるときは「頭の中で映像をイメージしてみる」ことを意識してみましょう。
- 新聞記事や本を読みながら、内容を映画のように頭の中で映像で再現してみる
- 言葉で説明された手順を実際にやっている自分を頭に思い描いてみる
- 数字の語呂からイメージする映像を頭に思い浮かべてみる(電話番号、歴史の年号など)
このように、頭に映像として思い浮かべた情報は、長期記憶として保持されやすくなります。
イメージが苦手な方も、新聞や本を読みながら映像を思い浮かべる練習を続けることで、少しずつ想像力を高められます。
1日数分からでも、生活に取り入れて試してみると良いです。
関連記事:効率よく覚えるのにイメージ記憶が大切な理由|コツやトレーニング方法を紹介
② 丸暗記を避けて理解を伴う学習を行う
急いで暗記しようとすると、多くの人が「丸暗記」に頼ってしまいがちです。
しかし、単に言葉や数字をそのまま覚え込んでも、それらは短期記憶として扱われ、時間が経つとすぐに忘れてしまいます。
この問題を避けるためには、知識を一つずつ「深く理解する」姿勢が欠かせません。
- なぜそうなるのか
- どうしてその表現が使われているのか
- どんな経緯でこの公式や理論が生まれたのか
こうした理解を伴った学習は、情報を長期記憶に残しやすくし、知識を自分のものとして定着させる効果を発揮します。
自分の知識として長く脳に保持しておきたいことに関しては、それだけ時間をかけて「深く理解する」ことを意識してみましょう。
③ 軽い運動を取り入れながら覚える
軽い運動を取り入れながら学ぶ方法は、記憶力を高めたいときにとても効果的です。
実際、研究によっても軽い運動が脳を活性化させ、情報の定着を助けることが明らかになっています。
そのため、何か覚えたいことがあるときも、軽く体を動かしながら覚えることで記憶が定着しやすくなるのです。
ここで大切なのは「軽く行う」という点であり、激しい運動はかえって脳にストレスを与え、集中を妨げてしまいます。
運動がハードすぎると、逆に脳にストレスを与え負担となってしまうため、以下のような軽めの運動を取り入れるようにしましょう。
- ウォーキングやジョギング
- ヨガ、太極拳
- 簡単なダンスやエクササイズ(音楽を伴うものもおすすめ)
体を適度に動かしながら学習することで、記憶の定着がスムーズになり、学習効果を自然に高められます。
関連記事:記憶力を上げるトレーニング11選|簡単&習慣化しやすい方法まとめ
④ 音読や復唱で情報を強化する
音読や復唱は、視覚と聴覚を同時に使うことで記憶を補強する効果が確認されています。
ウォータールー大学の研究によれば、声に出して覚えた語句は黙読よりも記憶に残りやすいと報告されています。
これは声に出すという能動的な行為が情報を強調し、脳に刻み込む働きをするためです。
さらに自分の声を耳で聞くことで二重の刺激が加わり、暗記科目やスピーチ練習にも効果的といえます。
ただし長期的な学習では黙読が有利な場面もあるため、状況に応じた使い分けが重要になります。
参考:This time it’s personal: the memory benefit of hearing oneself
⑤ 記憶ゲームや暗算で脳を刺激する
短期記憶を鍛えるためには、遊び感覚で脳を使うトレーニングも効果的です。
神経衰弱や暗算などのシンプルな課題は、脳に心地よい負荷を与え、継続しやすいのが特徴です。
記憶を保持しながら使う作業はワーキングメモリを強化し、集中力や処理速度の向上にもつながります。
- トランプを使った神経衰弱(ペアのカードを覚えてめくる)
- 数字や図形の順番を一時的に覚えて答える「Nバック課題」
- 短時間で解く暗算トレーニング(足し算・引き算・掛け算)
- 買い物リストや単語を記憶し、後から思い出すチャレンジ
- カードを使った「絵合わせ」や「パターン再現」ゲーム
日常のスキマ時間に取り入れることで、自然と記憶力の底上げが期待できます。
また、楽しみながら取り組めるため、続けやすく、自然と記憶力の底上げが期待できます。
関連記事:【記憶力を高めるゲーム】無料で鍛える!子ども・高齢者向けおすすめ15選
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
年齢別の短期記憶トレーニング
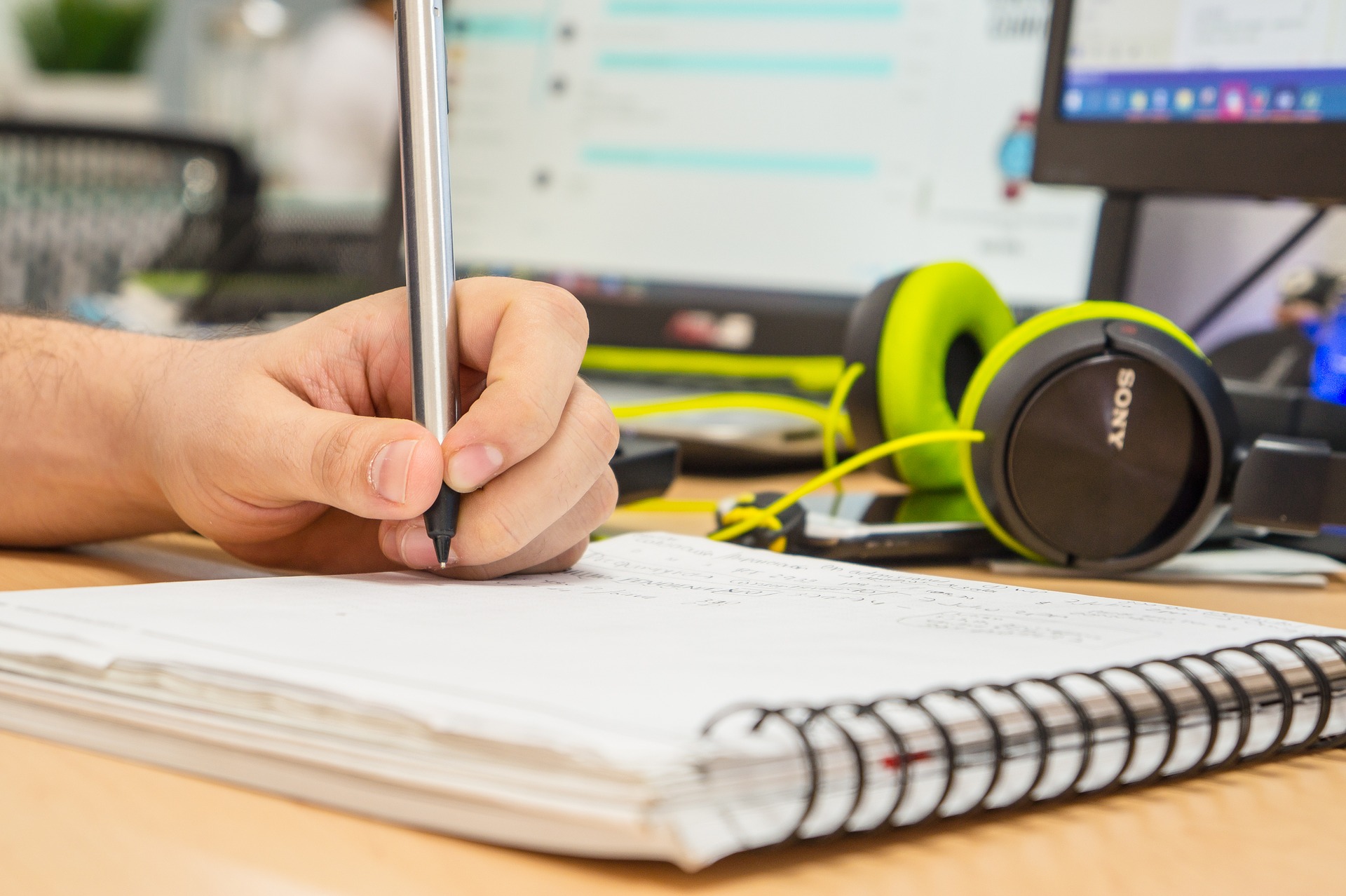
短期記憶の鍛え方は年齢によって効果的な方法が異なります。
子ども、大人、高齢者それぞれに合わせた工夫を取り入れることが、継続的に記憶力を高める秘訣となります。
- 子どもに効果的な遊び・プリント学習
- 大人におすすめの学習・仕事での鍛え方
- 高齢者・認知症予防に役立つ方法
子どもに効果的な遊び・プリント学習
子どもの短期記憶を鍛えるには、遊びと学習をバランスよく取り入れることが大切です。
遊びでは楽しく脳を刺激し、プリント学習では集中力を持続させる工夫が欠かせません。
それぞれの特徴を理解して組み合わせることで、自然に記憶力を伸ばすことができます。
- トランプを使った神経衰弱
- しりとりや言葉をつなぐ遊び
- カルタや絵合わせゲーム
これらの遊びは、同年代とも楽しみながら短期記憶を高められるため継続しやすいでしょう。
- 学研「幼児ワーク」
- 数字や図形を短時間で記憶して答える課題
- ポピー「ポピっこ」
- 間違い探しや図形パズルを解くプリント
- Z会 幼児コースのプリント教材
- 文章を読んで内容を再現する練習問題
- 七田式プリントA・B・C
- 右脳を使ったイメージ記憶や瞬間記憶トレーニング
これらプリント学習は体系的に記憶力を伸ばす仕組みが整っており、七田式のような右脳開発教材を組み合わせると効果がさらに高まります。
大人におすすめの学習・仕事での鍛え方
大人が短期記憶を強化するには、日常の学習や仕事の中で意識的に訓練することが効果的です。
例えば、読んだ文章を要約したり会議の内容をメモなしで再現する取り組みは、記憶保持と情報整理の両面を刺激しています。
さらに、暗算やNバック課題といった認知トレーニングを継続すると、仕事の効率や情報処理速度の向上が見込めるのです。
こうした習慣を積み重ねるほど記憶力は磨かれ、学習成果や業務パフォーマンスの向上に直結していきます。
短い時間でも毎日取り組む姿勢が、継続的な成長を支える鍵となるのです。
高齢者・認知症予防に役立つ方法
高齢者における短期記憶トレーニングは、認知症予防や生活の質を維持する上で大きな意味を持ちます。
例えば、買い物リストを覚えてから店に行く、新聞記事を音読して内容を話すといった日常動作は効果的です。
また、クロスワードや計算プリントなどの軽い課題は無理なく続けやすく、脳の活性化を促進します。
さらに、会話や趣味活動を通じて社会的交流を持つことは、記憶力だけでなく精神的な健康維持にもつながります。
楽しみながら継続できる工夫を取り入れることが、長期的な予防効果を生み出す鍵となります。
関連記事:高齢者の記憶力トレーニング8選|今日からできる脳活・アプリ・面白ゲーム
記憶術を取り入れて短期記憶を強化する

短期記憶を強化するには、記憶術を積極的に取り入れることが有効です。
情報を効率よく整理し、脳に残りやすい形に変換することで、忘れにくい知識として活用できます。
次のように記憶術を取り入れて短期記憶を強化する方法について見ていきます。
- 短期記憶を長期記憶に変える方法
- 記憶術で集中力と記憶力を同時に鍛える
それぞれ順番に解説します。
短期記憶を長期記憶に変える方法
短期記憶を長期記憶に移すには、反復と関連付けを意識した学習が欠かせません。
記憶はまず海馬で一時的に保持されますが、必要と判断された情報だけが整理されて長期記憶として保存されます。
この際、復習を繰り返すことで海馬が「重要な情報」と認識しやすくなり、記憶の定着率が高まるのです。
また、エビングハウスの忘却曲線の研究からも、学習直後は記憶が急速に失われることが示されており、30分後や数時間後に復習を行うと効果的であることが確認されています。
さらに、新しい情報を既存の知識や体験と結びつけたり、ストーリー化やイメージ化することで、脳内のネットワークが強化され、忘れにくい長期記憶へと変わっていくのです。
参考:記憶の保持率と時間の関係から考える効果的な復習方法|国立大学法人 大阪教育大学
関連記事:忘れない勉強法|エビングハウスの忘却曲線と復習スケジュール完全ガイド
記憶術で集中力と記憶力を同時に鍛える
記憶術を活用すると、集中力と記憶力を同時に鍛えられます。
例えば、マインドマップを使った学習では情報を階層的に整理でき、思考の流れを把握しやすくなるため集中が途切れにくくなります。
さらに、語呂合わせや頭文字法を取り入れると遊び感覚で学べるので、学習の負担を感じにくく継続しやすいのが利点です。
加えて、イメージ法やストーリーメソッドを実践すると、記憶が視覚や感情と結びつき、忘れにくく残りやすくなります。
このように記憶術は、集中と記憶の双方を高めるための実践的な手段といえます。
トレーニングしても短期記憶が良くならないと悩んだら、専門家の方法を学び実践してみるのが近道です。
関連記事:【簡単に実践できる】おすすめ記憶術トレーニング14選&アプリを紹介
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
短期記憶力を下げる原因と注意点
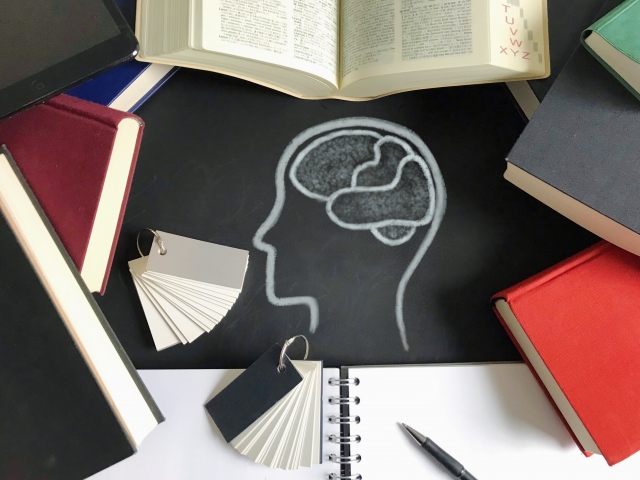
短期記憶力を下げる要因は、私たちの日常生活に密接に関係しています。
無自覚のうちに記憶力を損なう行動を続けると、学習や仕事の効率も大きく落ちてしまいます。
- ストレスや疲労がもたらす影響
- 生活習慣の乱れと睡眠不足
- マルチタスクやスマホ依存の弊害
ストレスや疲労がもたらす影響
強いストレスや慢性的な疲労は、脳の海馬に負担をかけ、記憶の保持力を低下させることが研究で示されています。
交感神経が過度に優位になると、集中力が落ちるうえに情報を整理する力も弱まるのです。
また、ストレスホルモンであるコルチゾールが増えると、短期記憶から長期記憶への移行が妨げられる仕組みが働きます。
さらに、記憶を司る脳の海馬を萎縮させるとされています。
日常的にリフレッシュの時間を取り、規則正しい休養を心がけることが大切です。
結果的に、精神面の安定が記憶力の維持に直結するのです。
参考:[コラム] ストレスホルモン「コルチゾール」と副腎の関係|小西統合医療内科
生活習慣の乱れと睡眠不足
生活習慣の乱れ、特に睡眠不足は短期記憶力を著しく下げる要因となります。
睡眠中に脳は情報を整理し、必要な記憶を固定化する働きを担っています。
そのため、寝不足が続くと新しい知識が定着しにくくなり、思考の切り替えや判断力も落ちやすくなるのです。
さらに夜更かしや食生活の偏りが重なると、脳の代謝や血流が悪化して記憶の効率も下がります。
まずは十分な睡眠とバランスの取れた生活リズムを整えることが欠かせません。
関連記事:記憶力と睡眠の関係
マルチタスクやスマホ依存の弊害
一度に複数の作業をこなそうとするマルチタスクは、脳の処理能力を分散させ、記憶の定着を妨げます。
短期記憶は容量が限られているため、次々と新しい情報が入ると古い内容が保持されにくくなるのです。
特にスマホ依存は、通知やSNSのチェックなどによって注意が細切れになり、集中を阻害する大きな要因です。
習慣的に情報を切り替えることが、記憶を浅いレベルで消耗させる原因になります。
意識的にシングルタスクを選び、デジタルデトックスの時間を確保する姿勢が求められます。
関連記事:スマホとストレスが思考力低下を招く?改善習慣と記憶術で取り戻す力
短期記憶に著しい困難がある場合の背景
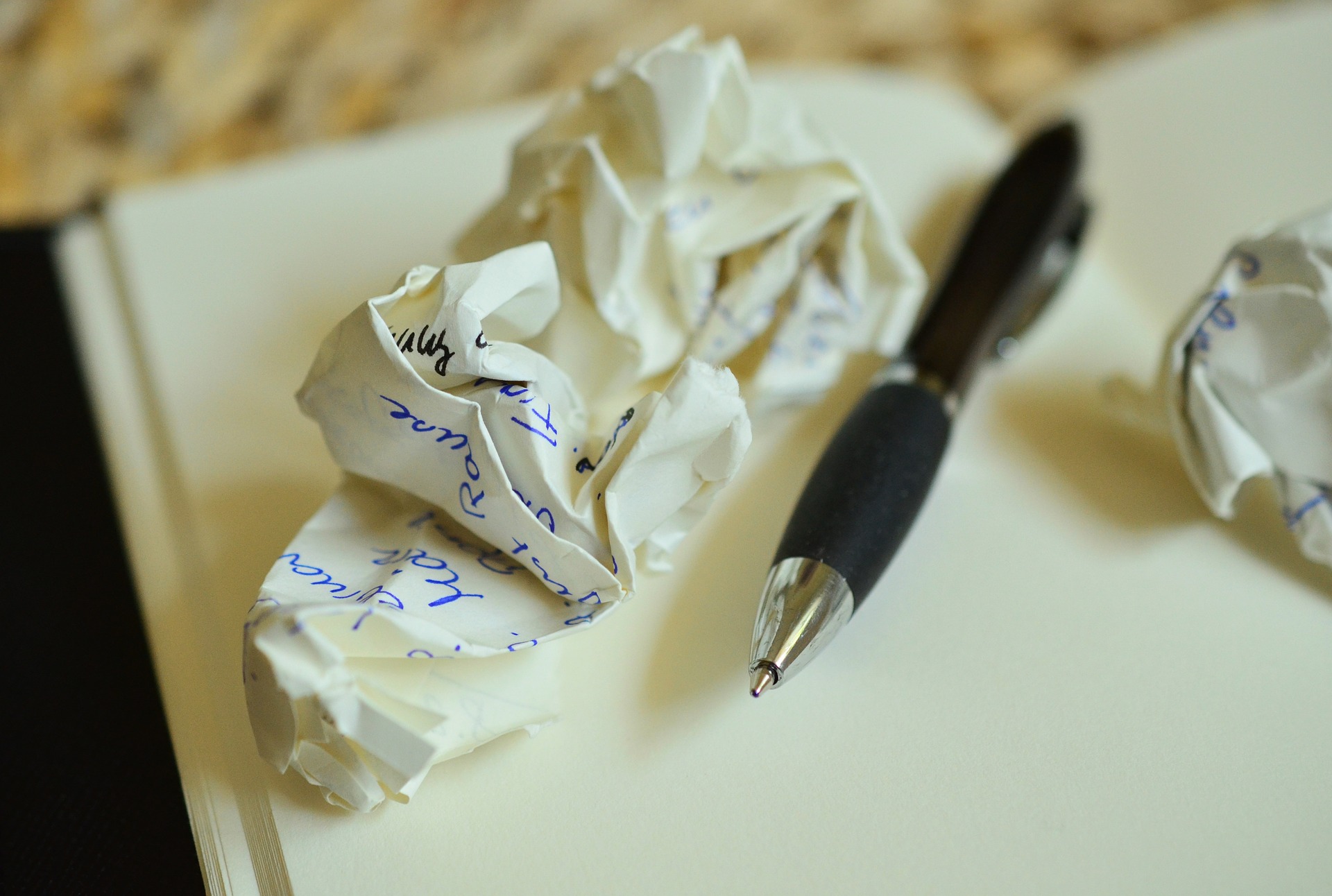
短期記憶に著しい困難がある背景には、医学的な要因と生活習慣的な要因が複雑に関わります。
脳の海馬や前頭葉の働きに障害が生じると、情報を一時的に保持し処理する力が低下します。
また、精神的ストレスや生活習慣の乱れも無視できない要因です。
- アルツハイマー型認知症や脳梗塞など神経疾患による脳機能障害
- 外傷性脳損傷などで海馬が損傷するケース
- うつ病や強いストレス、睡眠不足による記憶機能低下
- 薬の副作用による一時的な記憶障害
- 加齢に伴う脳の老化による自然な低下
これらの要因が重なり合うことで、短期記憶に深刻な困難が現れる場合があります。
早期に背景を見極め、医療機関での適切な対応や生活改善を図ることが重要です。
短期記憶の鍛え方に関するよくある質問
短期記憶の鍛え方に関するよくある質問を解説します。
短期記憶を鍛えるとどれくらいで効果が出る?
短期記憶を鍛えると、早い人では数週間ほどで効果を感じることがあります。
ただし多くの人は数か月単位の継続的な練習によって徐々に改善を実感するのが一般的です。
焦らず段階的に取り組む姿勢が成果につながり、継続こそ最大のポイントになります。
毎日どのくらいトレーニングすればよい?
短期記憶を鍛えるには、毎日15分から30分程度の練習を継続することが効果的です。
長時間行うよりも、集中して短時間を繰り返すほうが定着しやすく効率も良くなります。
スキマ時間を活用して1日の中に小分けで取り入れると習慣化しやすい点も魅力です。
子どもや高齢者にも効果的な方法はある?
子どもには遊び感覚で楽しめるカードゲームや記憶遊びが効果的といわれています。
高齢者には音読や暗唱など、日常生活で無理なく続けられる方法が適しています。
年齢を問わず楽しみながら続ける工夫が成果を生み出す鍵になるといえます。
脳トレアプリだけで記憶力は向上する?
脳トレアプリは記憶力を高める一助になりますが、それだけで大幅な改善は見込めません。
睡眠や食事、運動など生活習慣全体の改善と合わせて取り入れることが重要です。
補助的な役割として利用し、日常生活での多様な刺激と組み合わせると効果的です。
まとめ|短期記憶は鍛えられる能力として今日から実践しよう
本記事では、短期記憶の仕組みと鍛え方について解説しました。
ワーキングメモリを意識し、Nバックや暗算、イメージ化・復唱・軽運動で定着を促す要点を整理しています。
今日から15分のトレーニングを始め、生活習慣も整えてみてください。
「もっと集中力や記憶力を高めて、勉強や仕事に活かしたい」という方には、「吉永式記憶術」もおすすめです。科学的根拠に基づいた実践的なトレーニング法で、初心者でも無理なく取り組めます。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い指導を通じて記憶力向上と目標達成をサポートしています。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education
吉永式記憶術の口コミ・評判
吉永式記憶術は多くの方からお喜びの声を頂いております。
その声の一部をご紹介します。
50音に漢字のイメージをくっつけていく課題は、最初は覚えられなかったのですが、2週間ぐらい取り組むと10分ぐらいで覚えられるようになってきました。
真面目に取り組めば必ず結果が出る価値のあるものだと思います!孫にも伝えていきたいです!
引用:YGC吉永ジーニアスカレッジ 受講生実績
死ぬほど暗記が苦手だったのに、今ではスーッと覚えられて全く忘れないです!
ビジネスで成功して会社員から独立。人生が180度変わりました!
落ち続けた宅建試験に合格できました!
今まで苦労して勉強したTOEICのスコアがアップしました!外資系企業に転職できました!
学習障害の診断を受けて数学は絶対にできないと言われていたのに国公立医学部に合格できました。
引用:吉永式記憶術
先生のカウンセリングでトラウマに気づき語学習得も新たなチャレンジもできるようになりました!
引用:YGC吉永ジーニアスカレッジ 受講生実績

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。











