 キツネさん
キツネさん
「ワーキングメモリ」という言葉をご存知でしょうか?
脳や記憶、教育の分野において最近特に注目されている言葉で、私たちの生活にも深い関わりを持っています。
- 言われたことをすぐに忘れてしまう
- 暗算や暗記がスムーズにできない
- 2つのことを一度にやるのが苦手
こうした悩みを持つ方はワーキングメモリを鍛えることで、少しずつ解決していくことができるかもしれません。
今回の記事ではそんなワーキングメモリに関する情報や、普段の生活の中にも取り入れられる鍛え方について紹介していきます。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
ワーキングメモリとは?わかりやすく解説

ワーキングメモリとは、一時的に情報を保持しながらその中で思考や操作を行う脳の機能です。つまり、「脳内のメモ帳」として、会話の理解や計算、日々のタスク遂行に欠かせません。
一時的に情報を保ちつつ処理する機能は短期記憶と似ていますが、ワーキングメモリはさらに情報を加工・操作する点が異なります。
この機能には個人差があり、学習や仕事のパフォーマンスに影響を与えることも知られています。
H3 Baddeley & Hitchの理論とその後の拡張
Alan Baddeley と Graham Hitch が1974年に提唱したワーキングメモリモデルは、情報処理のしくみを3つの要素で説明します。
- 言語情報を扱う「音韻ループ」
- 視空間情報を扱う「視空間スケッチパッド」
- そしてそれらを統括し処理資源を制御する「中央実行系」
2000年には「エピソード・バッファー」という第四の構成要素が加わり、視覚・音声・意味情報を統合する役割が明確になりました。
これらのモデルは、記憶と認知機能の複雑な連携を理解する上で重要な枠組みです。
脳のどの部分が使われているのか
ワーキングメモリは主に前頭前野が中心となって機能しています。
この部位は計画や意思決定、情報の統制など高次認知機能を担っており、ワーキングメモリを制御する「心の黒板」とも形容されます。
さらに、頭頂皮質、前帯状皮質、大脳基底核の一部も連携しながら認知処理を助けています。また、海馬や歯状回などの領域も、必要な情報を保持し不必要な情報を抑制する神経メカニズムにおいて重要な役割を果たすことが近年の研究で明らかになっています。
参照 : UTokyo 作業記憶(ワーキングメモリ)の脳メカニズムを解明
ワーキングメモリが低いとどうなる?

ワーキングメモリが低いと、短期記憶や注意力、処理速度の低下が目立ち、学習や日常生活にさまざまな困難が生じます。
たとえば、会話の途中で内容が飛んでしまったり、複数のタスクを効率よくこなせず、計画が立てられないこともあります。
こうした困りごとを理解することで、適切な支援や習慣形成につなげられます。
処理速度や注意力への影響
ワーキングメモリが低い場合、視覚情報をすばやく処理する処理速度(PSI)が低下しやすく、板書やプリントの内容を見て覚える作業が遅れがちになります。
また、注意の切り替えが苦手なケースもあり、授業中や会話中に集中を維持しにくくなります。
こうした処理速度の遅れは、学習効率や日々の生活リズムにも影響を及ぼすことが明らかになっています。
低下のサインと自己チェック項目
低いワーキングメモリには、以下のようなサインがみられることがあります。
- 話の内容をすぐ忘れる
- 複数のタスクを同時にこなせない
- 忘れ物やミスが増える
- 会話がかみ合わない場面がある
- 計画や整理が苦手
これらの傾向は、自覚だけでなく周囲の指摘や小さなトラブルの蓄積として現れることも多く、家族や教師と共有して早期に対策を講じることが大切です。
ワーキングメモリの平均値と比較
成人のワーキングメモリの平均的な能力を測る指標としては、数字であれば「5~7桁」、言葉なら「2~4語」が保持可能とされています。
加えて、年齢ごとの成長傾向としては、7歳で1語、11歳で2語、20歳前後で約3語を保持できるという報告もあります。
このように、ワーキングメモリには加齢による変化があり、自身の傾向を知ることは適切な訓練法やサポートを選ぶ上で重要です。
ワーキングメモリと発達障害(ADHD)との関係

ワーキングメモリは情報の一時保持と処理を担う重要な脳機能ですが、ADHD(注意欠如・多動性障害)のある方においては、しばしばこの機能に弱さが見られます。
その結果、指示された内容を直前に忘れてしまう、不注意な行動が増えるなどの困難につながります。
ただし一方で、記憶力や学習成果が高いケースもあり、ワーキングメモリとADHDの関連は一律ではありません。
ADHDの特徴とワーキングメモリの関係性
ADHDでは、不注意や衝動性がワーキングメモリの弱さと深く関連していることが知られています。
例えば、人から受けた話や指示をすぐ忘れてしまったり、複数の情報を同時に処理する作業が苦手だったりするのは、ワーキングメモリの低さが原因のひとつとされています。
しかし、学力や記憶力自体は高いこともあり、これはワーキングメモリが「作業用の机」に例えられるように、「記憶の引き出し(長期記憶)」とは別の能力であることの表れです。
参照
: d-career ADHDの特性:ワーキングメモリ
: ワーキングメモリ(記憶力)とは?発達障害との関係、IQ検査、治療法について
発達障害でもワーキングメモリが高い人の傾向
一方で、ADHDのある方でも、ワーキングメモリが高いタイプも存在します。
興味や関心が強い対象に対しては、驚くほど集中し記憶処理がスムーズになることがあります。これは、課題への動機づけや親和性によってワーキングメモリのパフォーマンスが変わることを示唆しています。
つまり、環境や課題内容によって能力の発揮度が左右されるのがADHDの特徴のひとつです。
ワーキングメモリを鍛えて容量を増やすトレーニング

ワーキングメモリを向上させるには、日常的に負荷をかけ続けることが大切です。
具体的には、計算や会話、アプリといったトレーニングを通して「瞬時に保持し処理する力」を養います。また、複数の課題を同時にこなすデュアルタスクや、イメージやメモ術を活かす記憶術も効果的で、脳の柔軟性や情報処理力の改善につながります。
これらの方法をどのように活用すればよいか、以下のセクションで詳しく見ていきましょう。
脳トレーニングの具体例(暗算・会話・アプリ)
ワーキングメモリを鍛える日常的な方法には、以下のようなものがあります。
- 暗算:買い物中に合計金額を計算
- 音読:文章を読みながら要約
- 会話:相手の発言を記憶しながら応答
- アプリ:脳トレアプリで短期記憶タスクを反復
特に、アプリを6週間以上継続使用すると効果が高まるという研究もあります。スマートフォンで簡単に始められるのが利点です。
参照 : 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター|あたまとからだを元気にするMCIハンドブック
関連記事 : 高齢者の記憶力トレーニング8選|今日からできる脳活・アプリ・面白ゲーム
デュアルタスクとは?
デュアルタスクとは、複数のタスクを同時に処理するトレーニングで、認知負荷を高める効果があります。
- 「歩きながら暗算」
- 「スクワットしながら言葉しりとり」
- 「手遊びしながら数字を逆唱」
このように、運動と認知課題を組み合わせた「コグニサイズ」は、国立長寿医療研究センターでも推奨されています。
認知機能の維持・向上に有効で、家庭で無理なく実践できます。
記憶術(イメージ法、メモ術)
記憶力を高めるテクニックとして、以下のような方法が知られています。
- イメージ法:数字や言葉を映像として思い描く
- 場所法:情報を「場所」に結びつけて記憶する(メモリーパレス)
- メモ術:脳外に記録し、ワーキングメモリを節約する
特に、方眼ノートなどに短く記録するメモ術は、緊張時にも思考整理を助ける手段として注目されています。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
ワーキングメモリ・記憶力に関するよくある悩み
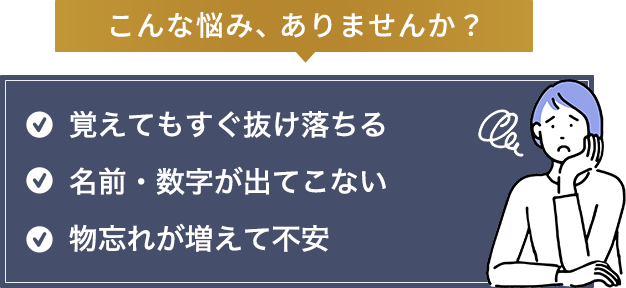
覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。
それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。
無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
ワーキングメモリのテスト・測定法を知ろう

ワーキングメモリの状態を把握するには、定期的な検査やセルフチェックが効果的です。
認知機能は年齢や生活習慣によって変化するため、早期に気づき、適切なトレーニングや環境調整に繋げることが大切です。
専門機関での測定に加え、自宅でできる簡易な方法も多数あります。
HUCRoW以外の代表的なテスト
医療・教育の現場で使用されるワーキングメモリ測定法には、いくつかの標準的な検査があります。
特に代表的なものとして以下が挙げられます。
- AWMA(Automated Working Memory Assessment)
- WAIS(ウェクスラー式知能検査)に含まれるワーキングメモリ指数
- WISC(子ども向け知能検査)のサブテストとしての数字スパン
これらは診断・支援の出発点として用いられ、正確な把握に役立ちます。
自宅でできる簡易セルフチェック
ワーキングメモリを気軽に確認したい場合は、オンラインツールやアプリを使った簡易チェックがおすすめです。
以下のような方法がよく使われています。
- 数字スパンテスト(順・逆順記憶)
- Corsiブロックタッピングテスト(視覚的な順番記憶)
- デジタル記号置換テスト(記号と数字の対応を高速処理)
これらは医療診断ではないものの、記憶力の傾向を知る参考になります。
ワーキングメモリに困難を抱える人への対応策

ワーキングメモリが低くても、工夫次第で日常生活や学習・仕事の質を大きく改善できます。
重要なのは、情報負荷を軽減する工夫や可視化の習慣、反復や補助を取り入れることです。
以下では、大人向けと子ども向けに分けて具体的な対応策をご紹介します。
大人の場合の工夫(仕事・生活)
ワーキングメモリが苦手な大人には、以下のような対応策が効果的です
- 情報の受け皿を外部に作る(メモ・スマホ・付箋など)
- タスクの見える化:To-Do リストやスケジュールで整理
- 切り替えタイミングの設定:タイマーやアラームを活用
- 集中環境の整備:ノイズキャンセラーや仕切りの使用
こうした工夫によって、記憶の負荷を減らし、行動の確実性と安心感が高まります。
関連記事 : 【簡単に実践できる】おすすめ記憶術トレーニング14選&アプリを紹介
子どもの支援方法(学校・家庭)
子どもがワーキングメモリの困難を抱える場合、以下の方法が支援につながります。
- 情報を視覚化:絵や図、手順書で示して理解しやすく
- 指示を段階的に簡潔に伝える:一度に複数の情報を伝えない
- 繰り返しによる定着:翌日や数日後に復習の時間を設ける
- 遊びやゲームを取り入れる:数字ゲーム、後出しじゃんけん、絵本読み聞かせなど楽しみながら訓練
これらの支援は、子どもの自信と学びの持続性を高める手助けになります。
ワーキングメモリに関するよくある質問
ワーキングメモリに関して、「大人でも鍛えられるの?」「どのくらい効果があるの?」「処理速度と記憶力はどう違うの?」という疑問はとても多いです。
そこで以下では、それぞれの疑問に対し、研究結果や認知心理学の視点からわかりやすく回答していきます。
大人でも鍛えられるの?
研究によると、健康な大人でもワーキングメモリの訓練により機能向上が期待できることが示されています。
例えば、構造化されたトレーニングを一定期間続けた被験者に、ワーキングメモリや推論力の向上が見られたという報告があります。
一方で、速度や幅広い認知へ効果が波及するには限界があるともされています。これは、訓練対象や継続期間、方法の違いによって効果が変わるためであり、一般的には短期的な向上がまず期待できるといえます。
参照 : ワーキングメモリトレーニングと知能(J‑Stage)
トレーニングはどのくらい効果がある?
ワーキングメモリのトレーニングは、訓練したタスクに対しては確かな成果が確認される「トレーニング効果」が得られることが多いです。しかし、日常生活や他の認知課題にまでその効果が波及する「転移効果」は限定的とする研究が多いのも事実です。
一部の研究では、中高年で処理速度や推論力にも長期的な改善が認められたという結果もありますが、総じて「短期的な成果」「タスク依存の改善」がメインであると考えられます。
参照 : ワーキングメモリトレーニングと流動性知能(J‑Stage)
処理速度と記憶力の違いは?
「処理速度」とは、新しい情報をどれだけ速く理解・反応できるかという能力です。
一方「ワーキングメモリ」は、その情報を一時的に保持しながら操作する機能を指します。処理速度が速いと、同じ内容を短時間で記憶しやすくなるという利点がありますが、ワーキングメモリとは別の認知資源です。
研究によれば、処理速度はしばしば一般知能との相関が強く、情報保持そのものよりも反応性に関与する要素とされています。
まとめ|ワーキングメモリを鍛えて集中力と記憶力を底上げしよう!
ワーキングメモリは、集中力や判断力、記憶の整理に欠かせない「脳の作業机」ともいえる存在です。そしてその機能は、意識的なトレーニングによって強化できます。
特に、軽い運動やイメージを使った記憶術、日々の会話や暗算といった習慣は、ワーキングメモリの向上に効果的であることが科学的にも示されています。
まずは、ウォーキングやストレッチなどの軽運動に加えて、1日数分の記憶トレーニングを取り入れてみましょう。生活の中に無理なく続けられる形で取り組むことが、成果を生むカギです。
さらに「記憶力」や「集中力」を効率よく伸ばしたい方には、科学的根拠に基づいた記憶術トレーニングの活用もおすすめです。
ワーキングメモリを効果的に鍛えるメソッドを知りたい方は、下記より詳細をご覧ください。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。












