 キツネさん
キツネさん
「お酒は記憶力に悪いのかな?」
「勉強と両立できるの?」
二日酔いや寝つきの悪さで学びが台なしになった経験は、誰しもありますよね。
お酒と記憶力の関係は、良い面と悪い面が入り交じるデリケートなテーマです。
「嫌なことは飲んで忘れる」という発想は身近ですが、実際の脳への影響は単純ではありません。
本記事では、アルコールが脳に及ぼす作用と、勉強に活かせる上手な飲み方を丁寧に解説しています。
要点を押さえて飲酒のタイミングと量を整え、今夜の一杯に自分なりのルールを設けましょう。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
お酒と記憶力の基本的な関係

お酒と記憶力の関係は、健康維持や認知機能に深く関わる大切なテーマです。
社会人で試験勉強などする際には、お酒の勢いで勉強したくなる場合もありますね。
ここでは、以下について順番に解説します。
- 過度な飲酒が脳に与える危険性
- 飲酒習慣と認知症リスクの関連
- 「嫌なことを忘れるためのお酒」は逆効果になる理由
それぞれ見ていきましょう。
過度な飲酒が脳に与える危険性
過度な飲酒は脳の神経細胞を傷つけ、海馬の機能を低下させる恐れがあります。
短期間の大量摂取は急性中毒や記憶の断片化を招き、長期的には脳の萎縮や認知力低下につながります。
厚生労働省は適度な飲酒量を1日純アルコール約20g(ビール中瓶1本、日本酒1合、ワイン2杯程度)としています。
この目安を守り、飲酒量を管理することが記憶力を守るために重要です。
参考:アルコール|厚生労働省
飲酒習慣と認知症リスクの関連
飲酒習慣は認知症の発症リスクに密接に関わっていることが、日本の大規模調査でも明らかになっています。
国立がん研究センターの多目的コホート研究(JPHC Study)では、約4万3千人を対象に20年間追跡した結果、週75g未満の少量飲酒者と比べて、週450g以上の多量飲酒者や長期の非飲酒者は認知症リスクが高いことが確認されました。
特に継続して飲酒している人では、飲酒量が増えるほどリスクが高まる傾向が示されています。
一方で、非飲酒者のリスク上昇には、過去の病歴やアルコール代謝に関わる遺伝的要因が影響している可能性も指摘されています。
この研究から、多量飲酒を避けつつ少量にとどめる「節度ある飲酒」が、認知症予防や健康維持の観点から重要であると結論づけられています。
「嫌なことを忘れるためのお酒」は逆効果になる理由
嫌なことを忘れるためにお酒を飲む習慣は、一時的な気分転換になるものの根本的な解決にはつながりません。
アルコールは記憶の定着を妨げるため、ストレス解消どころか翌日に強い倦怠感や不安感を残す可能性があります。
その結果、嫌な出来事をより強く思い出してしまい、自己嫌悪や精神的な負担を増幅させてしまうのです。
さらに、この行動が繰り返されると飲酒量が増え、依存症に発展するリスクを高める恐れがあります。
健全に嫌な出来事と向き合うためには、運動や趣味、カウンセリングなど別の方法を取り入れることが効果的です。
関連記事:簡単・効果的!記憶術テクニック13選|仕組みと記憶力アップのコツを解説
お酒で記憶をなくすのは「脳がまひ」するから

お酒を大量に飲むと「記憶がなくなる」のは、脳の働きがアルコールでまひするためです。
特に新しい記憶を司る海馬が影響を受けると、その間の出来事を保存できなくなります。
同時に、小脳がまひすれば千鳥足や呂律の乱れが現れ、さらに進行すると脳全体が機能不全に陥り、昏睡に至る危険もあります。
つまり、「記憶が飛ぶ」状態は単なる酔いではなく、脳が危険信号を出している証拠です。
繰り返すことで脳細胞がダメージを受け、認知症リスクも高まるため、節度を持った飲酒が不可欠といえます。
参照:東邦大学医療センター 佐倉病院 脳神経内科「お酒とからだ〜脳神経との関係」
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶力に関するよくある悩み
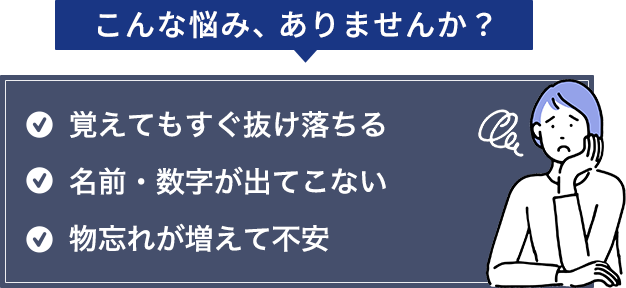 ▼
▼覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。
それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。
無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。
今ならLINE登録だけで、
記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
お酒で記憶力が上がると言われる噂の真相

お酒で記憶力が高まると聞いたことがある人もいるかもしれません。
しかし、実際には科学的根拠が限られており、誤解を招きやすいテーマでもあります。
- 学習直後の少量飲酒が記憶定着に与える可能性
- 実験結果と現実生活の違いを理解する
- 例外的効果に依存しないリスク管理
それぞれ順番に解説します。
学習直後の少量飲酒が記憶定着に与える可能性
一部の研究では、学習直後に少量のアルコールを摂取すると、前日に覚えた内容が翌日によく思い出せる可能性が示されています。
例えば、エクセター大学の研究では88名の参加者に語彙課題を与え、飲酒群と非飲酒群を比較した結果、飲酒群の方が多くの単語を記憶していました。
この現象は、アルコールによって新しい情報の取り込みが一時的に抑えられ、その分直前の学習内容に脳資源が集中したためと考えられています。ただし、この効果は「特定条件での一時的な観察結果」であり、日常生活で再現できるものではありません。
実際の勉強習慣に応用するのはリスクが大きく、少量であっても飲酒は睡眠の質を低下させ、翌日のパフォーマンスを妨げる可能性が高いのです。
結論として、勉強効率を高めたい人が飲酒に頼るべきではなく、睡眠・復習・運動といった健全な方法を優先するのが賢明です。
参考:Alcohol boosts recall of earlier learning|University of Exeter
実験結果と現実生活の違いを理解する
先程のエクセター大学の研究などでは、学習直後に飲酒した人が翌日に学んだ内容をよく覚えていたと報告されています。
しかし、この効果は特定の条件下でのみ確認された一時的な結果であり、日常生活で同じように再現できるとは限りません。
現実には飲酒量やタイミングを細かく調整することは難しく、むしろ記憶の欠落や健康被害といった悪影響を招く可能性のほうが高いのです。
さらに、アルコールの影響は体質や健康状態によって大きく異なるため、誰にでも当てはまるものではありません。
したがって、実験結果を過信せず、科学的知見を正しく理解して活用する姿勢が健康を守る上で欠かせないといえます。
例外的効果に依存しないリスク管理
お酒に含まれる限定的な効果だけを根拠に、記憶力向上を目的とした飲酒を習慣化するのは危険です。
なぜなら、アルコールには依存性や肝機能障害、生活習慣病リスクといった重大なデメリットが存在します。
長期的に見れば、わずかなプラス効果よりも健康を損なうリスクのほうがはるかに大きいのです。
記憶力を鍛えるには、睡眠・学習習慣・運動など健全な手段のほうが確実で持続性があります。
そのため、アルコールに頼らずリスクを避ける選択こそ賢明な判断といえます。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
勉強とお酒を両立させる上手な方法

勉強や仕事を頑張ったあとにお酒を楽しみたいと思う人は多いでしょう。
ただし、飲み方を工夫しないと集中力や記憶力に悪影響を与えてしまいます。
- 勉強や仕事後のごほうびとして飲む
- アルコール度数の低いものを少量に留める
- アルコール分解を助ける食材や飲み物を取り入れる
- 「寝酒」は避けて自然な睡眠を優先する
ここでは、それぞれのポイントについて順に説明していきます。
勉強や仕事後のごほうびとして飲む
お酒は勉強や仕事を終えたごほうびとして楽しむことで、モチベーション維持につながります。
前もって「ここまでやったら飲む」と区切りを設定すれば、集中力を高めつつ充実した達成感を得られるのです。
ただし、勉強の途中に飲んでしまうと脳の働きが低下し、効率が落ちるため注意が必要になります。
あくまで努力の成果を確認する場面で活用することで、飲酒を前向きな習慣へと変えることができるでしょう。
このように、ごほうびとしての飲酒は勉強とのバランスを取る工夫のひとつといえます。
アルコール度数の低いものを少量に留める
勉強との両立を意識するなら、アルコール度数の低い飲み物を選び、量を抑えることが重要です。
なぜなら、強いお酒や大量摂取は脳の働きを鈍らせ、学んだ知識の整理や記憶の保持を妨げてしまうからです。
軽めのビールやワインを少量だけにしておけば、リラックス効果を得ながら体への負担を小さくできます。
さらに、翌日に影響を残さないためには「少し足りない」と感じるくらいでやめておくのが理想的です。
この習慣を守ることで、健康と学習効率を両立しやすくなるのです。
アルコール分解を助ける食材や飲み物を取り入れる
飲酒による体への負担を和らげるためには、アルコール分解を助ける食材や飲み物を取り入れる工夫が欠かせません。
例えば、しじみや枝豆、チーズなどは肝臓の働きを支え、豚肉やレバーなどのビタミンB群を含む食品は代謝を促進します。
また、水分をこまめに摂ることで体内のアルコール濃度を下げ、翌日の体調不良を防ぎやすくなるのです。
一緒に摂るものを意識するだけで、お酒の影響を和らげつつ学習に支障を残さない効果が期待できます。つまり、飲み方だけでなく食べ方の工夫も両立には大切な要素といえるのです。
- しじみの味噌汁:オルニチンが肝機能をサポート
- 枝豆やチーズ:たんぱく質が分解酵素の働きを助ける
- 豚肉やレバー:ビタミンB群が代謝を促進
- 水やスポーツドリンク:体内のアルコール濃度を下げ、脱水を防ぐ
「寝酒」は避けて自然な睡眠を優先する
勉強後の休息には十分な睡眠が欠かせませんが、寝酒に頼ると睡眠の質を下げてしまう危険があります。
確かにアルコールは寝つきを良くする作用がありますが、深い眠りを妨げて脳の回復や記憶整理を妨害します。
その結果、せっかく学んだことが定着せず、翌日のパフォーマンス低下につながりやすくなるのです。
そのため、就寝の3~4時間前に飲み終えることから逆算し、勉強を終わらせるのが良いでしょう。
また、自然な睡眠を確保するためには、軽いストレッチや入浴など、飲酒以外のリラックス方法を取り入れるのが望ましいです。
このように「寝酒を避ける」ことは、勉強とお酒を両立させるうえで非常に重要なポイントになります。
参考:寝酒とは何か?【睡眠に与える影響とリスク】|阪野クリニック
二日酔いが勉強効率に及ぼす影響

二日酔いは単なる体調不良にとどまらず、学習効率を大きく低下させる要因になります。
頭痛やだるさだけでなく、脳の記憶・集中機能に深刻な影響を及ぼす点が見逃せません。
- 睡眠の質低下による記憶定着への悪影響
- 翌日の集中力や注意力に現れる問題
- 試験前日の飲酒を避けるべき理由
ここでは、それぞれの影響について詳しく見ていきます。
睡眠の質低下による記憶定着への悪影響
二日酔いの最大の問題は、アルコールによって睡眠の質が著しく低下する点にあります。
アルコールは寝つきを良くする作用がある一方で、深い睡眠を妨げ、脳が学習内容を整理する重要な段階を奪ってしまうのです。
特に記憶を長期保存へと移行させるプロセスが阻害され、せっかく勉強した内容が定着しにくくなります。
そのため、飲酒をした翌朝には「学んだはずなのに覚えていない」という状況に陥りやすくなります。
つまり、睡眠の質を下げることで学習効率を大幅に損なうのが二日酔いの大きなリスクなのです。
関連記事:記憶力と睡眠の関係
翌日の集中力や注意力に現れる問題
二日酔いになると脳の働きが鈍くなり、集中力や注意力が大きく低下します。
頭痛や吐き気などの不快な症状に気を取られることで、勉強に必要な持続的な集中ができなくなるのです。
また、作業効率が著しく下がるだけでなく、誤字や計算ミスといった小さなエラーも頻発しやすくなります。
特に論理的な思考や複雑な問題解決には影響が大きく、学習成果に直結する点が深刻といえます。
したがって、翌日に高いパフォーマンスを求められる場面では飲酒を避けることが望ましいのです。
試験前日の飲酒を避けるべき理由
試験前日に飲酒をすると、睡眠の質や脳の働きが低下し、学習内容が頭に残りにくくなります。
たとえ短時間のリフレッシュ目的であっても、アルコールは記憶の整理を妨害し、翌日の試験に大きな不利をもたらします。
また、二日酔いによる体調不良は試験本番での集中を乱し、本来の力を発揮できない原因になります。
その結果、長期間準備してきた努力が飲酒によって水の泡になる可能性すらあるのです。
このように試験前日は飲酒を避け、最大限のコンディションを整えることが成功につながるといえます。
お酒で記憶をなくさないための対策

お酒を飲んで記憶をなくすのは脳がまひするほどの危険な状態を意味します。
しかし、飲み方や習慣を少し工夫するだけで、リスクを大幅に減らすことができます。
- まずは飲みすぎないことを徹底する
- 食べ物と一緒に摂取して吸収を遅らせる
- 十分に水分摂取で代謝を促す
ここでは、それぞれのポイントをわかりやすく解説していきます。
まずは飲みすぎないことを徹底する
大前提として、お酒を飲みすぎないという強い意志を持つことが欠かせません。アルコールの分解能力や許容量は人によって異なり、体質やその日の体調によっても変動します。
「自分はこれくらい大丈夫」と思っていても、気づいたら泥酔して記憶を失うことは十分に起こり得ます。
さらに、過剰な飲酒は単なる記憶障害にとどまらず、急性アルコール中毒のリスクを大幅に高める危険があります。
飲み会でも周囲の目よりも自分の命と健康を優先し、飲みすぎない姿勢を徹底することが最も重要な対策なのです。
食べ物と一緒に摂取して吸収を遅らせる
空腹でお酒を飲むと、アルコールが一気に体に回り、悪酔いや記憶障害を引き起こしやすくなります。
そのため、飲酒の際には必ず食べ物と一緒に摂ることが大切です。
特に脂質やたんぱく質を含む食材は吸収を遅らせる働きがあり、体への負担を軽減できます。
- アルコールの吸収を緩やかにして悪酔いを防ぐ
- 胃の粘膜を保護して刺激を和らげる
- 血中アルコール濃度の急上昇を抑え、記憶障害を防ぐ
- 飲み会などでも体調を崩しにくくなる
「飲むときは必ず食べる」という意識を持つだけで、健康的にお酒を楽しむ習慣につながります。
結果として、記憶を失わずに安心して飲酒を楽しむことができるでしょう。
十分に水分摂取で代謝を促す
お酒を飲み続けると血中アルコール濃度が上昇し、脳や体に大きな負担を与えてしまいます。
そのため、飲酒時にはこまめに水分を摂ることが不可欠であり、代謝を促すことで体調不良を防ぐ効果もあります。
実際に、水や炭酸水を取り入れるだけで翌日の体調が大きく変わると感じる人も少なくありません。
- アルコール度数の高いお酒は水や炭酸で割る
- お酒と水を交互に飲む習慣をつける
- 飲み会中は定期的に水を注文する
こうした工夫を意識するだけで、酔いが和らぎ記憶を失うリスクを減らすことが可能になります。
水分補給を徹底することは、体を守りながらお酒を楽しむうえで欠かせない基本の対策といえるのです。
お酒と勉強に関するよくある質問
お酒と勉強に関するよくある質問を解説します。
試験前夜に少量のビールなら問題ない?
試験前夜に「少量のビールならリラックス効果もあるのでは」と考える人は多いですが、実際にはアルコールは睡眠の質を低下させる作用が確認されています。
深い眠りが妨げられると記憶の定着が阻害され、翌日のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。
したがって、少量であっても試験直前は避けることが望ましいといえます。
ノンアルコール飲料は記憶力や勉強に影響する?
ノンアルコール飲料はアルコール度数0.00%のものもありますが、0.5%未満を含む製品も存在しています。
0.00%なら問題ないですが、少量のアルコールであっても人によっては眠気や集中力低下を引き起こす可能性があります。
さらに心理的に「飲酒した」という感覚が働くことで勉強への意欲が弱まることもあるため注意が必要です。
ウイスキーとビールで勉強への影響は違う?
ウイスキーとビールではアルコール度数が大きく異なるため、同じ量を飲んだ場合でも体内への吸収スピードや血中濃度が変わってきます。
ウイスキーのような高濃度のアルコールは少量でも脳機能に強い影響を与える可能性が高いです。
一方、ビールも量が増えれば同様に集中力や記憶力を低下させるため、どちらも勉強前には避けることが賢明です。
まとめ|お酒と記憶力の関係を理解して勉強に役立つ飲み方を選ぼう

本記事では、お酒が記憶力や学習効率に及ぼす影響、そして勉強と両立させるための飲み方や工夫について解説しました。
「酒は百薬の長」と言われるように、自分の体に合った量を守れば、健康に良い影響を与えることもあります。
しかし、限度を超えると記憶を失ったり、脳へのダメージが増えたり、認知症リスクを高めたりと、途端に害となってしまいます。
だからこそ、お酒のリスクを理解したうえで適切に付き合えば、学習や仕事の質を上げる味方にもなり得ます。
もし「自分は飲み方が乱れているかも」と感じたなら、この記事を参考にして、少しずつ改善を試してみてください。
「もっと集中力や記憶力を高めて、勉強に活かしたい」という方には、「吉永式記憶術」もおすすめ。科学的根拠に基づいた実践的なトレーニング法で、初心者でも無理なく取り組めます。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い指導を通じて記憶力向上と目標達成をサポートしています。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。












