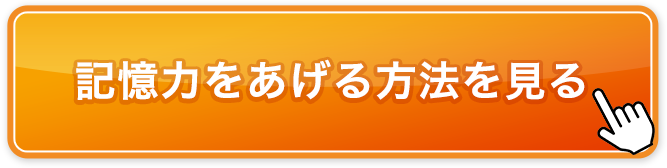キツネさん
キツネさん
「覚えたはずの内容をすぐ忘れてしまう!」
社会人になると暗記に苦労する場面が多くなり、記憶力の衰えを感じて悩む人も少なくありません。
そこで今回は、仕事や資格勉強で使える社会人向けの暗記テクニックを紹介します。
短時間でも記憶を効率良く定着させる方法を、具体的に解説していきますので、ぜひ活用してみてください。
なお、記憶力の上げ方については記憶力を上げる方法とは?|誰でもできる記憶向上テクニックを紹介の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
もくじ
社会人に暗記が必要な理由
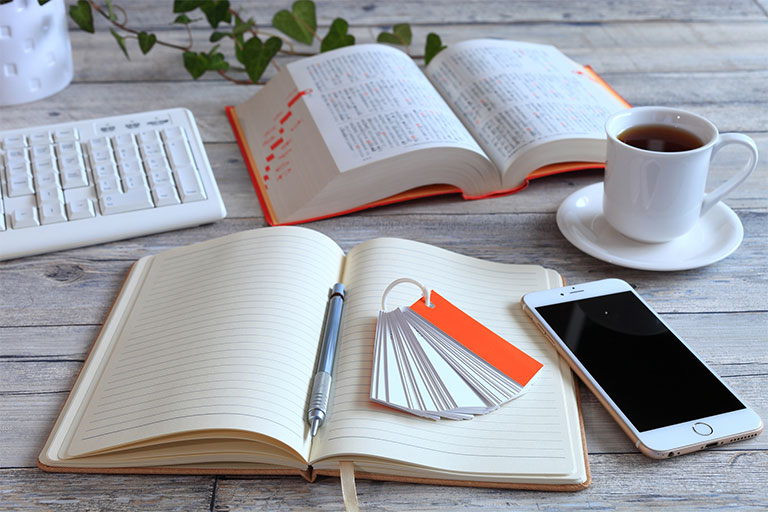
社会人になると学び続ける場面が数多くあり、暗記力を磨くことは、日々の仕事の質や成果に直結していきます。
新しい知識を素早く吸収し、必要な場面で即座に引き出せる力が求められる場面が少なくありません。
社会人にとって暗記が役立つ場面は以下の通り。
- 専門知識を素早く習得できる
- 商談や会議で説得力が増す
- 資格取得や試験対策に必要
それぞれ順番に解説します。
① 専門知識を素早く習得できる
社会人になると、業務に必要な専門用語や社内ルール、法律知識、業界の最新動向などを短期間で習得しなければなりません。
たとえば、次のような対応知識への対応が求められます。
- 営業職:商品スペックや契約条件
- 技術職:機械の操作手順やトラブル対応マニュアル
- 管理職:労務管理や法改正
これらを毎回調べていては業務が滞ってしまうため、スムーズに仕事を進めるためにも暗記によって即座に引き出せる状態を作ることが重要です。
知識の土台が頭に入れば、新たな情報も自然に整理されていき、応用力や判断力も向上していきます。
日々の業務に直結する基礎知識は、暗記の積み重ねが支えとなるでしょう。
② 商談や会議で説得力が増す
会議や商談の場では、正確な数値や事例を即答できると説得力が高まります。
たとえば、営業先で自社の売上実績や導入事例、競合比較データなどをすぐに説明できれば、説得力が高まります。
経営会議では、過去の数値や法改正の内容を即答できれば、意思決定もスムーズに進みます。
プレゼンでは話す内容を暗記しておくことで、必要なデータや要点をスムーズに提示でき、相手の信頼を得やすくなるのです。
一方、毎回資料を確認しないと答えられない状態では、準備不足や経験不足・プロ意識の欠如など負の印象を与えてしまうこともあります。
重要なポイントを暗記して臨むことで、会話の流れも途切れず、交渉の主導権を握りやすくなるでしょう。
③ 資格取得や試験対策に必要
社会人のキャリアアップには資格取得が重要になります。
例えば、昇進や昇給のために資格取得を奨励する企業は珍しくありません。
資格試験では膨大な知識を正確に記憶する必要があり、暗記力が大きな強みになるのです。
特に法律・会計・IT・医療分野では、専門用語や制度の理解が不可欠で、定義やルールを正確に記憶することが合格の鍵になります。
簿記試験では仕訳ルールや勘定科目、法令試験では条文の要件を正しく覚えることが合格への近道になります。
効率的な暗記法を使えば学習時間が短縮でき、忙しい仕事の合間でも継続学習しやすくなるでしょう。
身につけた暗記の習慣は、資格取得後の実務でもさまざまな場面で役立ちます。
関連記事:仕事終わりの大人にオススメの学習法5選!資格勉強が頭に入らない原因や対策は?
社会人のための暗記テクニック7選

社会人になると、効率的に暗記する力は仕事の成果に大きく影響します。覚え方の工夫によって、短期間で必要な知識を身につけることが可能です。
そのためのテクニックは以下の通り。
- 覚える目的を明確にする
- 覚える情報を厳選する
- 図や表にして覚えやすくする
- アウトプット前提でインプット
- 五感を活用する
- 短時間で頻繁に復習する
- 睡眠と運動を確保する
それぞれ順番に解説します。
① 覚える目的を明確にする
暗記する前に「何のために覚えるのか」をはっきりさせることが重要です。
例えば営業職なら、商談での顧客対応力向上が目的になりますし、資格試験では合格点を取るための範囲を優先するべきです。
目的が定まれば必要な情報も自然に絞り込むことができ、より効率的に覚えることができます。
曖昧なまま暗記を始めると、覚えなくてもよい情報まで手を広げてしまい、非効率になりがちです。
まず「どこで使うか」「どの程度必要か」を意識するだけで、暗記の負担は大きく軽減されるでしょう。
② 覚える情報を厳選する
社会人の学習時間は限られているため、覚える情報は重要度を基準に取捨選択する必要があります。
例えば資格勉強なら過去問頻出の項目を優先し、出題頻度が低い内容は後回しにします。
ある程度学習が進んだ段階では、すでに身につけた内容とまだ覚えきれていない部分を整理し、不足している箇所に重点的に取り組みます。
業務マニュアルでも、全て丸暗記せず、自分の担当範囲やよく使う手順を優先するのが効率的です。
仕事においては、具体的な業務範囲を上司や関係者に確認しておくことでムダを防げます。
すべてを完璧に覚えようとすると挫折しやすくなるため、必要十分な知識を見極める力が求められます。
③ 図や表にして覚えやすくする
文章だけで暗記を進めると、情報量が膨らみ過ぎて整理が難しくなります。
そのため、図や表を使って情報を視覚的に整理すると理解が深まりやすいです。
- 業務の流れはフローチャートにまとめる
- 複数の商品は表形式で特徴を比較する
- 法律の条文はマインドマップで関連項目をつなげる
こうした方法を活用すれば、情報の構造が整理されて全体像を把握しやすくなります。
複雑な内容も視覚的に整理されるため、自分だけでなく説明を受ける相手の理解も早まります。
説明やプレゼンの準備でも使いやすくなり、アウトプットの質が向上するでしょう。
さらに記憶の手がかりが増えることで、復習時にも素早く思い出せる助けになります。
紙のノートでもPCソフトでも対応できるため、自分に合った方法で整理を工夫すれば暗記の定着を後押しできるはずです。
参考:マインドマップの書き方・描き方「6つの法則」
④ アウトプット前提でインプット
暗記を効率化するには、最初から人に説明するつもりで学ぶのが有効です。
例えば社内研修の講師役を任されたと仮定し、学んだ内容を誰かに説明できるよう準備します。
説明を前提にすると、理解の浅い部分に自ら気づきやすくなります。
さらに、アウトプットする場があると集中力が高まり、記憶の定着が促進されるでしょう。
実際に同僚や家族に説明したり、自分用のノートに図解してまとめ直したりする練習にも役立ちます。
アウトプットを繰り返すほど知識が整理され、自信を持って活用できるようになるでしょう。
⑤ 五感を活用する
暗記は視覚・聴覚・触覚など複数の感覚を使うほど定着しやすくなります。
例えば、
- 色ペンを使って重要箇所を色分けする
- 録音して自分の声を繰り返し聞く
- 営業トークを録音して確認する
視覚・聴覚・触覚といった五感を組み合わせることで、脳の複数の領域が同時に刺激され、記憶のネットワークがより強固に築かれやすくなります。特に「音声+色+書き取り」などの多感覚連動は、学習効果を高める有効な手法です。
受験勉強や資格対策はもちろん、営業トークや商品知識の習得にも応用できる実践的なテクニックです。
⑥ 短時間で頻繁に復習する
長時間まとめて詰め込むよりも、短時間の復習を何度も繰り返した方が記憶は定着しやすくなります。
- 毎朝10分だけ前日の内容を振り返る
- 昼休みにクイズ形式で要点を確認する
- 帰宅後にその日の学びを要点だけ復習する
- 通勤中に音声教材を聞き流す
- スマホアプリのフラッシュカードで隙間時間に確認する
このように、間隔を空けて復習する「間隔反復法」を活用すれば、忘却曲線に逆らって記憶を長期間保てます。
一度に多くを覚えようとせず、日々の隙間時間を活用してコツコツ積み重ねる方が負担も小さくなるはずです。
続けるほど内容が整理され、応用力も自然と高まっていくでしょう。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
⑦ 睡眠と運動を確保する
記憶の定着には学習内容だけでなく、体のコンディション管理も重要です。
十分な睡眠と適度な運動を取り入れることで、脳の働きが整い学んだ内容が記憶に残りやすくなります。
- 毎日6〜7時間以上の質の高い睡眠を確保
- 就寝90分前にスマホやPCの画面を見ない
- 朝の散歩や軽いジョギングで脳を活性化
- ストレッチやヨガで緊張をほぐしリラックス
- 隙間時間に階段を使って軽く体を動かす
睡眠中は記憶が整理・固定される大切な時間帯です。
また、適度な運動は血流を促進し、集中力や思考力も高めてくれます。
こうした習慣を整えることで、暗記効率も自然と向上していくでしょう。
時間がない社会人が効率よく暗記するコツ

仕事や家庭で忙しい社会人でも、工夫次第で短時間の暗記を効果的に進められます。
- 目標の細分化とスケジューリング
- ポモドーロ・テクニック
- 通勤時間の活用と音声学習
- 間違えた箇所を重点的に復習する
それぞれ詳しく解説していきます。
目標の細分化とスケジューリング
業務マニュアルや新商品の内容を一度に覚えようとすると、情報量が膨大になり混乱しやすくなります。
たとえば、長期的なゴールから逆算して覚える範囲を期間ごとに細かく分けると負担が軽減されるでしょう。
- 1ヶ月単位では「今月中にクレーム対応マニュアルの全手順を暗記する」
- 1週間単位では「今週は商品Aの特徴と説明トークを覚える」
- 1日単位では「今日は主要取引先3社の担当者名と過去の商談内容を確認する」
こうして細かく目標を決めれば、毎日の学習内容がはっきりします。
小さな達成感を重ねるうちに知識が自然と積み上がり、暗記が負担に感じにくくなるのです。
スケジュール管理アプリや手帳を使って進捗を見える化すれば、継続もしやすくなります。
ポモドーロ・テクニック
仕事で新しい知識を覚えるときは、長時間集中し続けるのが難しくなります。
そこで「25分作業+5分休憩」を基本とするポモドーロ・テクニックを取り入れると、集中力を保ちやすくなるのです。
例えば、マニュアルの読み込みを25分進めたら、5分間ストレッチをしたり軽く体を動かしたりします。
短く区切って作業を進めることで、脳の負担が軽減され、記憶も効率良く定着していくのです。
作業内容や体調、オフィスの忙しさや周囲の状況に応じて、「50分作業+10分休憩」など時間は適宜調整して構いません。
タイマーアプリを活用すれば簡単に実践でき、仕事の合間にも取り入れやすくなるでしょう。
通勤時間の活用と音声学習
通勤や移動の時間も暗記を進める良い機会です。
満員電車や移動中でも、音声学習を活用すれば手を使わずに学べます。
例えば、自分で録音した要点を聞き返したり、資格試験の解説音声を繰り返し再生したりする方法が効果的です。
耳からのインプットは視覚とは別の刺激になり、記憶の定着を助けます。
移動のスキマ時間を活用すれば、忙しくても学習の習慣が続けやすくなるのです。また、音声アプリや録音機能を使えば、自分専用の復習教材も簡単に作成できます。
このように日常の移動時間を学習に充てることで、暗記の負担も大きく減るでしょう。
間違えた箇所を重点的に復習する
暗記の効率を高めるには、正解した部分よりも誤答部分に重点を置くことが重要です。
人は間違えた内容の方が印象に残りやすく、繰り返し確認することで弱点克服が進みます。
間違いノートや復習アプリを使い、誤答箇所をリスト化しておくと管理もしやすくなります。
3色ボールペンを使って、覚えた箇所、覚えていない箇所を色分けするのも効率的に学ぶのに役立つでしょう。
さらに、復習のタイミングを分散させることで、長期記憶への定着も促されます。こうした工夫が継続的な成果につながるのです。
社会人の暗記を妨げる悪い習慣と改善策

効率よく暗記を進めるためには、妨げとなる悪習慣を見直すことが重要です。
ここでは、社会人が陥りやすい注意点とその改善策を紹介します。
妨げとなる悪習慣は以下の通り。
- 詰め込み学習の危険性
- スマホ依存が記憶に与える悪影響
- 睡眠不足が記憶力低下を招く理由
- ストレスが暗記に及ぼす影響と対策
それぞれ順番に解説します。
詰め込み学習の危険性
詰め込み学習は短期間に大量の情報を覚えようとする学習法ですが、脳の記憶処理に必要な整理時間が不足し、長期記憶への定着が阻害されます。
脳は学んだ情報を短期記憶から長期記憶へ移行させる際、繰り返し復習することで記憶を強固にしていきます。
しかし詰め込みではこの反復が行えず、多くの情報が短期間で失われやすくなるのです。
忙しい社会人に多い例としては、以下のようなものがあります。
- 試験直前の休日に10時間かけて参考書を読み込む
- 深夜に詰め込み暗記をする
こうした学習は一見効率的に思えても、脳の定着には不向きで、かえって記憶が断片化しやすくなります。これらはその場しのぎになりやすく、直後は覚えた感覚があっても数日後には多くを忘れてしまうリスクが高まります。
分散学習は忘却曲線の特性を考慮し、適切なタイミングで復習を繰り返すことで記憶を安定させます。
短期間で一気に詰め込むより、日々こまめに繰り返す方が暗記効率は向上するでしょう。
関連記事:大人も使える暗記方法5選|やってはいけない勉強法も
スマホ依存が記憶に与える悪影響
スマホの過剰な使用は集中力や記憶力に悪影響を及ぼすことが知られています。
学習中によく見られる具体的な行動は次の通りです。
- SNSを頻繁に確認する
- 通知音で集中が途切れる
- 学習中に動画アプリを流す(ながら学習)
スマホが近くにあるだけで脳は無意識に注意を奪われ、記憶力が低下しやすくなります。
通知が鳴るたびに集中が途切れると、情報を整理して記憶する力が弱まることも。
頻繁に注意を切り替える状況では、ワーキングメモリに大きな負荷がかかり、学習内容が断片化しやすくなるのです。
さらに、短時間で集中し直すことは意外と難しく、結果として学習効率が下がってしまいます。
スマホによる主な弊害は以下のように整理できます。
・ワーキングメモリに負荷がかかる
・情報の整理・統合が妨げられる
・集中状態に戻るのに時間がかかる
・学習意欲の低下を招く
スマホの通知をオフにし、手元や視界から遠ざけるだけでも集中しやすい環境が整います。
こうした工夫を日常的に取り入れれば、安定した暗記力の向上が期待できるでしょう。
関連記事:スマホの弊害は?記憶力を低下させるメカニズムも紹介
睡眠不足が記憶力低下を招く理由
十分な睡眠は記憶の定着に欠かせない役割を果たしています。
脳は睡眠中に学んだ情報を整理し、短期記憶から長期記憶へと移行することが知られています。
とくに深いノンレム睡眠の時間帯で、この情報整理が集中的に行われるのです。
しかし睡眠が不足すると、この重要なプロセスが十分に働かなくなり、せっかく覚えた内容も短期間で忘れやすくなります。
また慢性的な睡眠不足は注意力や集中力も低下させ、学習効率そのものが落ち込みがちです。
睡眠不足によって生じる主な弊害は次の通り。
- 記憶の整理が不十分になる
- 覚えた内容が短期間で消失しやすくなる
- 集中力・注意力が低下する
- 思考力や理解力も鈍くなる
- 学習意欲が減退する
学習効果を高めるには、学んだ後にしっかり睡眠を取り、生活リズムを整えることが重要です。
こうした習慣を維持すれば、安定した記憶力と学習効率の向上が期待できるでしょう。
関連記事:記憶力と睡眠の関係
ストレスが暗記に及ぼす影響と対策
適度なストレスは暗記に役立ちますが、ストレスが高まるとコルチゾールが分泌され、海馬の働きが鈍くなるのです。
集中が乱れ、新しい情報を覚えにくくなるだけでなく、理解力や思考力も低下します。
ストレスが続くと学習意欲も減退し、学びを継続しづらくなるでしょう。
ストレスによる暗記への影響は以下です。
- 新しい情報が覚えにくくなる
- 集中力や注意力が不安定になる
- 理解力や思考力が鈍る
- モチベーションが維持できなくなる
- 学習を継続しづらくなる
ストレスを軽減する方法としては、適度な有酸素運動や瞑想、リラクゼーション法の活用が有効です。
これらの習慣を取り入れることで、海馬の健康が守られ、安定した学習効果が期待できるでしょう。
参考:海馬とは?!記憶をつかさどる脳の海馬について徹底解説
社会人の暗記に関するよくある質問
社会人でも暗記力は今から鍛えられる?
暗記力は年齢に関係なく鍛えることが可能です。
学習した情報を繰り返し復習し、分散学習を取り入れることで記憶は定着していきます。
また、アウトプットを意識した学習法も効果的です。
新しい知識を他人に説明する練習をすると、理解が深まり記憶が整理されやすくなります。
さらに、運動や睡眠を意識して生活習慣を整えることで脳の働きも活性化します。
忙しくて勉強時間が取れない時は?
短時間でも集中して学習する工夫が有効です。
例えば通勤中に音声教材を活用したり、1日10分だけ暗記カードで復習する方法があります。
まとまった時間が取れなくても、隙間時間を積み重ねれば学習量を十分に確保できるのです。
大切なのは毎日少しずつ継続することで、短い時間でも繰り返せば、知識は着実に蓄積されていくでしょう。
効果的な復習のタイミングは?
復習は忘却曲線を意識して行うと効果的です。
一つの目安として、学習から3分後、30分後、3時間後、3日後、30日後という風に3の付く間隔で復習すると記憶が安定します。
最初は短い間隔で繰り返し、その後は少しずつ間隔を広げるのが理想です。
このサイクルを意識すれば、長期記憶への定着が促進されます。
計画的に復習を組み込むことが記憶維持の鍵です。
仕事に役立つ暗記のコツは?
実務に結びつけて学ぶと記憶が強化されます。
学んだ内容を実際の業務を想定したり、実際に活用することで、知識が自然と定着するでしょう。
また、関連する事例や自分の経験と結びつけると理解が深まります。
暗記の際は要点を整理して簡潔にまとめ、イメージや図解を活用するとさらに効果的です。
人前で緊張して思い出せない時はどうする?
緊張で思い出せなくなるのはよくあることで、深呼吸をして気持ちを落ち着けると集中力が戻りやすくなります。
また、事前に模擬練習を重ねておいて、伝える内容に集中すると本番でもあがりにくくなるでしょう。
完璧に覚えようとせず、要点を絞って整理しておくことも有効です。
万一思い出せなくても慌てず対応しましょう。
関連記事:前日からでも大丈夫!スピーチを暗記して成功させるためのポイント&練習方法
暗記力を高める食べ物はある?
バランスの良い食事が脳の働きを支えます。
青魚に含まれるDHA・EPA、ナッツ類のビタミンE、卵のコリンなどは神経機能に良い影響を与えます。
また、野菜や果物から摂取できるポリフェノールも脳の老化予防に役立つとされています。
過度な偏食を避け、栄養バランスを意識することが大切です。
まとめ|社会人でも記憶力は鍛えられる

本記事では、社会人が暗記力を高める理由、実践テクニック、注意すべき習慣、よくある質問への対策について解説しました。
限られた時間の中でも工夫次第で暗記力は向上し、仕事や資格取得に役立てることが可能です。目的を明確にし、情報を整理しながら反復学習を取り入れることで記憶は安定します。
さらに、睡眠や運動、食事、ストレス管理といった生活習慣の見直しも重要です。日々の積み重ねを続ければ、年齢に関係なく記憶力は鍛えられていくでしょう。
自分に合った方法を見つけ、焦らず着実に取り組むことが、悩みからの解放につながります。
「もっと効率よく覚えられるようになりたい」と感じた方には、記憶力を高めるトレーニングの活用もおすすめです。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
Wonder Educationでは、誰でも記憶力を高められる記憶術講座を提供しています。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。