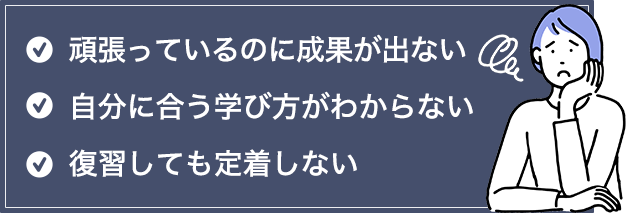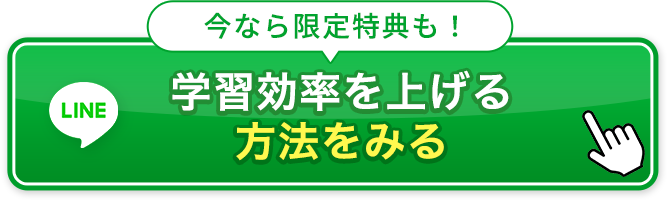キツネさん
キツネさん
「勉強したいのに時間がない…」
「社会人でも毎日勉強を続けられる方法はないの?」
忙しい生活の中で勉強を継続するのは簡単ではありません。
本記事では、社会人が効率的に勉強を進めるためのタイムスケジュールの立て方やアプリ活用術を解説します。
資格試験やスキルアップを目指す社会人におすすめで、効率的な方法が学べます。
読むことで、無理なく続けられる勉強習慣を身につけ、目標達成へ一歩近づけます。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
なぜ社会人の勉強にタイムスケジュールが必要なのか?

社会人にとって勉強は、限られた時間を効率的に使う工夫が求められます。
そのためには無計画に学ぶのではなく、具体的なタイムスケジュールを立てることが不可欠です。
- タイムスケジュールを立てる目的・メリット
- 逆算スケジュールの基本手順(長期・週・日)
- 調整日や振り返りを組み込む必要性
それぞれ順番に解説します。
タイムスケジュールを立てる目的・メリット
勉強においてタイムスケジュールを作成する狙いは、学習の成果を高めつつ途中で挫折しない環境を整えることにあります。
社会人は仕事や家庭の用事に追われ、勉強が後回しになりやすい状況に置かれがちです。
そこであらかじめ計画を立てておくことで、限られた時間を効果的に活用できるのです。また、進捗を目に見える形で管理できるため、小さな達成感を積み重ねやすくなります。
これが学習を継続するモチベーションにつながり、最終的には知識が体系的に身につき、目標の達成に一歩ずつ近づいていくのです。
参考:タイムスケジュールとは?メリットや作り方、作成のポイントを説明|Chatwork
逆算スケジュールの基本手順(長期・週・日)
逆算スケジュールとは、ゴールの日から逆向きに計画を立てる方法です。
たとえば「3か月後にTOEIC800点を取る」という目標がある場合、まず長期の目標を設定し、そこから1か月ごとに必要な得点や学習範囲を区切ります。
さらに週ごとに「模試を1回解く」「単語帳を500語学ぶ」といったステップに分解します。
最後に日単位で「朝に単語を50語覚える」「夜にリスニングを30分行う」といった具体的な行動に細分化します。
この方法を使えば、学習の順序がはっきりし、無駄な迷いを減らせるため集中力が高まり、効率よく目標に近づけるのです。
参考:スケジュール化を逆算と積算で考える : PJ活動お役立ちコラム
調整日や振り返りを組み込む必要性
学習計画は思い通りに進まないことが多く、仕事の残業や体調不良で勉強時間が削られる場面もあります。
そこで、週に1日は「調整日」として設定しておけば、進まなかった分を取り戻せるのです。
例えば「平日は1時間勉強する」と決めても残業できない日があるかもしれません。
その場合、日曜にまとめて復習する時間を確保しておけば計画全体が崩れにくくなります。
さらに週末や月末に振り返りを行い「英単語は予定より覚えられたか」「模試の点数は伸びているか」を確認すれば、改善点を次の計画に反映できます。
こうした調整と振り返りを重ねることが、社会人が無理なく学習を継続するための土台になるのです。
社会人が続けやすい勉強スケジュールの作り方

社会人が勉強を継続するためには、無理のない計画を立てることが重要です。
そのためには、短期集中と柔軟性を意識したスケジュールを組む必要があります。
- ゆるめスケジュールで心と時間に余裕を持たせる
- 短時間×分散学習で記憶定着と集中を両立
- スタート・終了時間を設けて先延ばし対策
それぞれ順番に解説します。
ゆるめのスケジュールで心と時間に余裕を持たせる
勉強計画を立てる際に大切なのは、無理に詰め込みすぎないことです。余裕のない計画は、予期せぬ予定変更や疲労によって崩れやすく、挫折の原因になります。
そのため、あらかじめ余白を残した「ゆるめスケジュール」を設定することが効果的です。
例えば、最初のうちは毎日必ず勉強するのではなく、週3回で実行できる量に設定してみると、仕事や家庭の事情に左右されにくくなります。
そして慣れてきたら徐々に学習量を増やしていけばよいのです。
信州大学の瀧川佳苗・鈴木俊太郎(2016)は「スモールステップ方略(物事を達成するための工夫された方法・やり方)」が目標達成に有効であると示しています。
つまり、小さな成功体験を積み重ねることで自己効力感も高まるとされているのです。
短時間×分散学習で記憶定着と集中を両立
学習効率を高めるには、長時間勉強を続けるよりも、分散学習(短時間の学習を複数回に分けて行う方法)が効果的です。
人間の集中力には限界があり、長時間続けると理解力や記憶力が下がってしまうためです。教育心理学の研究でも、分散学習は記憶の保持や再活性化を促すことが示されています。
また理化学研究所(2011)の実験では休憩を挟むことで学習内容が脳に長期保存されやすくなることが明らかになっています。
このように短時間学習を分散して取り入れることで、集中力を維持しつつ知識を定着させることが可能になるのです。
特に忙しい社会人にとって、日常のすき間時間を活用できる点も大きなメリットといえます。
参考:運動学習の記憶を長持ちさせるには適度な休憩が必要|理化学研究所
スタート・終了時間を設けて先延ばし対策
社会人が勉強を続けられない原因の一つに、「後でやろう」と先延ばしする傾向があります。
そこで学習の開始時間と終了時間をあらかじめ設定することが有効です。
例えば、出勤前30分や寝る前20分など、習慣化しやすい時間を固定すると続けやすくなります。
こうして勉強を「やるべき習慣」として定着させることが大切です。
実際、日本の研究でも「能動的先延ばし」傾向を持つ人ほど、計画的に課題へ取り組み効率よく遂行する特徴が示されています(藤田・井上, 2025)。
このことからも、時間の枠を設けて計画的に行動する工夫は先延ばし防止に役立つといえます。
参考:予習等の授業外学習における能動的先延ばし—課題提出における行動指標と自己報告の関連—
効率的な学習スケジュール例|時間帯・場所別

社会人が学習を習慣化するには、生活のリズムに合わせて時間帯や場所を工夫することが欠かせません。
そのためには、通勤や昼休みといった日常の隙間時間を学習に組み込み、週末を柔軟に活用することが重要です。
- 通勤中・移動中にできるスキマ勉強活用法
- 昼休みや自習室、帰宅後の時間帯別勉強配分
- 週末の調整日or実験日として使うスケジュール例
それぞれ順番に解説します。
通勤中・移動中にできるスキマ勉強活用法
通勤や移動中はまとまった時間を確保しにくいですが、短時間で集中できる勉強には最適です。
例えば、音声教材やポッドキャストを聞けば、両手が塞がっていても知識を吸収できます。
また、スマホアプリを活用すれば、クイズ形式で暗記科目を反復できるため、効率的に記憶を定着させられます。
そのため、忙しい社会人にとって通勤時間は勉強量を増やす重要な資源となります。
つまり、移動時間を学習に変換することで、成果が自然に積み重なっていくのです。
昼休みや自習室、帰宅後の時間帯別勉強配分
昼休みや帰宅後の時間は、集中力のピークを意識して学習内容を分けると効果的です。
昼休みには短時間で区切れる暗記作業を行い、帰宅後は腰を据えて理解が必要な課題に取り組むなど工夫すると良いです。
さらに自習室を利用する場合は、周囲の学習意欲に触れることで自然と集中力が高まります。
このように時間帯ごとに勉強を配分することで、効率と継続性を両立できます。
結果として、学習を無理なく日常生活の一部に組み込むことが可能になるのです。
週末の調整日or実験日として使うスケジュール例
週末はまとまった時間を確保しやすいため、平日で遅れた学習を取り戻す調整日にするのが有効です。
また、新しい学習法や教材を試す実験日として活用すれば、自分に合ったスタイルを見つけやすくなります。
例えば、以下のようなタイムテーブルを組むと効率的です。
- 9:00~10:30 平日に学んだ内容を復習(ノート整理・問題演習)
- 10:45~12:00 遅れた学習範囲のキャッチアップ
- 13:00~14:30 新しい学習法やアプリを試す実験時間
- 14:45~16:00 予備やアウトプット練習(模擬テストなど)
- 16:15~17:00 次週の学習計画を立案・調整
このように午前中は復習と補填、午後は実験やアウトプットに時間を割くと、知識の整理と理解の深化が進みます。
さらに、週末に次週の計画を見直すことで、学習の軌道修正がスムーズに行えます。
長期的に学習習慣を維持するためにも、週末を戦略的に設定することが大切なのです。
勉強法・学習方法に関するよくある悩み
▼頑張っているのに成果が出ない——。
それは能力ではなく、学びの順番が整理されていないだけかもしれません。
まずは無料動画で、学習方法の基本となる手順を確認。
理解と復習の流れが明確になり、学習効率の違いを実感できます。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
社会人が勉強を管理するのにおすすめのアプリ&ツール
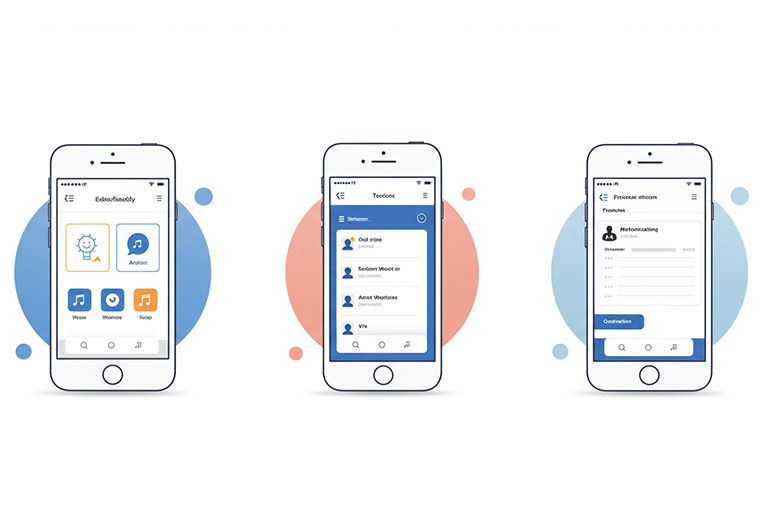
社会人が勉強を継続するには、学習内容だけでなく管理方法を工夫することが重要です。
そのためには、学習アプリや時間管理術、進捗を見える化する仕組みを取り入れることが効果的です。
- スマホ学習アプリや勉強管理アプリの活用
- ポモドーロ・テクニックなど時間管理術の組み込み
- TODOアプリやスプレッドシートで学習の進捗管理
それぞれ順番に解説します。
スマホ学習アプリや勉強管理アプリの活用
学習アプリや勉強管理アプリは、学習を習慣化するうえで欠かせないサポート役になります。
例えば、英単語や資格試験の暗記アプリを使えば、通勤中や休憩時間といった隙間時間を有効活用できるのです。
また、勉強記録アプリの一例として「Studyplus」が挙げられます。
学習時間や教材ごとの進捗を可視化でき、グラフや記録を通じて達成感を得やすくなるのが特徴です。
さらに学習量を数値で確認することでモチベーションが維持され、改善点を把握しやすくなります。
このようにアプリを日常に取り入れることで、無理なく勉強を継続できる仕組みが整います。
ポモドーロ・テクニックなど時間管理術の組み込み
効率的に学習を進めるには、時間を区切って集中力を維持する方法が効果的です。
ポモドーロ・テクニックは25分の集中と5分の休憩を繰り返すスタイルであり、生産性を高める工夫として知られています。
- 学習する内容を決める
- タイマーを25分に設定して取り組む
- タイマーが鳴ったら5分休憩を挟む
- これを4セット続けた後、15〜30分の長めの休憩を取る
- 学習時間が終わるまで2~4を繰り返す
この流れをアプリで管理すると、自分で時計を確認せずに学習リズムを整えられます。
さらに時間を記録することで、どの学習にどれだけ取り組んだかを客観的に確認可能です。
こうした時間管理術を導入すれば、限られた時間でも達成感を得やすくなります。
参考:ポモドーロ・テクニック|コラム|学生相談所|東京大学相談支援研究開発センター
TODOアプリやスプレッドシートで学習の進捗管理
TODOアプリやスプレッドシートを活用した学習管理は、効率的に勉強を継続するうえで有効です。
TODOアプリでは課題を小さなタスクに分割して登録し、完了時にチェックすることで達成感を得られます。
TodoistやGoogle ToDoリスト、Notionなどは操作性や習慣化サポートに優れており、学習に取り入れやすいのが特徴です。
一方、スプレッドシートは学習時間や進捗を日付ごとに整理し、数値やグラフで可視化できるのが強みです。
進み具合を客観的に把握できるため、計画の修正や改善が容易になるため、パソコン得意な人は活用してみるのも良いでしょう。
このように、デジタルツールを使った進捗管理は達成感と可視化の両面で学習を後押しし、社会人の学びを長期的に支えてくれます。
参考:Google ToDo リスト – Google Play のアプリ
記憶術×タイムマネジメントで学習効率を最大化!
記憶術×タイムマネジメントで学習効率を最大化する方法は、社会人の勉強習慣づくりにも有効です。
場所法やストーリーメソッドなどを活用すれば、単なる暗記ではなくイメージで情報を整理できるため、必要なときに素早く思い出せます。
さらに繰り返し学習と組み合わせることで、忘却曲線を抑えながら長期記憶に定着させることが可能です。
このように記憶術は、試験対策や実務での成果に直結する強力な学習法といえるでしょう。
効率的に知識を吸収したい方は、記憶術を体系的に学べるWonder Educationの記憶術講座を活用してみるのがおすすめです。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
まずは体験から始めて、自分に合った学習スタイルを確立してみましょう。
毎日勉強している社会人の1日のタイムスケジュール例

社会人が勉強を習慣化するには、ライフスタイルに合わせて1日の流れを工夫することが欠かせません。
そのため、仕事や家庭の状況に応じたタイムスケジュールを組むことで無理なく継続できます。
- 会社員(資格試験)
- 主婦(語学学習)
- 夜勤ワーカー(専門スキル)
それぞれ順番に解説します。
会社員(資格試験)
資格試験の合格を目指している会社員にとって、限られた時間をどのように学習へ振り分けるかが合格への分かれ道になります。
出勤前や昼休み、帰宅後といった隙間時間やまとまった時間をうまく組み合わせることが重要です。
例えば、以下のようなタイムスケジュールが効果的です。
- 6:30〜7:00|過去問1ページ+答え合わせ
- 8:00〜8:30|音声講義で通勤リスニング
- 12:15〜12:30|単語アプリで復習
- 20:00〜21:00|模試+間違い直し
このように学習を習慣化することで、知識が計画的に積み重なり、資格取得への道筋が明確になります。
結果として、継続的に取り組める体制が整い、達成感と自信を持ちながら学習を進められるのです。
主婦(語学学習)
語学習得を目標とする主婦にとっては、家事や育児の合間を活用しながら無理なく続けられる学習リズムを作ることが大切です。
日々の生活サイクルに語学学習を組み込むことで、自然に習慣化できます。
例えば、次のようなタイムスケジュールがおすすめです。
- 9:30|ラジオ英会話で“ながらリスニング”(20分)
- 13:00|文法アプリで集中学習(20分)
- 16:30|単語アプリでミニテスト(10分)
- 22:00|YouTubeでシャドーイング練習(40分)
このように細切れ時間と落ち着いた時間をバランスよく使えば、生活に負担をかけずに学習を続けられます。
結果として、語学力を段階的に積み重ね、日常生活の中で自然に成長を実感できるのです。
夜勤ワーカー(専門スキル)
専門スキルを磨きたい夜勤ワーカーにとって、不規則な生活リズムに合わせた柔軟な学習管理が重要です。
体調を優先しつつ、無理なく続けられる方法を組み込むことでスキル習得を効率化できます。
例えば、次のようなタイムスケジュールが効果的です。
- 9:00|動画教材で学習+朝食(45分)
- 15:00|テキスト演習 or 実技練習(60分)
- 18:00〜|参考書や業界ブログで情報収集(15分)
- 土曜午前|復習+週の学習計画見直し(週1のボーナス時間)
このように疲労時は軽め、頭が冴えている時は集中的に取り組むメリハリをつけることで、夜勤生活の中でも無理なく専門スキルを磨いていけます。
継続と工夫を重ねれば、不規則な勤務形態でも着実に成長を実感できはずです。
社会人の勉強スケジュールに関するよくある質問
社会人の勉強スケジュールに関するよくある質問について解説します。
勉強時間が確保できない場合はどうすればいい?
勉強時間が取れないときは、隙間時間を細かく活用するのが最も現実的です。
例えば通勤中に音声教材を聞く、昼休みに単語を確認するといった小さな積み重ねが効果を生みます。
短時間でも継続することで学習習慣が形成され、まとまった時間がなくても成果につながるため、無視できません。
つまり、5分ほどの細切れの時間であっても無駄にしない工夫が、学習の継続を支えるポイントになります。
スケジュール通りにいかない時の対処法は?
計画通りに進まないときは、無理に追いつこうとせず調整日を設けることが重要です。
あらかじめ予備日を設定しておけば、突発的な予定や体調不良にも柔軟に対応できます。
また、優先順位を整理し取り組むべき学習だけに絞れば、負担を抑えつつ継続が可能になります。
このように柔軟に修正できる余白を持つことが、スケジュール管理を成功させる鍵となります。
モチベーションが続かないときの工夫は?
モチベーションが下がったときは、学習の目的を再確認することが効果的です。
例えば資格取得後のキャリアアップや語学習得での活用場面を具体的に思い描くと意欲が高まります。
さらに小さな達成を記録し見える化すれば、継続による手応えを実感できるでしょう。
このように目標の再認識と成果の可視化が、学習を続けるための強力な支えとなります。
社会人向けの勉強計画表のテンプレートは?
勉強計画表は自分でゼロから作ることもできますが、時間効率を考えると既存のテンプレートを利用する方が現実的です。
特に社会人は限られた時間の中で学習を進める必要があるため、進捗を記録しやすく、計画を見直しやすい仕組みが役立ちます。
- 日付ごとに「学習時間」と「学習内容」を分けて書けるフォーマット
- 目標や到達度を設定でき、達成度を可視化できる表形式
- スプレッドシート(ExcelやGoogleスプレッドシート)で自動集計可能なもの
- アプリやWebサービスと連動して、通知やリマインダーを設定できる形式
例えば、Googleスプレッドシートを利用すれば、学習内容を入力すると自動で週ごとの合計時間を集計することも可能です。
また、日ごとに「必ずやること(必須)」「できればやること(任意)」を分けて書くと、計画倒れを防ぎやすくなります。
社会人向けの勉強計画表のテンプレートの一例を紹介します。
| 日付 | 学習時間 | 学習内容 | 優先度(高/中/低) | 達成度(%や◎△×) | 振り返りメモ |
| 9/1 | 30分 | 英単語暗記(TOEIC) | 高 | ◎ | 通勤中に音声教材を活用 |
| 9/2 | 45分 | 資格試験過去問演習 | 高 | △ | 問題数をこなせなかった |
| 9/3 | 20分 | 読書(ビジネス書) | 中 | ◎ | 昼休みに読書で気分転換 |
| 9/4 | 60分 | プログラミング練習 | 高 | × | 仕事疲れで集中できず |
| 9/5 | 15分 | 前日の復習 | 中 | ◎ | 寝る前にアプリで復習 |
このように、便利なテンプレートを活用することで、社会人でも効率よく学習を継続できるのです。
まとめ|スケジュールを立てて勉強を効率的に進めよう!

本記事では、社会人が勉強を効率的に進めるためのタイムスケジュールの立て方と、学習をサポートするアプリ活用法について解説しました。
社会人は限られた時間をどう管理するかが成果を左右します。
今日から自分の生活リズムに合ったスケジュールを組み、アプリを取り入れて学習習慣を定着させましょう。
目標達成の第一歩を今すぐ始めることが大切です。
「もっと記憶力を高めて仕事や勉強に活かしたい」という方には、「吉永式記憶術」もおすすめ。科学的根拠に基づいた実践的なトレーニング法で、初心者でも無理なく取り組めます。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い指導を通じて記憶力向上と目標達成をサポートしています。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。