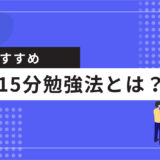キツネさん
キツネさん
そんな経験はありませんか?
お酒を飲むと楽しくリラックスできますが、飲みすぎると記憶が飛んでしまうことがあります。
これは単なる酔いではなく、脳が一時的に麻痺して記憶を作れなくなる現象です。放置すると脳の萎縮や認知症リスクにもつながるため、注意が必要です。
本記事では、お酒で記憶をなくす原因と防ぐ方法、記憶をなくさない人との違い、さらにお酒との上手な付き合い方まで徹底解説します。
健康的に楽しみながら記憶力も守るヒントを知りたい方はぜひ参考にしてください。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
なぜお酒で記憶をなくすのか?

お酒を飲みすぎたときに「記憶が飛ぶ」のは、単なる酔いではなく脳の機能が一時的にストップしている状態です。
ここでは、その仕組みとリスクについて詳しく解説します。
脳が「麻痺」して記憶が作られない仕組み
アルコールは脳の海馬に作用し、新しい記憶を作る働きを阻害します。酔っている間の出来事が思い出せないのは、脳が「記録」自体をできていないためです。
この状態はブラックアウトと呼ばれ、一晩のうちに何時間分もの記憶が抜け落ちることもあります。
飲みすぎると脳が萎縮する危険性
慢性的に大量の飲酒を続けると、アルコールの神経毒性により脳の萎縮が進行します。脳の容量が減ると記憶力や判断力の低下を招き、日常生活にも影響を及ぼします。
特に前頭葉や海馬といった「記憶をつかさどる領域」が影響を受けやすいため、早い段階からの予防が重要です。
お酒と認知症リスクの関係
アルコールによる記憶障害は一時的なものにとどまらず、長期的には認知症リスクを高めるとされています。
海外の疫学研究でも、大量飲酒者はそうでない人に比べてアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症の発症率が高いと報告されています。
記憶が飛ぶ経験が繰り返されるなら、将来的な脳の健康にも注意を払うべきでしょう。
参照
: 厚生労働省 飲酒|e-ヘルスネット
: アルコール性認知症・脳の萎縮について
: MDPI アルツハイマー病の修正可能な危険因子としてのアルコール
お酒で記憶をなくさないための具体的対策

お酒による「記憶の飛び」は体質だけでなく、飲み方や周囲の工夫によっても防ぐことが可能です。
ここでは、記憶をなくさないために今日から実践できる具体的な方法を紹介します。
飲みすぎないための工夫(量・度数・ペース)
最も確実な対策は「飲みすぎないこと」です。アルコールは摂取量に比例して脳への影響が大きくなるため、度数が高いお酒を一気に飲むのは避けましょう。
特に短時間での多量摂取はブラックアウトのリスクを急激に高めます。自分のペースを守り、「適量をゆっくり飲む」意識が大切です。
- ビール(中瓶500ml・アルコール度数5%)=約20g
- 清酒(1合180ml・アルコール度数15%)=約22g
- ウイスキー・ブランデー(ダブル60ml・43%)=約20g
- 焼酎(35度・1合180ml)=約50g
- ワイン(1杯120ml・12%)=約12g
厚労省では「純アルコール量20g程度/日」が適量の目安とされます。連日の飲酒を避け、ゆっくり飲むのが重要です。
参照 : 厚生労働省 アルコール
食べ物と一緒に摂取して吸収を抑える
空腹時の飲酒はアルコールの吸収が早く、血中濃度が急上昇するため記憶を失いやすくなります。
タンパク質や脂質を含む食べ物と一緒に飲むと吸収が緩やかになり、酔いの進行も穏やかになります。
特にチーズやナッツ、枝豆などはアルコールとの相性が良い定番のおつまみです。
- 飲酒前に軽く食べてから飲む
- 脂質・タンパク質を含む食べ物を選ぶ(チーズ、ナッツ、枝豆など)
- 空腹で一気に飲むのを避ける
参照 : 全国健康保険協会 お酒と上手に付き合おう
関連記事 : 記憶力アップに効く食べ物ランキング10|即効性のある食品から日常メニュー例まで
十分な水分補給で代謝を助ける
アルコールは利尿作用が強く、体内の水分を奪います。脱水状態になるとアルコールの分解が滞り、酔いやすく記憶障害も起きやすくなります。
また、飲酒中は定期的に水を挟むことで血中アルコール濃度の上昇を防ぎ、代謝をサポートできます。「お酒1杯につき水1杯」を目安にすると効果的です。
- お酒1杯ごとに水1杯を挟む
- 炭酸水やお茶などノンアル飲料を組み合わせる
- 翌朝も十分に水分をとり、脱水を防ぐ
参照 : Cleansui アルコールを飲むとなぜ脱水症状になるの?
サプリや栄養素でアルコール分解をサポート
アルコールの分解にはビタミンB群や肝機能を助ける栄養素が関わっています。
例えばオルニチン(シジミに多く含まれる)やウコン由来のクルクミンは肝臓の働きを助け、分解をサポートするとされています。
市販のサプリメントを活用する方法もありますが、体質に合うかどうかを確認して取り入れるとよいでしょう。
- シジミやアサリに含まれる「オルニチン」を摂取
- ウコンに含まれる「クルクミン」で肝機能サポート
- ビタミンB群で代謝を促進
- サプリメントは飲酒前・中・後の摂取を意識
参照 : オルニチンの疲労回復効果
「お酒で記憶がなくならない人」との違いは?

同じ量を飲んでも記憶をなくしてしまう人と、しっかり覚えていられる人がいます。
この違いは「気合い」や「意志の強さ」ではなく、体質や脳の状態に左右される部分が大きいのです。
体質やアルコール分解酵素の差
お酒を飲んだときの体の反応は、アルコールを分解する酵素の働きに左右されます。
特に「ALDH2(アルデヒド脱水素酵素2)」の活性が弱い人は、少量でも酔いやすく、ブラックアウトも起きやすいとされます。
反対に、分解酵素が活発な人は血中アルコール濃度が急上昇しにくく、記憶をなくしにくい傾向があります。
飲酒習慣と耐性の影響
日常的に飲酒している人はアルコールへの耐性ができやすく、同じ量でも酔い方が異なります。ただし「慣れている=安全」というわけではありません。
耐性がある人でも脳へのダメージは進行しており、記憶力の低下や依存リスクが高まることもあります。
耐性の差は一時的な違いに過ぎず、長期的には健康リスクを伴います。
ストレスや精神状態との関係
ストレスが強いときや精神的に不安定なときは、同じ量を飲んでも記憶が飛びやすいことがあります。これは、脳がストレスホルモンに影響されて働きが鈍くなり、アルコールとの相乗効果で記憶形成が阻害されるためです。
気分が落ち込んでいるときや不安を解消する目的での飲酒は、ブラックアウトを招きやすいので注意が必要です。
関連記事 : ストレスは記憶力の大敵!脳との関係・記憶を回復させる対処法を解説
記憶力に関するよくある悩み
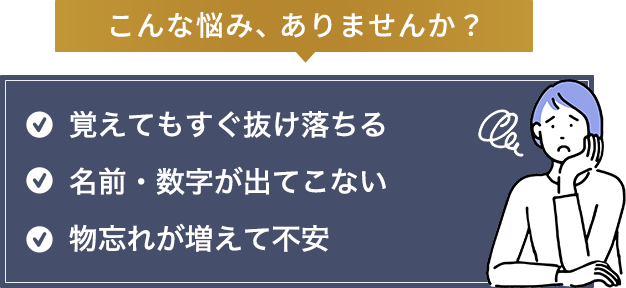
覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。
それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。
無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
「お酒で記憶力が上がる」という噂の真相

「お酒を飲むと頭が冴える」「少し飲んだ方が勉強や仕事がはかどる」といった声を耳にすることがあります。
しかしこれは本当に正しいのでしょうか?ここでは、その噂を科学的に検証していきます。
少量の飲酒がリラックスを促す可能性
少量のアルコールには、緊張を和らげてリラックスを促す効果があることが知られています。これはアルコールが脳内のGABA神経を活性化し、不安を抑える作用を持つためです。
実際に「少し飲んだ方が集中しやすい」と感じる人がいるのは、この影響によるものです。
ただし注意したいのは、長期的な飲酒習慣は神経系の調節機能を乱し、耐性や依存の形成につながるという点です。したがって「一時的な気分転換」にとどめ、日常的な手段として頼らないことが重要です。
参照 : 浅川クリニック 世田谷内科 アルコールの摂取が脳に及ぼす影響
勉強や仕事に活かせるお酒との付き合い方
勉強や仕事中に飲酒するのは非効率ですが、「頑張った後のごほうび」として取り入れるとモチベーション維持につながります。
特に低アルコール飲料やワイン1杯など、少量であればリラックス効果を得つつ翌日に影響を残しにくいといえます。
大切なのは「楽しむ時間」と「集中する時間」を分けて考えることです。
「眠るための飲酒」は逆効果
寝つきを良くする目的でお酒を飲む人もいますが、アルコールによる睡眠の質は低下します。浅い眠りが増え、夜中に目が覚めやすくなるため、結果的に翌日の記憶力や集中力に悪影響を与えるのです。
もし眠れないときは、就寝前のストレッチや入浴、ブルーライトを避けるといった方法を取り入れる方が健康的です。
関連記事 : 記憶力と睡眠の関係
お酒と記憶に関するよくある質問(FAQ)
Q1:お酒を飲むとすぐ記憶がなくなるのは病気ですか?
多くの場合は飲みすぎによる一時的な記憶障害(ブラックアウト)ですが、頻繁に起こる場合は脳や肝機能に問題がある可能性もあります。
気になる場合は医療機関に相談しましょう。
Q2:お酒を飲んでも記憶をなくさない人との違いは?
アルコール分解酵素の活性や飲酒習慣の有無、ストレスの状態などが影響しています。
「強いから安心」というわけではなく、脳へのダメージは進行する点に注意が必要です。
Q3:お酒を飲むと勉強や記憶力が上がるって本当ですか?
少量ならリラックス効果で集中しやすくなるケースもありますが、長期的には神経機能を乱し、記憶力を下げるリスクが大きいです。
勉強や仕事後の「ごほうび」として少量楽しむ程度にとどめましょう。
Q4:お酒を飲んでも記憶をなくさない方法はありますか?
飲みすぎない・食べながら飲む・水分補給をこまめに行うことが基本です。
必要に応じてアルコール分解を助ける栄養素やサプリを活用するのも一つの方法です。
まとめ|お酒で記憶をなくさない工夫はできる

お酒を飲んで記憶が飛んでしまうのは、脳の記憶形成が一時的にストップする仕組みによるもので、誰にでも起こり得ます。
しかし、飲み方を工夫したり、食事や水分を意識したりすることで、そのリスクは大きく下げられます。
加えて、普段から睡眠や栄養、そして記憶術を取り入れて脳の記憶力を高めておくことも有効です。
飲酒による記憶の抜け落ちを完全に防ぐことはできませんが、「忘れにくい脳」を育てておくことで、影響を最小限に抑えることができます。お酒を楽しみながらも、賢く脳を守る工夫を実践していきましょう。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。