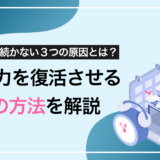キツネさん
キツネさん
そんな悩みを抱えていませんか?
年齢のせいだと思いがちですが、実はストレスが脳に大きな影響を与え、記憶力を低下させている可能性があります。
ストレスが続くと、脳を酷使するホルモンが分泌され、記憶をつかさどる海馬の働きが弱まり、思い出す力や新しい情報を覚える力が落ちてしまうのです。
しかし、正しい知識と対処法を知っていれば、記憶力は回復・改善が可能です。
この記事では、ストレスと記憶力の関係を脳科学の視点から解説し、セルフチェック方法や具体的な改善策、受診が必要なケースまで専門的に紹介します。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
ストレスで記憶力は本当に低下するのか?

ストレスがどの程度記憶力に影響するかは、人によって感じ方が異なります。
まずは自分のストレスレベルと記憶力の関係を把握し、さらに年代別でどのような傾向があるかを見ていきましょう。
ストレス度をセルフチェック
日常的にストレスをどの程度抱えているかを簡単に把握することは、記憶力低下の予防に不可欠です。
次のような質問に「はい」が多ければ、記憶力に影響が出ている可能性が高いです。
- 最近、物忘れや「あれ、何だっけ」が増えている
- 睡眠が浅い/寝付きが悪い日が頻繁にある
- 気分が落ち込みやすい、疲れが抜けない
- 締め切り・対人関係で緊張・不安を感じることが多い
加えて、あるアンケート調査では、ストレスを感じている人の約6割以上が記憶力の衰えを実感しており、「名前が出てこない」「ぼーっとする」といった具体的症状が報告されています。
参照 : 第一工業製薬
記憶力低下に悩む人の年代別傾向(10代・20代・30代)
ストレスによる記憶の問題は、若年層でも無縁ではありません。
例えば、ある調査によると、20代でも約 70%程度の人が「時々物忘れをする」と回答し、「最近知ったこと・人の名前を思い出せない」などの具体的な忘れ方を経験していることが分かっています。
ただ、年代が上がるにつれて、物忘れの種類や頻度が変化します。10代は学習内容や日常の情報の記憶忘れが中心であるのに対し、30代では仕事や家庭のストレス・睡眠不足などが複合的に影響し、「重要な予定」や「人との約束を守る能力」にまで影響が拡大する傾向があります。
参照 : ネオマーケティング 記憶力に関する調査
関連記事
: 【要注意】20代で記憶力が低下?ストレス・病気・生活習慣まで原因と対策を網羅解説
: 記憶力が急に落ちた…30代で記憶力が低下する原因&改善法を解説
: なぜ?40代になると勉強が頭に入らない!記憶力を取り戻す学習方法
: 【物忘れがひどい…】50代で記憶力が低下する原因は?|セルフチェック・対策まで解説
脳がストレスに影響を受けるメカニズム

ストレスは単に“気持ちの問題”ではなく、脳の構造や機能そのものに変化をもたらします。
ここでは、ストレスが脳をどう疲弊させ、海馬が萎縮する過程、それが緩やかに取り除かれたときにどのように回復が可能かを、最新の研究から解説します。
ストレスでの脳は疲弊する
慢性的なストレスにさらされると、脳は常に緊張状態に置かれ、注意力・判断力などの認知機能への負荷が高まります。
実際、日本の研究で、ストレス負荷のある環境にいる人では、集中力低下や記憶の定着率が有意に悪くなるというデータがあります。
さらに、情報量が多い日常やマルチタスクが重なると、脳が“処理待ち”の状態となり、“脳疲労(ブレインフォグ)”と呼ばれる状態を引き起こします。これにより新しい情報の取り込みや記憶呼び出しに支障が出ることが指摘されています。
ストレスホルモン「コルチゾール」と海馬の萎縮
ストレスが長期間続くと、「コルチゾール」というホルモンの分泌が慢性的に高い状態になります。
日本の研究では、慢性ストレス曝露モデルのげっ歯類で、コルチゾール増加に伴って海馬の神経細胞の形態変化および萎縮が観察されています。
特に永井裕崇氏らの研究で、慢性社会ストレスが前頭前皮質および海馬の構造的変化を引き起こすことが確認されており、これが記憶力低下と関連しています。
参照 : 慢性社会ストレスによる神経細胞の機能形態変化とその意義
ストレスがなくなれば記憶力は回復する
幸いなことに、海馬萎縮やコルチゾールの過剰分泌による記憶低下は、必ずしも不可逆ではありません。
例えば、ストレス環境を改善したり、十分な睡眠・適切な運動・マインドフルネス瞑想などの介入を行うことで、ホルモンバランスが整い、海馬の神経新生が促進されるという動物モデルの報告があります。
また、人間でもストレス軽減プログラムを通じて、記憶力や注意力が改善したというケースがあります。
参照 : 東京理科大学 精神的ストレス
ストレスで起こりやすい記憶障害
ストレスが強くなると、単なる物忘れ以上の記憶障害が現れることがあります。
ここでは、ストレスによって生じる代表的な記憶障害「解離性健忘」と、「一時的に記憶が飛ぶ」ようなケース、それぞれの特徴や注意点を確認しましょう。
解離性健忘とは?
解離性健忘は、強度のストレスやトラウマがきっかけで発症する心理的な記憶障害で、自分にとって重要な出来事やエピソードが思い出せなくなる状態です。
時には、ある期間の行動が記憶に全く残らず、過去の出来事を意識的に探しても出てこないことがあります。これが日常生活に影響を及ぼす場合、診断対象となる可能性があります。
医師監修の記事によれば、通常の「よくある忘れ物」と異なり、記憶が欠けている期間が明確であり、他の原因(脳の損傷・薬物等)が除外される必要があります。
一時的に記憶が飛ぶケース
ストレスが一時的に高まった直後には、「何を話していたか忘れた」「今日の予定を抜かしていた」など、短時間の記憶が飛ぶような症状が出ることがあります。
これは必ずしも解離性健忘ではなく、脳がストレスによって情報処理や注意力が一時的に低下するためです。
例えば、試験前の極度の緊張・プレッシャー状態や強い睡眠不足下、急な精神的ショックを受けたときなどが典型です。
こうしたケースでは、休息・ストレス軽減・リラックス法などを行うことで記憶障害が改善することが多いです。
記憶力を回復させるストレス対処法

ストレスで記憶力が低下していても、適切な対処を行えば回復は十分可能です。
このセクションでは、生活習慣から思考習慣、記憶術まで、すぐに実践できる具体的な改善策を紹介します。
生活習慣の改善(睡眠・運動・栄養)
睡眠時間・質を改善することは、記憶の整理・定着に不可欠です。
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド」では、規則正しい生活と適度な身体活動が良質な睡眠を促し、睡眠休養感を高めることが推奨されています。
また、筑波大学の研究で、10分間の軽運動(ヨガ・太極拳等)が海馬を刺激し、一時的に記憶力を向上させることが実証されており、ストレス下でも運動が記憶力回復の助けになることがわかります。
- 毎日6〜8時間の規則正しい睡眠をとる
- 就寝前1時間はスマホ・PCを避ける
- 軽い有酸素運動(ウォーキング・ヨガなど)を週3回以上
- 野菜・魚・ナッツなど脳に良い栄養素を意識的に摂取
参照
: 健康づくりのための睡眠ガイド 2023
: 筑波大学 短時間の軽運動で記憶力が高まる
呼吸法やマインドフルネスで脳を休める
呼吸法や瞑想、マインドフルネスはストレスホルモンを減少させ、注意散漫な思考を鎮める効果があります。
深呼吸や腹式呼吸を数分行うだけで自律神経が整い、脳がリラックス状態に入りやすくなります。
これにより、記憶に関わる海馬や前頭前野の働きがサポートされ、集中力が戻りやすくなります。
- 1日3回、深呼吸をゆっくり5分間行う
- 腹式呼吸を意識して自律神経を整える
- 朝や寝る前に短時間の瞑想を習慣化する
- マインドフルネスアプリを活用して続けやすくする
よかったこと日記やポジティブ思考の習慣
毎日「今日は良かったこと」を3つ書き出す習慣は、ストレスの肯定的要素への注意を向け、ネガティブ思考のループを断ち切る助けになります。
ポジティブ心理学の研究でも、このような記録がストレス感・不安感の軽減に繋がり、間接的に記憶力低下を防ぐことが示唆されています。
習慣として朝晩どちらかに行うとより効果的です。
- 1日3つ、その日の「良かったこと」をノートに記録
- 朝に書けば「前向きなスタート」、夜に書けば「安心感」で眠れる
- ネガティブにとらえがちな出来事も「学び」に変換して書く
- 継続のために、寝る前や朝食後など決まった時間に習慣化する
ストレスの少ない働き方を考える
仕事や学業の過度なプレッシャーがストレス源となる場合、タスクの優先順位の見直し、休憩のタイミング調整、業務の分担・断る勇気を持つことが重要です。
また、勤務時間外の連絡を制限する、適切な休暇を取るなど、ワークライフバランスを意識することが脳の回復に役立ちます。
- タスクを「重要度・緊急度」で整理して優先順位を明確にする
- こまめに休憩をとり、1時間に5分程度は脳をリセットする
- 業務過多の場合は同僚や上司に相談し、分担・調整する
- オンオフを切り替えるため、勤務時間外は通知をオフにする
記憶術トレーニングで脳を鍛える
記憶術はただ暗記力を高めるだけでなく、情報の整理や呼び起こしをスムーズにする能力を鍛える方法です。
例えば、「場所法」「ストーリーメソッド」「イメージ連想法」などを取り入れると、新しい情報を覚える効率が上がります。
ストレスが軽減され、これらの技術を使いこなせると記憶力回復の加速にもつながります。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
- 場所法:自宅や通学路を思い浮かべ、覚えたい情報を配置する
- ストーリーメソッド:単語や数字を物語にして関連付ける
- イメージ連想法:人名や単語をビジュアル化して結びつける
受診が必要なケースと診療科の目安
ストレスによる物忘れは一時的なことも多いですが、症状が長引いたり日常生活に支障をきたす場合は、専門医への受診を検討しましょう。
特に「同じ話を何度も繰り返す」「仕事や学業に著しい支障がある」「強い不安や抑うつを伴う」といった場合は要注意です。
診療科としては、心療内科・精神科・神経内科が一般的です。医師による問診や検査によって、ストレス性の記憶力低下なのか、うつ病や認知症など別の疾患なのかを見極めることができます。
早めの受診が適切な治療や回復につながります。
参照 : 厚生労働省「こころの病気について知る」
まとめ|ストレスと記憶力の関係を理解して今日から改善を
ストレスは脳に直接影響し、記憶力の低下を招くことが科学的に示されています。
しかし、睡眠・運動・栄養の見直しやマインドフルネスの実践、ポジティブ習慣を持つことで脳は回復力を発揮します。
さらに、記憶術を取り入れることで情報整理と想起の力を強化でき、ストレスによる物忘れを補うことが可能です。
特に Wonder Education では、最新の脳科学を取り入れた記憶術トレーニングを提供しており、勉強や仕事で成果を上げたい方に最適です。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education
ストレスを正しく理解し、今日から改善への一歩を踏み出しましょう。

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。