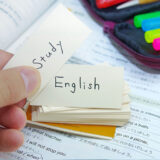キツネさん
キツネさん
「魚を食べると頭が良くなるって本当?」
「子どもの学力や自分の集中力は食事で変えられるの?」
など、疑問を抱く人は少なくありません。
普段の食生活を工夫すれば、勉強や仕事の成果を高めたいという思いに応えられる可能性があります。
この記事では、魚と脳の関係を科学的根拠と通説の両面から整理し、効果的な食べ方やサプリとの比較も解説します。
特に子どもの成長を支えたい親世代や、集中力を伸ばしたい学生・社会人におすすめです。
本記事を読むことで「魚を食べると頭が良くなる」の真偽を理解し、実生活で役立つ知識を得られるでしょう。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
魚で頭が良くなるって本当?科学と通説を比較

魚を食べると頭が良くなるという通説は本当なのか、その科学的根拠と社会的な影響を整理しました。
ここでは、魚で頭が良くなるというテーマに関連する要素を比較し、理解を深めるための切り口を紹介します。
魚で頭が良くなることについて以下の通り解説します。
- DHA・EPAが脳の神経伝達を助ける仕組み
- 嘘と言われる根拠とその誤解
- 「さかなさかな〜♪」の歌が与えた影響とは?
それぞれ順番に見ていきましょう。
DHA・EPAが脳の神経伝達を助ける仕組み
魚に多く含まれるDHAやEPAは、脳の神経細胞膜を柔軟に保ち、情報伝達をスムーズにします。
細胞膜がしなやかであるほど神経伝達物質のやり取りが効率的になり、記憶や学習に関わるシナプス機能の維持に役立ちます。
一方で、DHAは加齢とともに体内から減少し、物忘れや認知機能の低下を招くリスクが高まります。
そのため、全年代で意識的に摂取することが重要であり、特に青魚を週に2~3回取り入れるだけでも効果が期待できます。
つまりDHA・EPAは「頭を良くする」というよりも、“脳のコンディションを整える”基礎栄養素として考えるのが現実的です。
- 脳の神経細胞膜を柔軟に保ち、情報伝達を円滑にする
- 記憶力や学習能力を支えるシナプス機能を維持する
- 血液をサラサラにし、脳梗塞や動脈硬化を予防する
- 悪玉コレステロールや中性脂肪を減らし、生活習慣病リスクを下げる
- 加齢による脳機能低下や認知症予防に役立つ
つまりDHA・EPAは「頭を良くする」よりも「脳を健康に保つ」働きが強く、日常的に魚を取り入れる習慣が将来の知的活動を支える基盤になるのです。
嘘と言われる根拠とその誤解
「魚を食べれば必ず頭が良くなる」という考え方は、科学的にはやや誇張された通説です。
実際、DHAやEPAの不足が認知機能の低下と関係することは多くの研究で示されていますが、短期間でIQが向上するような即効性は確認されていません。
誤解が広まった背景には、2000年代初頭に文部科学省が推進した「魚を食べて賢くなろう」キャンペーンや、CMなどでの簡略化されたメッセージの影響が挙げられます。
例えば、「DHAは記憶力を上げる」といった広告文句が一般化することで、科学的根拠と宣伝目的が混同されてしまったケースも見られます。
つまり、魚は脳の健康を支える重要な食品である一方で、万能な頭脳強化策ではないという冷静な理解が必要です。
「さかなさかな〜♪」の歌が与えた影響とは?
日本で「魚=頭が良くなる」というイメージを強く根付かせたのが「おさかな天国」の歌です。
この歌は1991年(平成3年)にJF全漁連によって展開されたキャンペーンの一環で、「魚を食べよう」=「健康・賢さにつながる」というイメージを親しみやすい形で定着させました。
実際に放送後は、子ども向けの給食献立や家庭での魚料理への関心が高まり、「魚=頭が良くなる」という印象が文化的に広まった背景にもなっています。
このように、科学だけでなくメディアや歌による心理的な刷り込みも人の行動に大きな影響を与えることが分かります。
参照 : 魚食普及ソングの元祖「おさかな天国」
脳の発達を支える魚の選び方と食べ方

脳の成長や機能維持には、魚に含まれるDHAやEPAなどの栄養素を効果的に摂取することが重要です。
ここでは、魚を取り入れる際に知っておくべき種類や年代ごとの効果、さらに調理方法による違いを解説します。
- DHA・EPAが豊富な魚ランキング
- 妊娠期・乳幼児・学童・高齢者の効果
- 調理法で変わる栄養吸収率(生・缶詰・焼き)
それぞれ順番に解説します。
DHA・EPAが豊富な魚ランキング
DHAは脳の神経細胞膜を構成し、情報伝達や記憶・学習に欠かせない成分です。
一方EPAは血液をサラサラにして血管の健康を守り、動脈硬化や心疾患の予防に役立ちます。
魚によって含有量は大きく異なるため、両方のランキングを把握することが効率的な摂取につながります。
DHA・EPAの摂取には、どの魚を選ぶかが重要です。以下のランキングは、文部科学省「食品成分データベース」などの公的資料に基づいています(100gあたりの含有量)。
含有量が多いからといって、そればかりを食べるのではなく、週に2〜3回を目安に、調理しやすい魚・家庭で食べやすい魚を選ぶことが続けるコツです。
- ミナミマグロ(トロ):DHA約4,000mg、EPA約1,600mg
- クロマグロ(トロ):約3,200mg、EPA約1,400mg
- サンマ:約2,200mg、EPA約1,500mg
- ブリ:約1,700mg、EPA約940mg
- ウナギ:約1,100mg、EPA約580mg
このように、DHAはマグロやサバに多く、EPAはサバやマグロに豊富です。
青魚を中心にさまざまな魚を取り入れることで、脳と血管の両方を健康に保つ効果が期待できます。
参照 : 日本食品標準成分表
妊娠期・乳幼児・学童・高齢者の効果
魚に含まれるDHAやEPAは、ライフステージごとに異なる働きを持っています。
DHAやEPAの摂取効果は、年代や体の発達段階によって異なります。とくに妊娠中の女性や乳幼児期には、発達中の脳神経の形成に不可欠な栄養素です。
- 妊娠期|胎児の脳や神経の発達を助け、視覚機能の形成をサポートする
- 乳幼児|視覚や認知機能の発達を促し、学習の土台を築く
- 学童期|記憶力や集中力を高め、学習効率を向上させる
- 高齢者|認知症予防や脳の老化抑制に役立ち、物忘れを防ぐ効果が期待できる
このようにDHA・EPAは年代ごとに効果が異なり、家族全員の健康を守るために有効です。
健康にも良い影響を与えるため、世代に応じて魚を習慣的に取り入れることを推奨します。
参照 : オメガ3脂肪酸EPAとDHA:生涯にわたる健康効果
調理法で変わる栄養吸収率(生・缶詰・焼き)
調理方法によって、DHAやEPAの「残存率(失われにくさ)」は大きく異なります。
特に缶詰や刺身は栄養を逃しにくく、効率よく摂取可能です。缶詰は加工で栄養を逃さず、缶汁まで食べることでさらに効率的に補えます。
調理方法ごとのDHAやEPAの吸収率は以下の通りです。
| 調理法 | DHA残存率 | EPA残存率 |
| 生(刺身など) | 100 % | 100 % |
| 焼き(グリル) | 約 87 % | 約 92 % |
| 焼き(フライパン・油なし) | 約 85 % | 約 80 % |
| 揚げ(フライ) | 約 58 % | 約 51 % |
参照 : 日本脂質栄養学会
このように調理法ごとに残存率や吸収率は異なります。
日常的には刺身や焼き魚をバランスよく組み合わせることが望ましいでしょう。
サプリと魚、どちらが効果的?

健康的な食生活を目指すなら、まずは魚が理想的。ただし魚嫌いの人や調理が難しい場合は、サプリを補助的に活用するのが現実的な選択肢です。
ここでは、サプリと魚のメリットや注意点を整理します。
- DHAサプリの効果と注意点
- 魚を中心とした自然な摂取のメリット
それぞれ順番に解説します。
DHAサプリの効果と注意点
DHAサプリは、手軽に必要量を補える利便性が最大の特徴です。
特に魚をあまり食べない人や忙しい生活を送る人にとっては、安定した摂取源として役立ちます。
しかし一方で、過剰摂取による副作用や品質の差による有効性の違いには注意が必要です。
つまりサプリは「補助的な役割」として活用すべきものであり、万能な代替手段ではありません。
信頼できるメーカーを選び、用量を守ることが安全かつ効果的な利用につながるのです。
魚を中心とした自然な摂取のメリット
魚から直接DHAやEPAを摂ることには、サプリにはない利点が多く含まれています。
魚にはタンパク質やビタミンD、カルシウムなど他の栄養素も同時に含まれており、相乗効果が期待できます。
さらに食事として楽しめるため、継続しやすく生活習慣の改善にもつながるのが大きな強みです。
ただし水銀や環境汚染のリスクを避けるため、種類や食べ方に配慮することが必要になります。
つまり魚中心の摂取は、栄養バランスと食文化の両面から見ても望ましい選択肢だといえるでしょう。
頭が良くなる食事を支える「組み合わせの工夫」

脳の働きを最大限に活かすには、主食=糖質(脳のエネルギー源)、たんぱく質=神経伝達物質の原料、ビタミンB群=糖質を脳に運ぶサポーターとして、それぞれの役割を意識した食事が重要です。
ここでは、主食・たんぱく質・ビタミンを組み合わせる工夫と、具体的に実践できるレシピの形を紹介します。
- 主食とビタミン・たんぱく質のバランス
- 実践例:一汁三菜で脳を育てるレシピ
それぞれ順番に解説します。
主食とビタミン・たんぱく質のバランス
主食とビタミン・たんぱく質のバランスは、脳の働きを安定させるうえで欠かせません。
糖質は脳の唯一のエネルギー源となるため、主食は必須ですが、炭水化物だけでは代謝に必要な補助栄養素が不足します。
ビタミンB群は糖質をエネルギーに変換する酵素の働きを助け、効率的に脳へ供給する役割を果たします。
さらに、たんぱく質に含まれるアミノ酸は神経伝達物質の材料となり、集中力や記憶力を支える仕組みを強化します。
例えば白米に魚や肉、卵、大豆製品を組み合わせることで、糖質の代謝と神経活動が同時にサポートされるのです。
このように主食だけでなく副菜も意識的に取り入れることで、学習や仕事における脳のパフォーマンスが安定します。
習慣として続けることで、日常生活の集中力や思考力の基盤を築けるのです。
実践例:一汁三菜で脳を育てるレシピ
実践例として、日本の伝統的な一汁三菜は脳を育てる理想的な食事法です。
汁物で水分やミネラルを補い、主菜でたんぱく質やDHAを摂取し、副菜でビタミンや食物繊維を加えることで栄養が整います。
家庭で無理なく取り入れられるため、学習や集中力を支える基盤になります。
- 汁物:味噌汁に豆腐やわかめを入れ、水分とミネラルを補給する
- 主菜:焼き魚や鶏肉の照り焼きでDHAやたんぱく質を摂る
- 副菜:ほうれん草のお浸しやひじき煮でビタミン・食物繊維を補う
- 主食:白米や雑穀米で脳のエネルギー源となる糖質を確保する
このように、一汁三菜を実践すれば栄養バランスが自然と整い、脳の発達や働きを日常的に支えられます。
無理なく続けやすいため、習慣化しやすいのも大きな利点です。
よくある質問|魚と脳の関係Q&A
魚と脳の関係に関するよくある質問について解説します。
魚を食べるだけで成績アップする?
魚を食べること自体が直接的に成績向上を保証するわけではありません。
しかしDHAやEPAが脳の働きを助けることは多くの研究で示されており、学習効率を高める環境づくりには貢献します。
つまり食事だけでなく、睡眠や学習習慣と組み合わせることで真価を発揮するのです。
魚は学力アップの万能薬ではなく、生活全体を支える要素と理解することが正しい考え方といえます。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
子どもが魚嫌いな場合の代替案は?
子どもが魚を嫌う場合には、無理に食べさせるのではなく代替策を工夫することが効果的です。
例えば魚の缶詰やフィッシュソーセージ、DHA入り食品を活用すれば必要な栄養を補えます。
また魚を小さくほぐしてカレーやハンバーグに混ぜると、抵抗なく取り入れやすくなります。
このように調理法や代替食品を工夫することで、魚嫌いでも脳に必要な栄養を確保できるのです。
魚を毎日食べても問題ない?
魚を毎日食べることは基本的に健康に良いとされますが、注意点もあります。
一部の大型魚は水銀を含むため、妊娠中や小児は摂取量に配慮する必要があるのです。
また脂質や塩分の多い調理法ばかりだと生活習慣病リスクを高めてしまいます。
つまり種類や調理法を工夫し、週に数回を目安に青魚などを中心に食べるのが安心で効果的な方法といえます。
まとめ|魚を“脳活”に取り入れた生活を今日から始めよう
本記事では、魚を食べると頭が良くなる理由と、効果的な食べ方について解説しました。
DHAやEPAは脳の神経細胞を支え、記憶力や集中力の維持に役立ちます。
魚を取り入れる工夫は、缶詰や簡単なレシピを活用すれば誰でも続けられるので、今日から魚を“脳活”に取り入れて、学習や仕事の成果を高めていきましょう。
最後に、今日から実践できる具体的な行動や魚を使った食材・レシピの紹介を通して、持続的に取り組む方法を紹介します。
今日からできる3つのアクション
脳の健康を考えるなら、魚を生活に取り入れる習慣を小さな工夫から始めることが大切です。
まず次の3つに取り組んでみると良いでしょう。
- 週に2回以上、魚を食卓に取り入れる
- 缶詰や冷凍品を常備する
- 近くの回転寿司屋を調べる
この3つの行動は継続しやすく、日常生活に負担なく取り入れられる点が大きな強みになります。
つまり無理のない工夫を重ねることが、脳を長く健やかに保つための第一歩といえるでしょう。
魚中心のおすすめ食材・レシピ紹介
魚を継続的に食べるには、調理のしやすさとおいしさを両立したレシピを取り入れるのが効果的です。
サバ缶を使った味噌煮やイワシのトマト煮、鮭のホイル焼きなどは栄養価が高く、短時間で作れる実用的な料理です。
また、DHAやEPAを逃さず摂れる調理法を意識することで、魚の持つ力を余すことなく活かせます。
このように具体的な食材やレシピを選ぶことで、毎日の“脳活”を楽しみながら継続できる生活に変えられるのです。
「もっと記憶力を高めて勉強や仕事に活かしたい」という方には、「吉永式記憶術」もおすすめ。科学的根拠に基づいた実践的なトレーニング法で、初心者でも無理なく取り組めます。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い指導を通じて記憶力向上と目標達成をサポートしています。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。