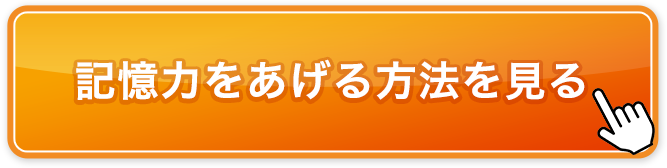キツネさん
キツネさん
仕事の習得につまずくと焦りやストレスが積み重なり、さらに覚えにくくなる悪循環に陥りやすいものです。
この記事では、 仕事が覚えられない原因や年代別の特徴、病気の可能性、具体的な改善策まで詳しく解説します。
仕事の覚え方に不安がある20代〜60代の方が、原因を整理し、自分に合った対処法を見つけられる内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。
なお、記憶力の上げ方については記憶力を上げる方法とは?|誰でもできる記憶向上テクニックを紹介の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
もくじ
【原因編】仕事が覚えられない10の理由

仕事を覚えられないと感じる背景には、さまざまな要因が存在します。
単なる能力の問題ではなく、環境や体調、教育の仕方も関係しているのです。
- メモや記録を取らない
- 教わった内容を理解できていない
- 集中力や記憶力が低下している
- 教育・指導方法が合っていない
- 仕事量や情報量が多すぎる
- ストレスや精神的な負担が大きい
- ハラスメントの多い職場環境
- 作業環境が整っていない
- 体調不良や疲労がある
- 反復練習や復習が不足している
それぞれ順番に解説します。
① メモや記録を取らない
仕事を覚えるためには情報の整理が欠かせません。
メモを取らない場合、重要なポイントや手順が曖昧になりやすく、復習も難しくなります。
一度聞いただけで完璧に記憶するのは困難ですが、 メモがあれば後から見返すことで理解が深まり、忘れても確認できます。
さらに、記録を取る習慣があれば、知識の蓄積や整理が進み、応用力の向上にもつながります。
覚えにくいと感じたときは、まずメモの取り方を見直すのが効果的です。
② 教わった内容を理解できていない
表面的に教わった内容をなぞっても、本質的な理解が伴わなければ記憶に残りません。
仕事の流れや目的を理解していないと、作業手順だけを覚えても応用が利きにくくなります。
理解が浅いままだと応用的な質問やイレギュラー対応で混乱しがちなので、 ポイントは「なぜこの作業が必要なのか」を常に意識することです。
疑問があれば積極的に質問し、背景まで理解すれば記憶の定着が大きく変わるでしょう。
改善策としては、以下のような方法が有効です。
- 作業の目的や全体の流れを図解して整理する
- 上司や先輩に理由を確認しながら学ぶ
- 自分の言葉で手順を説明し直す練習を行う
- 業務マニュアルを読み込んで背景知識を補う
- 失敗事例や過去のケースを振り返る習慣をつける
これらを継続すれば、理解力と応用力の向上につながるでしょう。
③ 集中力や記憶力が低下している
十分な集中力が保てなければ、教わった内容も頭に入りにくくなります。
睡眠不足や疲労、心配事などが集中を妨げる原因になるのです。
また、加齢やストレスによって記憶力そのものが低下することもあります。
集中できる環境づくりや、適切な休憩、睡眠の確保は非常に重要です。
集中が途切れやすいときは短時間の反復学習を取り入れると、記憶の安定に役立つでしょう。
関連記事:仕事に集中できない3つの原因とは?集中を維持する効果的な対処法を徹底解説
④ 教育・指導方法が合っていない
人によって理解しやすい教え方は異なります。
説明が抽象的すぎたり、逆に細かすぎたりすると理解が進みにくくなるのです。
また、一度に大量の情報を詰め込まれても消化しきれないこともあります。
相手の理解度に合わせた指導が行われていないと、学習効率は大きく低下します。
視覚的な資料を使う、実演してもらう、繰り返し練習するなど、柔軟な指導法が求められます。
自分に合う学び方を上司や先輩に相談するのも効果的な対策でしょう。
⑤ 仕事量や情報量が多すぎる
扱う仕事が多岐にわたると、覚えなければならない情報も膨大になります。
新しい業務に次々と取り組むうちに、過去に覚えた内容が薄れていくこともあります。
また、同時に複数の仕事を進めるマルチタスク状態が続くと、集中力が分散されやすくなるのです。
情報が整理されないまま増え続ければ、混乱やミスの原因にもなります。
タスクの優先順位を決めたり、学ぶ範囲を段階的に絞ったりする工夫が有効でしょう。
⑥ ストレスや精神的な負担が大きい
強いプレッシャーや職場の人間関係の悩みがあると、精神的な余裕が失われます。
不安や緊張が高まることで、集中力や記憶力が著しく低下するのです。
「失敗してはいけない」と思うほど、緊張によって本来の力を発揮できなくなるケースもあります。
さらに、慢性的なストレスは睡眠の質を悪化させ、体調にも悪影響を及ぼします。
適度に休息を取り、気分転換を心がければ、学習効率の改善につながるでしょう。
⑦ ハラスメントの多い職場環境
上司や同僚からのパワハラ、モラハラなどのハラスメントは大きな心理的負担になります。
職場の人間関係が悪化すると、安心して学ぶことが難しくなります。
怒鳴られたり、人格を否定されたりする状況が続けば、萎縮して質問すらできなくなるでしょう。
萎縮状態では新しい情報を受け入れる余裕がなく、記憶にも定着しにくくなります。
安全で支援的な職場環境が整わない限り、学習の効率も著しく下がる傾向が強まります。
⑧ 作業環境が整っていない
整理されていない作業スペースや騒がしい職場では集中が妨げられます。
必要な道具が見つからない、資料がバラバラに管理されているなども効率を下げる要因です。
物理的な環境の乱れは心理的な負担にもつながり、学習への集中が続きません。
整ったデスク、整理されたマニュアル、静かな作業場所は記憶の定着にも良い影響を与えます。
まずは身の回りの環境を見直すだけでも、仕事の覚えやすさは大きく変わります。
⑨ 体調不良や疲労がある
身体が万全でなければ、当然ながら集中力や記憶力も低下します。
慢性的な寝不足や栄養不足、運動不足は学習効率を著しく悪化させるのです。
また、肩こりや腰痛などの身体的不調が続くと、集中力が途切れやすくなります。
体力的な負担が減れば、自然と仕事を覚える余裕も生まれてくるでしょう。
十分な休息、適切な食事、軽い運動を日常に取り入れることが大切です。
⑩ 反復練習や復習が不足している
新しい知識や技能は、繰り返し練習することで初めて定着します。
一度聞いただけでは短期記憶にとどまり、すぐに忘れてしまう可能性があるのです。
反復することで記憶は長期記憶に移行し、自然に思い出せる状態になります。
たとえば、仕事の手順やルールなどをノートに書きとめておき、毎日少しの時間で復習するなども効果的です。
復習の間隔を空けすぎると、学んだ内容が曖昧になりやすくなります。
仕事を覚えにくいと感じたときこそ、こまめな復習と実践の積み重ねが効果的でしょう。
【特徴編】仕事を覚えられない人の年代別の傾向

仕事を覚えにくさには年代ごとの特徴があり、年齢や環境によって悩みの原因は異なります。
- 20代|慣れない職場環境と緊張で覚えられない
- 30〜40代|業務の複雑化や家庭との両立が負担に
- 50〜60代|記憶力や集中力の低下が影響することも
それぞれ順番に解説します。
20代|慣れない職場環境と緊張で覚えられない
20代は初めての職場で緊張しやすく、職場環境に適応するまでに時間を要することが多いです。
緊張状態が続くと集中力が下がり、教わったことが頭に入りにくくなるのです。
さらに、 職場の雰囲気や人間関係に不安を感じると、注意がそれて学習効率も落ちやすくなります。
上司の指導法や職場の教育体制によっても習得スピードに差が出るため、積極的に質問したり、メモを活用したりする工夫が役立ちます。
経験を積むことで徐々に余裕が生まれ、理解も深まっていきます。
30〜40代|業務の複雑化や家庭との両立が負担に
30〜40代は担当する業務の幅が広がり、内容も複雑になる時期です。
同時に 家庭では育児や家事、親の介護など、私生活の負担も増えがちになります。
複数の責任を抱える中で新しい知識を覚えるのは簡単ではありません。
睡眠不足や疲労がたまると集中力も低下しやすく、結果として仕事の習得が遅れることもあります。
優先順位を整理し、無理のないスケジュールを組むことが重要です。
周囲のサポートを得ながら、少しずつ知識を積み重ねる姿勢が必要でしょう。
関連記事:【物忘れしてしまう…】30代で記憶力が低下する原因とは? 改善方法3選も
50〜60代|記憶力や集中力の低下が影響することも
50〜60代になると、年齢とともに記憶力や集中力の低下を感じる場面が増えてきます。
若い頃のように短期間で多くの知識を詰め込むのは難しくなりますが、意味を理解して覚える学び方が効果を発揮します。
ただ暗記するのではなく、 仕事の背景や目的を理解することで内容が整理され、記憶にも残りやすくなるのです。
また、身体の疲労や体調不良も集中力に影響するため、無理をせずこまめに復習を繰り返すことが重要です。
適度な休息や体調管理を心がけながら、自分に合ったペースで学ぶ工夫が成果につながるでしょう。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
【病気の可能性】発達障害・うつ・軽度知的障害とは?

「仕事が覚えにくい」という悩みの背景には、性格や環境だけでなく、病気が関係していることもあります。
本人も周囲も気づかずに悩みを深めてしまうケースもあるため、正しい理解と早めの対応が大切です。
- 発達障害(ADHD・ASD)の特徴と対策
- うつ病・適応障害などの精神的要因
- 境界知能・軽度知的障害による影響
それぞれ順番に解説しますので、心当たりがある方は必要に応じて適切に対処してみてください。。
① 発達障害(ADHD・ASD)の特徴と対策
ADHDの人は、周囲の刺激に気を取られやすく、注意がそれやすい傾向があります。
一方でASDの人は、変化や曖昧な指示に対して戸惑いやすく、状況に応じた対応が難しく感じることがあります。
そのため、仕事の手順を覚えにくかったり、同じミスを繰り返してしまうこともあるでしょう。
ただし、自分が得意な分野では高い集中力や能力を発揮できる場面もあります。
仕事を覚えるときは、 手順を紙に書き出したり、図や表を使って整理したりすると理解しやすくなります。
さらに、上司や同僚にわかりやすく説明してもらうよう頼むのも効果的です。
必要であれば専門の診断を受け、支援制度や配慮を活用することも大切でしょう。
② うつ病・適応障害などの精神的要因
うつ病や適応障害があると、集中力や意欲が大きく落ち込んでしまうことがあります。新しい知識を吸収する気力が湧かず、覚えようとしてもなかなか頭に入らないと感じるはずです。
さらに、物事を悪く考えやすくなり、「自分は覚えられない」と思い込んでしまうこともあるでしょう。症状が悪化すると、仕事だけでなく日常生活全体に支障が出ることもあります。
そのまま無理を続けず、少しでも早く専門の医療機関に相談してみることをおすすめします。
治療と並行して、急がず焦らず、ゆっくり学べるスケジュールを組むと気持ちも少し楽になります。
職場の人に相談して、配慮してお休みをもらうなどすれば、負担を減らす助けになるでしょう。
③ 境界知能・軽度知的障害による影響
境界知能や軽度知的障害があると、理解力や記憶力の習得に時間がかかることがあります。
仕事を覚えるには繰り返し練習することが必要になり、複雑な手順では混乱やミスが起こりやすくなるのです。
しかし、 図や写真を使った手順書や、作業を細かく分けた説明を取り入れると理解しやすくなります。
十分な練習時間を確保し、自分に合った説明を相談しながら進めることが大切です。
また、専門機関で評価を受け、支援制度を利用すれば、成長の大きな助けになるでしょう。
【対策ガイド】今日からできる10の改善法

仕事を覚えるのが難しいと感じたときは、日々の工夫で改善できることが多いです。
ここでは、すぐに実践できる10の具体的な方法を紹介します。
- メモやノートを必ず取る
- わからない点は積極的に質問する
- 仕事の優先順位を明確にする
- TODOリストを作り小さな作業に分けて取り組む
- 復習や反復練習を習慣化する
- 集中できる環境を整える
- 休憩を適切に取りリフレッシュする
- 仕事の流れや目的を理解する
- 先輩や上司にフィードバックを求める
- モチベーション維持の工夫をする
それぞれ順番に解説します。
① メモやノートを必ず取る
仕事を覚えるには、情報を整理して残すことがとても大切です。
繰り返しにはなりますが、 一度聞いただけでは忘れてしまうことが多いため、メモやノートを取る習慣を身につけましょう。
箇条書きや図、フローチャートなど、自分が理解しやすい形でまとめると復習もしやすくなります。
メモは後で読み返すことで記憶を補強でき、復習のタイミングでも役立つはずです。
忘れてもすぐに確認できる環境を整えれば、不安も減少するでしょう。
② わからない点は積極的に質問する
仕事を覚える際、疑問を放置すると誤ったまま覚えてしまうことがあります。
わからない点は早めに質問し、曖昧な部分を解消することが大切です。
質問を重ねることで、自分の理解が不十分な箇所にも気づけます。
ただし、同じ内容を繰り返し尋ねないよう、事前にメモを見返す習慣も心がけましょう。
上司や先輩も質問の内容を把握しやすくなり、より的確なアドバイスを受けられます。
早めの解決は効率の向上につながります。
③ 仕事の優先順位を明確にする
仕事が多いと、何から手をつけるか迷うことがあるため、 前日のうちに優先順位を決めておくと、当日の作業がスムーズになります。
その場合は「重要度」と「緊急度」の2軸で優先順位を決めるのが効果的です。
たとえば、重要かつ緊急な業務は即対応、重要だが緊急でない業務は計画的に進めるなど、あらかじめ仕分けておくと整理しやすくなります。
判断に迷うときは、上司に優先順位の確認を依頼するのも一つの方法です。
優先順位が明確になるだけで、作業の見通しが立ち、無駄な迷いを減らせます。
④ TODOリストを作り小さな作業に分けて取り組む
大きな仕事に取り組むときは、作業を細かく分けたToDoリストを活用すると良いでしょう。
例えば 「資料作成」の場合、「情報収集」「下書き作成」「上司確認」「修正清書」と段階的に分解します。
こうすることで進捗が把握しやすくなり、達成感も得られます。
さらに、重要度と緊急度を基準に優先順位を決めれば、作業効率が高まりはずです。
タスク管理には「マネーフォワード クラウド」のテンプレートに加え、Trello、Google ToDoリスト、Todoist、Stockといったアプリの活用も役立ちます。
業務全体の見える化が進み、作業負担の軽減にもつながるでしょう。
⑤ 復習や反復練習を習慣化する
一度覚えた内容でも、時間が経つと自然に忘れてしまうことがあります。
そのため、復習を繰り返すことで知識が定着し、長期間思い出しやすくなるのです。
特に 道具の操作、美容師の頭髪カット、機械の扱い、接客時の言葉遣いなど、手や体を使う仕事では反復練習が欠かせません。
例えば、毎朝の作業開始前に手順を確認したり、終業後に当日の作業内容を振り返る習慣を取り入れると効果的です。
短時間でも毎日継続すれば理解が深まり、自信も高まります。
繰り返し実践するうちに自然と応用力も備わっていくでしょう。
⑥ 集中できる環境を整える
集中力が欠けると、せっかく覚えた仕事の手順や内容も身につきにくくなります。
仕事に集中するには、 物理的な環境だけでなくデジタル環境の整備も重要です。
通知をオフにする、集中タイマーアプリを使うなど、注意をそらす要素を減らしましょう。
また、早朝の静かな時間帯を活用したり、必要な資料だけを手元に置いて視界を整理することも効果的です。
「集中できる空間」を意識的につくることで、学習効率が大きく変わってきます。
⑦ 休憩を適切に取りリフレッシュする
仕事を覚えようと集中していても、長時間続ければ注意力は低下しやすくなります。
適度に休憩を挟めば疲労の蓄積を防ぎ、集中力も戻りやすくなるはずです。
仕事中は「50分作業して10分休憩する」サイクルを意識すると効果的で、集中力に合わせて時間を調整してみると良いです。
さらに、2時間ごとに15分ほどの少し長めの休憩を入れると頭がリセットされ、作業のミスも減ります。
散歩や軽いストレッチなどで体を動かすと、気分転換になり集中力も回復しやすくなるでしょう。
無理に作業を続けるより、定期的に休憩を入れた方が仕事の習得もスムーズに進むはずです。
⑧ 仕事の流れや目的を理解する
作業手順だけを覚えようとすると、応用が利かなくなることがあります。
なぜこの仕事が必要なのか、全体の流れはどうなっているのかを理解することが大切です。
目的がわかると、手順の意味も理解しやすくなり、自然と記憶の定着も良くなります。
また、全体像を把握していればイレギュラー対応にも柔軟に対応しやすくなるでしょう。
最初は難しくても、仕事の背景や目的を意識することが、理解力を高めるポイントです。
⑨ 先輩や上司にフィードバックを求める
仕事を覚えるときは、自分だけで試行錯誤を続けるより、先輩や上司からアドバイスを受ける方が効率的です。
例えば 「もし気づいた点があれば教えていただけますか」「改善できる部分があれば教えてください」と声をかけると良いでしょう。
フィードバックを受けることで、自分では気づきにくいクセやミスも早めに把握できます。
どの部分を改善すれば良いのか具体的にわかれば、次の作業でも注意を向けやすくなります。
アドバイスを素直に受け入れ、修正を重ねるうちに仕事の精度も高まっていくでしょう。
周囲の助言を前向きに取り入れる姿勢が、成長を早める力になるはずです。
⑩ モチベーション維持の工夫をする
仕事を覚えるには、継続して学び続ける意欲が欠かせません。
しかし、思うように覚えられないと、やる気を失ってしまうこともあるでしょう。
そこで、次のように自分なりのモチベーション維持の工夫が重要になります。
- 小さな目標をこまめに設定する
- 達成したら自分にご褒美を用意する
- 進捗を可視化して成長を実感する
- 周囲に取り組みを報告して応援を受ける
- 失敗しても原因を分析し前向きに切り替える
目標を小さく設定し、達成ごとに自分を褒める習慣をつけると前向きになりやすいのです。
また、同僚や家族に努力を共有して励ましてもらうのも良い方法です。
自分に合った方法で気持ちを前向きに保てば、自然と学ぶ意欲も続きやすくなるでしょう。
記憶術を活用すれば仕事を覚えやすくなる

仕事を覚えるときは、記憶術を活用すれば効率良く習得できます。
ただ暗記するのではなく、実際の業務と結びつけながら覚えると定着しやすくなります。
特に次のような記憶術を取り入れると効果的です。
- マニュアルの手順を図解して全体像を視覚化する
- 顧客名や商品コードを語呂合わせで記憶する
- 接客フレーズや電話対応をロールプレイで体に覚えさせる
- 作業手順をストーリー化して順番を整理する
- 復習日を決め、間隔反復で定期的に振り返る
さらに、脳の働きに合わせた次のような方法も有効です。
- イメージ法で内容を映像として記憶に残す
- 場所法(Loci法)を使い、情報を空間に結びつける
- マインドマップで情報を整理し関連付ける
- 人に教えることでアウトプットし理解を深める
- 十分な睡眠と栄養で脳の状態を整える
これらを組み合わせて実践すれば、仕事の理解が進み応用力も育ちます。
 キツネさん
キツネさん
関連記事:記憶力を伸ばせば仕事は楽しくなる!今日から実践できるコツを紹介
仕事覚えられないに関するよくある質問
最後に、「仕事が覚えられない」と悩む人からよく寄せられる質問に、ひとつずつ答えていきます。
仕事を覚えられないのは甘え?
仕事を覚えられないことを単なる甘えと決めつけるのは早計です。
多くの場合、 原因は記憶力そのものではなく、教え方や環境、体調、ストレス、理解不足など複数の要素が絡んでいます。
誰でも初めは覚えられないことが普通であり、工夫や練習を重ねることで徐々に習得できるものです。
周囲のサポートや適切な方法を取り入れれば、改善の余地は十分にあります。
どうしても覚えられない仕事は辞めるべき?
どうしても覚えられないと感じたときは、 すぐに辞めるのではなく、まず原因を整理することが大切です。
仕事内容が自分に合っていないのか、指導方法に問題があるのか、体調面で負担が大きいのかを客観的に見直しましょう。
改善策を試みた上で、それでも適性が合わないと判断した場合に転職を検討するのが現実的です。
焦らず慎重に判断することが重要です。
仕事を覚えられない人に向いている職業は?
記憶力に不安があっても、工夫しながら取り組みやすい仕事はたくさんあります。
ルーティン作業が多い職種やマニュアル化されている業務、作業内容が明確で繰り返し練習できる仕事は習得しやすい傾向です。
具体的には、清掃スタッフ、工場での検品・組立作業、倉庫内ピッキング、宅配ドライバー、簡易な事務補助(データ入力など)などが挙げられます。
また、「興味を持てること」や「過去に経験があること」も職種選びの大事なヒントになります。得意・不得意を整理しながら、無理なく続けられる選択肢を探してみましょう。
40代でも仕事が覚えられないのは普通?
40代で新しい仕事を覚えるのに苦労するのは珍しくありません。
加齢による記憶力や集中力の低下、家庭や健康面での負担、責任の重さなどが影響します。
ただし、 意味を理解しながら学ぶ、経験と結びつけて覚える、復習を重ねるといった工夫で十分に改善できます。
年齢を理由に諦める必要はなく、自分に合った学び方を見つけることが大切です。
まとめ|原因を知り、正しい対策で悩みから脱却しよう

本記事では、仕事が覚えられない原因、年代別の特徴、病気の可能性、改善策について解説しました。
仕事を覚えられない背景には、記憶力だけでなく、環境・体調・ストレス・指導方法など複合的な要因が影響しています。
正しい対策を取れば、多くの場合は改善が可能なので、諦める必要はありません。
また、記憶術やモチベーション維持の工夫を取り入れることで、仕事習得のスピードも高まります。
自分に合った方法を見つけ、焦らず着実に取り組むことが、悩みからの解放につながります。
「もっと効率よく覚えられるようになりたい」と感じた方には、記憶力を高めるトレーニングの活用もおすすめです。Wonder Educationでは、誰でも取り組める 記憶術講座 を通じて、仕事への自信回復をサポートしています。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。