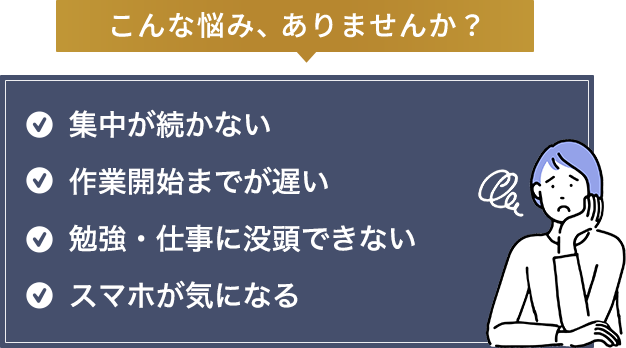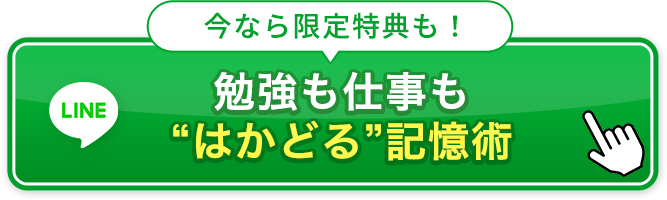キツネさん
キツネさん
「人間の集中力はどれくらい続くのか?」と疑問に思ったことはありませんか。
授業や会議で数十分も経つと注意が散漫になったり、仕事中に何度も休憩したくなったりするのは、多くの人が経験していることです。
実際、研究では集中力の持続時間は15分〜90分程度とされ、一日の中で集中できる合計時間にも限界があると報告されています。
本記事では科学的データをもとに、集中力の平均持続時間や切れる原因、そして具体的な改善方法をわかりやすく解説します。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
人間の集中力はどのくらい続くのか?

集中力がどれくらい持つのかは、多くの人が気になるテーマです。
実際には「15分しか続かない」という説もあれば、「90分ごとに集中と休憩のサイクルがある」という研究も存在します。
ここでは、代表的な研究データや脳科学の仕組み、そして一日の中で集中しやすい時間帯について解説します。
集中力の平均持続時間(15分・45分・90分サイクル説)【研究データ】
集中力の持続時間については諸説あります。
心理学や脳科学の研究では、以下のような見解が示されています。
- 15分説:授業や会議での注意力は15分前後で低下しやすい
- 45分説:作業効率が落ち始めるのは45分程度が目安
- 90分説:人間の覚醒リズムは約90分ごとに切り替わる(ウルトラディアンリズム)
つまり、集中の持続時間には個人差があり、作業内容や環境によっても変動します。短時間で区切る方法から90分サイクル活用まで、自分に合ったリズムを探ることが重要です。
関連記事 : 15分だけ集中する勉強法を紹介!
参照
: 日本教育心理学会「授業中の集中力の持続について」
: Kleitman, N. (1963). Sleep and wakefulness. University of Chicago Press.
集中力が切れるメカニズム(脳の仕組み)
集中力が途切れる背景には、脳の仕組みが関わっています。
主な要因は以下の通りです。
- 前頭前野の疲労:集中や判断を担う領域だが、酷使すると機能が低下
- 情報処理の過負荷:大量の刺激を処理すると疲労物質が蓄積
- エネルギー不足:脳はブドウ糖を多く消費し、不足すると思考力が落ちる
つまり、集中力が切れるのは意志の弱さではなく脳の自然な反応です。定期的な休憩や栄養補給は、集中力の維持に欠かせません。
参照
: 国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)「前頭前野の役割と疲労」
: 脳科学辞典「前頭前野」
一日の中で集中しやすい時間帯
集中力は一日を通して一定ではなく、体内時計やホルモンのリズムに左右されます。
研究では、多くの人に共通するピークが報告されています。
- 午前10時前後:朝食後に覚醒が高まり、集中力が増す
- 午後2時〜4時:昼食後の低下を経て、再び集中しやすくなる
- 夜型の人:夕方〜夜にかけて集中力が高まる傾向あり
このように、集中しやすい時間帯は人それぞれ異なります。自分の体内リズムを把握し、重要なタスクをその時間に配置すると効率が上がります。
関連記事 : 集中力は時間帯で決まる!仕事や勉強で活かせる攻略法を紹介
参照
: 東京大学大学院医学系研究科「体内時計と集中力の関係」
: National Sleep Foundation「Best Times for Productivity」
集中力の限界は本当にある?

「人間の集中力は◯分しか持たない」といった説を耳にすることがあります。
なかでも「8秒しか続かない」という極端な説も話題になりましたが、実際には科学的に根拠が薄いと言われています。
ここでは、研究に基づく集中力の実際と、作業ごとの集中可能な目安時間を解説します。
「限界8秒説」は誤解?研究の実際
「人間の集中力は8秒しか続かない」という説は、カナダ・マイクロソフト社が発表した調査をもとに広まりました。
しかし、これは主にインターネット利用時の注意の持続時間を調査したもので、人間の集中力全般を示すものではありません。
心理学や教育学の研究では、集中力は作業内容や環境により大きく異なるとされています。つまり、8秒という数字は誤解を招きやすく、実生活の集中力を正しく反映しているとはいえないでしょう。
参照 : Microsoft Canada (2015). “Attention Spans Research Report”
作業ごとの集中時間の目安
集中力の限界は作業の種類によって変わります。
代表的な作業ごとの集中可能時間の目安は以下の通りです。
- 講義、授業を聞く:15〜20分で注意力が低下しやすい
- 会議やディスカッション:30〜40分程度が限界とされる
- 単純作業(入力・整理など):60分前後は維持できる
- 読書や学習:45〜60分で集中が途切れやすい
- 創造的な作業(企画・執筆・研究など):90分が一区切り
このように、集中できる時間は作業の性質に依存します。
自分が取り組むタスクの種類を意識し、適切に休憩を挟むことが集中を持続させる鍵となります。
参照
: 日本教育心理学会「授業中の注意持続について」
: 東京大学大学院「集中力と作業効率に関する研究」
関連記事:集中力を回復する方法を紹介|仕事や勉強の生産性を上げる休憩とは
集中力が続かない原因
「集中しようと思ってもすぐ気が散ってしまう」という経験は誰にでもあります。
集中力が続かないのは性格や意志の弱さではなく、生活習慣や環境、心理的な要因が影響しています。
ここでは代表的な3つの原因を紹介します。
睡眠不足や生活リズム
睡眠は脳の働きを回復させる最も基本的な要素です。睡眠が不足すると前頭前野の機能が低下し、集中力や判断力が著しく下がります。
また、生活リズムの乱れも体内時計を狂わせ、集中が必要な時間に脳が覚醒できなくなります。
- 睡眠時間が6時間未満
- 夜更かしや休日の寝だめでリズムが乱れる
- 就寝前のスマホやPCによるブルーライト刺激
規則正しい睡眠を心がけることで、集中力は大幅に改善します。
ストレス・不安
強いストレスや不安は、脳が常に危険に備えようとするため注意が分散し、集中力が続かなくなります。
特に交感神経が優位になると、心拍数が上昇し、頭の中で余計な考えが浮かびやすくなります。
- 職場や人間関係でのプレッシャー
- 将来や成果に対する不安
- 完璧主義による過度な緊張
深呼吸や瞑想、適度な運動は自律神経を整え、集中状態を取り戻すのに効果的です。
環境要因(雑音・人の気配)
集中力は環境に大きく左右されます。静かな場所であれば集中しやすい一方、人の話し声や動きがあると無意識に注意が奪われます。
また、視界に人が入るだけでも気が散ることがあります。
- オフィスやカフェでの雑音
- 近くにいる人の気配や視線
- 散らかったデスクや部屋
耳栓やノイズキャンセリングイヤホン、仕切りの設置など物理的に環境を整えることで、集中しやすさは格段に上がります。
関連記事 : 実際に試してわかった集中力UPグッズ|勉強・在宅ワーク・ADHD対応まで
集中力を長く維持する方法

集中力は放っておくと短時間で途切れてしまいますが、正しい方法を取り入れれば長く維持することが可能です。
ここでは、科学的に効果が実証されている代表的な方法を4つ紹介します。すぐに取り入れられる習慣が多いため、日常の仕事や勉強に活かせます。
ポモドーロ・テクニック
ポモドーロ・テクニックとは、「25分間集中+5分休憩」を1サイクルとし、4サイクルごとに15〜30分の休憩を取る方法です。短時間で区切ることで脳の疲労を防ぎ、集中力が回復しやすくなります。
特に単純作業や学習に効果的で、タスク管理のしやすさから多くの研究者や企業でも推奨されています。
- 25分は「一つのタスクだけ」に集中する
- 休憩中はスマホを見ず、軽く体を動かす
- 4セットごとに長めの休憩を入れる
関連記事 : 集中力を上げる具体的な方法11選!集中できない理由と効率よく高めるアプローチ
休憩・仮眠・運動
集中力を維持するには、適度な休憩を取り入れることが欠かせません。特に、20分程度の仮眠は「パワーナップ」と呼ばれ、脳をリフレッシュする効果が高いとされています。
また、短時間の運動やストレッチも血流を改善し、脳への酸素供給を増やすため集中力が戻りやすくなります。
- 1時間に5〜10分の休憩を挟む
- 15〜20分の仮眠で眠気を軽減
- 軽いストレッチや散歩で気分転換
カフェイン・水分補給
カフェインは脳内のアデノシン受容体をブロックし、眠気を防いで集中力を高めます。特にコーヒー1杯(約100mgのカフェイン)が適量とされ、過剰摂取は逆効果になるので注意が必要です。
また、水分不足も脳の働きを鈍らせるため、こまめな水分補給が欠かせません。
- コーヒーや緑茶を午前中〜午後早めに飲む
- 200ml程度を数回に分けて水分補給
- 夜遅くのカフェイン摂取は避ける
食事・栄養
食事の内容も集中力の持続に直結します。
脳のエネルギー源はブドウ糖ですが、血糖値が急激に上下すると眠気や集中力低下を招きます。
そのため、GI値の低い食品やバランスの取れた栄養が推奨されます。特に魚のDHA・EPA、ナッツ類のビタミンEは脳機能の維持に効果的です。
- 玄米や全粒パンなど低GI食品
- 魚(サバ・イワシ)に含まれるDHA・EPA
- ナッツやチョコレート(ポリフェノール)
関連記事 : 【集中力を高める食べ物】即効&持続に効く13選|試験・仕事・子ども向けに紹介
集中力に関するよくある悩み
▼集中できず、勉強や仕事がなかなかはかどらない——。
それは意思や根性ではなく、脳の使い方が原因かもしれません。
まずは無料動画で、要点を捉えて整理し、思い出しやすくする基本の流れを確認。
理解のムダが減り、集中しやすい状態を無理なく実感できます。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
さらに集中が続く時間を伸ばす方法①「没頭」

あなたは、時間を忘れてゲームや漫画に集中したことがありませんか?
それこそが「没頭」と呼ばれる状態です。
ここではさらに高い次元の集中をつくりだす「没頭」の仕組みや、方法を紹介していきます。
没頭(フロー体験)とは
没頭とは、米国心理学者のミハイ・チクセントミハイが命名した心理学用語で、時間や自我を忘れて一つのことに夢中になる状態のことを指し、フロー体験とも呼ばれています。
アスリートが我を忘れて集中する「ゾーンに入った」状態も、没頭状態のことを指しています。
しかし、没頭はアスリートのような特別な人にしか起こらないわけではありません。
例えば、締切に追われ他事を一切考えず仕事に集中していると、気付けばもう終業時間だったという経験も、仕事に没頭している状態だといえます。
参照:フロー体験(没頭)とは?フロー体験を促進するには? | Well-Being 青山学院大学 研究プロジェクト
没頭により得られる効果
ハーバード大学の心理学者マシュー A. キリングスワースとダニエル T. ギルバートが行った調査では、人間は今やっていることと他のことを考えていると不幸せになるという結論に至っています。
つまり、没頭により一つのことに夢中になっている状態は、作業効率が上がるだけでなく幸福度も上がるということです。
ゲームや漫画に夢中になっている間、あなたは今の状態を不幸だと感じるでしょうか?
おそらく、得も言われぬ興奮と満足感に満たされているはずです。
一つの物事に没頭している状態はマインドフルネスの状態ともいえるので、ストレスから解放されて幸福度が上がるのです。
 キツネさん
キツネさん
没頭状態を作り出すには
没頭は偶発的なものではなく、下記に示す一定の条件を満たせば誰でも促すことができます。
- 自分が行うことを理解していること
- 自分の意思によって即時実行できること
- 成果がすぐにわかること
- 自分の能力に見合った難易度であること
- 今から行うことが好きである、または意義を見出していること
- 注意散漫になる原因は取り除くこと
取り組むことが自分のスキルに見合った難易度であれば、行動を理解しているので、自分の意思で思うように事を運ぶことも可能でしょう。
そもそも、難易度が高すぎても低すぎても面白いと思えないので没頭できません。
また、外的な要因で集中力が途切れないようにスマホの通知はオフにしておくことをオススメします。
さらに集中が続く時間を伸ばす方法②「心理的安全性」

長時間集中できる環境には「心理的安全性」が保たれていることが大切だといわれています。
心理的安全性は比較的新しい言葉ですが、集中力を維持する環境づくりには非常に重要な考え方です。
注目を集めている「心理的安全性」
「心理的安全性」は、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授により提唱された言葉で、米Google社もチームの構築に重要な因子として取り入れています。
自分が思うように発言や行動をしても他者から責められる不安のない状態を「心理的安全性」が保たれていると表現します。
つまり、なにも恐れることなく自由に考え、行動できる状態のことです。
 キツネさん
キツネさん
心理的安全性が集中力を上げる理由
心理的安全性が保たれていると脳の前頭前野が活性化されます。
前頭前野は集中力や感情に関わるので、心理的安全性が保たれた状態だと集中力が上がりやすくなります。
また、他人におびえることなく自由に発言や行動ができるので、ストレスを感じないため注意散漫になりません。
注意散漫にならないということは没頭状態にも入りやすくなり、より高い集中力を長い時間維持できるようになります。
心理的安全性を保つには
心理的安全性の大敵はストレスですので、日頃からストレスを溜め込まないように意識することが大切です。
もし、ストレスを感じたら趣味に興じてみたり、人に会ってみるなどしてストレスを解消しましょう。
ストレスは早期発見、早期発散が原則です。
また、チームであれば、お互いが多様性を認め、遠慮なく協力を求められる関係性の構築が大切です。
 キツネさん
キツネさん
集中力の持続に関するよくある質問
集中力については「年齢で変わるのか?」「カフェインは本当に効果があるのか?」など、多くの疑問が寄せられます。
ここでは特によくある4つの質問に答えていきます。
集中力は年齢で変わる?
集中力は年齢によって変化します。一般的に、若年層は短時間に高い集中力を発揮できますが、持続時間は短めです。
一方、中高年は短期的な集中力は下がるものの、長時間にわたる粘り強い集中が可能になるといわれています。
年齢と集中力の特徴
- 10〜20代:瞬発力は高いが持続は短い
- 30〜40代:集中の質が安定し、持続も伸びやすい
- 50代以降:短期集中は低下するが、経験値により補える
このように年齢で傾向はありますが、生活習慣や脳トレーニングによって改善は十分可能です。
カフェインで本当に集中力は上がる?
カフェインには覚醒作用があり、短期的に集中力を高める効果が科学的に確認されています。
適量の摂取であれば作業効率や注意力が改善されますが、過剰摂取は不安感や不眠を招くため注意が必要です。
効果的な摂取の目安
- 1回あたり100mg程度(コーヒー1杯)
- 1日400mgまでが安全とされる(個人差あり)
- 午後遅い時間の摂取は避ける
つまり、カフェインは「正しく使えば集中力をサポートするツール」といえます。
集中力を鍛えることはできる?
集中力は訓練によって高めることが可能です。脳は可塑性を持ち、習慣やトレーニングによって集中の持続力が改善されることが研究で示されています。
特に瞑想やマインドフルネスは、集中力強化に有効とされています。
効果的なトレーニング例
- 毎日5分のマインドフルネス瞑想
- 読書や暗記学習で「集中を続ける練習」
- タイマーを使ったポモドーロ法の習慣化
継続的に行うことで、集中できる時間は少しずつ伸びていきます。
一日の集中できる時間の上限は?
研究では、成人が1日に「深い集中」を維持できるのは合計で約4〜6時間程度といわれています。
残りの時間は軽い作業やルーチン業務にあてるのが効率的です。
集中時間の目安
- 1回の集中:45〜90分
- 深い集中の合計:4〜6時間/日
- 軽作業:それ以上可能
つまり「1日中集中する」のは不可能であり、限られた集中時間を重要なタスクに充てることが最も効果的な働き方です。
まとめ|科学的根拠を活かして集中力を伸ばそう

集中力は「15分〜90分サイクル」などの研究データや、睡眠・ストレス・環境といった要因によって大きく左右されます。
しかし、休憩の取り方やポモドーロ・テクニック、食事や栄養管理など、科学的に効果が認められた方法を取り入れることで、集中力を長く維持することは可能です。
さらに、没頭状態(フロー)や心理的安全性を意識することで、より高いパフォーマンスを引き出せます。
もし「自分一人では集中を鍛えにくい」と感じるなら、記憶術を応用したトレーニングも有効です。正しい方法で脳を鍛え、集中力を武器にして、学びや仕事の成果を最大化していきましょう。
Wonder Educationでは、誰でも記憶力を高められる記憶術講座を提供しています。再現性の高い指導で、記憶力向上とそれによる目的の達成をサポートしていますので、ご興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせください。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。