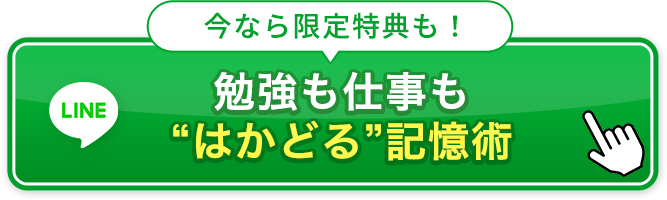キツネさん
キツネさん
つい眠気やだるさに負けてしまい、勉強や仕事が思うように進まないことは誰にでもあります。
本記事では、集中できる飲み物の効果や種類、時間帯ごとの活用法を詳しく解説します。
勉強や受験に励む学生、仕事の生産性を高めたい社会人におすすめです。
読むことで、自分に合った飲み物を選び、集中力を最大限に引き出す習慣を身につけられます。
もくじ
飲み物が集中力アップにつながる理由

「何を飲むか」も大切ですが、そもそも仕事中に休憩時間をとって「何かを飲む行為」そのものが大切です。
特にオフィスワーカーは座り仕事が多くなります。厚生労働省も作業1時間以内に10~15分の休憩をはさむことを推奨しています。
参照:VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて|厚生労働省
飲み物休憩は、次に挙げるようなメリットがあります。
- 水分を摂取できる
- エネルギーや有効成分を補給できる
- 自分へのご褒美になる
それぞれ見ていきましょう。
① 水分を摂取できる
私たちが仕事や勉強をするとき、水分不足の状態では本来のパフォーマンスが発揮できません。
学術誌『Frontiers in Human Neuroscience』(Frontiers Media発行)の研究によると、知的作業を行う前に約500mlの水を飲んだ人は、飲まなかった人に比べ反応時間が14%早くなっていました。
つまり今から集中するぞ、という時は水を飲んでから作業を開始したほうが効率が上がるのです。
作業前の水 : 水を飲んだグループは反応時間が平均14%短縮
また、水分を適切に摂取することでいわゆる「エコノミークラス症候群(静脈血栓症)」のリスクを予防できます。
東京大学の武藤氏の研究によると、1時間あたり80~120mlの水分摂取が必要と述べられています。
参照:健康を支える水
海外旅行に行くわけではありませんが、1時間作業をしたらコップ1杯の水を飲んで休憩しましょう。
 キツネさん
キツネさん
適切な水分摂取は、効率アップだけでなく健康面にも良いんですね。
② エネルギーや有効成分を補給できる
人の脳は体重の2%ほどの重さですが、エネルギー消費量は体全体の30%ほどを占めています。
つまり脳は高いエネルギーを必要とする器官です。
そんな脳は、糖の最終分解産物である「ブドウ糖」をエネルギー源としています。
ウエールズのSwansea大学教授のDavid Benton氏の研究によって、ブドウ糖を摂取した人は、記憶力や文章理解力が一時的に向上する傾向が報告されています。
ついカロリーが気になって糖分を避けてしまいがちですが、甘い飲み物にも良い面があるということです。
ちなみに糖分をエネルギーに変えるには、ビタミンB群が必要となり、海苔や肉・魚類などに多く含まれています。
- 脳はブドウ糖をエネルギー源にしている
- ビタミンB群を摂取することで、体内でブドウ糖を効率よくエネルギーに変換できる
- 海苔、鶏肉、豚肉、魚類、ゴマなどにビタミンB群が多く含まれている
③ 自分へのご褒美になる
仕事や勉強をすることは、必ずしも楽しくてワクワクするものばかりではありません。
ご褒美として飲み物を用意しておくことで、モチベーション維持につながります。
そうすることで、最後のもうひと頑張りができるはずです。
集中力を上げる飲み物【勉強・仕事・受験対応】

集中力を上げる飲み物とは、具体的にどんなものがあるのでしょうか。
ここでは定番からちょっと意外なものまで、8種類の飲み物について解説します。
- 緑茶・紅茶|L-テアニンがストレスを低減
- コーヒー|カフェインで覚醒し瞬時に集中力を高める
- ココア|テオブロミンで血流を促進して脳を活性化
- 炭酸水|適度な刺激&糖分対策に
- クエン酸飲料|疲労回復+エネルギー補給に
- 栄養ドリンク|効率的にエネルギーを補給
- 味噌汁|小腹が空いたときにも
- 水|脳の働きを保ち集中力低下を防ぐ基本飲料
それぞれのメリットをふまえて、あなたにとってモチベーションが上がる飲み物を選んでみてください。
① 緑茶・紅茶|L-テアニンがストレスを低減
日本人にとって「一息つく」といえば温かいお茶を思い浮かべる人が多いでしょう。この「ホッとする」感覚には科学的な裏付けがあると報告されています。
太陽化学株式会社の行った実験によって、「L-テアニン」という成分がリラックス効果をもたらしてくれることがわかっています。
実験では、L-テアニンを摂取後40分でリラックス状態を示すα波が増加したと報告されています。
水のみ摂取したグループと比べて平均1.2倍、条件によっては2倍以上に達した事例もありました。
参考:テアニンの学術データ | 健康を支える研究と技術 | 食と健康Lab
② コーヒー|勉強・仕事の王道。試験前は必須
もう一つの定番がコーヒーです。コーヒーに含まれるカフェインには集中を助ける作用があると広く知られています。
カフェインは摂取後約30分で血中濃度が上昇し、脳に作用するとされています。
仕事や勉強を始める30分ほど前にコーヒーを飲んでおけば、覚醒作用によって仕事の集中力が高まります。
注意点としては、過剰に摂りすぎないということです。厚生労働省では、健康な成人はカフェイン摂取を1日約400mg(コーヒーで2〜3杯程度)までと注意喚起しています。
不眠症や頭痛、イライラ感を引き起こす恐れがあるので、過剰摂取に注意しましょう。
- 過剰摂取は不眠症・頭痛などをもたらす。
- 健康な成人で1日マグカップ2〜3杯まで。
参考:食品に含まれるカフェインの過剰摂取について|厚生労働省
③ ココア|テオブロミンで血流を促進
コーヒーのカフェインは有名ですが、ココアの「テオブロミン」はあまり知られていません。
テオブロミンには血流促進作用が報告されており、体温上昇に寄与する可能性があります。
滋賀県立大学の灘本知憲氏指導のもと行われた研究では、18~24歳の女子学生にココア・同じ成分の飲料・水の3種類の飲料を飲んでもらい、体温の変化を調べています。
その結果、ココアを飲んだ女性には手首、足首、足指先に体温上昇傾向が見られました。
冬場の足先の冷えはつらいものです。ココアを飲むことで、デスクワークで冷えた指先を温めることができます。
 キツネさん
キツネさん
ココアは女性にとっても飲みやすいですし、体も温まるなんてうれしいですね。
④ 炭酸水|適度な刺激&糖分対策に
甘い飲み物は苦手で…という人には炭酸水がおすすめです。
炭酸水は無糖のものを選べば糖分を含まないため、糖分を摂り過ぎてしまう心配がありません。
また、会社の雰囲気によっては「仕事中に炭酸ジュースかよ…」といった目で見られるかもしれません。
しかし色のついたジュースではなく無味無色の炭酸水なら、炭酸の刺激で気分をリフレッシュしつつ、糖分摂取や周囲の目を気にせず楽しめます。
まとめ買いをすればコストも低く抑えられるのでおすすめです。
⑤ クエン酸飲料|疲労回復+エネルギー補給に
クエン酸飲料は疲労感の軽減やエネルギー代謝を助ける効果が期待できます。
クエン酸はエネルギー代謝に関わる成分で、柑橘系フルーツに多く含まれているのです。
例えばオレンジジュースなどは手軽に購入できますし、果糖も含まれているため即効性のあるエネルギー源となります。
注意点として、甘いジュースには過剰な糖分が含まれていることが多くあります。
最近では「無糖 キレートレモン」(ポッカサッポロ)など、無糖のクエン酸飲料も発売されていますので、適切に選んで飲むと良いでしょう。
- ジュースによっては糖分が多く入っている可能性あり
- 気になる場合は無糖のクエン酸飲料を選ぶ
⑥ 栄養ドリンク|効率的にエネルギーを補給
仕事中にゆっくりする時間が取れない場合は、栄養ドリンクを飲んでみてはいかがでしょうか。
リポビタンD(大正製薬)などが有名ですね。
このような栄養ドリンクには「タウリン」と呼ばれるアミノ酸の一種が多く含まれています。
タウリンの摂取は筋肉の疲労軽減や保護作用に寄与する可能性が報告されています。
また、カフェインも含まれることが多いので覚醒作用も期待できます。
デスクワークだけでなく、外回りの多い営業職や力仕事が多い場合は、栄養ドリンクを飲むことで
 キツネさん
キツネさん
コンビニでも入手しやすいですし、まさに効率的な飲み物と言えますね。
⑦ 味噌汁|小腹が空いたときにも
意外にも味噌汁は休憩時の飲み物として取り入れやすい選択肢です。
特に空腹で集中できないというときはお腹が満たされますし、発酵食品なので整腸作用もあります。
しっかり食事をとったら眠くなってしまい集中力が下がった、という経験は誰しも一度はありますよね。
集中力を維持するには、小腹を満たす軽食の代わりに味噌汁を活用するのも有効です。
- 飲み過ぎると高血圧などのリスクが伴う
- 塩分摂取が気になる人は、減塩味噌汁を選ぶ
⑧ 水|脳の働きを保ち集中力低下を防ぐ基本飲料
水は人間の体の約60%を占める基本的な成分であり、脳の働きを保つために欠かせません。
体内の水分が不足すると血流が悪くなり、酸素や栄養が脳に行き届きにくくなります。その結果、集中力の低下や頭の回転の鈍さにつながるのです。
特に仕事や勉強の合間に水分を摂ることで、脳のパフォーマンスを安定させることができます。
甘い飲み物やカフェインに頼る前に、まずは常温の水をこまめに飲むことが効果的です。
日中に1.5〜2リットルを目安に摂取すれば、脱水による疲労感を防ぎ、長時間の作業でも集中力を維持できるでしょう。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
集中力に関するよくある悩み
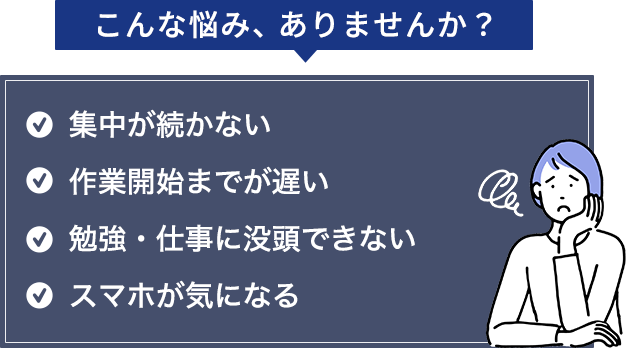 ▼
▼集中できず、勉強や仕事がなかなかはかどらない——。
それは意思や根性ではなく、脳の使い方が原因かもしれません。
まずは無料動画で、要点を捉えて整理し、思い出しやすくする基本の流れを確認。
理解のムダが減り、集中しやすい状態を無理なく実感できます。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
集中力アップに役立つ飲み物の選び方

集中力アップに役立つ飲み物の選び方は、成分や飲むタイミングを意識することで効果が大きく変わります。
- カフェインやテアニンなどの含有量を確認する
- 必要な水分量を把握してこまめに分けて飲む
- 甘さやカロリーを適度に抑える
- 飲む温度を季節や体調で調整する
- 飲む時間帯に合った種類を選ぶ
それぞれ順番に解説します。
カフェインやテアニンなどの含有量を確認する
集中力を高めるためには、カフェインやテアニンといった成分を意識して選ぶことが重要です。
カフェインには眠気を抑えて脳を覚醒させる働きがありますが、摂りすぎると緊張や不安を引き起こしやすいため注意が必要です。
厚生労働省によれば、成人におけるカフェイン摂取の目安は1日400mg未満とされ、コーヒーで換算すると4~5杯ほどです。
一方でテアニンはリラックス効果を持ち、カフェインと組み合わせることで覚醒と鎮静のバランスを保ち集中を持続させやすくします。
このように、緑茶や玉露など自然に両成分を含む飲み物を選ぶことは、無理のない集中状態を作るための賢い方法といえるでしょう。
参考:テアニンとは?9つの効果・効能や知っていると得する摂取方法を紹介!|NATURALTECH
必要な水分量を把握してこまめに分けて飲む
集中力を維持するためには、体内の水分バランスを安定させることが欠かせません。
脱水状態になると脳のパフォーマンスは低下し、思考力や記憶力が鈍って集中が続きにくくなります。
そのため一度に大量に飲むのではなく、こまめに分けて補給することが効果的です。
目安としては1日あたり体重×30ml程度の水分が推奨され、成人ではおよそ2.5L~3.5Lが目安となります。
仕事や勉強中は500mlのボトルを手元に置いて定期的に口にするのがおすすめです。
つまり、水分補給を習慣化することは、集中力を支える土台を整えるシンプルで確実な方法といえます。
甘さやカロリーを適度に抑える
飲み物を選ぶ際に糖分やカロリーを気にかけることは、集中力を持続させる上で非常に有効です。
糖分を多く含む飲料は一時的に脳を活性化させますが、その後急激に血糖値が下がり、眠気や倦怠感を引き起こすことがあります。
そのため、清涼飲料水やエナジードリンクの飲みすぎは作業効率を下げかねません。
一方で無糖のお茶やブラックコーヒー、または砂糖を控えた飲み方を選べば、血糖値の急変動を避けながら集中を維持できます。
つまり、カロリーを抑えた飲み物を意識的に選ぶことは、安定した作業リズムをつくる重要な工夫となるのです。
飲む温度を季節や体調で調整する
飲み物の温度は体の状態や集中力に大きな影響を与えるため、季節や体調に合わせて調整することが大切です。
冷たい飲み物は眠気を覚ます効果があり、夏場や頭をすっきりさせたいときに役立ちます。
一方で温かい飲み物はリラックスを促し、自律神経を整えて落ち着いた集中を生み出しやすくなります。
体が冷えている時に冷たい飲み物を摂ると逆効果になるため、状況に応じて適切な温度を選ぶことが望ましいです。
このように温度を意識して飲み物を選ぶことは、集中力を最大限に発揮するための簡単で効果的な方法になります。
飲む時間帯に合った種類を選ぶ
飲み物は時間帯ごとに適した種類を選ぶことで、集中力を効率的にコントロールできます。
朝や午前中はカフェインを含むコーヒーや紅茶が眠気を抑え、スムーズに作業へ入る手助けをしてくれます。
午後以降はカフェインの摂りすぎが夜の睡眠に悪影響を与える可能性があるため、ハーブティーやノンカフェイン飲料に切り替えるのが効果的です。
また重要な作業前にはリラックスと覚醒のバランスをとれる緑茶を取り入れるのもおすすめです。
つまり、時間帯に応じた飲み物の選び分けは、1日のパフォーマンスを安定させるのに役立ちます。
時間帯別の集中できる飲み物|朝〜夜

集中力を高める飲み物は、時間帯に応じて適切に選ぶことで効果が最大化されます。
- 朝:コーヒーや緑茶で集中力のスイッチを入れる
- 午後:水やクエン酸飲料で水分と活力を補給
- 夕方以降:ほうじ茶やココアなど穏やか系で集中継続
- 夜:カフェイン控えめ温かい飲み物で脳を休める
それぞれ順番に解説します。
朝:コーヒーや緑茶で集中力のスイッチを入れる
朝は1日の始まりであり、眠気を覚まして脳を活性化することが重要です。
この時間にコーヒーや緑茶を取り入れると、カフェインの覚醒作用が働き集中スイッチが入りやすくなります。
また緑茶に含まれるテアニンはリラックス作用もあるため、過度な緊張を和らげつつ作業効率を高められます。
ただしカフェインの過剰摂取は体調悪化や逆に集中力低下の原因となるため適量を飲みましょう。
このように朝の一杯は、脳を自然に活動モードへと導く効果的な習慣となります。
午後:水やクエン酸飲料で水分と活力を補給
午後は体内の水分が不足しやすく、集中力が途切れる原因となりやすい時間帯です。
そのため、こまめに水を飲むことで血流が促され脳への酸素供給がスムーズになります。
さらにクエン酸飲料を取り入れると、疲労物質である乳酸の分解を助け活力回復に役立ちます。
特に昼食後は眠気が出やすいため、刺激を与えすぎず体をリフレッシュする飲み物が適しています。
つまり午後は、脳と体をリセットする意味で水分とクエン酸の補給が効果的といえるのです。
夕方以降:ほうじ茶やココアなど穏やか系で集中継続
夕方は一日の疲労が蓄積し、強い刺激よりも心を落ち着かせる飲み物が有効です。
ほうじ茶はカフェインが少なく香ばしい香りがリラックスを促すため、緊張を和らげながら集中を続けられます。
またココアに含まれるテオブロミンは、カフェインよりも穏やかに覚醒を促し気分を前向きにしてくれます。
疲労回復と集中継続の両立が可能なため、夕方以降の作業や勉強には理想的な飲み物といえるでしょう。
このように落ち着きを与える飲み物を選ぶことは、夜に向けて集中を維持するカギとなります。
夜:カフェイン控えめ温かい飲み物で脳を休める
夜は睡眠に備えて脳を休めることが大切であり、カフェインを含まない飲み物を選ぶ必要があります。
カモミールティーやルイボスティーなどノンカフェインの温かい飲み物は、リラックス効果が高く副交感神経を優位にします。
これにより心身が休まり、翌日の集中力を高める準備が整いやすくなるのです。
また温かい飲み物は体温を上げて寝つきを良くする効果も期待できます。
つまり夜は、脳と体を休ませるために刺激の少ない温かい飲み物を選ぶことが重要といえるでしょう。
コンビニで買える集中できる飲み物

コンビニには、短時間で集中力を高めたいときに役立つ飲み物が豊富に揃っています。
- エナジードリンクのメリット・デメリット
- 太らない低カロリー系
それぞれ順番に解説します。
エナジードリンクのメリット・デメリット
エナジードリンクは眠気を抑えて、短時間で集中したいときに役立つ飲み物です。
カフェインやアルギニン、ビタミンB群が含まれており、脳を刺激して覚醒状態に導きやすくなります。
ただし糖分やカフェインの摂りすぎは健康リスクにつながるため、量やタイミングを意識して飲むことが大切です。
- 即効性があり短時間で集中力を高めやすい
- ビタミン類が代謝を助け疲労感を軽減する
- 手軽に購入できて種類も豊富に選べる
- カフェイン過剰摂取で不眠や動悸を起こす可能性がある
- 糖分が多く太りやすさや血糖値の乱高下を招く
- 習慣化すると依存的になり効果が薄れる恐れがある
また、エナジードリンクと栄養ドリンクが集中力に与える影響は、それぞれ次のような違いがあります。
- エナジードリンクは「瞬発的に集中したいとき」に有効
- 栄養ドリンクはタウリンやビタミン類が中心で「疲労回復や体の基盤を整えたいとき」に適している。
このように両者には役割の違いがあるため、目的に合わせて選ぶことで集中力と健康の両立が可能になるのです。
太らない低カロリー系
集中力を保ちながらカロリーを抑えたい方には、低カロリー系の飲み物が適しています。
- 南アルプスの天然水 スパークリング(サントリー)
- ウィルキンソン タンサン(アサヒ)
- 伊右衛門 特茶(サントリー)
- 十六茶W(アサヒ)
- ポカリスエット イオンウォーター(大塚製薬)
- アクエリアス ゼロ(コカ・コーラ)
このように、無糖炭酸水や特保系飲料、カロリー控えめのスポーツドリンクを選ぶことで、集中力を維持しながら体への負担を抑えることができます。
集中できる飲み物に関するよくある質問
集中できる飲み物に関するよくある質問を解説します。
夜にコーヒーを飲んで眠れないことはない?
夜にコーヒーなどのカフェイン入りの飲み物を飲むと眠れなくなる可能性があります。
カフェインは摂取後4〜6時間ほど覚醒作用が持続するため、就寝前は控えるのが賢明です。
そのため夜はカフェインレスのハーブティーやほうじ茶などを選ぶと安心できます。
勉強中の水分摂取量は?
勉強中は1時間あたりコップ1杯程度を目安に水分をとることが理想です。
水分不足は集中力や思考力を下げるため、のどが渇く前に少しずつ飲むことが大切です。
つまり勉強中は「こまめに分けて飲む」ことが最も効果的な水分補給法といえるでしょう。
集中を妨げる飲み物は?
砂糖が多く含まれる清涼飲料やアルコールは集中を妨げやすい飲み物です。
糖分過多は血糖値の乱高下を起こし、眠気やだるさを招くリスクがあります。
つまり集中したい場面では、糖分控えめで水分補給もできる飲み物を選ぶことが重要です。
まとめ|今日から始める集中力を高める飲み物の習慣
本記事では、集中できる飲み物の効果と選び方、そして時間帯別の活用法について解説しました。
飲み物はただの水分補給にとどまらず、成分や飲み方を工夫することで集中力を大きく左右します。
さらに、自分に合った飲み物をシーンごとに選ぶことで、仕事や勉強の効率を確実に高められるのです。
今日から意識的に飲み物を選び、集中力を最大化する習慣を取り入れてみましょう。
「もっと記憶力を高めて勉強や仕事に活かしたい」という方には、「吉永式記憶術」もおすすめ。科学的根拠に基づいた実践的なトレーニング法で、初心者でも無理なく取り組めます。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い指導を通じて記憶力向上と目標達成をサポートしています。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。