 キツネさん
キツネさん
会社や学校、式典の場面などでスピーチを求められる機会は意外と多いですよね。
スピーチを任されると「うまく話せなかったらどうしよう」と不安になる人も多いでしょう。
この記事では、スピーチに苦手意識がある方に向けて、暗記のコツや効果的な練習方法を紹介します。
この記事で紹介する方法はスピーチだけでなく、プレゼンにも応用できますので、ぜひ参考にしてみてください。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
スピーチを「全文暗記」する必要はない
スピーチを行う際、全文を暗記する必要はありません。
むしろ丸暗記は不自然な話し方になりやすく、少し間違えると動揺してしまう原因にもなります。
重要なのは、話す内容の構成や要点をしっかり把握し、自分の言葉で伝えることです。
キーワードや流れをメモで確認できれば、自然な口調で話しやすくなります。
また、聞き手との目線やリアクションにも意識を向けられるため、より説得力のあるスピーチになります。
今回紹介するコツを参考に、より効率的なスピーチの覚え方を習得してみてください。
スピーチを丸暗記するデメリット
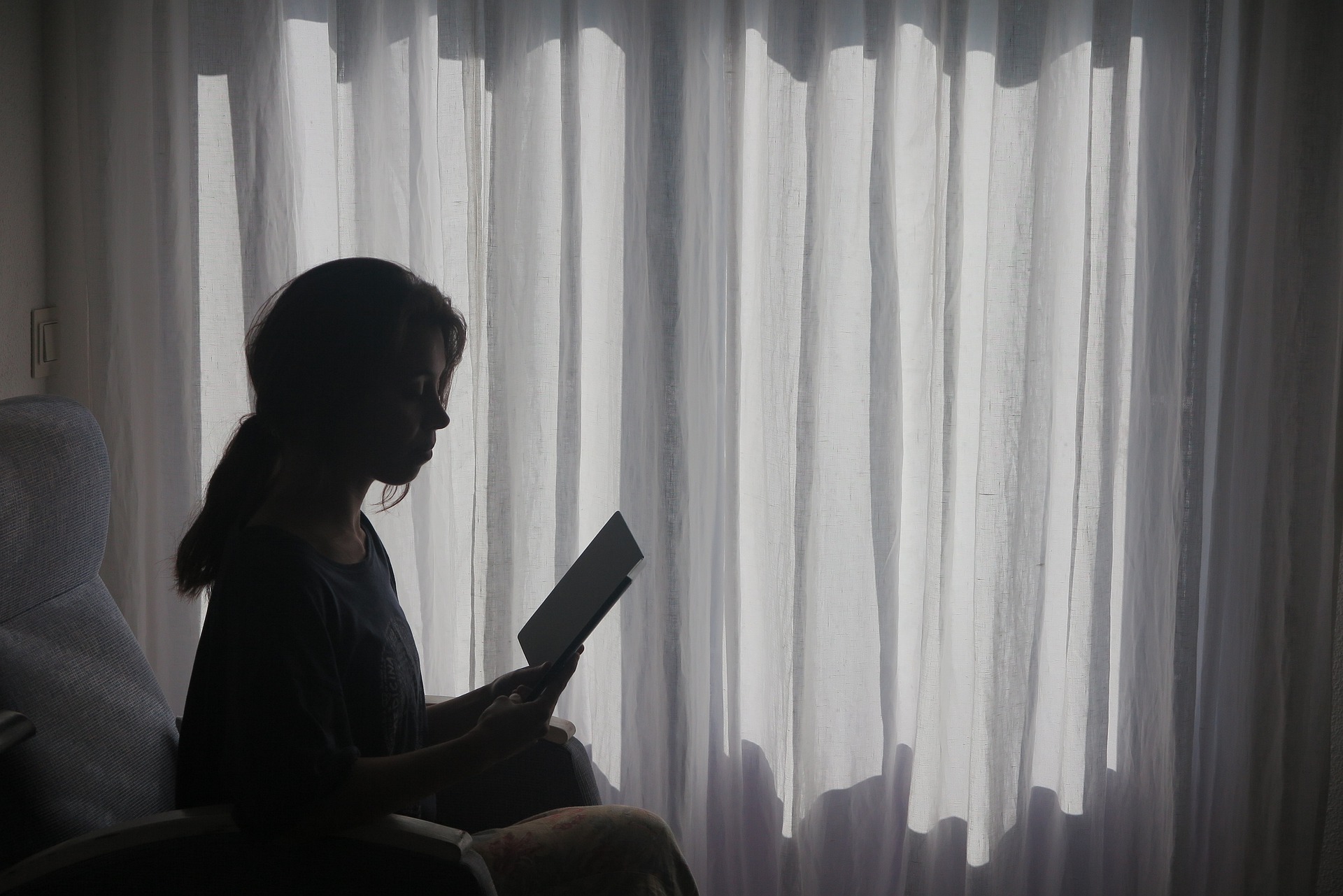
スピーチをすべて暗記して話す方法は、一見安心に思えるかもしれません。
しかし実際には、多くのリスクやデメリットが伴います。
スピーチを丸暗記することによる主なデメリットは以下の通りです。
- 一部を忘れると言葉に詰まる
- 棒読みのように聞こえる
- ハプニングに対応できない
それぞれ順番に解説します。
一部を忘れると言葉に詰まる
丸暗記していると、ひとつの言葉を忘れただけで、次に何を話すべきか分からなくなってしまいます。
「忘れてしまった」「話す順番を間違えた」となれば、頭が真っ白になり、その場で立ち尽くしてしまうこともあるでしょう。
丸暗記による過度な緊張は、本来伝えたい内容の質を下げてしまう要因にもなり得ます。
そのため、話の流れや要点をつかみながら練習することが重要です。
棒読みのように聞こえる
丸暗記してスピーチに臨むと「暗記した文章をそのまま再現する」だけになり、聴き手からすると棒読みのように聞こえてしまう可能性があります。
内容が優れていても、読み上げている印象を与えてしまうと、聴き手は機械的な印象を受けてしまいます。
こうした丸暗記による読み上げを避け「生きた言葉」として話すことで感情がこもることで、聴き手の心にも響きやすくなります。
ハプニングに対応できない
スピーチ本番には、思いがけないハプニングが起こるかもしれません。
- 開始が遅れて、スピーチの時間が短縮された
- 途中で緊急連絡が入り、一時中断になった
- 次のプログラムが遅れ、時間の尺が長くなった
こうした状況に遭遇した場合「話の長さを調整する」などの臨機応変な対応が求められます。
丸暗記していると「話を短縮したり、延長する」といった、急なハプニングに対する調整が難しくなります。
暗記できるスピーチ作りのコツ4選

スピーチを暗記する際に重要なのは、「内容の覚えやすさ」と「話の流れの自然さ」です。
無理に暗記しようとするよりも、伝えたいことを整理し、自然な構成に仕上げることで記憶しやすくなります。
- 伝えたい内容と話の流れを整理する
- 1トピックに1つの話題を心がける
- エピソードを盛り込む
- 結論から先に伝える構成にする
それぞれ順番に解説します。
伝えたい内容と話の流れを整理する
まず、スピーチで何を伝えたいのかを明確にすることが出発点です。
テーマが曖昧なままだと、自分でも話の流れを把握しづらくなります。
「導入・本題・結論」の三部構成を意識すれば、頭の中も整理しやすくなるでしょう。
話の全体像がイメージできるようになると、記憶にも自然と定着しやすくなります。
1トピックに1つの話題を心がける
スピーチの内容を考えるとき、多くの情報を盛り込みたくなることもあるでしょう。
しかし、1トピックの中で複数の話題に手をつけようとすると「次は何だったか」と考えてしまい、丸暗記に頼る傾向が強くなります。
そこで「1トピックにつき1つの話題」を心がけてみましょう。
- 自己紹介では複数の趣味を挙げるのではなく、1つの趣味に絞って深掘りする
- 多くの事例を広く紹介するよりも、1つの具体例を詳しく伝える
1つのことを掘り下げて話す方が新たに覚える負担が減り、話す際も自分の言葉で説明しやすくなります。
エピソードを盛り込む
自分が経験したことは、既に記憶として頭に残っているため、新たに覚える必要がありません。
そうした過去のエピソードを話題に盛り込むことで、自然と覚えることができます。
また、自身の経験に基づく話は説得力が生まれ、聴き手の心に残りやすくなる効果もあります。
結論をはっきりさせる
最初に、スピーチの目的や伝えたい結論を明確にしておくことが重要です。
ゴールが明確であれば、そこに至るまでに一つ一つの話題が「なぜ必要なのか」という意識も明確になります。
一つ一つの話題、そしてスピーチの結論が明確だと、話す内容を思い出しやすくなるうえ、聴き手にも伝わりやすくなります。
この記事ではスピーチづくりの3つのコツに絞ってお伝えしましたが、話し方のポイントやコツは、以下の記事でくわしくまとめられています。
 キツネさん
キツネさん
スピーチだけでなく、演説やセミナー、プレゼンでも役に立つ実用的な情報ですね!
スピーチの覚え方・記憶力に関するよくある悩み
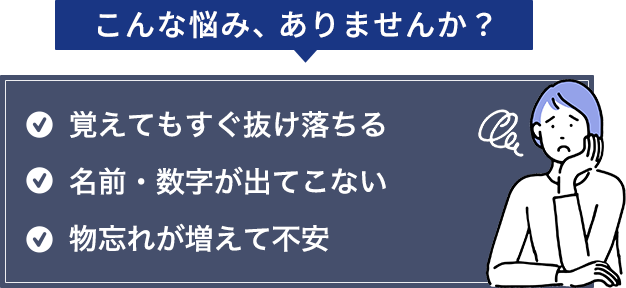 ▼
▼覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。
それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。
無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
英語スピーチ・3分スピーチはどう覚える?
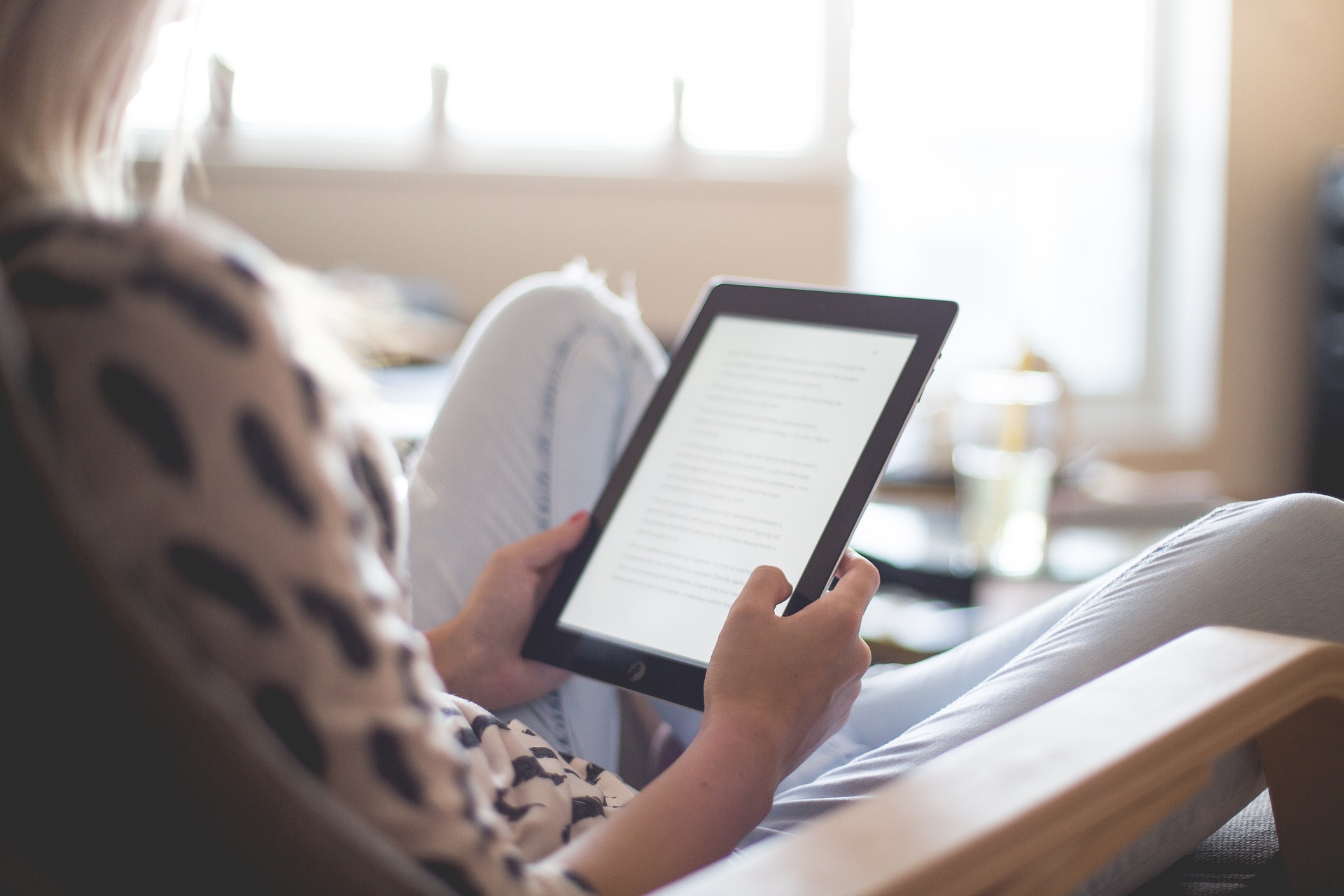
英語スピーチや3分間スピーチを覚えるには、構成を工夫し、話しやすい形で準備することが大切です。
内容を頭に入れやすくするためには、話す順序やキーワードの整理が効果的になります。
- 英語スピーチでの暗記のコツ
- 3分間スピーチで伝える構成法
それぞれ順番に解説します。
英語スピーチでの暗記のコツ
英語スピーチは全文を丸暗記するのではなく、話の流れと要点を把握しておくことがポイントです。
まず、自分の言葉でスピーチの意味を理解し、各段落のキーワードを明確にしてみましょう。
次に、それらをメモにして見ながら練習を繰り返すと、自然に内容が頭に入ってきます。
また、声に出して練習することで発音やリズムも整いやすくなり、本番でも落ち着いて話せるようになるでしょう。
3分間スピーチで伝える構成法
3分という限られた時間内で伝えるには、構成をしっかり決めておく必要があります。
「結論→理由→具体例→再結論」の順で話すことで、聞き手の理解を得やすくなります。
最初に結論を示すことで興味を引き、その後の展開にも注目してもらえるのです。
最後に再び結論を述べることで、印象が強まり、内容が記憶に残りやすくなるはずです。
スピーチを覚える5つの効率的な練習法

 キツネさん
キツネさん
ポイントを踏まえて、話す内容が決まりました!次は覚えてうまく話すための練習ですが、丸暗記にならないためにはどうすればいいんでしょう?
話す内容が決まれば、次はより良いスピーチとなるよう練習する段階です。
ここで「スピーチの丸暗記」をゴールにしてしまうと、無駄に時間と労力がかかってしまいます。
また、人によっては「あまり時間をかけていられない」という方もいるかもしれません。
本番に向けては、効率的な練習法を取り入れて仕上げていきましょう。
- 箇条書きで要点を整理する
- アクティブリコールを取り入れる
- 実際に話したものを録音・撮影する
- ゆっくり落ち着いて話す練習をする
- 毎日短時間でも声に出して繰り返す
① 箇条書きで要点を整理する
効果的な練習法の一つとして、テーマを箇条書きにしたメモを見ながら話すというものがあります。
例えば以下のようなメモを用意してみましょう。
- 自己紹介(部署・出身・趣味)
- 普段やっている仕事
- 大事にしていること
- そう思ったきっかけのエピソード
- 結論とこれからの目標
まずはこうした構成メモを見ながら、話せるよう練習してみましょう。
そうすれば丸暗記を避けつつ「生きた言葉」で大事なことが伝わるスピーチにつながります。
② アクティブリコールを取り入れる
新しいことを効率よく覚える方法の一つに「アクティブリコール」というものがあります。
新しいことを学んだ直後に、何も見ずに学んだことを書き出したり、声に出したりして思い出せる限りアウトプットを行うこと。「想起学習」とも呼ばれる。
受験勉強などでも取り入れられていますが、このアクティブリコールはスピーチの練習にも効果的です。
話す内容が書いたメモに目を通したら、一度伏せて内容を思い出しながら本番のように話をしてみましょう。
こうして何度もアクティブリコールを繰り返すうちに、少しずつスピーチが自分のものになっていきます。
③ 実際に話したものを録音・撮影する
ある程度話せるようになったら、実際にスピーチしている姿を録音・撮影してみましょう。
すると「誰かに聴かれている・見られている」という意識が生まれ、本番のような緊張感を持つことができます。
また、実際に話している姿や声を客観的に確認してみると「もっと抑揚をつけよう」「ここは間をとろう」など、新たな改善点も見つかるはずです。
 キツネさん
キツネさん
録音・撮影した上でスムーズに話すことができれば、より自信にも繋がりますね!
④ ゆっくり落ち着いて話す練習をする
声に出して練習する際は、自分が思っているよりも「ゆっくりと」「落ち着いて」話すことを心がけましょう。
人間は誰でも、緊張すると早口になる傾向があります。
つまり緊張感のある本番では、意識しないとどうしても早口になってしまうのです。
そのため練習の段階から「ゆっくり話すこと」に慣れておくと、本番も「いつものスピード」を心がけることができ、落ち着いて話すことに繋がります。
⑤ 毎日短時間でも声に出して繰り返す
スピーチ練習では、一度に長時間取り組むよりも、毎日少しずつ継続することが効果的です。
とくに、声に出して繰り返すことで記憶に定着しやすくなり、言い回しや語順も自然と身についてきます。
朝の通勤前や夜の入浴中など、短時間でも習慣として続けることで、スピーチの完成度は確実に高まります。
日々の積み重ねが、自信を持って話せる状態につながるのです。
スピーチを1日で覚える方法

スピーチを1日で覚えるには、短時間で記憶を定着させる方法が必要です。
まず、内容を3~4つのパートに分けて「図解」や「イメージ」で視覚的に整理しましょう。
次に、相手が目の前にいる想定で、声に出して何度もアウトプットする練習をします。
加えて、時間を区切り「10分集中→5分休憩」のサイクルを繰り返すと効率的です。録音して聞き返すと、内容の漏れや言い回しの改善にも役立ちます。
丸暗記ではなく、内容の「流れ」を体で覚えることが成功のカギとなります。
記憶術を活用すればスピーチも楽に覚えられる
どうしても覚えられないときには「記憶術」の力を借りるのも一つの手です。
たとえば「場所法(記憶の宮殿)」を使えば、伝えたい内容を自宅の部屋や通学路などに順番に配置して記憶できます。頭の中で空間をたどることで、順序立てて自然に話せるようになります。
また、重要なキーワードを視覚的なイメージに変換する「イメージ記憶」も効果的です。印象的な絵や動作と結びつけると、内容が記憶に残りやすくなります。
これらの記憶術を活用すれば、丸暗記に頼らず自然なスピーチが可能になります。
関連記事:記憶の宮殿とは?ギネス認定の記憶術を紹介
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
覚えたらあとは話すだけ!スピーチ当日の心構え

準備が整い、練習を重ねたらあとはスピーチ本番を迎えるのみです。
スピーチ当日は、事前の準備よりも心の持ちようが結果を左右する大切なポイントです。
ここでは、スピーチ本番に臨む際の心構えについて順番に解説します。
- 十分に睡眠を確保する
- 直前はリラックス&集中力を高める
- 話す自分を客観視する
- 聞き手の反応を見ながら話す
- 間違えても気にしすぎない
それぞれ順番に解説します。
人前で話をするのは誰もが緊張することですが、そんな緊張を和らげ、集中力を発揮する方法を紹介します。
自信を持ってスピーチ本番に臨めるよう、ぜひ試してみてください。
十分に睡眠を確保する
前日は早めに就寝し、しっかりと睡眠を取ることが重要です。
脳が最も活発に働くのは、質の良い睡眠をとった翌朝と言われています。
記憶の定着やストレスの軽減にもつながるため、遅くまで練習するより睡眠を優先しましょう。
当日のパフォーマンスを引き出すためには、健康な状態で臨む準備が不可欠なのです。
直前はリラックス&集中力を高める
本番直前は、焦って新しいことを詰め込むよりも、深呼吸などで心を落ち着かせましょう。
軽くストレッチしたり、ゆっくり目を閉じてイメージトレーニングをするのも効果的です。
その中でも特におすすめなのが呼吸法で、呼吸を整えることで脳への酸素供給が増え、集中力も向上します。
- 背筋を伸ばし、軽く目を閉じる
- 体の空気を全て吐き出す
- 鼻からゆっくり息を吸い込み、ゆっくりと吐き出す
- 1〜3を何度か繰り返す
このように呼吸を整えることで、心拍数も落ち着き、緊張を和らげることができます。
関連記事:テスト中に集中力を高める方法を解説!当日・直前・本番など場面ごとの対策も
話す自分を客観視する
緊張しすぎてしまうと、つい自分の世界に入り込んでしまいます。
そこで、自分が話している姿を少し離れた場所から見るような意識を持つと効果的です。
第三者の目線を取り入れることで、冷静さが戻り、話し方や姿勢にも余裕が出てきます。
心の中に「もう一人の自分」を置くようなイメージで話すと、安定感が生まれるでしょう。
 キツネさん
キツネさん
スピーチはもちろん、他の緊張感のある場面でも活用できそうなことばかりですね。これらのことを意識して、本番もがんばります!
参照:東洋大学 LINK@TOYO ビジネススキルを高める!プレゼンテーション・スピーチを上達させる3つのポイント
聞き手の反応を見ながら話す
スピーチ中は、ただ話すだけでなく「聞き手の反応に目を向けること」も大切です。
相手が頷いているか、表情がどう変化しているかを観察することで、話の伝わり方をその場で判断できます。
もし聞き手が難しそうな表情をしていれば、例え話を加える、言い回しを変えるなど、柔軟に対応する余地が生まれます。
また、聞き手とのアイコンタクトを意識すると、緊張がほぐれやすくなり、話す自分自身の安心感にもつながります。
一方通行ではなく、対話のように「伝わっているかどうか」を確認しながら話すことで、スピーチの説得力は格段に高まります。
間違えても気にしすぎない
スピーチ中に言葉を間違えたり、順序を飛ばしてしまっても大丈夫です。
多くの聞き手は細かいミスに気づきませんし、気にするのは自分だけということも多いです。
その場で言い直したり、別の表現に切り替える柔軟さがあれば問題ありません。
完璧を求めるよりも、誠実に伝える姿勢が大切なのです。
スピーチの暗記に役立つアプリ|機能別に解説
スピーチを効率よく覚えるには、自分に合ったアプリを活用するのが効果的です。
原稿作成、録音や分割練習、発話チェックなど、用途に応じた機能を使い分けることで、記憶の定着もスムーズになります。
- スピーチ原稿作成・保存の定番
- 録音して繰り返し聴ける
- 原稿を分割して練習できる
- 音声認識で発話練習ができる
それぞれ順番に解説します。
スピーチ原稿作成・保存の定番
文章の編集や保存、クラウド同期に対応したアプリが便利です。
外出先でも確認・修正ができるため、練習効率が大きく高まります。
- Googleドキュメント|複数端末で編集・保存できるクラウド文書アプリ
- Evernote|メモと添付ファイルの管理に優れ、カテゴリ別保存も可能
- Google Keep|シンプルで直感的に使えるメモアプリ。音声入力にも対応
スマホ1つで、いつでもアイデアの整理から原稿の推敲まで、幅広く対応できる点が魅力です。
本番直前の確認にもスムーズに使えるでしょう。
録音して繰り返し聴ける
録音して再生するだけでなく、速度調整や編集機能があるとより効果的です。
通勤・通学中にも繰り返し聴くことで、耳から覚えられます。
- ボイスメモ(iOS標準)|シンプルで使いやすく、再生も手軽
- Easy Voice Recorder|録音後の保存や整理がしやすいAndroid対応アプリ
- RecForge II|音質や録音設定の細かい調整が可能な高機能レコーダー
自分の声を聞き返すことで、話し方やテンポの改善にもつながります。
定着率も上がるため、暗記の仕上げにおすすめです。
原稿を分割して練習できる
セクションごとに練習できるアプリは、長文スピーチにとても便利です。
覚えたい範囲を選んで集中できるので、無駄がありません。
- Quizlet|カード形式で内容を分けて復習できる学習アプリ
- Studyplus|学習時間の記録や目標設定もできる自己管理アプリ
- AnkiMobile|記憶定着に特化した分散学習が可能な暗記アプリ
分割することで達成感が得られ、学習モチベーションが維持しやすくなります。
記憶の定着にも効果が高い方法といえるでしょう。
音声認識で発話練習ができる
話した内容が文字になることで、記憶の確認や修正点の発見につながります。
また、正しく発音できていないことのチェックもできるでしょう。
発音や言い回しのチェックにも便利です。
- Google音声入力|Android端末で使える正確な音声認識機能
- iPhoneメモの音声入力|iOS標準の簡単操作で即時テキスト化可能
- Otter.ai|会話内容をリアルタイムで文字起こししてくれる高性能ツール
実際に声に出して練習することで、スピーチ本番に近い形で対策できます。
誤認識があっても、それをヒントに修正できるのも利点です。
まとめ|正しく練習して自信を持って話そう!
本記事では、スピーチの覚え方や効果的な練習法について解説しました。
全文を丸暗記せずとも、構成やキーワードを整理し、自分の言葉で話すことが大切です。
また、記憶術やアプリを活用すれば、短時間でも効率的に準備が可能になります。
ちなみに、スピーチにも役立つ記憶力を上げたいなら吉永式記憶術という記憶術もおすすめです。記憶術は科学的に裏打ちされたスキルなので、誰でも習得できるメリットがあります。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
Wonder Educationでは、誰でも記憶力を高められる記憶術講座を提供しています。再現性の高い指導で、記憶力向上とそれによる目的の達成をサポートしていますので、ご興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせください。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。












