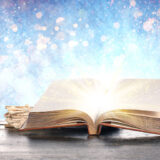キツネさん
キツネさん
「英単語や年号がなかなか覚えられない」
「ストーリー法を試してみたけれどコツが分からない」
そんな悩みを抱えていませんか。誰でも暗記に苦戦することはあり、工夫がなければ定着が難しいものです。
ストーリー法は初心者でも取り入れやすく、ほかの記憶術と組み合わせることで、記憶をより強固に定着させやすくなります。
本記事では、ストーリー法のやり方、メリット・デメリット、注意点、活用例について解説します。
読み終えれば、英単語や歴史年号を効率的に覚えられる学習法が分かり、日常の勉強や仕事にすぐに活かせるはずです。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
ストーリー法とは?基礎と適用範囲
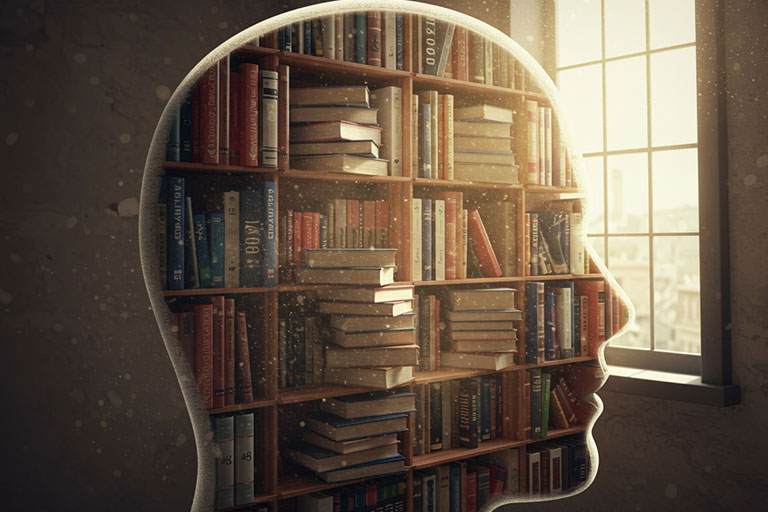
ストーリー法は、単なる暗記ではなく記憶に残る物語を作ることで知識を強固に結びつける学習法です。
文章や情報を意味のある流れに変えることで、脳は情報を整理しやすくなり、長期的な記憶保持につながります。
- ストーリー法とは?記憶術としての位置付け
- 物語化が記憶に与える心理学的効果
- ストーリー法が適している学習対象
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ストーリー法とは?記憶術としての位置付け
ストーリー法は、複数の情報を物語に変換しながら覚える方法で、記憶術の中でも実践しやすい位置付けにあります。
人はそもそも物語を理解し、共有してきた歴史を持っており、無関係な情報でもストーリーにすると想起が容易になるのです。
例えば、単語を順番に覚えるよりも、日常の場面に登場人物や行動を組み込んで関連付けた方が記憶定着が強化されます。
暗記カードのように単発で覚える手法と比べると、ストーリー法は長期記憶への橋渡しが得意で、学習や試験準備など幅広く活用されています。
また、創造力を使うため楽しみながら学べるという副次的な効果もあり、退屈になりがちな暗記作業を継続しやすいのです。
参考:暗記に命かけるスパイが直伝 ストーリー記憶法の威力|NIKKEIリスキリング
物語化が記憶に与える心理学的効果
物語化は記憶に大きな心理的効果をもたらします。
人は意味のない情報を保持しづらい一方で、文脈やストーリーがあると記憶効率が大幅に高まります。
実際にスタンフォード大学の研究では、事実だけより物語を交えた情報は最大22倍記憶されやすいと示されているのです。
物語は感情を動かし、意味記憶とエピソード記憶を同時に活性化させます。
そのためユーモアや驚きを盛り込むことで、さらに記憶に強く刻まれるのです。
参考:Harnessing the Power of Stories|Stanford University
ストーリー法が適している学習対象
ストーリー法はすべての分野に万能ではありませんが、特に順序や関連性のある情報を覚えるときに力を発揮します。
歴史の年号や出来事、語学学習における単語の暗記などでは、流れや場面を物語として組み立てることで理解と記憶が深まります。
- 歴史の年号や出来事(流れとして覚えやすい)
- 語学学習の単語(人物や道具に置き換えて記憶に残す)
- 資格試験や受験の暗記科目(補助手段として効率と継続性を高める)
一方で、計算式や単独の数値のように物語化が難しい対象には不向きです。
そのため学習分野に応じた使い分けが重要であり、適材適所で取り入れることで学習の効果が最大化されます。
ストーリー法のメリットとデメリット
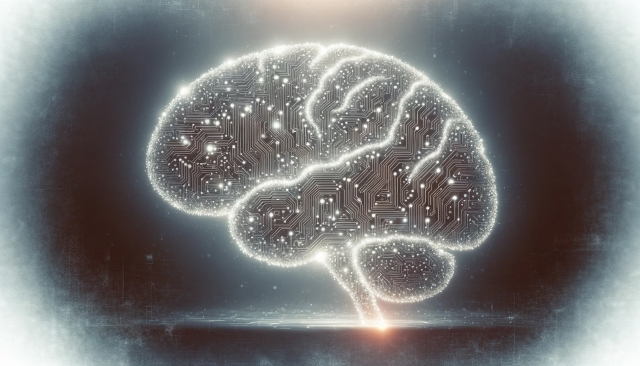
ストーリー法は、物語を用いて情報を関連付け、長期的に記憶へ残すための代表的な記憶術です。
しかし便利な一方で、必ずしもすべての学習に適しているわけではなく、限界や注意点も存在します。
そこで、ストーリー法のメリットとデメリットを解説していきます。
ストーリー法のメリット
ストーリー法のメリットについて整理すると、学習効率を上げる要素がいくつも見えてきます。
物語を通じて情報を関連付けることで、脳は情報を単なる断片ではなく一貫性のある流れとして捉えるのです。
特に歴史や語学など、順序や関係性を重視する学習内容においては大きな効果を発揮します。
- 情報を関連付けて記憶の定着率を高められる
- 感情を伴うエピソードで記憶が長期化しやすい
- 暗記作業が楽しくなり、継続しやすくなる
- 検索手がかりが増え、思い出しやすくなる
- 語学や歴史など順序や流れがある学習に有効
これらの利点を活かせば、苦手意識が強い暗記学習にも前向きに取り組めるようになります。
ストーリー法のデメリット
一方で、ストーリー法にはいくつかの注意点や限界も存在します。
便利ではあるものの、全ての情報が物語に適しているわけではなく、内容によっては逆効果になることもあります。
- 物語化に時間がかかり効率が下がる場合がある
- 複雑なストーリーは逆に混乱を招くことがある
- 数学の公式や抽象的な数値には不向き
- 物語を忘れると元の情報も思い出せなくなる
- 使いこなすには工夫や練習が必要になる
こうした弱点を理解したうえで、状況に応じて他の記憶術と併用することが効果的です。
ストーリー法のやり方|3ステップで実践
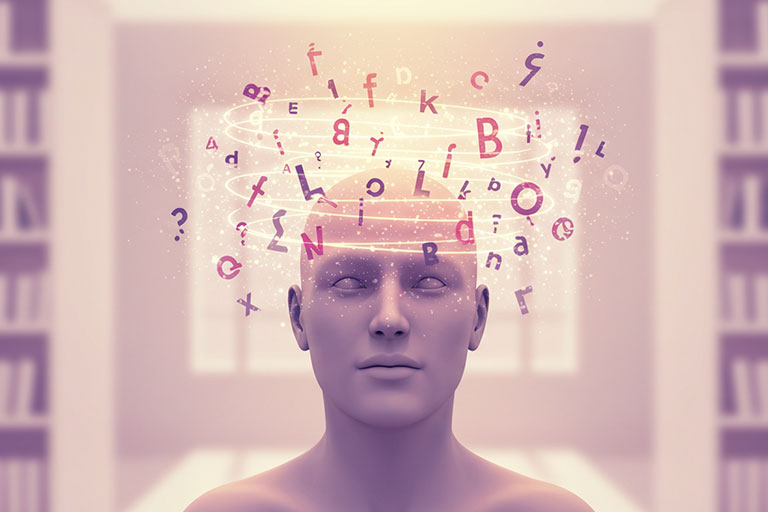
ストーリー法は、覚える情報を物語に変換して脳に定着させる記憶術のひとつです。
複雑な内容でも整理された流れに組み込むことで、検索の手がかりが増え、思い出しやすくなります。
- 覚える情報を分解して要素を抽出する
- 要素を関連付けて物語の流れを作る
- 物語を繰り返し想起して定着させる
それぞれのステップを丁寧に解説していきます。
① 覚える情報を分解して要素を抽出する
まずは覚えたい内容を細かく分解し、必要な要素を抜き出すことが重要です。
単語リストなら単語ごとに、歴史の流れなら出来事や登場人物ごとに切り分けると整理がしやすくなります。
情報を塊で覚えようとすると脳に負担がかかり、途中で混乱してしまう危険が高まります。
そこで最初に要素ごとに分ける作業を行うことで、後から物語化しやすくなるのです。
この段階を丁寧に行うかどうかで、その後のストーリー作りの質が大きく変わってきます。
- apple(リンゴ)
- book(本)
- run(走る)
② 要素を関連付けて物語の流れを作る
抽出した要素をつなげ、無理のない物語に変換することが次のステップです。
人間の脳は、意味のない羅列よりも因果関係や登場人物の動きを伴った物語を強く記憶します。
例 : 自然なストーリーに変換
「ある日、小学生のケンは公園でリンゴ(apple)を食べながら本(book)を読んでいた。すると急に大粒の雨が降ってきたので、ケンは走って(run)家へ帰った。」
関連性を強調するために、感情やユーモアを加えるのも効果的です。
自分なりに一貫した流れを持たせることで、記憶のフックが増え、思い出しやすさが高まるのです。
③ 物語を繰り返し想起して定着させる
一度作った物語は短期記憶にとどまりやすく、そのままでは忘却曲線に従って急速に失われてしまいます。
そこで意識すべきなのが復習のタイミングです。数時間後・翌日・数日後と間隔を空けて繰り返すことで、記憶は長期化しやすくなります。
- 学習後数時間以内に1回復習する
- 翌日にもう一度物語を想起する
- 数日後に再度復習して長期記憶に移行させる
さらに、声に出して物語を語ると視覚と聴覚を同時に使うことになり、記憶がより強化されます。
このステップを習慣化すれば、ストーリー法の効果は飛躍的に高まり、学習効率も持続的に向上していきます。
関連記事:忘れない勉強法|エビングハウスの忘却曲線と復習スケジュール完全ガイド
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
ストーリー法と他の記憶術の組み合わせパターン5選

ストーリー法は単独でも効果的ですが、他の記憶術と組み合わせることでさらに定着率が高まり、学習効率が大きく向上します。
異なる記憶術を重ね合わせることで、情報に複数の検索手がかりを与え、想起がスムーズになるのです。
- ストーリー法と場所法の併用
- ストーリー法と数字変換法の融合
- ストーリー法と頭文字法の組み合わせ
- ストーリー法と連想イメージ法の活用
- ストーリー法と歌やリズム法の統合
それぞれの活用法を具体的に説明していきます。
ストーリー法と場所法の併用
場所法は「記憶の宮殿(メモリーパレス)」とも呼ばれ、空間に情報を配置して記憶する技術です。
この方法とストーリー法を掛け合わせると、物語の流れと空間的な手がかりが同時に働き、想起の精度が高まります。
例えば、物語の登場人物が部屋を移動しながら情報を拾っていくイメージを作ると、順序や関係性が自然に定着します。
また、場所法の強みである「空間の順路」とストーリーの「時間的流れ」が合わさり、二重のフックが働くのです。
こうした工夫によって、大量の情報を長期に保持しやすくなります。
関連記事:記憶の宮殿(メモリーパレス)とは?ギネス認定の記憶術を解説!
ストーリー法と数字変換法の融合
数字変換法は、数字を語呂合わせや形に置き換えて記憶する技術です。
これをストーリー法に取り入れると、抽象的な数列もキャラクターや物体として物語に登場させられるため、記憶が具体化します。
例えば「314」を「サイ(3)が医者(1)に良い薬(4)を渡す」と物語化すれば、数列が印象的に残ります。
数字をそのまま覚えるよりも、動きや感情を伴ったストーリーにすると記憶効率が格段に高まるのです。
資格試験や暗証番号のような数字の暗記に特に適しています。
ストーリー法と頭文字法の組み合わせ
頭文字法は、リストや順序を頭文字でまとめて覚える手法です。
これにストーリー法を加えると、単なる文字列に意味や物語が加わり、想起の助けになることがあります。
たとえば、「UNHCR」という単語は覚えるのが難しいこともあるでしょう。
そこで「UNHCR」は「ウニ(U)がネギ(N)を抱え、骨(H)にチーズ(C)を乗せたラーメン(R)を食べる」といった物語にすると覚えやすくなります。
頭文字は短く簡潔ですが、単体では弱い手がかりになりやすい課題も残ります。
物語性を組み込む際は、登場物の関連・場所・因果を一本化しないと記憶装置として逆効果になり得る点に注意してください。
ストーリー法と連想イメージ法の活用
連想イメージ法(連想連結法)は、覚えたい情報をイメージに変換し、そのイメージ同士をつなぐ方法です。
ストーリー法と融合させれば、単なる絵の連鎖ではなく、意味のある流れを持った物語に昇華できます。
例えば「りんご」「本」「川」という単語を覚える際に、「りんごを食べながら本を読み、川辺でくつろぐ」という物語にすれば自然に定着します。
無関係に見える情報でも、ストーリーにすると一貫したつながりが生まれるのです。
視覚的記憶と物語の力を組み合わせることで、相乗効果を得られます。
関連記事:「連想結合法」で記憶力UP!脳科学×実践ステップで忘れない学びへ
ストーリー法と歌やリズム法の統合
歌やリズム法は、覚えたい内容を音楽やリズムに乗せて記憶する方法です。
これをストーリー法と一緒に使うと、物語がメロディに包まれ、耳からの想起が強化されます。
たとえば歴史の年号を物語化し、さらに歌に乗せて口ずさめば、聴覚と物語の両方が働くのです。
人はメロディとリズムを長期間保持する傾向があるため、歌を取り入れると復習が容易になります。
特に子どもや暗記が苦手な人に有効なアプローチといえるでしょう。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
ストーリー法で英単語と熟語を覚える方法
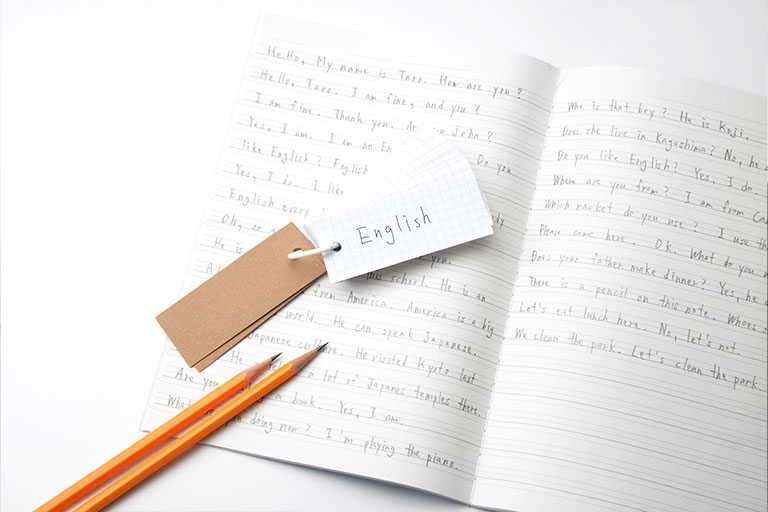
英単語や熟語を覚えるとき、ただ反復するだけでは定着が不十分になることが多いです。
しかしストーリー法を取り入れると、意味のある流れに変換でき、想起が容易になり学習効率が高まります。
- 英単語を短い物語に組み込んで定着させる
- 類義語や反意語を関連場面で覚える
- 作った物語を繰り返し音読して定着させる
順番に詳しく解説していきます。
① 英単語を短い物語に組み込んで定着させる
英単語を単独で暗記しようとすると、意味やスペルが断片的にしか残らず、忘れやすくなる傾向があります。
そこで、複数の単語を登場人物や場面に組み込み、短い物語を作ることで記憶のフックを増やすのです。
例えば「apple」「book」「run」を「少年がappleを食べながらbookを読み、急いでrunする」という物語に変換すれば、自然に覚えられます。
物語にすると脳が因果関係として処理するため、単語が単発で浮遊する状態を避けられます。
さらに感情やユーモアを入れると印象が強まり、記憶の保持が長期化するのです。
関連記事:【保存版】英単語を効率的に覚える7つのコツ|1日200語を無理なく覚える方法
② 類義語や反意語を関連場面で覚える
英語学習では、単語を一語ずつ暗記するよりも、類義語や反意語をまとめて覚える方が効率的です。
ストーリー法を活用すれば、意味が似ている単語や正反対の単語を同じ場面に登場させ、自然な文脈で理解できます。
例えば「happy」と「sad」は、主人公がテストで良い点を取ってhappyになり、友達の失敗を知ってsadになる、といった感情の変化を描けば強く印象に残ります。
また「big」と「large」をピザの大きさの場面に入れ、「He ordered a big pizza. It was so large that it covered the table.」のように使えば、微妙なニュアンスの違いを体感しながら覚えられるのです。
さらに「hot」と「cold」を天気の変化に、「fast」と「slow」を動物の競争に組み込むなど、対照的な状況を作ると記憶が鮮明になるでしょう。
物語を声に出して読み、数日おきに思い出すことで忘却曲線を補い、語彙が確実に定着していきます。
③ 作った物語を繰り返し音読して定着させる
ストーリーを作るだけでは短期記憶にとどまりやすいため、繰り返しの復習が欠かせません。
その際に音読を取り入れると、視覚と聴覚が同時に刺激され、記憶が強化されやすくなるのです。
物語を声に出して読むことで、言葉のリズムや発音も自然に身につき、英語力全体の底上げにもつながります。
また、復習の間隔を「数時間後」「翌日」「数日後」と空けて実施することで、長期記憶に移行しやすくなります。
ストーリー法と音読を組み合わせれば、暗記の精度も維持期間も大幅に向上するのです。
関連記事:短時間で効率よく暗記する11の方法|暗記が苦手な人でも驚くほど覚えるコツ!
ストーリー法を歴史年号や通史理解に活用する方法
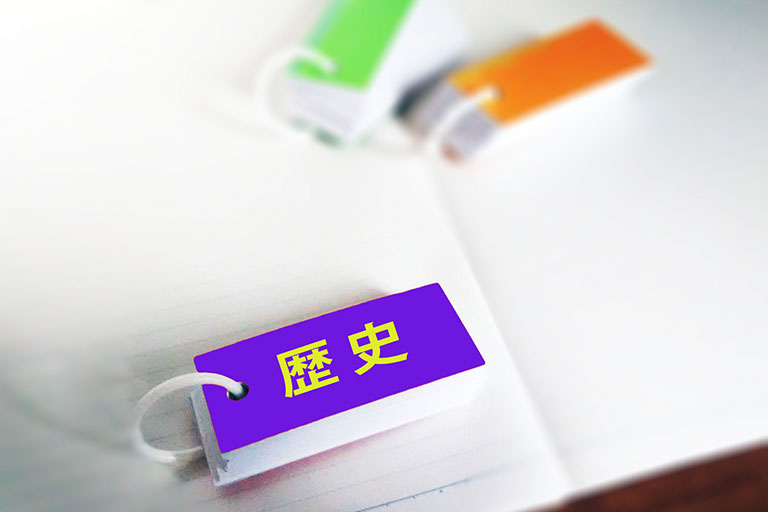
歴史学習は暗記が中心になりがちですが、ストーリー法を取り入れると流れを理解しやすくなります。
単なる数字や出来事の羅列ではなく、因果関係を伴った物語にすることで、自然に記憶が結びつくのです。
- 出来事を因果関係でつなぎ物語化する
- 年号は語呂と併用して補助的に使う
- 人物と事件を一連の物語で覚える
順を追って解説します。
① 出来事を因果関係でつなぎ物語化する
歴史は出来事の積み重ねですが、単独で覚えると断片的になり、流れを理解しづらくなります。
そこで、事件や政策を原因と結果のつながりでストーリー化することで、理解と記憶の両方を強化できるのです。
例えば「応仁の乱」は「幕府の権力争い」から「地方大名の対立」へ発展する流れを物語にすると、単なる年号暗記にとどまらず背景理解が深まります。
既に物語化されているマンガやYouTube動画を利用し、その流れにストーリー法を組み合わせると、自分で一から作るよりも効率的に記憶を定着させられます。
このように因果を意識した物語に変換すれば、学習した知識を再利用しやすくなるのです。
歴史の通史理解において特に有効な手法だといえるでしょう。
関連記事:歴史が覚えられない中高生へ|覚え方・ノート術・勉強のコツ総まとめ
② 年号は語呂と併用して補助的に使う
年号暗記は避けて通れませんが、数字だけでは記憶に残りにくく、時間が経つと忘れやすくなります。
そこで語呂合わせを作り、ストーリーの中に組み込むことで、数字の定着を助けられるのです。
例えば「1192(いい国)作ろう鎌倉幕府」という語呂を、将軍が国づくりを宣言する場面に入れ込むと、物語の一部として記憶が残ります。
語呂は数字をイメージに変える橋渡しであり、ストーリーとの併用によって意味づけが強まります。
この組み合わせによって、数字と歴史の内容を同時に思い出せるようになるのです。
関連記事:日本史の効率的な覚え方|NG暗記法と得点アップに効く対策まで解説
③ 人物と事件を一連の物語で覚える
歴史は人物と事件が相互に影響しながら展開していくため、両者をセットで覚えると効率的です。
人物ごとの行動や思想をストーリーに盛り込み、事件と結びつけることで、単なる名前の暗記ではなく背景を理解できます。
例えば織田信長を中心に「桶狭間の戦い」や「楽市楽座」を物語にまとめると、時代の特徴も自然に定着します。
人物と事件がリンクすることで、通史全体の流れが一本化され、理解の深さが増すのです。
こうした工夫を重ねれば、歴史学習は単なる丸暗記から一歩進んだ知識活用へと変わります。
関連記事:世界史を効果的に暗記する方法!苦手の原因と覚えるコツ・NG行動を解説
ストーリー法に関する注意点

ストーリー法は記憶を強化する優れた方法ですが、正しい使い方を意識しないと逆効果になることもあります。
複雑にしすぎたり無理につなげたりすると、覚えるどころか混乱を招いてしまうのです。
- 内容を盛り込みすぎて複雑化しない
- 登場人物や物の数を増やしすぎない
- 無理に話をつなげて不自然にしない
- 自分にとってイメージしやすい物語にする
- 繰り返し練習して記憶に定着させる
順を追って詳しく解説していきます。
内容を盛り込みすぎて複雑化しない
ストーリー法では情報を物語に変えることが大切ですが、内容を詰め込みすぎると逆効果になります。
一つの物語に多くの出来事や細部を盛り込みすぎると、全体像が複雑化して記憶が混乱してしまうのです。
例えば、いきなり単語10個を一気に使って長編の物語を作ると、細かい部分を思い出すのが難しくなります。
むしろ、情報を分けて複数の短いストーリーにすることで、記憶の効率が高まるのです。
覚える範囲を適切に分割し、シンプルな物語で定着させることを意識しましょう。
登場人物や物の数を増やしすぎない
ストーリーに登場させる人物や物の数が多すぎると、場面が混乱して記憶の助けにならなくなります。
特に学習の初期段階では、1人もしくは少数の登場人物に絞り、役割を明確にすると整理しやすいのです。
例えば、主人公1人に対して3つの単語を結びつける程度なら理解も記憶もスムーズになります。
しかし登場人物が5人以上になると、それぞれの役割や動きを追いかけるだけで負担が大きくなるのです。
登場させる要素を少なくすることで、物語全体の一貫性が保たれやすくなります。
無理に話をつなげて不自然にしない
ストーリー法の目的は自然な流れを作って記憶を助けることですが、無理に情報をつなげると逆効果になります。
不自然な展開はかえって違和感を生み、覚えるよりも混乱が増える原因になってしまうのです。
例えば、関係のない単語を強引につなげると、場面が不自然で印象が薄くなります。
一方で、日常的な状況や感情の流れに沿った物語なら自然に記憶へ残るのです。
違和感なくストーリーを作ることが、定着力を高めるコツになります。
自分にとってイメージしやすい物語にする
ストーリー法の効果は「自分がどれだけイメージしやすいか」に大きく左右されます。
他人にとっては面白い物語でも、自分が思い描きにくいものでは記憶の助けにならないのです。
そこで、自分の経験や興味に関連する場面を選び、鮮明にイメージできる物語を作ることが重要です。
例えば、好きな映画や趣味を題材にして英単語を組み込むと、自然に覚えやすくなります。
イメージの鮮明さが増すほど、記憶の定着も長期的に持続するのです。
繰り返し練習して記憶に定着させる
ストーリー法は作って終わりではなく、物語を定期的に思い出したり、声に出して語るたびに想起の経路が強化されます。
復習の方法は「集中学習」と「分散学習」に大別され、短期には集中学習でも覚えられますが、長期保持には間隔をあける分散学習が有利です。
- 集中学習:短期間に集中的に繰り返し覚える方法。短期試験対策には有効だが、忘却が早い傾向がある。
- 分散学習:時間を空けて繰り返し復習する方法。長期的な定着に優れており、学習効率も高い。
なお「間隔反復法」の中でも、復習間隔を徐々に広げる拡張型が常に最適とは限りません。
等間隔の分散でも十分に効果が確認されており、重要なのは想起を伴う復習を一定のリズムで続けることです。
初回は学習直後に短く復習し、以後は等間隔で思い出す、声に出す、要約するなどの検索練習を重ねると、短期記憶から長期記憶へ移行しやすくなります。
参考:復習間隔を少しずつ広げていくことは長期的な記憶保持を促進するか?
ストーリー法を身につけるための練習問題とトレーニング
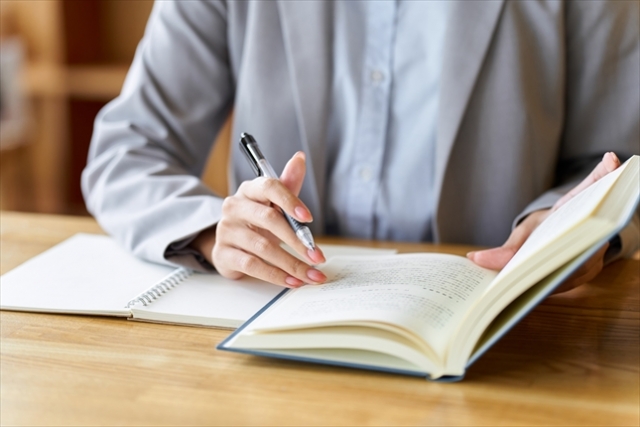
ストーリー法を効果的に活用するには、実際に練習を積み重ねることが欠かせません。
段階的に取り組める課題をこなすことで、自然に物語化する力が磨かれ、記憶効率も高まります。
- 三語を一分以内で物語化する初級練習
- 五語以上や数字を含む中級の物語化練習
- 場所法と組み合わせた上級実践練習
それぞれ具体的に解説していきます。
① 三語を一分以内で物語化する初級練習
まずは短時間で少数の単語をストーリーに変換する練習から始めると、基礎力がつきやすいです。
例えば「犬」「ボール」「公園」という三語を使って、一分以内に物語を作ると、無理なく流れがイメージできます。
この練習では正確さよりもスピードを重視し、即興的に物語化する柔軟さを養うのです。
単純な場面設定でも十分であり、継続するうちに自然と想像力が広がります。
基礎段階で反射的にイメージを結びつける感覚を身につけることが大切です。
② 五語以上や数字を含む中級の物語化練習
初級に慣れてきたら、五語以上や数字を含む情報を取り入れる練習に挑戦しましょう。
例えば「山」「本」「橋」「車」「2025」という要素を用いて、関連性を持つ物語を作ると実践力が鍛えられます。
このレベルでは複数の情報を一貫性ある流れに組み込む必要があり、整理力と工夫が求められるのです。
また、数字を物語に取り入れると抽象的な情報にもイメージが加わり、暗記効率が向上します。
難易度が上がる分、自然なストーリーに仕立てる工夫が必要になるのです。
③ 場所法と組み合わせた上級実践練習
ストーリー法を場所法と組み合わせると、物語の流れと空間の手がかりが重なり、強力な記憶術となります。
例えば玄関に友人、キッチンにリンゴ、リビングに本を置くように設定し、通学路や自宅を舞台に物語を展開します。
「玄関を開けると友人が巨大な本を抱えて立っている、キッチンでは鍋からリンゴが飛び出す」といった具体的な演出が効果的です。
空間の順路を思い出すことで自然にストーリー全体がよみがえり、記憶の再生精度が高まります。
繰り返し練習すれば長期的な記憶保持につながり、学習の定着力が一段と強まります。
関連記事:最強の記憶術「場所法」とは?やり方・例・英単語暗記への活用法も紹介
ストーリー法に関するよくある質問
ストーリー法に関するよくある質問を解説します。
ストーリー法は誰に向いている?
ストーリー法は、丸暗記が苦手で情報の流れを理解して覚えたい人向けです。
また、イメージを描くのが得意な人や、物語や映像を通じて理解する学習スタイルを持つ人にも適しています。
特に歴史や語学のように因果関係や文脈が重要な分野で大きな効果を発揮するのです。
英単語学習で日本語を混ぜてもいい?
英単語を覚えるときに日本語を混ぜても問題はなく、むしろ補助的に活用すると効果的です。
例えば「apple」を「リンゴを食べる少年」という物語に入れると、意味と単語が一緒に定着しやすくなります。
ただし日本語に頼りすぎると英語だけで想起する力が弱まるため、バランスが大切になります。
効果が出るまでどれくらい時間がかかる?
ストーリー法は即効性があり、短時間で記憶が定着する実感を得やすい学習法です。
しかし長期的に保持するには、繰り返しの練習や間隔を空けた復習が欠かせません。
一般的には数日から数週間の継続で安定し、長期間の記憶に移行するのです。
まとめ|ストーリー法を習得して勉強や仕事に活かそう!

本記事では、ストーリー法の基礎とやり方について解説しました。
物語化によって情報を整理しやすくなり、記憶の定着率を高められる点が大きな特徴です。
また、英単語や歴史年号の学習に効果的で、場所法や数字変換法など他の記憶術と組み合わせれば、さらに応用範囲が広がります。
注意点を押さえて練習を重ねることで、勉強や仕事に長く活かせるスキルとなるでしょう。
「もっと集中力や記憶力を高めて、勉強や仕事に活かしたい」という方には、「吉永式記憶術」もおすすめ。科学的根拠に基づいた実践的なトレーニング法で、初心者でも無理なく取り組めます。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い指導を通じて記憶力向上と目標達成をサポートしています。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。