 キツネさん
キツネさん
「友達はすぐに覚えられるのに、私は全然記憶力がない」
など、よく聞きますが記憶力に遺伝子は関係あるのでしょうか。
この記事では、遺伝子と記憶力の関係について解説します。
この記事を読むと、遺伝子よりも記憶力に影響を与える行動がわかります。
「遺伝子のせいで記憶力が悪いからどうしようもない」とお悩みの方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
なお、記憶力の上げ方については記憶力を上げる方法とは?|誰でもできる記憶向上テクニックを紹介の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
もくじ
記憶力は遺伝する?
「記憶力は生まれつき決まっている?」という疑問は、多くの人が抱えるものです。
ここでは、ツイン研究やGWAS(ゲノム全体関連解析)など、最新の科学的なエビデンスに基づき、記憶力の遺伝率や、母親・父親どちらからの影響が強いのかをわかりやすく解説します。
記憶力は遺伝するのか?みんなの疑問
記憶力は遺伝すると思いますか?「脳の作りは親の遺伝子が引き継がれるのでは?」と思われる方も多いようです。
確かに医学部の親は医者多いしわかるけど
それを理由に諦めるのは勿体ない気がする…
記憶力とかは遺伝しそうだけど、本当に勉強できるか
は本人の努力次第だと思う!
てか記憶力って遺伝するの?気になる…— かなへび (@tokageKawai) March 5, 2020
記憶力って遺伝と関係あるん?
記憶力いいから勉強ができるんじゃなくていっぱい勉強してきたから記憶力がいいっていう考えやったんやけど笑どうなんやろ〜
— みろ (@guratanga1ban) September 3, 2020
記憶力の遺伝率は?科学論文と脳の仕組み
ツイン研究やGWASの解析から、作業記憶(ワーキングメモリ)に関する遺伝率は30〜40%程度と推定されています。
例えば2-backテストを用いた研究では、その正答率のばらつきのうち約31〜41%が遺伝要因によるものとされています。
また、MRIを活用した脳構造解析では、記憶に関わる海馬や前頭前野の形状にも遺伝的な影響があることが示されています。
ただし、“遺伝しきり”ではなく、後天的な環境や訓練でも大きく変わる余地がある点が重要です。
参照 :
nature ワーキングメモリのパフォーマンスに関するSNPベースの遺伝率の実質的な推定
PMC ワーキングメモリ脳活性化の遺伝率
母親・父親どちらの影響が大きいのか?
遺伝の仕組みとしては、父母から23本ずつ染色体を受け継ぎますが、母親由来のX染色体が2本あるため、母系の影響が強いケースも一部で確認されています。
また、インプリンティング(遺伝子の親特異性発現)というエピジェネティクスのメカニズムにより、父方・母方どちらの遺伝が活性化されやすいかが決まり、記憶や認知にも影響する可能性があります。
そのため、「母親からの影響が強く出る場合がある」と科学的に考察されていますが、両親の遺伝子と育った環境の総和が、記憶力を形作るという点を押さえておくことが大切です。
遺伝子よりも記憶力低下に影響を与える3つの行動

今から、遺伝子よりも記憶力低下に影響を与える行動をご紹介します。
遺伝子よりも記憶力低下に影響を与える行動は、以下の3つです。
上記を読むと、遺伝子よりも記憶力低下に影響を与える行動がわかります。
さっそくみていきましょう。
行動①:スマホの使いすぎ
遺伝子よりも記憶力低下に影響を与える行動1つ目は「スマホの使いすぎ」です。
記憶力低下の原因の1つにスマホの使いすぎがあるといわれています。
記憶のメカニズム
情報を受け取る ➡︎ 作業記憶として一時的に保存 ➡︎ 睡眠中に記憶を定着
スマホの場合は短い時間でニュースアプリやツイートなど、さまざまなな情報を受け取ります。
すると、作業記憶領域が不足してしまい情報が作業記憶として保存されません。作業記憶に保存されない情報は、睡眠中に定着せず、記憶力の低下を感じます。
「記憶力が悪いのは遺伝子のせい?」と疑うよりも、スマホの使い方を見直した方が良さそうですね。
スマホを使いすぎで記憶力の低下が気になる人におすすめの設定があります。
それは「画面をモノクロ表示にすること」です。
色のない画面を見てもドーパミンの放出量が少なくなり、スマホを見続けたいと思わなくなるのです。
行動②:睡眠不足
遺伝子よりも記憶力低下に影響を与える行動2つ目は「睡眠不足」です。
アメリカの高校生120人を対象に睡眠と記憶力の関係を調査した研究によると、
睡眠時間を削って勉強した人は、6時間以上睡眠をとった人に比べて記憶力が悪かったのです。
研究では、睡眠不足が続くと脳の海馬が小さくなることも判明しています。
海馬が小さくなると、記憶力を低下させる可能性があるのです。
記憶力の低下は、遺伝子よりも睡眠の影響を大きく受けると言っても過言ではないでしょう。
記憶力を低下させないためには最低6時間以上の睡眠をとることがおすすめです。
関連記事 : 記憶力と睡眠の関係
行動③:過度なストレス
遺伝子よりも記憶力低下に影響を与える行動3つ目は「過度なストレス」です。
遺伝により生まれながらに記憶力がいい人でも、過度なストレスを受け続けると、記憶力が低下する恐れがあります。
長期的なストレスは、脳の海馬を萎縮させ、記憶力低下を招くのです。
うまくストレスを発散し、健全な心を維持することが大切です。
過度なストレスにより記憶力の低下を感じている人は、簡単なストレス発散方法から試してみてください。
遺伝子に左右されず記憶力が良い人の特徴3選

今から、遺伝子に左右されず記憶力が良い人の特徴をご紹介します。
遺伝子に左右されず記憶力が良い人の特徴は、以下の3つです。
上記を読むと、遺伝子に左右されず記憶力が良い人の特徴がわかります。
さっそくみていきましょう。
特徴①:好奇心旺盛
遺伝子に左右されず記憶力が良い人の特徴1つ目は「好奇心旺盛」です。
こどもがアニメのキャラクターや電車などの名前を鮮明に記憶していて驚いたことはありませんか。
これには、遺伝子や記憶力なんてものは関係なく、好きだったから覚えたのです。
つまり、 好奇心を持つことで無意識に記憶力が上がります。
「2019年度 記憶力日本選手権大会」優勝者の池田 義博によると、
記憶力を高めるのは遺伝子ではなく、好奇心を持つことです。
好奇心を持つことでモチベーションも上がり、時間の感覚が消えるほどの高い集中「フロー状態」に入る可能性もあります。
この集中状態が驚異的とも思える記憶力につながるのです。
好奇心を高めるためには以下の3つの方法がおすすめです。時間にゆとりがある休日にぜひ実践してみてください。
特徴②:新しいことに挑戦する
遺伝子に左右されず記憶力が良い人の特徴2つ目は「新しいことに挑戦する」です。
日常生活を送っていると、学校に行ったり、職場に行ったりと毎日同じようなルーティンワークになってはいませんか。
遺伝子に左右されず記憶力が良い人は、常に新しいことに挑戦しています。
新しいことに挑戦と聞くと、大きなことを始めるイメージを持ってしまいます。
しかし、いつもと違う道を通って通勤するといったわずかな変化を加えることも、新しい挑戦と言えるでしょう。
遺伝子に左右されず記憶力が良い人が実践する「新しい挑戦」の例をご紹介します。
これらを全てやる必要はありません。
運動が得意な人は運動を、料理が得意な人は料理で、新しい挑戦することから始めてみましょう。
常に新しい挑戦をする習慣が身に付いたら、遺伝が気にならないくらい記憶力が良くなっているでしょう。
特徴③:適度な運動をする
遺伝子に左右されず記憶力が良い人の特徴3つ目は「適度な運動をする」です。
ジュネーブ大学の神経科学者たちが公表したジャーナル誌「Scientific Reports」によると、
運動すると「エンドカンナビノイド」と呼ばれる化学物質が活性化されます。
この活性化により記憶に重要な「脳の海馬」の信号伝達能力が、刺激の量に応じて変化・適応する仕組みが確認されました。
つまり、運動することで記憶を司どる「脳の海馬」が活発になるということです。
以下のようなゆっくり体を動かす運動を10分程度行うことがおすすめです。
「記憶力がいい人の特徴をもっと知りたい!」という方は、以下の記事も合わせて読んでみてくださいね。
<合わせて読みたい>
記憶力に関するよくある悩み
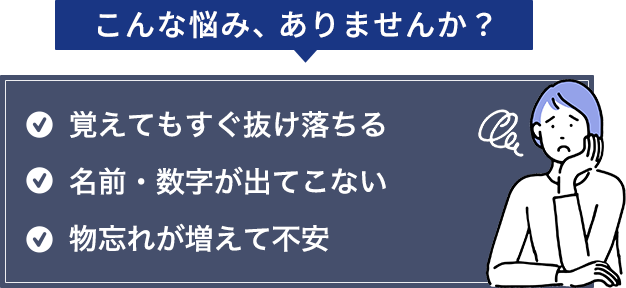 ▼
▼覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。
それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。
無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。
今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!
記憶力は遺伝子よりも環境や教育の影響が大きい

記憶力が高いのは親の遺伝子の影響と思われがちです。
しかし、 記憶力に大きな影響を与えるのは遺伝子ではなく、環境や教育なのです。
学校の授業で教えられことを単純に覚えようとしていませんでしたか。
記憶力には人それぞれ差があります。自分に合った「記憶の仕方」を知ることが重要なのです。
子どもの頃は記憶することに熱心ですが、記憶の仕方には目を向けません。
親や周囲の教育が記憶力の向上にとって遺伝子より大きな影響を与えます。
また、オフィスや自宅で高い記憶力を発揮するためには、環境を整えることが大切です。
仕事や学習で使わないものは目の届かないところに置くなど、環境を整えることが遺伝子よりも大きく記憶力に影響するでしょう。
【実践編】遺伝子に左右されず記憶力をアップさせる方法

遺伝子に左右されず記憶力をアップさせる実践的な方法をご紹介します。
遺伝子に左右されず記憶力をアップさせる実践的な方法は以下の3つです。
すぐに実践できるものばかりですので、記憶力が悪いのは遺伝子のせいだと悩まれている方は、ぜひ実践してみてください。
「記憶力を上げる具体的な方法ないかな…」という方は、以下の記事も合わせて読んでみてください。
まとめ|遺伝だけじゃない、記憶力は鍛えられる
記憶力は確かに遺伝の影響を一部受けますが、科学的には環境や行動によって大きく伸ばせることが明らかになっています。
日々の睡眠、ストレス管理、そして反復学習などの習慣を整えるだけでも、記憶力は確実に改善します。
さらに、近年注目されているのが「記憶術」の活用です。場所法や連想法など、脳の仕組みに基づいたテクニックを学ぶことで、記憶の効率を格段に高められます。
もし「覚えられない」「すぐ忘れる」と悩んでいるなら、一度記憶術を体系的に学んでみるのも良いでしょう。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。














