 キツネさん
キツネさん
資格や試験の勉強がつらい…。暗記ノートを作って学習効率を上げたいけれど、どんな作り方をすればいいのかな…?
勉強するときにノートをとるけれど、ただ書き写すだけでは効果が薄くて、結局どこを見返せばいいのか迷いますよね。
本記事では、中学生から社会人まで使える効果的な暗記ノートの作り方、教科別のコツなどを具体例とともに紹介します。
暗記に時間がかかる人や、資格試験や受験を控えている方にとって、勉強効率を大きく変えるヒントが見つかります。
ぜひ最後まで読んで、あなただけの最強の暗記ノート術を身につけてください。
「自分に自信が持てず、常に不安」
「人の顔と名前が覚えられない」
「資格試験に合格したい」
「英単語が全然覚えられない」
「本の内容をすぐ忘れる」
それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士
吉永 賢一
偏差値93
東京大学理科3類合格
IQ180を持つメンサ会員
講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導
記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師
書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ
暗記ノートを作るメリット

暗記ノートは、勉強の効率を高めるための有効な手段です。
情報を自分の手でまとめ直すことで理解が深まり、記憶にも定着しやすくなります。
- 記憶の定着が早くなる
- 重要な情報を整理しやすい
- 自分だけの復習用資料になる
それぞれ順番に解説します。
① 記憶の定着が早くなる
暗記ノートを作成する際には、授業や教科書の内容を自分の言葉でまとめ直す必要があります。
こうした作業は、受動的な暗記では得られない深い理解と記憶の定着を促進します。
さらに、書きながら視覚・触覚・思考を同時に使うことで、脳が情報を整理しやすくなります。
一度理解した情報は忘れにくく、繰り返し見直すことで記憶が強化されるため、試験前の効率的な勉強にも役立つでしょう。
② 重要な情報を整理しやすい
暗記ノートを使うことで、学習内容の中から必要な要点を選び取り、見やすくまとめる力が養われます。
無駄な情報を省きつつ、必要な内容を視覚的に整理することで、後から見直した際にも短時間で復習できる利点があります。
自分にとって必要な形式でまとめることで、情報の優先順位も把握しやすくなり、学習計画全体の最適化にもつながるのです。
③ 自分だけの復習用資料になる
暗記ノートは、市販の参考書にはない「自分専用の復習教材」として活用できます。
自分の理解度や弱点に応じて内容を更新できるのが強みです。
たとえば苦手な分野には図やメモを追加し、重要箇所を色分けして強調するといった工夫が可能です。書き直しを重ねることで、自分に最適な復習資料へと進化させられます。
他人に頼らず、自分自身の勉強スタイルを確立する手助けにもなるでしょう。
暗記ノートの種類と作り方|3つの基本パターン

暗記ノートには、目的や学習スタイルに応じたさまざまな作り方があります。
ここでは代表的な3つのパターンを紹介し、それぞれの特徴と作成手順をわかりやすく解説します。
- ストーリー理解型の暗記ノート
- 問題復習型の暗記ノート
- 弱点克服型の暗記ノート
それぞれ順番に解説します。
① ストーリー理解型の暗記ノート
このノートは、物事の因果関係や時系列をストーリーとしてまとめていく方法です。
- 教科書の章ごとの流れを大まかに把握する
- 出来事・原因・結果を時系列で書き出す
- それぞれの関係を図や矢印でつなぐ
- 自分なりの物語として一連の流れにまとめ直す
歴史、理科、倫理などの科目で効果を発揮します。
重要なのは、単なる羅列ではなく「流れ」を意識することです。
話のつながりを頭に描きながら組み立てることで、丸暗記では得られない深い理解が定着しやすくなります。
覚えた内容が脈絡をもって再現できるようになる点が、このノートの最大の魅力といえるでしょう。
②問題復習型の暗記ノート
一方で自分が間違えた問題だけを集めたのが「問題復習型の暗記ノート」です。
コツはつまずいたポイントを解説に書き込むことです。
- 間違えた問題をピックアップする
- 問題文をノート左側に書く
- 正しい答えとその理由を右側にまとめる
- 自分の間違いや気づきをメモする
英語、数学、理科などの演習が多い科目に向いています。
このノートは、「ミスの傾向を可視化し、次に活かす」ことが目的です。
なぜ間違えたのかを短くメモし、再度出題されたときにどう解くかをシミュレーションすると効果的。間違いを「教訓」に変える視点で、活用するのがポイントです。
単なる答え合わせではなく、学びを深めるツールとして活用しましょう。
③ 弱点克服型の暗記ノート
自分の苦手分野に焦点を当てて、効率的に克服するためのノートです。
- テストや日々の勉強でミスが多い分野を洗い出す
- その原因や要点を見直す
- 何がわからなかったのかを自分の言葉で書く
- 補足図や表で視覚的にも整理する
「わかっているつもり」を防ぎ、理解の穴を埋めるのに役立ちます。
解説を書いても理解があいまいな場合は、さらにかみ砕いて説明する訓練にもなります。
苦手をそのままにせず、意識的に記録して見返すことを習慣にすることで、点数アップに直結するノートになるでしょう。
暗記ノートを作る際の注意点

暗記ノートを正しく作らなければ、かえって非効率になることもあります。
内容を記録するだけでなく、見返したときの使いやすさや継続性も意識する必要があります。
- 必要な要点だけを簡潔に書く
- 字を丁寧に読みやすく書く
- まとめすぎて省略しない
- 色分けは3色までにする
- 定期的に見直して更新する
- 1教科1冊にまとめる
- 時間を決めて作成する
それぞれ順番に解説します。
① 必要な要点だけを簡潔に書く
暗記ノートには、すべての情報を詰め込もうとせず、重要な部分に絞って書きましょう。
膨大な量を書いても、復習のときに必要な情報が見つけにくくなってしまいます。
まずは授業や教科書の中から重要語句・用語を抽出し、それを簡潔に要約するのがポイントです。
ひと目で要点がわかるように、箇条書きや枠で整理する工夫を加えると効果的です。
短くても本質を押さえることで、ノートとしての機能が高まるでしょう。
② 字を丁寧に読みやすく書く
読み返したときに理解できない暗記ノートは意味がありません。
どんなに良い内容であっても、字が乱雑だと集中力を削がれ、記憶にも残りづらくなります。
大切なのは、自分が後で見てストレスを感じずに読めるレベルの丁寧さで書くことです。
丸文字や極端に小さい文字は避け、見やすさを意識して整えましょう。
書くスピードよりも正確さと視認性を優先すると、ノートの完成度が格段に上がります。
③ まとめすぎて省略しない
要点を押さえることは重要ですが、「キーワードだけ」では記憶の再生が難しくなります。
たとえば「光合成」と書くだけでなく、「植物が太陽光を使って栄養を作るしくみ」といった説明を添えると、後で見返したときにも理解が深まります。
その場で覚えているつもりでも、時間が経つと文脈を忘れてしまうことがあるため、補足説明を適度に加えましょう。
自分の言葉で要点を説明する形をとると、思い出しやすくなり記憶にも定着しやすくなります。
④ 色分けは3色までにする
ノートに色を使うと視覚的に区別がつきやすくなりますが、使いすぎると逆効果です。
原則として3色以内にとどめ、役割をはっきりさせて使うことが重要です。
たとえば、赤は重要語句、青は補足説明、緑は自分の気づきといったように、色の意味を固定すると見返しやすくなります。
過度にカラフルなノートはかえって読みにくく、集中力を妨げることもあるため注意しましょう。
統一感を持たせることが、視認性と記憶のしやすさに直結します。
⑤ 定期的に見直して更新する
暗記ノートは作って終わりではなく、繰り返し見返すことが前提です。
また、学習が進むにつれて情報の整理や新しい発見もあるため、定期的な更新が必要です。
1週間に1回などスケジュールを決めて見直し、追加・修正・削除を繰り返して内容を最適化しましょう。
更新することで理解の深さが増し、自分専用の完成度の高いノートになっていきます。
継続的に活用する姿勢が、暗記力の向上を支えてくれるはずです。
⑥ 1教科1冊にまとめる
教科ごとにノートを分けることで、情報の整理と復習の効率が向上します。
複数の教科を1冊にまとめてしまうと、必要な情報を探すのに時間がかかり、学習効率が下がる原因になります。
1教科1冊を原則とし、さらに単元や分野ごとに目次やインデックスをつけると、見やすさが格段に良くなります。
ノートの一貫性を保つことが、学習リズムを安定させるポイントになります。
学びやすさを意識した構成にすることで、継続的に使いたくなるノートになるでしょう。
⑦ 時間を決めて暗記ノート作成する
暗記ノート作りに時間をかけすぎると、肝心の勉強時間が削られてしまいます。
最初にノート作成の目的と時間配分を明確にし、集中して効率的に取り組むことが重要です。
たとえば「1単元あたり30分」といった時間制限を設けると、情報を取捨選択しながらまとめる力も自然と身についてきます。
限られた時間で最大限の成果を出す意識が、学習全体の質を高めてくれるでしょう。
完成度よりも活用度を重視して作成を進める姿勢が大切です。
科目別|暗記ノートの作り方のコツ
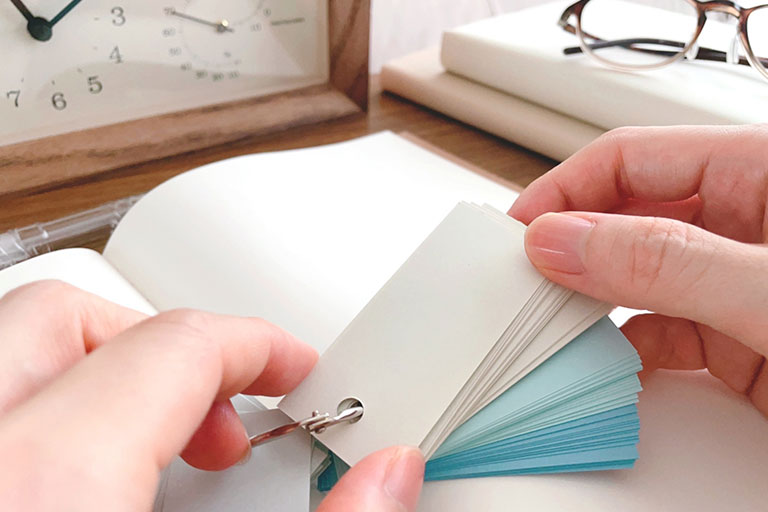
暗記ノートは、教科ごとの特性を理解して工夫することで、より記憶に残りやすくなります。
科目に応じた記録方法を実践すれば、効率的に学習内容を整理し、復習の質も向上します。
- 英語|単語と例文をセットで書く
- 数学|公式と解き方を整理する
- 社会|年号と出来事を並べて覚える
- 理科|図と用語をセットで記録する
- 国語|重要語句と意味をまとめる
それぞれ順番に解説します。
英語|単語と例文をセットで書く
英語の単語は、意味だけでなく例文と一緒に書くことで、実際の使い方まで理解できます。
文章の中でどう使われているかを意識することで、暗記だけで終わらず応用力が身につきます。
自分の日常や興味に関連した例文にすれば、記憶への定着率がさらに上がるでしょう。
英作文や会話の力も養えるため、長期的に役立つ学習法といえます。
- 単語の意味と例文をセットで記録する
- 例文は自分にとって身近な内容にする
- 意味が似た単語や対義語も書く
- 定期的に見直し、音読する
例文ごと覚えることで、実践的な英語力が育ちます。
数学|公式と解き方を整理する
数学では公式を覚えるだけでなく、どのように問題へ応用するかが重要なポイントです。
ノートには公式の意味と使い方、例題をセットにしてまとめると効果的です。
間違えた問題や苦手な単元を記録することで、自分専用の復習資料ができます。
図や式を丁寧に書くことで、解法の流れが視覚的に理解しやすくなります。
- 公式と使用例をセットにする
- 例題の途中式もすべて記録する
- 間違えた原因を言葉で残す
- 理解が浅い部分は色を変えて強調する
使える知識として定着させることが目的です。
社会|年号と出来事を並べて覚える
社会科では、年号と出来事をセットで覚えることで、歴史の流れを体系的に理解できます。
縦に並べて書くと視覚的に把握しやすく、時系列のつながりも明確になります。
事件の背景や影響まで記録すると、より深い理解につながり記憶も定着しやすくなります。
関連する人物名や語句を一緒に書けば、入試や試験でも応用が効くでしょう。
- 「年号+出来事」を縦に一覧化する
- できるだけ時代の流れを意識して並べる
- 背景や影響を短く添える
- 重要語は色ペンで強調する
年表感覚で整理すると、歴史の流れが見えやすくなります。
理科|図と用語をセットで記録する
理科は視覚情報が多いため、図と用語を組み合わせることで効率的な暗記が可能になります。
たとえば「人体のつくり」では、体の部位ごとの名称や働きを図にまとめると理解が深まります。
実験の手順や結果も図と一緒に記録することで、流れを視覚で把握できるようになります。
図を描くのが苦手でも、簡単な形だけでも十分に効果があります。
- 用語は図とセットで記録する
- 実験内容は手順と結果を図で整理する
- 色分けして見やすくまとめる
- 重要語には簡単な説明も添える
図で理解する習慣が、記憶定着の鍵になります。
国語|重要語句と意味をまとめる
国語では、語句の意味だけでなく、文中での使われ方や例文も一緒に記録することが大切です。
四字熟語や古文単語などは、現代語訳や似た表現を並べておくと理解が深まります。
また、自分の言葉で言い換える習慣をつけることで、応用力が自然と身についていきます。
読解力の土台にもなるため、受験対策や文章力の向上にも役立ちます。
- 語句+意味+使用例の順で記録する
- 出てきた文章の一部も書いておく
- 意味を自分の言葉で言い換える
- 漢字や読み方も併せて覚える
語句の深い理解が、読解や記述の力に直結します。
暗記ノートの上手な活用方法5選
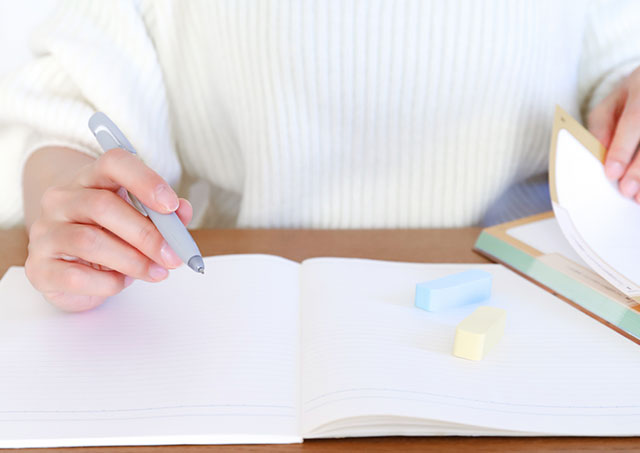
暗記ノートを作った後は、活用方法次第で記憶の定着度が大きく変わります。
日々の学習にどう組み込むかが、効率的な暗記のカギになります。
- 毎日の習慣として読み返す
- 赤シートで隠して確認する
- 友達と問題を出し合う
- 暗記カードとして持ち歩く
- テスト前に集中して使う
それぞれ順番に解説します。
① 毎日の習慣として読み返す
暗記ノートは一度作って終わりではなく、繰り返し見直すことで真価を発揮します。
毎日のスキマ時間や通学中などに目を通すことで、脳が情報を「重要な記憶」と認識しやすくなります。
復習の間隔を徐々に広げる「間隔反復」の方法を取り入れると、より効果的に記憶が定着していきます。
この習慣を続けることで、テスト直前に焦らず準備できるようになるでしょう。
② 赤シートで隠して確認する
赤シートを使えば、覚えたいキーワードを隠して自分で答える練習ができます。
たとえば、英単語の意味や歴史の年号を赤文字で書いておき、テストのように確認するのが効果的です。インプットとアウトプットを同時に行えるのがこの方法の強みです。
自分で問題を出す感覚で確認できるため、インプットとアウトプットを同時に行えるのが強みです。
記憶の定着率を高めたいなら、ぜひ取り入れてほしい方法といえます。
③ 友達と問題を出し合う
暗記ノートを使って友達とクイズ形式で問題を出し合うのも、有効な活用法のひとつです。
自分だけで勉強するよりも、他人とやり取りをすることで記憶の引き出しが刺激されます。
また、友達からの質問によって盲点に気づいたり、自分の理解度を客観的に把握することも可能になります。
互いに教え合うことで、自然と知識が深まっていくのがこの方法の魅力です。
④ 暗記カードとして持ち歩く
暗記ノートの中でも特に重要な部分を抜き出して、カード化して持ち歩くと便利です。
コンパクトで場所を選ばず使えるため、待ち時間や移動中などちょっとした時間も無駄にせず活用できます。
要点を短くまとめる練習にもなるので、内容の整理にもつながります。
暗記メモをカードとして持ち歩ける形にすることで、学習へのハードルも自然と下がっていくでしょう。
⑤ テスト前に集中して使う
テスト直前は、暗記ノートを徹底的に活用する絶好のタイミングです。
自分がまとめた内容だからこそ理解がしやすく、短時間でも効率的に復習できます。
特に、間違えやすいポイントや苦手分野を見返すことで、最後の仕上げとして役立ちます。
「これさえ見れば安心」と思えるノートを作ることで、自信にもつながるでしょう。
関連記事 : 一夜漬けで暗記するコツ8選|前日でも点が取れる最速勉強法
暗記ノートに関するよくある質問

暗記ノートの作り方について、予想される質問をまとめてみました。
どれもよく聞かれる質問ばかりです。
ぜひ事前に知って失敗を回避しましょう。
暗記ノートにおすすめのノートは?
使いやすさや機能性を重視するなら、罫線入りのB5サイズが最もおすすめです。
赤シートに対応していたり、余白が取りやすい仕様のノートを選ぶことで、暗記効率が格段に向上します。
- コクヨ キャンパス暗記用ノート(ドット入り罫線)
- ナカバヤシ ロジカルノート暗記用シリーズ
- ショウワノート ジャポニカ学習帳 赤シート対応版
- マルマン ルーズリーフ 暗記学習用(セミB5)
これらは書き心地や視認性にも優れており、暗記に適した設計となっています。
自分に合ったタイプを選ぶことで、ノート作りがさらに楽しくなるでしょう。
1ページあたりどのくらいの量を書けばいい?
1ページに詰め込みすぎず、見やすさを意識することが大切です。
目安としては、見出しと3〜5項目程度の情報がバランスよく収まる程度が良いでしょう。
余白を残すことで、あとから書き足しや補足もできるようになります。
初めてでも作りやすい暗記ノートは?
項目ごとに色分けし、整理された構成にするのがポイントです。
はじめての方は、見出し・要点・補足の3段階でまとめると簡単に作れます。
テンプレートを参考にすれば、誰でも無理なく作成できるようになるでしょう。
暗記ノートはムダなのでは?
「ノートを作ること」自体が目的になると、確かにムダに感じるかもしれません。
しかし、暗記ノートは復習のツールとして活用することで、記憶の定着や理解を深める効果があります。大切なのは、作って終わりにせず、繰り返し見返す学習の道具として使うことです。
なので作って満足せず、見返すためのノートという意識を持ちましょう。
キツネさん
授業のノートを見返さずにテストに突入…その失敗、経験あります。
暗記ノートに適したサイズは?
携帯性と書きやすさのバランスから、B5サイズが最も使いやすいとされています。
学校や自宅でも扱いやすく、持ち歩く際もかさばらない点がメリットです。
小さいサイズは見づらく、大きすぎると持ち運びや復習で不便になる場合もあります。
持ち運びを重視するなら、もっと小さめのA6サイズやカードタイプなど目的に合わせて使い分けると良いです。
ノートとルーズリーフどちらがいい?
ルーズリーフはページの入れ替えや差し替え・追加ができるため、暗記ノートには向いています。
一方、ノートは流れを保ちやすく、見返しやすさでは優れています。
今回紹介した暗記ノートの種類や目的、自分の勉強スタイルに合った方を選ぶのがよいでしょう。
暗記ノート作りに役立つアプリは?
GoodnotesやNotabilityなどのノートアプリは、タブレットを使った学習に便利です。
暗記用アプリ「Anki」や「Monoxer」なども、デジタルで効率的に覚えるのに役立ちます。
紙と併用することで、より柔軟に学習を進められるようになるでしょう。
まとめ|暗記ノートを活用して効率的に学習しよう!
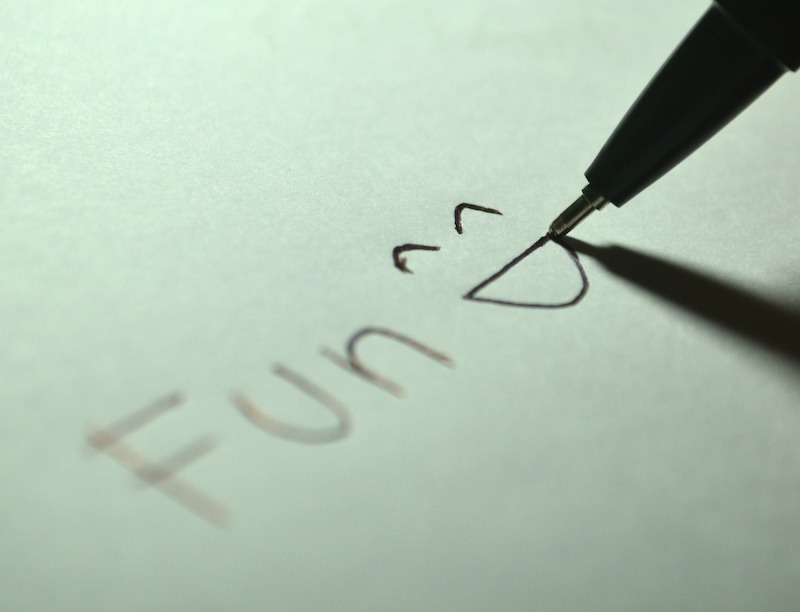
本記事では、暗記ノートのメリット、種類、作り方、活用方法について解説しました。
ストーリー理解型や問題復習型など、目的や学習スタイルに合わせて暗記ノートを工夫すれば、記憶の定着が格段に高まります。
自分に合った方法を見つけて、暗記ノートを日々の学習に取り入れてみましょう。
さらに効率よく覚えたい方は、Wonder Educationが提供する記憶術講座を活用してみてください。
また、吉永式記憶術では、期間限定で無料動画教材を公開しています。科学的根拠に基づいたトレーニングにより、記憶力の向上を実感できるはずです。
\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/
記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役
Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、
新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。
学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?
「人、人、人、全ては人の質にあり。」
その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。
「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!
その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。











